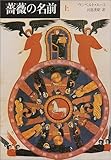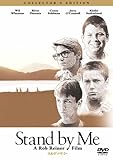監督 ウィリアム・フリードキン 出演 ジーン・ハックマン、フェルナンド・レイ、ロイ・シャイダー
ウィリアム・フリードキンが乗りに乗っていた時代の大傑作だねえ。きのう見た「ザ・タウン」のカーチェイスや銃撃戦はなつかしい感じがいっぱいだったが、「フレンチコネクション」は「なつかしい」ではなく、この当時の到達点だ。ストーリーはあるのだけれど、そのストーリーを超えて映像が、ただただ映像が充実していく。ストーリーを超えて存在する。その力に驚く。
走る地下鉄を、高架下から見上げながらポパイが車で追いかけるシーン。そんなことは現実にはできないのかもしれないけれど、できないとはいわせないぎりぎりの水準のところをやっている。これはCGに頼らない映像のすごさだねえ。いまだったらCGでやってしまうから、すごいはすごいが、映像に厚みがない。この厚みというのは、アクションの定義とは矛盾するようだけれど、ゆっくり感にある。早すぎない。目がおいついていけないスピードではなく、目がしっかりおいついていけるスピードの限界で動く。これがいいんだろうなあ。
しかし、昔のスタントマンは大変だっただろうなあ。カメラも必死だっただろうなあ。いのちをかけた真剣さが映像に緊張感をもたらすのだと実感できる。
地下鉄の中での銃撃戦やパニックも、驚くほど地味なのだが、その地味さ加減が現実感になる。客はパニックを起こして逃げるが、いまの映画のようにものすごいスピードでは逃げない。ぶつかりながら、もたもたと逃げる。そこにリアリティーが生まれる。
車をつかわないシーンでもそれは同じ。ポパイが走る、走る、走る。それはまあ、映画だから全力で走っているシーンをつないでいるのだけれど、その走りが「苦しい」ところがいいなあ。ジーン・ハックマン自体がスマートではないのだけれど、どこかにもたもた感が残る。そうすると、そのもたもた感から、肉体の親密感のようなものが広がってくる。いつも、そこに肉体がある、という感じが映画なのだ。いまの映画も肉体を伝えるけれど、それは鍛え上げられすぎていて、ついていけない。まねできない。まねできる、これをやってみたい、そう感じさせないとおもしろくないねえ。親密感がわかないねえ。
もうひとつ。車を解体してヘロインを探し出すシーンも大好きだなあ。どこまでもどこまでも解体していく--というのはコッポラの「カンバセーション」(なぜか、主演はジーン・ハックマンだね。共通しているね)にもあるけれど、おもしろいねえ。車がスクリーンの中で拡大されて、解体される。そうすると、車の「肉体」のようなものが見えてくる。手触りが濃密になる。こんなに解体して、どうやってもとに戻すんだ--とびっくりしてしまうが、もちろん手品みたいにもとに戻るのもいいねえ。
つくづく思うのは、この時代の役者は、みんな「肉体」で動いていた。肉体を動かして演技していた。いまも肉体を動かしている、というかもしれないけれど、いまは、肉体の動きをカメラで加速している。それが余分だねえ。
あくまでカメラは役者の肉体を追いかける。カメラが役者の肉体を後押ししたり、引っ張ったりすると、スピードは出るが、肉体の「濃さ」「重さ」がなくなる。そのカメラも、昔の映画は重たかったねえ。動きがもったりしている。これが尾行のシーンなんかには効果的だなあ。いまの映画は尾行するとき(群集のなかを動くとき)も安定しているが、昔はもたもた。このもたもたのなかに、時間のおもしろさがある。時間をかける、時間がかかる。時間は「間」だね。そこに間があるから、観客は想像力を投げ込むことができる。いまの映画は「間」がないのだ。
映画はまたジーン・ハックマンのすけべそうな魅力も伝えている。若い女をみるときの目付きが、何か甘ったれたところがある。それがおもしろい。甘ったれたところがあるというのは、まあ、脇が甘いということかもしれない。それが女に手錠かけられて動けないというセックスシーンにつながったりする。そしてまた、役どころの、「勘が鋭い」というところにもつながる。甘い部分があるというのは、一種の弱みだけれど、その弱い部分を補うようにして勘というものが発達する--というのは、私の思い込みだけれど。
フェルナンド・レイにも色気があるなあ。地下鉄でジーン・ハックマンの尾行を巻くシーン。声に出すわけではないが、ドア越しに「アデュー」と目でつげる。手でつげる。この手の動きが、ラスト寸前のジーン・ハックマンの手の動きと呼応するところもいいなあ。
犯罪者と刑事というのは、一種の「愛人関係」だねえ。それがあるから、おもしろいんだろうなあ。
(「午前10時の映画祭」青シリーズ2本目)
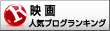
ウィリアム・フリードキンが乗りに乗っていた時代の大傑作だねえ。きのう見た「ザ・タウン」のカーチェイスや銃撃戦はなつかしい感じがいっぱいだったが、「フレンチコネクション」は「なつかしい」ではなく、この当時の到達点だ。ストーリーはあるのだけれど、そのストーリーを超えて映像が、ただただ映像が充実していく。ストーリーを超えて存在する。その力に驚く。
走る地下鉄を、高架下から見上げながらポパイが車で追いかけるシーン。そんなことは現実にはできないのかもしれないけれど、できないとはいわせないぎりぎりの水準のところをやっている。これはCGに頼らない映像のすごさだねえ。いまだったらCGでやってしまうから、すごいはすごいが、映像に厚みがない。この厚みというのは、アクションの定義とは矛盾するようだけれど、ゆっくり感にある。早すぎない。目がおいついていけないスピードではなく、目がしっかりおいついていけるスピードの限界で動く。これがいいんだろうなあ。
しかし、昔のスタントマンは大変だっただろうなあ。カメラも必死だっただろうなあ。いのちをかけた真剣さが映像に緊張感をもたらすのだと実感できる。
地下鉄の中での銃撃戦やパニックも、驚くほど地味なのだが、その地味さ加減が現実感になる。客はパニックを起こして逃げるが、いまの映画のようにものすごいスピードでは逃げない。ぶつかりながら、もたもたと逃げる。そこにリアリティーが生まれる。
車をつかわないシーンでもそれは同じ。ポパイが走る、走る、走る。それはまあ、映画だから全力で走っているシーンをつないでいるのだけれど、その走りが「苦しい」ところがいいなあ。ジーン・ハックマン自体がスマートではないのだけれど、どこかにもたもた感が残る。そうすると、そのもたもた感から、肉体の親密感のようなものが広がってくる。いつも、そこに肉体がある、という感じが映画なのだ。いまの映画も肉体を伝えるけれど、それは鍛え上げられすぎていて、ついていけない。まねできない。まねできる、これをやってみたい、そう感じさせないとおもしろくないねえ。親密感がわかないねえ。
もうひとつ。車を解体してヘロインを探し出すシーンも大好きだなあ。どこまでもどこまでも解体していく--というのはコッポラの「カンバセーション」(なぜか、主演はジーン・ハックマンだね。共通しているね)にもあるけれど、おもしろいねえ。車がスクリーンの中で拡大されて、解体される。そうすると、車の「肉体」のようなものが見えてくる。手触りが濃密になる。こんなに解体して、どうやってもとに戻すんだ--とびっくりしてしまうが、もちろん手品みたいにもとに戻るのもいいねえ。
つくづく思うのは、この時代の役者は、みんな「肉体」で動いていた。肉体を動かして演技していた。いまも肉体を動かしている、というかもしれないけれど、いまは、肉体の動きをカメラで加速している。それが余分だねえ。
あくまでカメラは役者の肉体を追いかける。カメラが役者の肉体を後押ししたり、引っ張ったりすると、スピードは出るが、肉体の「濃さ」「重さ」がなくなる。そのカメラも、昔の映画は重たかったねえ。動きがもったりしている。これが尾行のシーンなんかには効果的だなあ。いまの映画は尾行するとき(群集のなかを動くとき)も安定しているが、昔はもたもた。このもたもたのなかに、時間のおもしろさがある。時間をかける、時間がかかる。時間は「間」だね。そこに間があるから、観客は想像力を投げ込むことができる。いまの映画は「間」がないのだ。
映画はまたジーン・ハックマンのすけべそうな魅力も伝えている。若い女をみるときの目付きが、何か甘ったれたところがある。それがおもしろい。甘ったれたところがあるというのは、まあ、脇が甘いということかもしれない。それが女に手錠かけられて動けないというセックスシーンにつながったりする。そしてまた、役どころの、「勘が鋭い」というところにもつながる。甘い部分があるというのは、一種の弱みだけれど、その弱い部分を補うようにして勘というものが発達する--というのは、私の思い込みだけれど。
フェルナンド・レイにも色気があるなあ。地下鉄でジーン・ハックマンの尾行を巻くシーン。声に出すわけではないが、ドア越しに「アデュー」と目でつげる。手でつげる。この手の動きが、ラスト寸前のジーン・ハックマンの手の動きと呼応するところもいいなあ。
犯罪者と刑事というのは、一種の「愛人関係」だねえ。それがあるから、おもしろいんだろうなあ。
(「午前10時の映画祭」青シリーズ2本目)
 | フレンチ・コネクション [DVD] |
| クリエーター情報なし | |
| 20世紀フォックス・ホーム・エンターテイメント・ジャパン |