監督 ルネ・クレマン 出演 アラン・ドロン、マリー・ラフォレ、モーリス・ロネ
アラン・ドロンは不思議な役者である。美形は美形である。だが、品がない。色でいうと「原色」である。どんな色でも黒を加えると色が落ち着き、品が出てくる。(好みの問題かもしれないが、私はそう感じる。。)アラン・ドロンには、その色をおさえる「黒」が欠けている。色が剥き出しである。その剥き出しの感じが、品がない、という印象を呼び覚ます。
この映画では、その品のなさが「個性」として生かされているが、一か所、とても色気があるシーンがある。「持ち味」を上回って、努力というか、肉体を懸命に動かすシーンがあり、それが「原色」を抑え、色気になる。
モーリス・ロネのサインを偽造する--偽造するために練習するシーンである。投影機を買い込み、小さなサイン壁いっぱいの大きさに拡大する。その拡大されたサインを全身をつかってなぞる。手先でサインの癖を盗むのではなく、全身で盗む。小さな紙にサインするときでも、肉体は微妙に全身をつかっている。その全身の感覚を、そっくりそのまま盗むのである。そのときの、他人になる感覚。アラン・ドロンの肉体それ自体を裏切りながら鍛えていく--そのシーンがとても迫力がある。
私には気に入った映画の気に入ったシーンは真似してみたくなるという癖があるが、「太陽がいっぱい」では、この偽造の練習シーンである。
このほかにも、この映画ではアラン・ドロンは「肉体」を酷使している。船からボートにほうりだされ、漂流して日焼けするシーン。その日焼けの皮膚が破れて、いわゆる皮がむけるシーン。その日焼けの肩の色、皮むけぼろぼろな感じ--これをメーキャップではなく、実際の肌でやっている。なんだか、すごい。
その「肉体」を酷使した海のシーンでは、別の「肉体」の酷使の仕方もしている。モーリス・ロネを殺した跡、死体を布でつつむ。ロープで縛る。揺れる船の上での、その悪戦苦闘ぶりが、かなりの時間をかけて描かれる。--こういうシーンは映画ならではである。台詞は何もない。やっていることはわかりきっている。わかりきっていることだけれど、そういうことは普通ひとはみないし、やったこともない。だからほんとうのところ肉体がそのときどんなふうにして動くは知らない。その観客の、知っているようで知らないことを、アラン・ドロンが全身で再現する。サインの偽造の練習も、あ、そうか、とわかるけれど、そういうことは実際には誰も体験していない。その体験していないことを肉体でみせるが役者なのだ。
あ、そうなのだ。おもしろいのは、すべて肉体なのだ。アラン・ドロンがモーリス・ロネの靴を履いてみたり、服を着てみたり、そしてそのまま鏡に姿を映して自分に口づけしてみたりも、ストーリーでもことばでもなく、ただ肉体なのだ。アラン・ドロンという特有の顔をもつ男の、特権的な肉体の動き。それが、この映画のおもしろさの核心である。
肉体を酷使して酷使して、その最後--ああ、これで幸せになれると笑みを浮かべるクライマックスの、アラン・ドロンの顔。肉体が、そのとき、顔そのものになる。特権の花が華麗に、華麗過ぎるほど華麗に、満開になる。
アラン・ドロンという役者は私は好きではないけれど、こういう特権的な顔を見るだけのために、この映画を見るのもいいかもしれない。犯罪映画を、まるで美男子の悲劇のように華麗に描いてしまうルネ・クレマンには、まあ、脱帽すべきなのだろう。
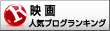
アラン・ドロンは不思議な役者である。美形は美形である。だが、品がない。色でいうと「原色」である。どんな色でも黒を加えると色が落ち着き、品が出てくる。(好みの問題かもしれないが、私はそう感じる。。)アラン・ドロンには、その色をおさえる「黒」が欠けている。色が剥き出しである。その剥き出しの感じが、品がない、という印象を呼び覚ます。
この映画では、その品のなさが「個性」として生かされているが、一か所、とても色気があるシーンがある。「持ち味」を上回って、努力というか、肉体を懸命に動かすシーンがあり、それが「原色」を抑え、色気になる。
モーリス・ロネのサインを偽造する--偽造するために練習するシーンである。投影機を買い込み、小さなサイン壁いっぱいの大きさに拡大する。その拡大されたサインを全身をつかってなぞる。手先でサインの癖を盗むのではなく、全身で盗む。小さな紙にサインするときでも、肉体は微妙に全身をつかっている。その全身の感覚を、そっくりそのまま盗むのである。そのときの、他人になる感覚。アラン・ドロンの肉体それ自体を裏切りながら鍛えていく--そのシーンがとても迫力がある。
私には気に入った映画の気に入ったシーンは真似してみたくなるという癖があるが、「太陽がいっぱい」では、この偽造の練習シーンである。
このほかにも、この映画ではアラン・ドロンは「肉体」を酷使している。船からボートにほうりだされ、漂流して日焼けするシーン。その日焼けの皮膚が破れて、いわゆる皮がむけるシーン。その日焼けの肩の色、皮むけぼろぼろな感じ--これをメーキャップではなく、実際の肌でやっている。なんだか、すごい。
その「肉体」を酷使した海のシーンでは、別の「肉体」の酷使の仕方もしている。モーリス・ロネを殺した跡、死体を布でつつむ。ロープで縛る。揺れる船の上での、その悪戦苦闘ぶりが、かなりの時間をかけて描かれる。--こういうシーンは映画ならではである。台詞は何もない。やっていることはわかりきっている。わかりきっていることだけれど、そういうことは普通ひとはみないし、やったこともない。だからほんとうのところ肉体がそのときどんなふうにして動くは知らない。その観客の、知っているようで知らないことを、アラン・ドロンが全身で再現する。サインの偽造の練習も、あ、そうか、とわかるけれど、そういうことは実際には誰も体験していない。その体験していないことを肉体でみせるが役者なのだ。
あ、そうなのだ。おもしろいのは、すべて肉体なのだ。アラン・ドロンがモーリス・ロネの靴を履いてみたり、服を着てみたり、そしてそのまま鏡に姿を映して自分に口づけしてみたりも、ストーリーでもことばでもなく、ただ肉体なのだ。アラン・ドロンという特有の顔をもつ男の、特権的な肉体の動き。それが、この映画のおもしろさの核心である。
肉体を酷使して酷使して、その最後--ああ、これで幸せになれると笑みを浮かべるクライマックスの、アラン・ドロンの顔。肉体が、そのとき、顔そのものになる。特権の花が華麗に、華麗過ぎるほど華麗に、満開になる。
アラン・ドロンという役者は私は好きではないけれど、こういう特権的な顔を見るだけのために、この映画を見るのもいいかもしれない。犯罪映画を、まるで美男子の悲劇のように華麗に描いてしまうルネ・クレマンには、まあ、脱帽すべきなのだろう。
 | 太陽がいっぱい [DVD] |
| クリエーター情報なし | |
| パイオニアLDC |

























