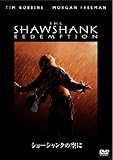監督 ウィリアム・ワイラー 出演 オードリー・ヘップバーン、グレゴリー・ペック
オードリー・ヘップバーンの透明な美しさが輝いている映画である。何度見ても、その透明さに驚く。
と、書いたあとでこんなことを書くのは変かもしれないが、私がこの映画でいちばん好きなのは舞踏会のシーン。オードリー・ヘップバーンがドレスの下でハイヒールを脱ぐ。右足をほぐし、左足の裏側をかく。そんなしぐさをする。そして靴が倒れる。
王女もそんなことをするんだ--という、うれしいような感覚が、この瞬間生まれるから、というのはもちろんだけれど……。
このシーン、とっても変でしょ? 何がって、ドレスの下なんて、見えない。それなのにカメラは平気でドレスの下にもぐりこんでオードリー・ヘップバーンの足を写している。俗なことばでいえば「盗撮」だね。しかも、堂々とした盗撮だねえ。
でも、映画だから、もちろん「盗撮」ではない。
では、何か。
映画の「暗示」である。
この映画は、オードリー・ヘップバーン王女様が、窮屈な生活から逃れ、ひととき、庶民にもどり、ふつうの生活を楽しむ。その解放感を描いているのだが、その喜びは、実は「外側」だけではない、解放は「外側」だけではない、という暗示である。
それは、オードリー・ヘップバーンがセックスをしたという意味ではなく、その楽しみはセックスにつながる楽しみであるという暗示である。
もともと靴を脱ぐというのはセックスをするという意味に重なる。だからポルノ映画で娼婦がハイヒールを履いているのは、実はセックスをしていません、という意味なのである。その姿態が見えていても、隠しています、という意味なのだ。だから、エロチックなのだ。
この映画では、この靴と肉体の関係はもう一度出てくる。
オードリー・ヘップバーンはベッドのなか。外から音楽が聞こえてくる。その様子を見るためにオードリー・ヘップバーンが窓に駆け寄る。そのとき侍女が「スリッパを履いて」と注意する。それは足がよごれるというよりもスリッパを脱ぐということがセックスにつながるからである。
スリッパは「裏窓」でもセックスの象徴としてつかわれていた。グレイス・ケリーがジェームズ・スチュアートのアパートに泊まりに行く。そのときスリッパをもっていく。それは靴を脱ぐ。セックスもする、ということである。知人がスリッパに目を止めたとき、ジェームズ・スチュアートが「そんなところまで見るなよ」というような顔をするのはそのためである。
そういう暗示を踏まえて、「ローマの休日」を見つめなおすと、ますますおもしろくなる。どこまでもどこまでも清純なオードリー・ヘップバーン。世間知らず。その美しさ。世間知らずだけれど、人間だから嘘をつくことくらいは知っている。知っているけれど、嘘がどんな結果を引き起こすか--まあ、自分で責任をとったことがないので、それもよく知らない。だから、真実の口の中へ手を突っ込むことが出来ない。グレゴリー・ペックの芝居にびっくりしてしまう。これもたわいのないシーンといえばたわいのないシーンなのだが、嘘のかけひきと思うとおかしいねえ。嘘を楽しんでいる。男と女は、ときどき嘘を楽しむね。相手の表情がかわるのが楽しくて。
オードリー・ヘップバーンが、いわゆるグラマーな体つきでないのも、この映画からセックスを隠し、逆にセックスを感じさせる。オードリー・ヘップバーンよりはるかに王女っぽいグレイス・ケリーがこの役をやっていたら、こんな映画にはならない。少女のまま(少年っぽいとさえいえる--パジャマ姿が、とくにそう感じさせるねえ)オードリー・ヘップバーンだから、それが「恋の芽生え」、そしてそれゆえのセックスを知らない興奮、ときめき、清らかなあこがれになる。装飾の少ないブラウス、そしてシンプルなスカートは、その固い殻のなかで動く肉体をすっきりと暗示する。装飾のない裸の肌の美しさを、処女をそのまま感じさせる。
処女だから無防備、処女だからそれを守ってやろうとする男。「騎士道」のかっこよさ。むり、というか、粋。やっている本人にいちばん無理なことが他人からは「美しく」見える。そこには一種の逆説のセックスがひそんでいる。矛盾が感じさせるエロチシズムがある。そういうもの、隠されたこころの動きを、カメラは、ほんとうは撮っている。スカートのなかの「盗撮」のように。
*
付録。オードリー・ヘップバーンがグレゴリー・ペックのアパートへ行って、「ここはエレベーター?」と聞くシーンもおもしろいなあ。これと逆が「チャンス」にある。ピーター・セラーズがエレベーターのなかで、「ここにはテレビはないの?」と聞く。エレベーターと部屋の区別がつかない。この混同が「高貴」の象徴であるらしい。
(午前十時の映画祭37本目)