季節の物売り 江戸情緒 ① 福寿草売り
|
季節の物売り 「きんぎょぇ~きんぎょッ」金魚屋さんがくると、一斉に物売りの声に魅かれて外に飛び出す。 |
 (初夏の物売りの図)
(初夏の物売りの図)
橋の上には薬売り、旗を持つ祈祷師(?)、或いはこの人も薬売りで、同業者同士が橋の上で出会い、互いに振り返ってみているのかもしれない。
初鰹売り、橋のたもとに花屋、その手前に乾物屋、画面左端にも物売りらしき人がいるが何を商っているのか不明。橋のたもと右側の家の軒下には「吊り忍」が下がっている。これも物売りから手に入れたのだろう。そのすぐ上には、買ったばかりの菖蒲をさげている人がいる。
季節は初夏、汗ばむような午後の時間帯だろう。笠をかぶる人。扇を頭にかざし日差しを避ける人、菖蒲をさげた人も
手拭いで額の汗をぬぐっている。庶民達が行きかう賑やかな往来を描いている。
福寿草売り

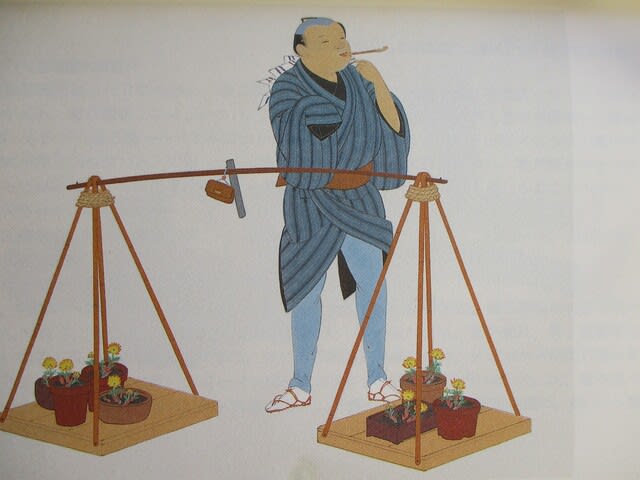
「福寿草売り12月25日 春に至る迄、梅福寿草などの盆花町に商ふ」(東都歳時記)
福寿草は、元旦草とも言い、歳末に福寿草売りから買って、正月の床の間を飾ったという。
左の写真は女性の売り子さんが描かれている。女性の物売りが実在したのかどうかわからないが、
当時、飾り絵として販売された絵も多く、特に人気のあった歌舞伎役者の売り姿の絵に人気があったようだ。
左の絵が実際の福寿草売りの風俗画ではないかと思う。
煙草入れを帯から抜いて、てんびん棒にかけ、一服している姿が現実感があって私は好きだ。
40年も前、母の願いでよく神社仏閣いった。
境内に並んだ出店を見てまわるのも参拝の楽しみだった。
当時、よく福寿草を購入した。
一芽、30円ぐらいだったと思う。数年続いた30円の売値も50円になり、どんどん値が上がった。
現在では350~400円、当時の価格の約10倍もしている。
あの時購入した福寿草は毎年、庭の陽だまりで元気に花を咲かせている。
増えた分だけ、美しいと褒めてくれた人に分けてあげるので、
年数の割には株は一向に大きくならない。
母との想い出に繋がる懐かしい匂いのする初春の花である。
(季節の香り№33) (2012.12.8記)















