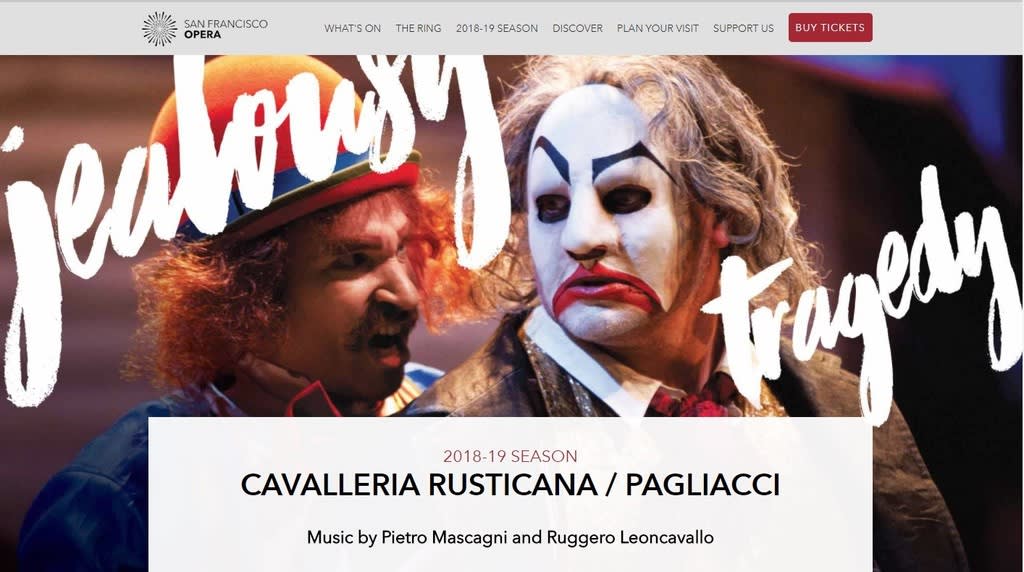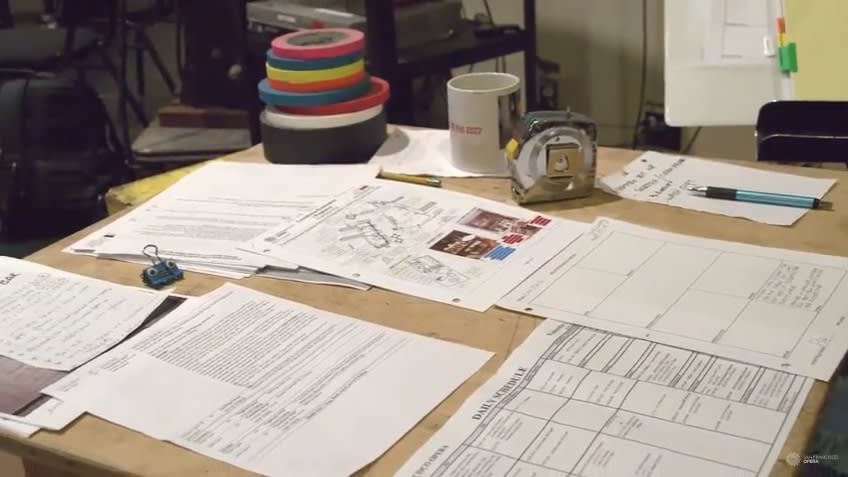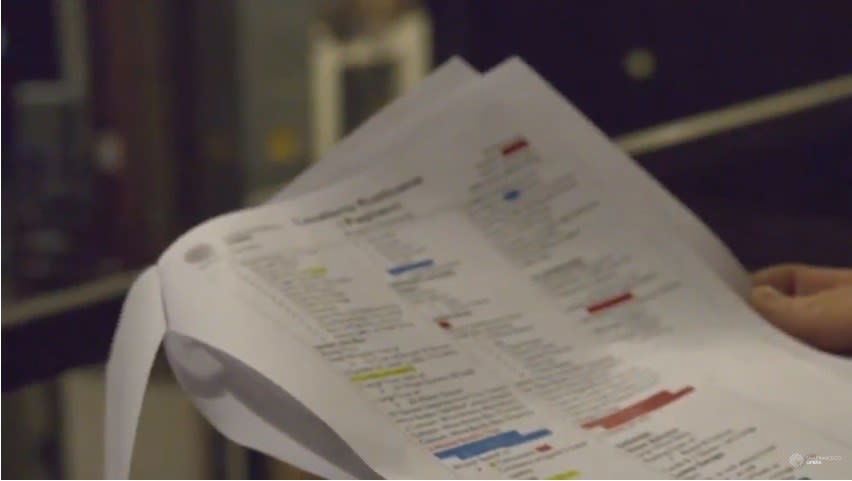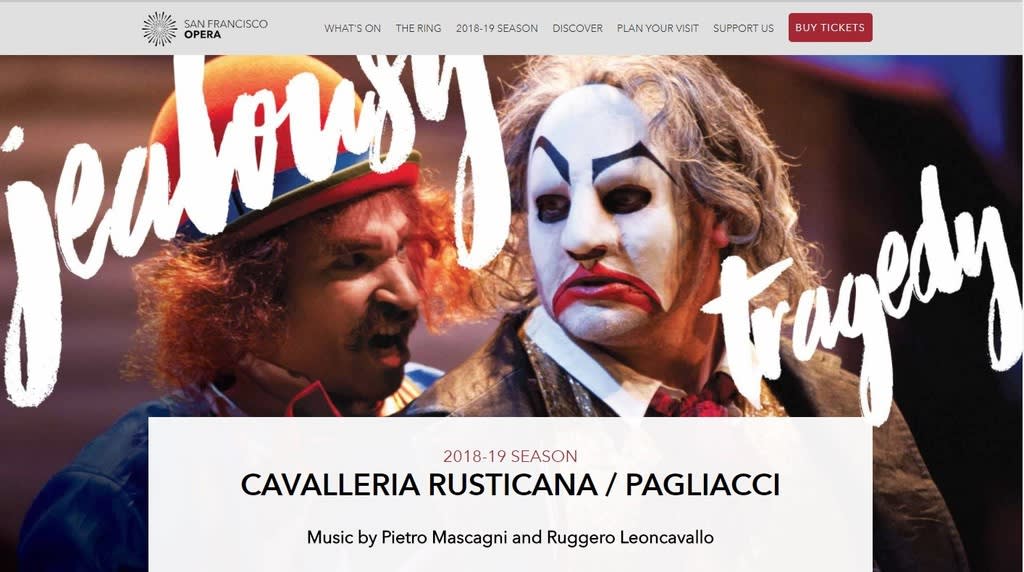すでに何回か紹介しましたが、昨年2018年9月に、ホセ・クーラが演出・舞台デザインを手がけた道化師とカヴァレリア・ルスティカーナのプロダクションが、アメリカ・サンフランシスコオペラの2018/19シーズンの開幕公演として上演されました。
→ (レビュー編) (告知編)
ただし、ちょうど同じ時にエストニアでプッチーニの西部の娘の演出・指揮に取り組んでいたクーラは、残念なことに、再演の演出も出演もできませんでした。そのためこの再演にあたって、クーラは、サンフランシスコで演出を担当したホセ・マリア・コンデミと一緒に、事前に時間をかけてしっかり準備をしたということです。
そういう経過をふまえ、サンフランシスコオペラのHPには、クーラのディレクターズ・ノート(演出ノート)が掲載されています。今回は、その内容を紹介したいと思います。
「ヴェリズモ・マニア」を自称するほど、ヴェリズモのオペラの研究を深めてきたクーラの、カヴァレリアと道化師の作品論、今回の演出のコンセプト、現代社会への批判として今日に通用する作品のテーマに関することなどが記されています。
クーラが書いたセットのスケッチや、発想のもとになったアルゼンチンのイタリア系移民地区のストリートアートの写真なども掲載されています。
また、クーラのプロダクションが2015年にテアトロコロンで上演された時の様子や、クーラの詳しい作品解釈、動画などもブログ記事で紹介しています。よろしければご覧いただけるとうれしいです。
→ 「カヴァレリア・ルスティカーナと道化師の演出」
なお、いつものように和訳の誤りや直訳、ご容赦ください。

CAVALLERIA RUSTICANA / PAGLIACCI
Director's Note by José Cura
カヴァレリア・ルスティカーナ / 道化師 ディレクターズ・ノート ホセ・クーラ
私が最初にカヴァレリア・ルスティカーナと道化師の演出と舞台デザインを依頼された時、この2つのオペラを、1900年代初頭のアルゼンチンのイタリア人移民へのオマージュとして形づくるという考えがすぐにわきあがった。
ヴェリスモ運動のこの二つの象徴的な作品の精神――その両方、過激さと臆病さ、明るさと暗さ、愛情深さと残忍さ――それらは、そのルーツであるイタリア人の祖先たちに非常によくあてはまるように思われた。そしてブエノスアイレスのイタリア人地区であるラ・ボカは、そのすべての歴史と、絵になる色とりどりの美しさによって、理想的な設定だった。

台本に合わせて、私は、実際には存在しないスペースをセットに追加することにした――食堂、教会、アルフィオとローラの家など。それ以外の風景 - 広場、物干しの綱がついた窓、教区――はすべて計画段階からあった。
私はコスチューム・デザイナーのフェルナンド・ルイスに、衣装について、カヴァレリア・ルスティカーナで通常見られるようなグレーの色合いである必要はないという考えを投げかけた。むしろ、色彩やその「即興的」な感覚は、つつましい暮らしの人々の集団が、自分が持っている最高の服を着たときのものだ。
ブエノスアイレスのレサマ公園にある壁画(Escenográfico)の写真を見つけたとき、啓示は起きた。ラ・ボカ地区の入り口を彩っている1999年に完成したこのストリートアートは、私にとって、道化師と完全に関連づけられる一連のキャラクターを描いている。

カヴァレリア・ルスティカーナと道化師は、イタリアのヴェリズモ(リアリズム)の文学的伝統にもとづいている。ジョヴァンニ・ヴェルガ(イタリアの作家、カヴァレリア・ルスティカーナの原作者)とルッジェーロ・レオンカヴァッロの両者が、人生そのもので起こったイベントから、彼らの文学的なインスピレーションを見出した。
道化師の物語の由来を説明する2つの説がある。1つめは、レオンカヴァッロ自身が幼い頃、コメディアンのネッダが、その愛人を現行犯で捕らえた彼女の演技のパートナーであり夫であるジョバンニ・ダレッサンドロの手によって殺されたことを目撃したというもの。
2つめは、ルッジェーロ・レオンカヴァッロの父親が、自分の息子に彼自身が裁判に関わった同じ様な犯罪を語ったものだという。
さらに複雑なことに、レオンカヴァッロの作品は、スペインの劇作家マヌエル・タマーヨ・イ・バウス(Manuel Tamayo y Baus)による『新演劇』(Un Drama Nuevo:1867)と題された戯曲に「危険なほど」似ていると示唆した音楽学者がいる。
レオンカヴァッロを盗作だと非難するのは少し行き過ぎだ。私はむしろ、彼が劇場の動向に精通していたことについて彼を「非難」したい。それは彼がおそらくタマーヨの作品を知っていて、そこから影響を受けたことを意味する。それは伝統的に、創造の世界ではいつもそうであり、これからも続く。
大体において、道化師とカヴァレリア・ルスティカーナのプロットは、互いにかなり似ている――既婚女性の違法な関係は、裏切られた夫の嫉妬を引き起こす。しかし、カニオのキャラクターと今日との関連性は圧倒的だ――人生とアルコールに押しつぶされた、盛りを過ぎたアーティスト。
今日においてほど、「目新しさ」が一旦なくなったために、多くの才能が捨てさられるのを見ることはない。2本の映画の後、人気を失った俳優、あるいはもっと悪い場合、舞台とスクリーンの巨人たちがちょっとした役を演じるだけに追いやられ、かろうじて食べていくことができる―― これらは、一瞬だけ輝く「瞬間のスター」の背景の効果的な装飾。
犠牲者のリストは非常に長く、そこに含まれてるのは俳優だけではない。準備のないままに、目まぐるしく動きの速いキャリアに投げ込まれた歌手や、勝利のプレッシャーの下でドーピングに頼るアスリートたちがいる。

そのリストはさらに大きくすることができる――ただ私たちのまわりを注意深く見るだけで。「カニオ症候群」は今日、これまで以上に蔓延している。
「私たちの衣装だけでなく、私たちの魂を考えてみてください。私たちもまた、肉と骨をもつ人間なのだから」とプロローグのなかで著者は訴える。
プロローグは、私にとってこのプロダクションの最も感動的な瞬間の一つであり続ける。その言葉は、物乞いと新聞配達の少年だけが聞き、感じた。関連づけられた物語を描き出すためにこれらのキャラクターを使用することは、ステージングの非常に重要な部分を活気づける――両方のオペラを通じた2つのキャストの存在。
両方のオペラで同じセットを共有するという選択において、課題は、司祭や市長、バーテンダー、理髪師、食料雑貨屋、子どもたちなどによって、社会的に構造化された町を構築することだった。
そこで、カヴァレリアの冒頭には、ネッダとピエロが一座のポスターを掲示するのが見える。道化師では、サントゥッツァが妊娠7ヶ月のお腹を抱えていて、同様に、マンマ・ルチアは、ウェイターのシルヴィオに助けられながら、まだ彼女の居酒屋を経営しているようにした。

しかし、私の一番気に入っている瞬間は、依然としてエンディングだ。ルチアが、「喜劇は終わった」( “La commedia è finita”)と叫ぶ―― 彼女の本来の権利として、まるで「信託」のように。
それはただ老いた女性の声なのではなく、地球の声、全宇宙の声でもあり、全世界にむけて「バスタ!」 “Basta!”――「もうたくさんだ!」と叫んでいる。
(原文:サンフランシスコオペラHP)



*画像は、劇場のHPなどからお借りしました。