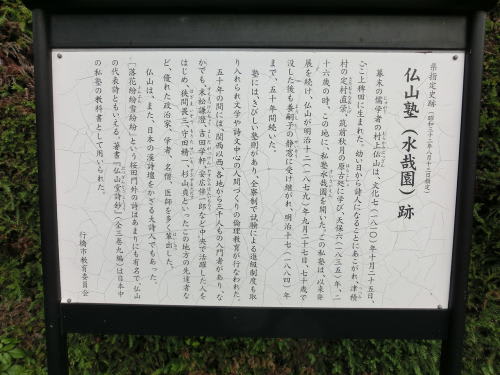三丁弓の岩

城井ノ上城址登り口
岩井 護は、飯塚市出身で、福岡市に住み、博多の郷土史に造詣が深い。
戦国ものをはじめ歴史・時代小説などを執筆している作家である。
『 雲の砦 』 は、旧・築城町寒田の城井谷 ( きいだに ) の城井ノ上城主の宇都宮鎮房と
中津城に居を構えていた黒田官兵衛孝高 ( 後の如水 ) と長政親子の戦いと、
薩摩藩に逃げる八重姫を描いた小説である。
この作品は、昭和44年 ( 1969年 ) フクニチ新聞に85回連載されたものである。
中津城に赴いた鎮房は、酒席で長政に謀殺された。
黒田官兵衛孝高の肥後の鎮圧に同行していた朝房 ( 鎮房の嫡男 ) は、
熊本県の木葉で黒田官兵衛孝高に切腹を命じられ、拒む朝房を惨殺する。
政略結婚させられた鎮房の双生児の娘のうち、姉の鶴姫は鎮房謀殺後、
小犬丸の河原で磔にされる。
ふたごは不吉として家臣に預けられていた双子の妹・八重姫は家臣二人に守られて
寒田 ( さわだ ) の城井谷を脱出し薩摩藩に向かった。
八重姫たちは、臼杵から日向街道を南下、宇根原地区の山道を豊後と日向の国境近くにたどり着く。
そこで見たものは、 「 城井谷の城井ノ上城付近の山々の眺めとそっくりだったのだ。
陽射しをはね返して、ぎらぎら光っている雲の頂きは、緑の山頂で懐深い城井谷の暮らしを
四百年にわたって見守って来た、城井ノ上城の厳しい姿とそっくりだった 」 とある。
城井ノ上城の入り口には、男三人が座れるほどの大きな穴があり、
攻めの手を防ぐのに三丁の弓で足りたという 「 三丁弓の岩 」 が砦となった。
岩井 護 ( いわい まもる ) は、昭和2年 ( 1929年 ) 嘉穂郡飯塚町 ( 現・飯塚市 ) に生まれた。
西南学院大学在学中から 「 九州文学 」 に参加していた。
九大付属図書館在籍中に書いた「雪の日のおりん」で第10回小説現代新人賞受賞した。
小説 「 花隠密 」 (講談社刊)が松平健の主演で舞台となり、大阪の新歌舞伎座などで上演された。
花を愛した徳川家斉にハナショウブを献上する肥後と宇和島の 「 花戦争 」 を背景とし、
勝負に負けた宇和島から花作りの秘密をさぐりに肥後に潜入する 「 花隠密 」 の悲恋を描いた作品や、
「 まぼろしの南方録 」 「 踏絵奉行 」 「 福沢諭吉 」 「 西南戦争 」 などがある。
2013年1月30日没。