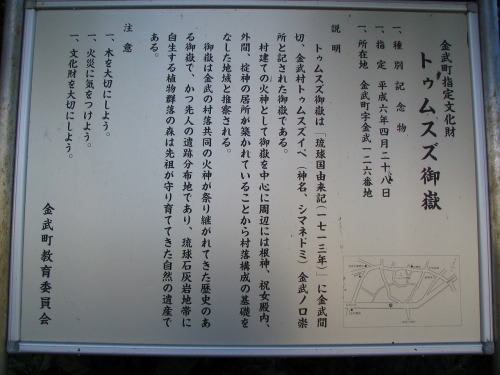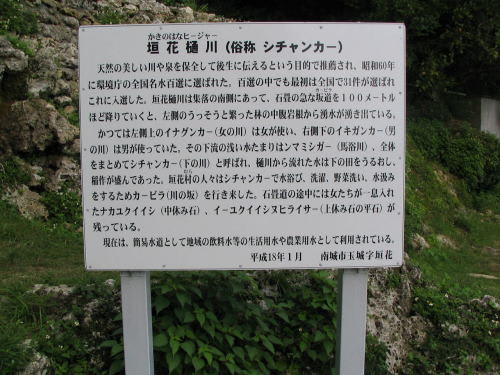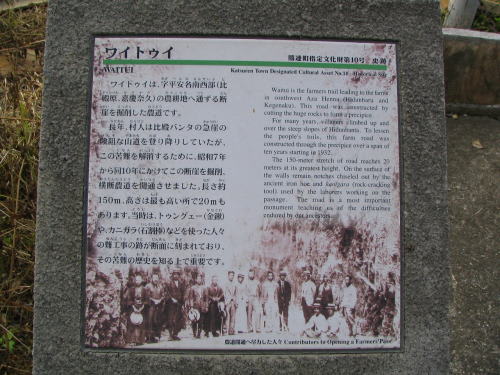玉城城跡
The Ruins of Tamagusuku Castle
( 国指定史跡 )
National Historical Monument
指定年月日 : 昭和 62 ( 1987 ) 年8月21日
Designaed Date : August 21,1987
所在地 : 沖縄県南城市字玉城門原、伊佐昆原
Location : Tamagusuku,Nanjyou-shi,Okinawa-ken
玉城城跡は玉城集落の北方約700mにある石灰岩の小山を利用して築かれた城で、
アマツヅグスクとも呼ばれている。
周辺にはミントングスクや垣花城跡、糸数城跡があり、
城内は石垣によって三つに分けられている。
現在はその石垣がよく残っているのは、
中心部分の一の郭だけで、一の郭の入り口は自然岩をくりぬいて造られている。
また、城内には住居跡と思われる場所や拝所が数ヵ所点在している。
この城はアマミキヨが築いたという伝説もあり、
東御廻り ( アガリウマーイ ) の拝所にもなっている。
古い時代の祭祀を理解する上で重要な場所である。
Tamagusuku Castle was built so as to take advantage of a small mountain whichis 700m.
to the north of Tamagusuku village. It is also called Amatsugusuku.
There are Mintongusuku, the site of Kakiniohana Castle and Itokazu Castle around the area.
The im\nside of the castle was divided into three parts.
The middle is the only part that has the stone gate left in a good condition.
A natural limestone was hollowed out as an entrance to the first part.
there are several places to give prayers and place which
is believed to have been a residence in the castle.