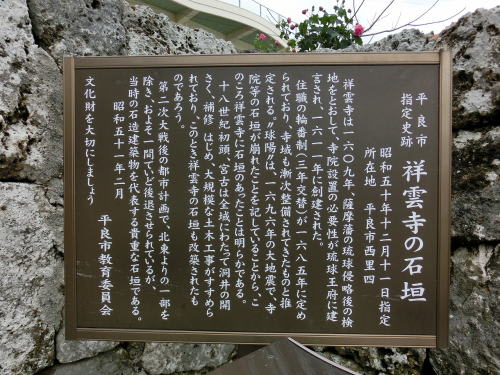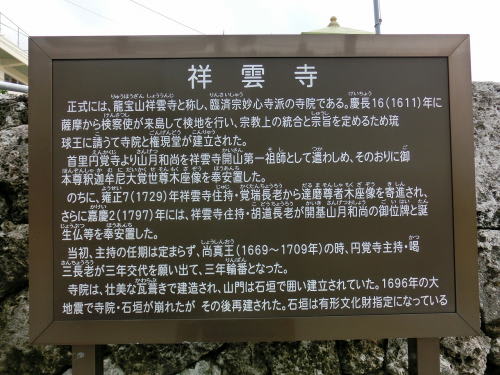「鏡原馬場跡」

かつての競馬の審判台

城間正安と中村十作の顔がある 「 人頭税廃止100周年記念碑 」
「 史跡 鏡原馬場跡 」 と刻まれた石碑の隣には70センチ程度に積み上げた石垣作りの審判台。
あの記念すべき年、審判台の上に立った4人の目には何が映ったのだろうか。
宮古島の南西にある鏡原馬場に大歓声が沸き上がったのは1894年(明治27年)3月。
琉球処分で沖縄が日本に併合されてから15年後のことだった。
宮古の農民代表として人頭税廃止を国会に請願し、
税撤廃の確信を得て帰島した城間正安、中村十作、平良真牛、西里蒲の慰労祝賀会。
漲水港で4人を出迎えた農民数百人は鏡原馬場まで約3キロの道のりを宮古の伝統舞踊クイチャーで練り歩く。
そののち、島内から優れた馬を集め、当時、農民に禁じられていた競馬を催した。
そんな悪税が廃止に近づいたとき、宮古農民は禁を犯して喜びを競馬にぶつけたのだった。
琉球王国が琉球藩となった1872年(明治5年)、
沖縄本島では士族だけに制限していた乗馬を農民にも許可している。
ところが、宮古島では翌1873年の富川親方規模帳(琉球王府高官の布告)で、
農民の乗馬を改めて禁じ、競馬に参加した場合にはムチ打ち刑に処すと通告した。
本島と離島・宮古島の温度差。宮古方言で「ヌーマピラス」と呼ばれた競馬も本島とは性格が異なる。
娯楽的な色彩はなかった。
宮古島は平坦地が比較的多く、馬が最も警戒するハブ(馬は微量の蛇毒で絶命)も生息していないため
馬産に適しており、王朝時代から沖縄最大の馬供給地になっていた。
1653年から琉球王府の江戸上り(慶賀使、謝恩使派遣)が始まると、宮古上布とともに宮古馬も献上させた。
その献上馬の選定会が競馬だった。
献上先は首里王府、薩摩藩に加えて徳川将軍家である。
記録には残っていないが、よほど精錬された走りが求められたのだろう。
明治から昭和初期の宮古競馬は鏡原に加えて友寄、宮国、新里、与那覇、友利、福里、新城、比嘉の馬場でも行われたが、
ムチを振るうと失格になったという。本島にはそこまで厳格な決まりはない。
「水の入った茶碗を騎手の手のひらにのせて走らせても、水がこぼれなかったという。
乗る人に震動を感じさせない絶妙な走法」(宮古研究第4号・宮古の在来馬)
という宮古競馬は王朝時代の精錬された献上馬選定の名残りである。
そんな献上馬の安定供給を図るため、琉球王府は常駐した御目利(馬役人)に馬帳(馬の居住台帳)を提出させ、
生死も毎年届け出を命じる徹底した管理ぶりだった。