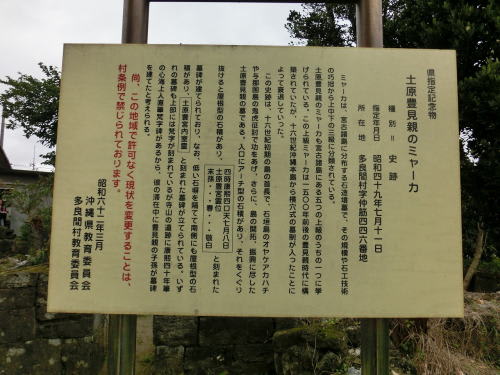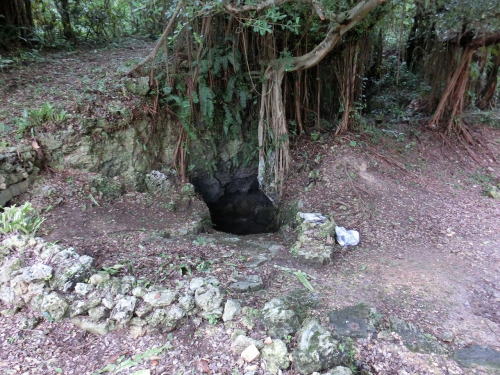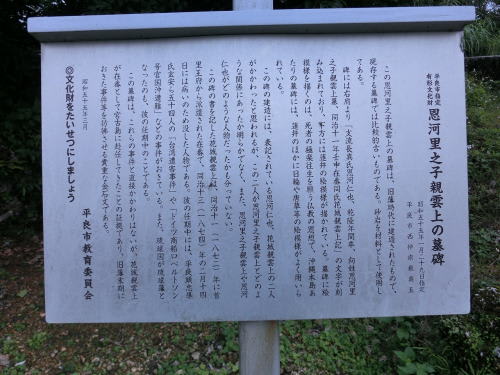伊江島のゴヘズ洞穴遺跡
Cave Gohezu of Ie island
( 県指定史跡 )
Prefectural Historical Monument
指定年月日 : 昭和 52 ( 1977 ) 年5月9日
Designaed Date : May 9,1977
所在地 : 沖縄県国頭郡伊江村字 西江上 ゴヘズ原
Location : Nishieue ,Ie-son,Kunigami-gun,Okinawa-ken
伊江島のゴヘズ洞穴遺跡は、伊江島のほぼ中央に位置する通称ゴヘズ山(高さ約82m)と呼ばれる
山の琉球石灰岩洞穴内にある遺跡である。
洞穴の入り口は一辺がおよそ2.5mの三角形状の縦穴になっており、
地表下約3.8mで広い床面に達する。
床面は北側へ約19m延びた主洞を形成しており、更に下方へ細く延びた下洞がある。
多量の鹿の化石が洞穴内で出土しており、
数少ない沖縄の旧石器時代遺跡の中でも、遺物の出土の豊富なことと、
保存が良好なことで他に例をみない貴重な遺跡である。
The site is located in a Ryukyuan limestone cave at a mountain known as Gohezu
( about 82m. high ) which is a the central part of the Ie island.
The entrance of the cave is a triangle pit with a 2.5m.
side, and the floor is at 3.8m. below ground.
The floow stretches 19m. to the north to form a main part, and goes further to a narrow paet.
Many fossil deers are found in the cave. It is a matchless site among a few remains of Old Stone
Age because it is rich in archaeological articles which are in a good condition.