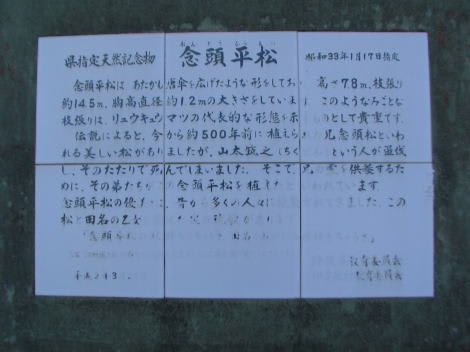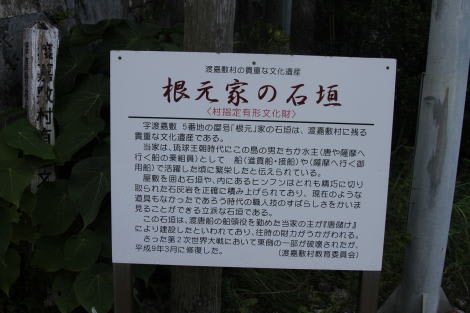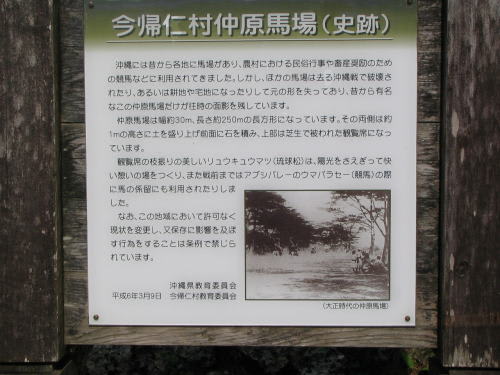大山貝塚
Oyama Shell Mound
( 国指定史跡 )
National Historical Monument
指定年月日 : 昭和 47 ( 1972 ) 年5月15日
Designaed Date : May 15,1972
所在地 : 沖縄県宜野湾市大山富盛原
Location : Oyama,Ginowan-shi,Okinawa-ken
大山貝塚は、国道58号線沿いの大山の南北に延びる
標高70m前後の琉球石灰岩丘陵上に位置する貝塚である。
近くにはミシュクムイと呼ばれる大山集落の拝所があり、
拝所の周辺に数基の岩陰墓が残っている。
1958年に発掘調査が行われ、沖縄の考古学調査で
層位学的に土器編年が行われた学史上も貴重な遺跡である。
貝塚内に堆積している黒色の土から土器、石器、
骨製品、貝殻、魚骨などが出土している。
特に深鉢の器形の土器は大山式土器と呼ばれ、
貝塚の時期を決める際の指標となっている。
The shell mound is located on a Ryukyuan limestone hill which is approx.70m.
above sea level and stretches north and south at Oyama and National Highway
58.
There is a sacred place of Oyama village called Misukumui and several rock
shelter graves nearby. As excavation was conducted in 1958.
This shell mound is significant because the chronological sequence research
on is
pottery was done stratigraphically by Okinawan archaeological investigation.