
時代劇の最大の見せ場は殺陣。テレビ時代劇でよくあるパターンとして、悪党どもが集まって悪だくみをしているところへ主役が颯爽と登場し、決めゼリフを決めて雑魚どもをバッタバッタと斬り倒し、最後に悪党の親玉を斬るというパターン。
決めゼリフの中でも特に有名なのが、高橋英樹主演『桃太郎侍』のセリフでしょう。
【ひとつ人の世生き血を啜り、ふたつ不埒な悪行三昧。みっつ醜い浮世の鬼を、退治てくれよう桃太郎】
よくできた数え歌です。そしてもう一つ有名なのが、里見浩太朗先生主演による『長七郎江戸日記』の決めゼリフ。
【俺の名前は引導がわりだ、迷わず地獄へ堕ちるがよい】
里見先生演じる松平長七郎長頼は、三代将軍徳川家光の弟で、将軍継嗣争いに敗れ切腹した、駿河大納言忠長卿の忘れ形見なんです。つまり将軍家の血筋。
その名を聴いても改心せず悪足掻きをするならば、止むを得ん、もはやこれまで。斬る!
そういう意味合いが込められている、よくできたセリフです。
ところで、こういう殺陣シーンの場合、主役は一人で何十人という敵を相手にします。
何十人もの敵を一人で相手にして、勝てるわけないじゃない⁉だから時代劇なんて嘘だ‼なんて声が聞こえてきそうですが、
いやいや、これがそうでもないのですよ。
俳優の宇梶剛士さんは、若い頃日本最大の暴走族「ブラックエンペラー」の名誉総長だった人物。その喧嘩の強さは伝説的だったらしい。
中でも、数百人対一人の喧嘩に勝ったという話は強烈です。宇梶さんによれば、数百人といっても全員を相手にする必要はないそうです。敵が何百人いようとも決してひるまず、静かに敵と対峙する。そしてここだというときに一歩前へ出る。
そうすると、宇梶さんの「気」に押されるように、敵が後ずさったそうです。そのうち緊張に耐えかねた敵の一人が角材を振り上げて襲ってきた。この角材を宇梶さんは余裕で取り上げ、5,6人の敵を返り討ちにします。
このことがきっかけで、恐怖が数百人全員に伝染していき、その数百人が一斉に逃げ出してしまった。宇梶さんはわずか5、6人を倒しただけで、対数百人の喧嘩に勝ったわけです。
先日紹介した宮本武蔵対吉岡一門の果し合いにしても、武蔵は敵の大将を最初に打ち取ってしまうことで、敵に敗北感を味合わせたわけです。あとはとっとと逃げるだけ、全員を相手にしなくても、勝負には勝っている。
だから桃太郎にしても長七郎にしても、本当は悪の親玉を最初に倒しちゃえば、余計な雑魚さんたちを斬る必要はなくなるわけですが、そこは様式美の世界ですから、親玉は最後に斬るという約束事が決まってる。
それでも往年の時代劇スターさんたちは、様式美の見せ方がうまかった。例えば後ろに敵がいたとしても、斬りこめない「気」を発しているように見せることができた。
宇梶さんの例にあるように、こちらの発する「気」が相手の「気」を上回っていれば、文字通り相手は「気圧されて」しまうわけです。だから後ろから斬りかかろうにも、「気」に圧倒されて動けなくなってしまう。
往年の時代劇スターさんは、そういうことの見せ方がうまかった。だから様式美の中に迫力があった。
様式美というのは「上手く」ないと面白く見せることができません。ヘタな役者が様式美の上っ面だけを真似ても、まるでリアリティのないつまらないものになってしまう。
時代劇がつまらなくなった原因の一つが、ここにある。
今、CS時代劇専門チャンネルを見れば、往年の里見先生や英樹さんの雄姿を見ることができます。この方々はやっぱり、様式美の見せ方がうまいですね。良い時代でした。
今回の表題のセリフは、そんな時代劇が一番良かった時代を想起させる、
ちょっと切ない、セリフです。












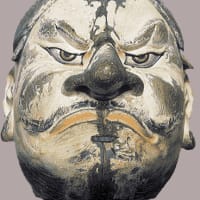







なんていうか…、タイトルに「日記」とあるように、ものすごく明るい日常的な作りで、うう〜ん、言わば「陰」の要素がまったく感じられなかった…。
ひたすらカラッと明るくて、暗さだけでなく湿り気もなくて…。
昭和の終焉の頃、演歌がそうなってしまったのと同じように、時代劇も陰を全部排除してしまって辿り着いたのがこれだったみたいなものを感じてしまいましたね…。
そして、意識的に見るのをやめていってしまった…。
要するに、時代劇と「気が合わなく」なってしまったんです…。
数年後に「鬼平」だけは復活したけど、「暴れ坊」含め、本当に当時の「誰からもクレームが来ないように」作られたカラッと明るい時代劇な肌に「合わな」かった…。
日本の時代劇は、完全に衰退してしまったと思います。
ただ、アメリカも西部劇は衰退した。
特に「インディアン」と戦う時代劇は、それこそ人権問題でもう二度と作れないでしょうね…。
西部劇でありながら、白人しか出てこないマカロ二・ウェスタン風のものをやるしかない。
ジョン・ウェインの「駅馬車」なんて、疾走する馬で奇襲をかけてくるインディアンを「怖い!」と本気で思うからこそ成り立つ映画で…。
私は10年くらい前に初めて見て、インディアンもただ侵略されただけじゃなく、こんなに本気で粛々と対抗して戦っていたんだと、こんなに強かったんだとびっくりしたくらいです。
でもそのうちアメリカでは、「駅馬車」は発売禁止になるかもしれないし、「駅馬車」を見るような人は白眼視されるようになるかも。
映画に対しても現代のりベラリティで、過去を裁くようになるかもしれない。
「インディアン」の土地を略奪したアメリカ人の末裔たちは、黒人奴隷を使っていた白人たちは、これからどうすればいいんでしょうね…。
今の人権で自分たちを裁く正しいやり方ってなんなんでしょう…。
話が脱線しちゃってスミマセン💧
何はともあれ、時代劇の衰退は本当に悲しいですね…。
こないだ「のぼうの城」を、15分くらいでギブアップしました…。
でも60〜70年代の時代劇なら大好き!ってワケでもないの…。(^_^;)
まあ、好みはいろいろですね。
典型的なのが必殺シリーズで、初期の『必殺仕置人』などを見ていると、実に悲惨で残酷な話が多い。怨みの度合い、深さというものがトンデモナイ‼今のテレビじゃ絶対できないレベルです。これが80年代になって方向転換し、軽薄短小な時代の風潮に見事に乗っかっていった。或る意味大したものです。
69年から放送された、松本白鸚(吉右衛門さんのお父さん)主演の『鬼平犯科帳』などは、吉右衛門版のような四季折々の風趣だとか、江戸情緒といったものがほとんど描かれない、人情の機微を細かく描いた人間ドラマである吉右衛門版とは違い、盗賊と火盗改との対決をスリリングに描いた、ハードボイルド・タッチなんです。白鸚さん演じる鬼平は、吉右衛門さんより厳しさが協調されてる。吉右衛門版をイメージして白鸚版を見ると、あまりの違いに戸惑います。
そういうものが求められていた時代だったのでしょうね。
『長七郎江戸日記』は80年代の時代劇ですから、時代の風潮に合わせた明るい時代劇でした。でも「ちゃんとした」時代劇を作ろうというスタッフなり出演者なりの意欲が充実していた作品でしたから、時代劇のレベルとしては、そんなに低いものではないです。なんといっても里見先生の舞いを舞っているような、優美で尚且つ力強い殺陣は素晴らしかった。あんな殺陣が出来る方、今はいませんねえ。
鬼平も終わってしまって、もうホントに、見るべき時代劇がない!大河ドラマは時代劇とはちょっと違うんだよなあ。高橋一生は良い演技してたけど、柳楽優弥のやる気があるのかないのかわからないような演技は苦手だ!
いや、それはどうでもいいんですが……良い時代劇が見たいですね。
人生は本当に、何がどう影響するか分かりませんね…。
子役って、成人した後にちゃんと売れてから、「えっ! あの作品の男の子、あなただったの!?」みたいなノリが一番幸せなような気がします。
時代劇、復活するか、完全に衰退か…。
どうなんでしょうね…。
太秦の衣装部とか、今どうなっているんだろう…。
結局コンテンポラリーに制作されなければ、小道具会社とかもやっていけなくなるし…。
映画会社はあとどのくらいの期間、倉庫に保存しとおいてくれるんでしょうね…。