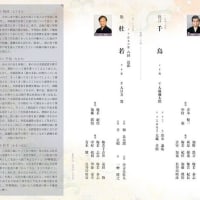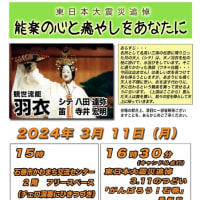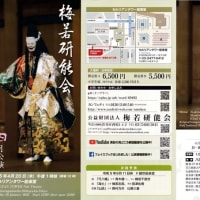地謡「在原の。跡な隔てそ杜若。跡な隔てそ杜若。沢辺の水の浅からず。契りし人も八橋の蜘蛛手に物ぞ思はるゝ。今とても旅人に。昔を語る今日の暮やがて馴れぬる。心かなやがて馴れぬる心かな。
地謡の初同上歌のシテの所作は定型で、「沢辺の水の」と右ウケしてから正面に出てヒラキ。唐織の着流しの姿なので動作はごく控え目です。「今とても旅人に」とワキへ向き、それから左に小さく廻りシテ柱にて正面へヒラキ。少々型が忙しく雰囲気が壊れそうなので ぬえはこのヒラキはしないつもり。上歌のトメにすぐワキへの言葉がありますので地謡の終わりにワキに向きます。
シテ「いかに申すべき事の候。
ワキ「何事にて候ぞ。
シテ「見苦しく候へども。わらはが庵にて一夜を御明し候へ。
ワキ「心得申し候。
能「江口」では世捨て人である西行に遊女が宿を貸さなかったことから人の六根が作る罪のために輪廻に迷うところにまで話が及び、遊女がじつは普賢菩薩であった、と逆転的な昇華を遂げるという、哲学的で壮大な物語に展開するのに比べて、「杜若」では あっさりと若い女性が僧を宿に誘い、僧も屈託なく承知しますね。なんだか違和感が残る問答なのではありますが、シテが人間の女性ではなく草木の精だから宿を貸すこともあまり問題にならないのかもしれません。
ここでシテは後見座にクツロギ「物着」となります。唐織を脱ぎ(ヌードにしないように、先に長絹を羽織らせてその下から唐織を引き抜きます)、長絹を羽織り、初冠を着けるという手順で、普通ならばそれほど難易度は高くありませんが、小書「恋之舞」になるとさらに初冠に「日陰之糸」を着け眞之太刀を刷くので大変になります。いずれにせよ物着のあとは長絹の下に縫箔を腰巻に着るので、これは最初から唐織の下に着込んでいます。なお「物着」の間、大小鼓と笛がアシライを打って(吹いて)くださいますが、これはシテが女性の役の場合に限ります。男性の役の「物着」ではアシライがないので無音で着替えをするわけで、後見にとってはお客さまの注目を浴びやすい分だけやりにくいかも。
物着が出来上がってシテは立ち上がり再びシテ柱先まで出ると大小鼓は「ヲキ」を打ってアシライを止め、その間にシテはワキに向いて「ヲキ」を聞いて謡い出します。
シテ「なうなうこの冠唐衣御覧候へ。
二度目の「なうなう」。これが二度あるのは珍しいですが「杜若」に限ったことでもありません。もちろん二度の「なうなう」はおのずと意味合いやシテのキャラクターが異なることになり、「杜若」では豪華な衣裳を誇るように光り輝くように謡うのが似つかわしいですね。シテは謡いながら衣裳をワキに見せるように両袖をあしらう「ヨセイ」という型をします。
ワキ「不思議やな賎しき賎の臥処より。色も輝く衣を着。透額の冠を着し。これを見よと承るは。何と言ひたる事やらん。
シテ「これこそこの歌に詠まれたる唐衣。高子の后の御衣にて候へ。またこの冠は業平の。豊の明の五節の舞の冠なれば。形見の冠唐衣。身に添へ持ちて候なり。
当然のごときワキ僧の疑問に対してシテの答えは二条の后と呼ばれた藤原高子(本来の読みは たかいこ)の衣裳であり、業平の冠であり、それぞれを形見として持っているのだ、と答えます。怪しい。
能「杜若」はこの物着まではごく自然な展開で、むしろ大きな事件や伏線もなく素直な能だと言えると思いますが、物着のあとは現代人からすると『伊勢物語』の理解が根本から覆されるような不思議な世界が次から次へと展開されて目が回りそう。
まずはこの「形見の冠唐衣」に続くシテの主張を読んでみましょう。
ワキ「冠唐衣はまづまづ措きぬ。さてさて御身は如何なる人ぞ。
シテ「まことは我は杜若の精なり。植ゑおきし昔の宿の杜若と。詠みしも女の杜若になりし謂れの言葉なり。また業平は極楽の。歌舞の菩薩の化現なれば。詠みおく和歌の言の葉までも。皆法身説法の妙文なれば。草木までも露の恵みの。仏果の縁を弔ふなり。
シテは自分のことを「杜若の精」とはっきり名乗っています。それは当然『伊勢物語』の9段の「唐衣着つゝ馴れにし」の歌に詠まれた杜若であり、その花が今人間の姿を借りて現れたのは、業平その人かあるいは彼が詠んだこの歌との関係が原因なのだろうと推測はできますね。
ところが ぬえにとって疑問なのは、その業平と杜若の関係はいわば一期一会の出会いのはずであって、とても彼から「形見」として冠をもらうほどの深い関係。。恋人のようなものではないはずだ、ということです。
考えてみればこの「杜若」のシテの扮装は、能「井筒」とまったく同じ出で立ちで、それは能の愛好者としては見慣れている姿でありながら、じつは女性の役でありながら男性の衣裳を着ている、というかなり異形の扮装です。しかし「井筒」のシテは業平の妻(とされている)紀有常の娘であり、彼女が「夫」の形見を持っているのは当然であり、彼女が男の扮装をするのもまた、愛する男との生活を懐かしんで、男の形見を身に着けることで一体化しようとした、と理解することが十分に可能です。
これは類例の「松風」「富士太鼓」「梅枝」でもまったく同じで、これらの能で女性のシテが男装をするのは、すべて失った恋人や夫が残した形見なのであり、それを身に着けるのはその愛する人と一体になりたい、という強い思慕のために他なりません。
これに対して「杜若」のシテと冠の持ち主である業平との関係は、たまたまある日に業平が詠んだ和歌のモチーフとなったに過ぎず、彼女は業平の恋人ではありません。そもそも人間でさえないのだから。
その上「井筒」ほかの上掲の能と「杜若」と決定的に違う点は、冠は業平の形見でありながら衣裳はまったく別の人間。。二条の后と呼ばれた藤原高子のそれなのであり、それは業平の恋人とされ、「唐衣」の歌で彼が思慕した相手のものだ、と言うのです。杜若の精であるシテにとって高子は面識さえないはずであり、唯一の接点は「唐衣」の歌で杜若がモチーフになり、その歌が高子を思って詠まれた、という一点だけなのです。杜若の精が遠く離れた都に住んでいた高子の衣裳を「形見」として賜る理由はありません。
これら、「杜若」のシテの性格およびその扮装には大いに疑問が生じますが、その疑問を解消するために、次にシテが語る業平の「本性」について注目する必要がありそうです。 (続く)
地謡の初同上歌のシテの所作は定型で、「沢辺の水の」と右ウケしてから正面に出てヒラキ。唐織の着流しの姿なので動作はごく控え目です。「今とても旅人に」とワキへ向き、それから左に小さく廻りシテ柱にて正面へヒラキ。少々型が忙しく雰囲気が壊れそうなので ぬえはこのヒラキはしないつもり。上歌のトメにすぐワキへの言葉がありますので地謡の終わりにワキに向きます。
シテ「いかに申すべき事の候。
ワキ「何事にて候ぞ。
シテ「見苦しく候へども。わらはが庵にて一夜を御明し候へ。
ワキ「心得申し候。
能「江口」では世捨て人である西行に遊女が宿を貸さなかったことから人の六根が作る罪のために輪廻に迷うところにまで話が及び、遊女がじつは普賢菩薩であった、と逆転的な昇華を遂げるという、哲学的で壮大な物語に展開するのに比べて、「杜若」では あっさりと若い女性が僧を宿に誘い、僧も屈託なく承知しますね。なんだか違和感が残る問答なのではありますが、シテが人間の女性ではなく草木の精だから宿を貸すこともあまり問題にならないのかもしれません。
ここでシテは後見座にクツロギ「物着」となります。唐織を脱ぎ(ヌードにしないように、先に長絹を羽織らせてその下から唐織を引き抜きます)、長絹を羽織り、初冠を着けるという手順で、普通ならばそれほど難易度は高くありませんが、小書「恋之舞」になるとさらに初冠に「日陰之糸」を着け眞之太刀を刷くので大変になります。いずれにせよ物着のあとは長絹の下に縫箔を腰巻に着るので、これは最初から唐織の下に着込んでいます。なお「物着」の間、大小鼓と笛がアシライを打って(吹いて)くださいますが、これはシテが女性の役の場合に限ります。男性の役の「物着」ではアシライがないので無音で着替えをするわけで、後見にとってはお客さまの注目を浴びやすい分だけやりにくいかも。
物着が出来上がってシテは立ち上がり再びシテ柱先まで出ると大小鼓は「ヲキ」を打ってアシライを止め、その間にシテはワキに向いて「ヲキ」を聞いて謡い出します。
シテ「なうなうこの冠唐衣御覧候へ。
二度目の「なうなう」。これが二度あるのは珍しいですが「杜若」に限ったことでもありません。もちろん二度の「なうなう」はおのずと意味合いやシテのキャラクターが異なることになり、「杜若」では豪華な衣裳を誇るように光り輝くように謡うのが似つかわしいですね。シテは謡いながら衣裳をワキに見せるように両袖をあしらう「ヨセイ」という型をします。
ワキ「不思議やな賎しき賎の臥処より。色も輝く衣を着。透額の冠を着し。これを見よと承るは。何と言ひたる事やらん。
シテ「これこそこの歌に詠まれたる唐衣。高子の后の御衣にて候へ。またこの冠は業平の。豊の明の五節の舞の冠なれば。形見の冠唐衣。身に添へ持ちて候なり。
当然のごときワキ僧の疑問に対してシテの答えは二条の后と呼ばれた藤原高子(本来の読みは たかいこ)の衣裳であり、業平の冠であり、それぞれを形見として持っているのだ、と答えます。怪しい。
能「杜若」はこの物着まではごく自然な展開で、むしろ大きな事件や伏線もなく素直な能だと言えると思いますが、物着のあとは現代人からすると『伊勢物語』の理解が根本から覆されるような不思議な世界が次から次へと展開されて目が回りそう。
まずはこの「形見の冠唐衣」に続くシテの主張を読んでみましょう。
ワキ「冠唐衣はまづまづ措きぬ。さてさて御身は如何なる人ぞ。
シテ「まことは我は杜若の精なり。植ゑおきし昔の宿の杜若と。詠みしも女の杜若になりし謂れの言葉なり。また業平は極楽の。歌舞の菩薩の化現なれば。詠みおく和歌の言の葉までも。皆法身説法の妙文なれば。草木までも露の恵みの。仏果の縁を弔ふなり。
シテは自分のことを「杜若の精」とはっきり名乗っています。それは当然『伊勢物語』の9段の「唐衣着つゝ馴れにし」の歌に詠まれた杜若であり、その花が今人間の姿を借りて現れたのは、業平その人かあるいは彼が詠んだこの歌との関係が原因なのだろうと推測はできますね。
ところが ぬえにとって疑問なのは、その業平と杜若の関係はいわば一期一会の出会いのはずであって、とても彼から「形見」として冠をもらうほどの深い関係。。恋人のようなものではないはずだ、ということです。
考えてみればこの「杜若」のシテの扮装は、能「井筒」とまったく同じ出で立ちで、それは能の愛好者としては見慣れている姿でありながら、じつは女性の役でありながら男性の衣裳を着ている、というかなり異形の扮装です。しかし「井筒」のシテは業平の妻(とされている)紀有常の娘であり、彼女が「夫」の形見を持っているのは当然であり、彼女が男の扮装をするのもまた、愛する男との生活を懐かしんで、男の形見を身に着けることで一体化しようとした、と理解することが十分に可能です。
これは類例の「松風」「富士太鼓」「梅枝」でもまったく同じで、これらの能で女性のシテが男装をするのは、すべて失った恋人や夫が残した形見なのであり、それを身に着けるのはその愛する人と一体になりたい、という強い思慕のために他なりません。
これに対して「杜若」のシテと冠の持ち主である業平との関係は、たまたまある日に業平が詠んだ和歌のモチーフとなったに過ぎず、彼女は業平の恋人ではありません。そもそも人間でさえないのだから。
その上「井筒」ほかの上掲の能と「杜若」と決定的に違う点は、冠は業平の形見でありながら衣裳はまったく別の人間。。二条の后と呼ばれた藤原高子のそれなのであり、それは業平の恋人とされ、「唐衣」の歌で彼が思慕した相手のものだ、と言うのです。杜若の精であるシテにとって高子は面識さえないはずであり、唯一の接点は「唐衣」の歌で杜若がモチーフになり、その歌が高子を思って詠まれた、という一点だけなのです。杜若の精が遠く離れた都に住んでいた高子の衣裳を「形見」として賜る理由はありません。
これら、「杜若」のシテの性格およびその扮装には大いに疑問が生じますが、その疑問を解消するために、次にシテが語る業平の「本性」について注目する必要がありそうです。 (続く)