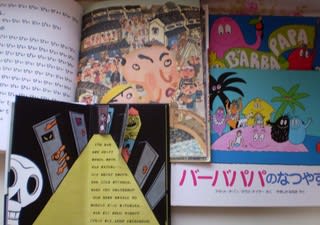最近は教室の仕事が忙しくて
めったにしていないのですが…
私は乳幼児を預かる有料ボランティアをしています。

そうしてお預かりする乳幼児さんのなかに
発達の遅れが疑われる子が 時々いるのです。
私は そうした診断をくだす専門家ではないので
はっきりしたことは言えないのですが
ていねいに「子どもの言動」を観察していると
さらに引っかかるところが増えてきます。

以前 お預かりした2歳の女の子は
お母さんや人と目が合わず 言葉も「ママ」「まんま」「あーとう」の3語でした。指差しはなく 「ママ」がお母さんを意味しているとは 気づいていませんでした。
預かっている間 回転椅子や家具に しじゅう よじ登ろうとし
おもちゃで遊ぶ姿は見られませんでした。
何度かお預かりするうちに
その子が 私といっしょに遊ぶことには 全く興味をしるさず
家具の取っ手をぺろぺろなめていることや
ぬいぐるみの目を嫌がって
悲鳴のような声で泣き続けることも気にかかりました。
そこで その子を預かる際
お迎えにいっている保育園の担任と園長先生に相談してみました。
すると 担任の先生は 「このくらいの言葉の子は 他にもいる…心配ない…」という判断でした。
が 園長先生は よく私の説明を聞いてくださって
「よく観察していてください。気になるところが たくさんあります。」と真剣な声で おっしゃいました。
私は よく考えた上で その子のお母さんに
保健センターで開かれている
「少し言葉の遅れのある子を対象としたグループレッスン」を
紹介してみました。
しかし それはその子のお母さんの強い反発を招く結果
となりました。

そのまま音信不通となってしまいました。
気がかり…くらいのうちに
早期療育を始めるのが一番…と思いつつも
伝える難しさを感じました。


一方 その1年前ほどにお預かりしていた
1歳後半の男の子は
お母さんに抱かれると反り返る
人への興味が薄い点は気になったものの
公園に連れて行くと
時折 こっちを見てにっこりするなど安心できる一面もありました。

ただ パニックを起こすと手のつけようがなく
頭をがんがん地面や壁に
打ち付けそうになるので
ひやひやすることの連続ではありました。

その子のお母さんは 発達障害とまでは考えが至らなかったものの
その子の育てにくさに 困惑気味でした。
私は その子のかわいらしい一面を言葉にしながら
「心配いりませんよ。」と繰り返して
励ますだけでした。
当時の私は その子がかわいくてならなくて
自分の中に「問題のない健康な子」としてその子を見たがる
<客観的になれない部分 >
>
を持っていました。
しかし
実際は
その男の子の発達には
見過ごすことの出来ない気になる問題が 多々ありました。

それなのに
「心配いりませんよ。」という言葉が
はたしてよかったのか?
私の言葉のせいで その子の療育が遅れたのではないか…
後悔しきりです。

でも 気になる点を並べたところで
不安を煽ったり 反発を招いただけだったのかも
しれませんが…。
2歳前後といえば
まだまだ グレーな時期。
ただ ちょっと成長がゆっくりだったり 個性が強いだけなのか?
発達障害を持っているのか?
専門家でも 判断に悩むのではないでしょうか?
今朝 晴れた日の青空みたいに のブログにうかがったら
1歳8ヶ月検診の様子が
マンガで わかりやすく描かれていました。
それを読んで 再び 発達が気になる子に出会ったとき
どうしたらいいんだろう…ともんもんと
考え込んでしまいました。
きっと こうだといい!という簡単な答えはなくて
ひとつのケースごとに
真剣に考えて 行動しなきゃならないんだろうな…とも思いました。
このブログは 自閉症というハンディーを持った 6歳の息子『青』くんの
成長が プロ級の(プロ?かも)マンガで描かれています。
きっと 来年は出版化されるんじゃないか…と
勝手に思っています。
ぜひ ぜひ 遊びに行ってみてくださいね。

web拍手を送る
めったにしていないのですが…
私は乳幼児を預かる有料ボランティアをしています。

そうしてお預かりする乳幼児さんのなかに
発達の遅れが疑われる子が 時々いるのです。
私は そうした診断をくだす専門家ではないので
はっきりしたことは言えないのですが
ていねいに「子どもの言動」を観察していると
さらに引っかかるところが増えてきます。

以前 お預かりした2歳の女の子は
お母さんや人と目が合わず 言葉も「ママ」「まんま」「あーとう」の3語でした。指差しはなく 「ママ」がお母さんを意味しているとは 気づいていませんでした。
預かっている間 回転椅子や家具に しじゅう よじ登ろうとし
おもちゃで遊ぶ姿は見られませんでした。
何度かお預かりするうちに
その子が 私といっしょに遊ぶことには 全く興味をしるさず
家具の取っ手をぺろぺろなめていることや
ぬいぐるみの目を嫌がって
悲鳴のような声で泣き続けることも気にかかりました。

そこで その子を預かる際
お迎えにいっている保育園の担任と園長先生に相談してみました。
すると 担任の先生は 「このくらいの言葉の子は 他にもいる…心配ない…」という判断でした。
が 園長先生は よく私の説明を聞いてくださって
「よく観察していてください。気になるところが たくさんあります。」と真剣な声で おっしゃいました。
私は よく考えた上で その子のお母さんに
保健センターで開かれている
「少し言葉の遅れのある子を対象としたグループレッスン」を
紹介してみました。
しかし それはその子のお母さんの強い反発を招く結果
となりました。

そのまま音信不通となってしまいました。
気がかり…くらいのうちに
早期療育を始めるのが一番…と思いつつも
伝える難しさを感じました。


一方 その1年前ほどにお預かりしていた
1歳後半の男の子は
お母さんに抱かれると反り返る
人への興味が薄い点は気になったものの
公園に連れて行くと
時折 こっちを見てにっこりするなど安心できる一面もありました。

ただ パニックを起こすと手のつけようがなく
頭をがんがん地面や壁に
打ち付けそうになるので
ひやひやすることの連続ではありました。

その子のお母さんは 発達障害とまでは考えが至らなかったものの
その子の育てにくさに 困惑気味でした。
私は その子のかわいらしい一面を言葉にしながら
「心配いりませんよ。」と繰り返して
励ますだけでした。
当時の私は その子がかわいくてならなくて

自分の中に「問題のない健康な子」としてその子を見たがる
<客観的になれない部分
 >
>を持っていました。
しかし
実際は
その男の子の発達には
見過ごすことの出来ない気になる問題が 多々ありました。

それなのに
「心配いりませんよ。」という言葉が
はたしてよかったのか?
私の言葉のせいで その子の療育が遅れたのではないか…
後悔しきりです。

でも 気になる点を並べたところで
不安を煽ったり 反発を招いただけだったのかも
しれませんが…。
2歳前後といえば
まだまだ グレーな時期。
ただ ちょっと成長がゆっくりだったり 個性が強いだけなのか?
発達障害を持っているのか?
専門家でも 判断に悩むのではないでしょうか?
今朝 晴れた日の青空みたいに のブログにうかがったら
1歳8ヶ月検診の様子が
マンガで わかりやすく描かれていました。
それを読んで 再び 発達が気になる子に出会ったとき
どうしたらいいんだろう…ともんもんと
考え込んでしまいました。
きっと こうだといい!という簡単な答えはなくて
ひとつのケースごとに
真剣に考えて 行動しなきゃならないんだろうな…とも思いました。
このブログは 自閉症というハンディーを持った 6歳の息子『青』くんの
成長が プロ級の(プロ?かも)マンガで描かれています。
きっと 来年は出版化されるんじゃないか…と
勝手に思っています。
ぜひ ぜひ 遊びに行ってみてくださいね。
web拍手を送る















 をまねくことが多いのです。
をまねくことが多いのです。

 のを待ちました。
のを待ちました。







 大きなハンバーガー何に使っているかというと
大きなハンバーガー何に使っているかというと 小さなハンバーガー10個と交換しています。
小さなハンバーガー10個と交換しています。











 引用…逸話は「こころのチキンスープ」 ジャック・キャンフィールド ダイヤモンド社 先生の話は「こころのチキンスープ2」
引用…逸話は「こころのチキンスープ」 ジャック・キャンフィールド ダイヤモンド社 先生の話は「こころのチキンスープ2」 
 という安さで
という安さで できれば
できれば