5歳になったふたごちゃん。
4歳の時に比べて、ずいぶん成長したように思えます。
どこが変わったかと言えば、何か欲求があるときは、
こちらの目を見て話せるようになったことです。
本当によく目が合うようになりました。
相手の目を見て話す
は、自然に身についたものではなくて、ふたごちゃんのお母さんの努力の
たまものです。
ふたごちゃんは、壁や家具に視線を注いだまま、
「お母さん、○○~!!」と欲しいもの(ジュースなど)を欲求していました。
ふたごちゃんのお母さんはそういうときは、
すぐに聞いてあげたいのをぐっと我慢して、知らんふりして、
きちんと目を見て言えたときに
要求をかなえてあげていました。
(ヒントを与えて、目をみるようにうながします)
そうやって繰り返し学習する中で、
声を出す時に相手の目を見る
ということができるようになってきました。
そして、人の目を見て、欲求を出すようになったことで、
コミュニケーションの質が上がり、
他にもさまざまなことを学べるようになってきました。
ふたごちゃんのひとり… ちゃんは、人への興味が高まり、
ちゃんは、人への興味が高まり、
小学生のお兄ちゃんに引っ付いて回り、
さまざまなまねっこをするようになりました。
そのため、かつてついていた診断名が
少し軽いものになったそうです。
次回に続きます♪

web拍手を送る
4歳の時に比べて、ずいぶん成長したように思えます。
どこが変わったかと言えば、何か欲求があるときは、
こちらの目を見て話せるようになったことです。
本当によく目が合うようになりました。
相手の目を見て話す
は、自然に身についたものではなくて、ふたごちゃんのお母さんの努力の
たまものです。
ふたごちゃんは、壁や家具に視線を注いだまま、
「お母さん、○○~!!」と欲しいもの(ジュースなど)を欲求していました。
ふたごちゃんのお母さんはそういうときは、
すぐに聞いてあげたいのをぐっと我慢して、知らんふりして、
きちんと目を見て言えたときに
要求をかなえてあげていました。
(ヒントを与えて、目をみるようにうながします)
そうやって繰り返し学習する中で、
声を出す時に相手の目を見る
ということができるようになってきました。
そして、人の目を見て、欲求を出すようになったことで、
コミュニケーションの質が上がり、
他にもさまざまなことを学べるようになってきました。
ふたごちゃんのひとり…
 ちゃんは、人への興味が高まり、
ちゃんは、人への興味が高まり、小学生のお兄ちゃんに引っ付いて回り、
さまざまなまねっこをするようになりました。
そのため、かつてついていた診断名が
少し軽いものになったそうです。
次回に続きます♪
web拍手を送る












 ちゃんが、
ちゃんが、 ちゃんは物を見分ける力が高そうだなと感じました。
ちゃんは物を見分ける力が高そうだなと感じました。 ちゃんだけだったのですが、
ちゃんだけだったのですが、 ちゃんはルールがわからず、途中でリタイアしたものの、カードを
ちゃんはルールがわからず、途中でリタイアしたものの、カードを ちゃんは、「しっかり見る」のは少し苦手なようで、
ちゃんは、「しっかり見る」のは少し苦手なようで、 ちゃんにも
ちゃんにも
 ちゃん、
ちゃん、
 簡単なやりとりでもいいので、
簡単なやりとりでもいいので、




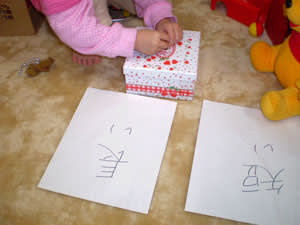





 目と目が合うことが少なく
目と目が合うことが少なく 声をかけても聞いていない場合がよくあり
声をかけても聞いていない場合がよくあり













 引っ張ってしまって 悪いのですが
引っ張ってしまって 悪いのですが







