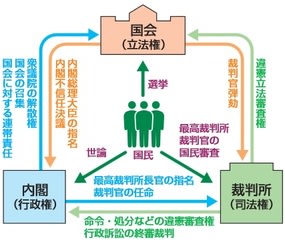第204回国会の内閣提出法律案は、最終的に63本でした。
うち、本則で3本以上の法律案を束ねた内閣提出法案は、実に26本にも上ります。
技術的に束ねざるを得ない改正法案があるのは事実ですし、束ね法案が一概によろしくない、というわけではありません。
ただ、複数の法律を改正等しようとするときにこれらを束ねて一本の法律案として国会に提出する「束ね法案」は、法律案を束ねることによって国会審議の形骸化を招来するとともに、国会議員の表決権を侵害しかねないものです。
また、どの法律がどのように改正されるのか等が国民に分かりづらくなり、適切な情報公開とはならないおそれもあります。
これらは、このブログにおいても何度も指摘してきたことです。
今次常会は、とにかく束ね法案の割合が高いと言わざるを得ません。今次常会の閣法の本数を絞るために、束ね法案を多用したのではないかと考えざるを得ない状況でもあります。
束ね法案の立案作業においては、複数の法律案の立案作業を同時並行で行わなければならず、改正内容も幅広く、合議等を必要とする組織体が多岐にわたることも少なくありません。
このため、束ね法案の立案作業は、一般に、束ねる法律案の本数が多ければ多いほど、従事する職員に負荷がかかることになり、また、日程の余裕が失われることになると考えます。
事実、今次常会では、特に束ね法案において条文誤りや参考資料の誤りが続発したのです。この点については、別途書きたいと思います。
今次常会の束ね法案について、とにかく束ねた本数が多いという意味で、デジタル改革関連法案を紹介します。
参議院で予算案3案を審査中の3月に、衆議院で早々に審議入りしましたが、新規制定法4本と束ね法案1本(この中に59本)を一括審議するという、丁寧とはほど遠い形で審議が行われてしまいました。
内容もさることながら、束ね法案と一括審議で済ませてしまう審議の在り方については、議会人として思うところが多々ありますし、これだけの本数を束ね、なおかつ所管が寄せ集めの担当であれば、参考資料の誤りが多発するのは避け難い側面があったのではないでしょうか。
なお、今回のデジタル改革関連5法案の法案名は下記のとおりです。
[デジタル改革関連5法案]
〇デジタル社会形成基本法案(新規制定法)
〇デジタル庁設置法案(新規制定法)
〇デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案(59本の束ね法案)
〇公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案(新規制定法)
〇預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案(新規制定法)
59本の束ね法案だった「デジタル社会の形成を図るための~法律」に含まれる法律は下記の通りです。
1.住民基本台帳法
2.社会福祉法及び介護福祉法
3.看護師等の人材確保の促進に関する法律
4.精神保健福祉士法
5.地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律
6.健康増進法
7.電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
8.個人情報の保護に関する法律
9.行政手続における特定の個人を識別するための電話の利用等に関する法律
10.地方公共団体情報システム機構法
11.公認心理師法
12.民法
13.抵当証券法
14.死産の届出に関する規程
15.地方自治法
16.農業協同組合法
17.農業保険法
18.戸籍法
19.公認会計士法
20.損害保険料率算出団体に関する法律
21.建設業法
22.土地改良法
23.船主相互保険組合法
24.建築士法
25.商品先物取引法
26.鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律
27.漁船損害等補償法
28.宅地建物取引業法
29.公共工事の前払金保証事業に関する法律
30.中小漁業融資保証法
31.土地区画整理法
32.内航海運組合法
33.国民年金法
34.確定給付企業年金法
35.農業信用保証保険法
36.建物の区分所有等に関する法律
37.不動産の鑑定評価に関する法律
38.不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律
39.漁業災害補償法
40.通関業法
41.社会保険労務士法
42.都市再開発法
43.大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
44.農住組合法
45.借地借家法
46.不動産特定共同事業法
47.政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
48.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
49.資産の流動化に関する法律
50.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
51.マンションの管理の適正化の推進に関する法律
52.高齢者の居住の安定確保に関する法律
53.マンションの建替え等の円滑化に関する法律
54.刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
55.犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
56.株式会社地域経済活性化支援機構法
57.大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法
58.公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
59.行政不服審査法
(参考)
「束ね法案と一括審議-その1」平成27年5月16日
「束ね法案と一括審議-その2」平成27年5月17日
「束ね法案と一括審議-その3」平成27年5月25日
「束ね法案と一括審議-その4」平成27年7月17日
「束ね法案と審議時間」平成27年7月18日
「第190回国会における束ね法案-その1」平成28年2月7日
「束ね法案と一括審議-番外編」平成30年1月19日
うち、本則で3本以上の法律案を束ねた内閣提出法案は、実に26本にも上ります。
技術的に束ねざるを得ない改正法案があるのは事実ですし、束ね法案が一概によろしくない、というわけではありません。
ただ、複数の法律を改正等しようとするときにこれらを束ねて一本の法律案として国会に提出する「束ね法案」は、法律案を束ねることによって国会審議の形骸化を招来するとともに、国会議員の表決権を侵害しかねないものです。
また、どの法律がどのように改正されるのか等が国民に分かりづらくなり、適切な情報公開とはならないおそれもあります。
これらは、このブログにおいても何度も指摘してきたことです。
今次常会は、とにかく束ね法案の割合が高いと言わざるを得ません。今次常会の閣法の本数を絞るために、束ね法案を多用したのではないかと考えざるを得ない状況でもあります。
束ね法案の立案作業においては、複数の法律案の立案作業を同時並行で行わなければならず、改正内容も幅広く、合議等を必要とする組織体が多岐にわたることも少なくありません。
このため、束ね法案の立案作業は、一般に、束ねる法律案の本数が多ければ多いほど、従事する職員に負荷がかかることになり、また、日程の余裕が失われることになると考えます。
事実、今次常会では、特に束ね法案において条文誤りや参考資料の誤りが続発したのです。この点については、別途書きたいと思います。
今次常会の束ね法案について、とにかく束ねた本数が多いという意味で、デジタル改革関連法案を紹介します。
参議院で予算案3案を審査中の3月に、衆議院で早々に審議入りしましたが、新規制定法4本と束ね法案1本(この中に59本)を一括審議するという、丁寧とはほど遠い形で審議が行われてしまいました。
内容もさることながら、束ね法案と一括審議で済ませてしまう審議の在り方については、議会人として思うところが多々ありますし、これだけの本数を束ね、なおかつ所管が寄せ集めの担当であれば、参考資料の誤りが多発するのは避け難い側面があったのではないでしょうか。
なお、今回のデジタル改革関連5法案の法案名は下記のとおりです。
[デジタル改革関連5法案]
〇デジタル社会形成基本法案(新規制定法)
〇デジタル庁設置法案(新規制定法)
〇デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案(59本の束ね法案)
〇公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案(新規制定法)
〇預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案(新規制定法)
59本の束ね法案だった「デジタル社会の形成を図るための~法律」に含まれる法律は下記の通りです。
1.住民基本台帳法
2.社会福祉法及び介護福祉法
3.看護師等の人材確保の促進に関する法律
4.精神保健福祉士法
5.地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律
6.健康増進法
7.電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
8.個人情報の保護に関する法律
9.行政手続における特定の個人を識別するための電話の利用等に関する法律
10.地方公共団体情報システム機構法
11.公認心理師法
12.民法
13.抵当証券法
14.死産の届出に関する規程
15.地方自治法
16.農業協同組合法
17.農業保険法
18.戸籍法
19.公認会計士法
20.損害保険料率算出団体に関する法律
21.建設業法
22.土地改良法
23.船主相互保険組合法
24.建築士法
25.商品先物取引法
26.鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律
27.漁船損害等補償法
28.宅地建物取引業法
29.公共工事の前払金保証事業に関する法律
30.中小漁業融資保証法
31.土地区画整理法
32.内航海運組合法
33.国民年金法
34.確定給付企業年金法
35.農業信用保証保険法
36.建物の区分所有等に関する法律
37.不動産の鑑定評価に関する法律
38.不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律
39.漁業災害補償法
40.通関業法
41.社会保険労務士法
42.都市再開発法
43.大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
44.農住組合法
45.借地借家法
46.不動産特定共同事業法
47.政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
48.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
49.資産の流動化に関する法律
50.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
51.マンションの管理の適正化の推進に関する法律
52.高齢者の居住の安定確保に関する法律
53.マンションの建替え等の円滑化に関する法律
54.刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
55.犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
56.株式会社地域経済活性化支援機構法
57.大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法
58.公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
59.行政不服審査法
(参考)
「束ね法案と一括審議-その1」平成27年5月16日
「束ね法案と一括審議-その2」平成27年5月17日
「束ね法案と一括審議-その3」平成27年5月25日
「束ね法案と一括審議-その4」平成27年7月17日
「束ね法案と審議時間」平成27年7月18日
「第190回国会における束ね法案-その1」平成28年2月7日
「束ね法案と一括審議-番外編」平成30年1月19日