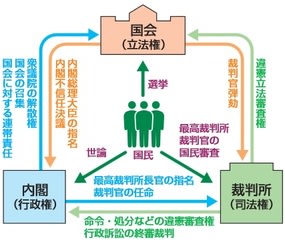「議院証言法と証人喚問-その1(再掲)」では、日本国憲法と議院規則との関わり、ならびに議院証言法について紹介しましたので、今回は実際の証人喚問の流れについて紹介します。
平成30年3月27日は、9時30分から参議院予算委員会、14時から衆議院予算委員会で証人喚問が行われます。
国会関係者ならずとも多くの方が関心を寄せる証人喚問を見守りたいと思います。
○平成30年3月27日(証人喚問当日)
9時30分開会
[参議院予算委員会]
1.人定質問(委員長)
2.宣誓及び証言に関する注意事項説明等(委員長)
3.宣誓(証人)※総員起立
4.宣誓書に署名捺印(証人)
5.委員長尋問(8分)
6.各会派尋問
(自30分、民27分、公15分、共12分、維10分、希会6分、立憲6分、無ク5分)
―証言聴取の終了―
7.証人退室
11時40分散会見込み
14時開会
[衆議院予算委員会]
1.人定質問(委員長)
2.宣誓及び証言に関する注意事項説明等(委員長)
3.宣誓(証人)※総員起立
4.宣誓書に署名捺印(証人)
5.委員長尋問(10分)
6.各会派尋問
(自35分、公25分、立憲22分、希望21分、無会6分、共6分、維5分)
―証言聴取の終了―
7.証人退室
16時10分散会見込み
(罰則)
正当の理由がなくて宣誓又は証言を拒んだとき、虚偽の陳述をしたときは刑罰に処せられる(議証法4、6、7条)。
なお、本エントリーは、平成30年3月27日0時30分現在のものです。
平成30年3月27日は、9時30分から参議院予算委員会、14時から衆議院予算委員会で証人喚問が行われます。
国会関係者ならずとも多くの方が関心を寄せる証人喚問を見守りたいと思います。
○平成30年3月27日(証人喚問当日)
9時30分開会
[参議院予算委員会]
1.人定質問(委員長)
2.宣誓及び証言に関する注意事項説明等(委員長)
3.宣誓(証人)※総員起立
4.宣誓書に署名捺印(証人)
5.委員長尋問(8分)
6.各会派尋問
(自30分、民27分、公15分、共12分、維10分、希会6分、立憲6分、無ク5分)
―証言聴取の終了―
7.証人退室
11時40分散会見込み
14時開会
[衆議院予算委員会]
1.人定質問(委員長)
2.宣誓及び証言に関する注意事項説明等(委員長)
3.宣誓(証人)※総員起立
4.宣誓書に署名捺印(証人)
5.委員長尋問(10分)
6.各会派尋問
(自35分、公25分、立憲22分、希望21分、無会6分、共6分、維5分)
―証言聴取の終了―
7.証人退室
16時10分散会見込み
(罰則)
正当の理由がなくて宣誓又は証言を拒んだとき、虚偽の陳述をしたときは刑罰に処せられる(議証法4、6、7条)。
なお、本エントリーは、平成30年3月27日0時30分現在のものです。