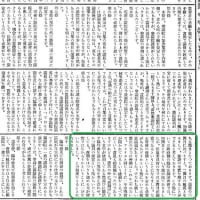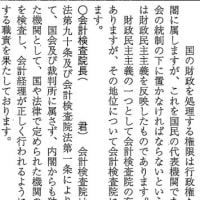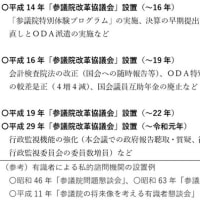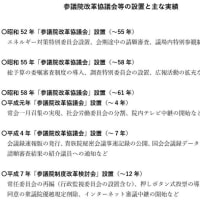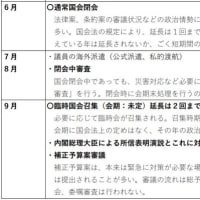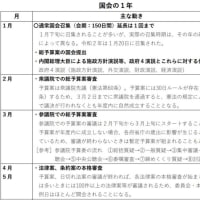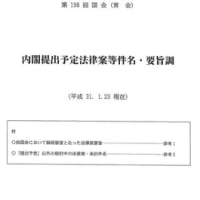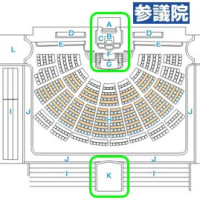7月15日、衆議院特別委員会で強行採決された安保法案の審議時間は、116時間30分でした。
ちなみに、この時間数の中には、野党が欠席して、質疑を行わなかった分、いわゆる「空回し」を含んでいます。
このブログで、幾度も取り上げたとおり、安保法案=「束ね法案」であり、既存の法律10本を1本に束ねた法案と、新法1本です。外形上は2法案ですが、実質は11本の法案を審議したのと同一です。
そこで、審議時間の側面から、なぜ与野党間の対立が激しくなっているのか、を見てみます。
まず、これまでの安保関連法での審議時間数を見てみたいと思います。
すべて衆議院委員会での審議時間です。
平成4年 (1992年)国連平和維持活動(PKO)協力法 87時間41分
平成11年(1999年)周辺事態法 94時間11分
平成13年(2001年)テロ対策特別措置法 33時間15分
平成15年(2003年)武力攻撃事態法など有事関連3法 92時間1分
平成15年(2003年)イラク復興支援特別措置法 43時間43分
今回の安保法案はどうなのか・・。
衆議院特別委員会での審議時間は、116時間30分であり、一見すると長いようにも見えますが、審議すべき法案数は、11にも及んでいます。1法案あたり、どの程度審議されたのかを計算すると、約10時間にしかなりません。
もちろん、単純に計算できない側面はありますが、我が国の在り方を大きく転換することになるであろう法案であることは、誰しも見解の一致するところだと思います。
また、与野党間で何か合意を見たのであればいざしらず、採決は、与党のみの強行採決でした。
幾つもの法案が束ねられたことにより、1法案あたりの審議時間は、これだけの重い法案であるにも関わらず、たったの10時間。充実審議を求める野党からすれば、審議時間は足りないと主張するはずであり、与野党間で激しく対立するひとつの要因であると指摘できると思います。
○衆議院委員会における長時間審議の例
1.昭和35年(1960年) 日米安全保障条約改定 136時間13分
2.平成24年(2012年) 社会保障・税一体改革関連法 129時間8分
3.昭和46年(1971年) 沖縄返還関連法 127時間14分
4.平成6年(1994年) 政治改革関連法 121時間38分
5.平成17年(2005年) 郵政民営化関連法 120時間32分
社会保障・税一体改革関連法が長時間審議を行った直近の例ですが、これは民自公の3党合意で審議しましたから、今回のケースとは色々異なります。個人的に、色んな思いが交錯する法律ですね・・。
ちなみに、この時間数の中には、野党が欠席して、質疑を行わなかった分、いわゆる「空回し」を含んでいます。
このブログで、幾度も取り上げたとおり、安保法案=「束ね法案」であり、既存の法律10本を1本に束ねた法案と、新法1本です。外形上は2法案ですが、実質は11本の法案を審議したのと同一です。
そこで、審議時間の側面から、なぜ与野党間の対立が激しくなっているのか、を見てみます。
まず、これまでの安保関連法での審議時間数を見てみたいと思います。
すべて衆議院委員会での審議時間です。
平成4年 (1992年)国連平和維持活動(PKO)協力法 87時間41分
平成11年(1999年)周辺事態法 94時間11分
平成13年(2001年)テロ対策特別措置法 33時間15分
平成15年(2003年)武力攻撃事態法など有事関連3法 92時間1分
平成15年(2003年)イラク復興支援特別措置法 43時間43分
今回の安保法案はどうなのか・・。
衆議院特別委員会での審議時間は、116時間30分であり、一見すると長いようにも見えますが、審議すべき法案数は、11にも及んでいます。1法案あたり、どの程度審議されたのかを計算すると、約10時間にしかなりません。
もちろん、単純に計算できない側面はありますが、我が国の在り方を大きく転換することになるであろう法案であることは、誰しも見解の一致するところだと思います。
また、与野党間で何か合意を見たのであればいざしらず、採決は、与党のみの強行採決でした。
幾つもの法案が束ねられたことにより、1法案あたりの審議時間は、これだけの重い法案であるにも関わらず、たったの10時間。充実審議を求める野党からすれば、審議時間は足りないと主張するはずであり、与野党間で激しく対立するひとつの要因であると指摘できると思います。
○衆議院委員会における長時間審議の例
1.昭和35年(1960年) 日米安全保障条約改定 136時間13分
2.平成24年(2012年) 社会保障・税一体改革関連法 129時間8分
3.昭和46年(1971年) 沖縄返還関連法 127時間14分
4.平成6年(1994年) 政治改革関連法 121時間38分
5.平成17年(2005年) 郵政民営化関連法 120時間32分
社会保障・税一体改革関連法が長時間審議を行った直近の例ですが、これは民自公の3党合意で審議しましたから、今回のケースとは色々異なります。個人的に、色んな思いが交錯する法律ですね・・。