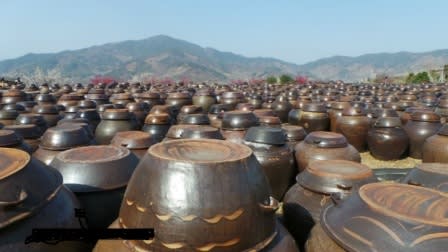昨日、今月いっぱいで幕を下ろすという鎌倉の神奈川県立近代美術館へ行って
きました。

鎌近エントランス
ここは・・・・まだ大きな夢を見ていた青春の季節、その頃出会った仲間たちと何回
か訪れたことがある。確かムンクの叫びを見たのも、佐伯祐三のパリの街角の絵
もここで見たような・・・そう思って過去の展覧会記録を検索してみたが、出てきた
開催年は私がまだ田舎にいる頃で・・・
残念ながら、はっきりしなかったが、そんなことはどうでもいい。
思い出したら行きたくなって、連れ合いを誘ったら、行っても良いという風情だった
ので、ありがたく同行してもらった。
チケットをみると「パート3:1951~1965」とあった。その時期の展覧会など
美術館の活動についてのパネル展示もあったのだが、その部分はほとんど
素通りしてしまった。草創期の美術館は、運営する人たちや芸術家たちなど
関わる人々に活発で精力的な息吹があったことだろう。
その一端を美術館から発送する年賀状の原画とその年賀状の展示に見た。
著名な画家に依頼された原画は、どれも素晴らしく、そんな素敵な年賀状
一体どんな人たちに送られたのだろう!
私は展示物の解説を逐一見ながら観賞する方だが、今回作品につけられた
解説は、作品そのものより作者についての説明が主だった。
当然ながら知らない画家(彫刻家)が多く、ざっと目を通すのに、時間がかかり
疲れそうだったので、途中でやめてしまった。
しかし、色遣いがちょっと不思議だったり、面白いと思った作品については
しっかり確認した。
その中の『門の広告』という絵、懐かしい名前「佐伯祐三」を見つけ嬉しかった。
絵も、風景ではあるらしいのだけれど、門に書かれた模様がグラフィックデザイン
の一部のような・・・それで到底風景画には見えなかったわけだけれど・・・
でも不思議と気に入った。
それから梅原龍三郎の『熱海野島別荘』、好きか嫌いかではなく、熱海を描く
のにこんな色を使うんだと、ふと見たら名前だけ知っている画家だった。こんな
絵を描く人だったんだと新鮮な思いがした。

一階通路にあるオブジェ


中庭にあるオブジェ