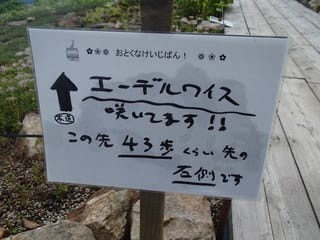2013年10月7日(月)~8日(火)
※紅葉山行第1弾
今週末で小屋閉めの船窪小屋。
松沢のおとうさん、おかあさんも喜寿を迎えこの小屋の記念すべき年に
まだ今年は上がっていない。
そこでちょうど最近はご無沙汰していたnomoemiさんから行かないかと
メールが来た。
私ももう小屋閉めまじかで、この日しかチャンスはないと行ってみた。
第1日目
天候:晴れのち曇り
週末から今日にかけて仕事であった。
昼に職場を出発。1時間ちょっとで七倉へ着。
nomoemiさんは少し前に先に行ってもらった。
駐車場は、平日ということもあり空いている。
13時半に出発。夕食の17時には行きたいところだ。
標準コースタイムは6時間。標高差も1400mある。
今回は、先週末からの鈍った体に鞭打っていくので、なるべく軽量化を図った。
のっけから急登で大汗。それでも地道に行くと1。時間ちょっとで
唐沢ノゾキ。
この日は気温高く暑い。
樹林の視界の効かない所を行くと、右に北葛岳が見えてきた。

北葛岳
岩小屋を過ぎたあたりから紅葉がきれいになってきた。
後ろを振り向くと大町の町並みと長野盆地も見えてきた。

大町から長野盆地方面
そして、唐沢岳も背後に見えてきた。

唐沢岳
そして、木のハシゴが連続する鼻突八丁。
この上にダケカンバとナナカマドの素敵な紅葉が出てきた。

樹林も低く、道もザレてくると一登りで天狗の庭。
ここからの展望は、いつ来てもすばらしい。

天狗の庭から高瀬ダム槍方面
残念ながら槍はガスがかかりたまにしか見えなかった。
上を見ると小屋のある稜線が見える。もう一息だ。

北葛岳と蓮華岳
天狗まで3時間と順調にきた。
しかしここからあまりペース上がらず。
稜線に出てからは、小走りで行く。

小屋手前
それでも何とか17時には到着。
恒例の鐘を鳴らしてもらい。お茶一杯いただき、夕食へ。
この日は、私も含め11名。若者が多かった。
いつもながらおいしい食事をいただく。

夕食
nomoemiさんが一生懸命担ぎ上げたマツタケも添えてあった。
国産天然ものはうまいね~
そして、18時半からのお茶会まで時間あったので、外でまったり。
まだ雲があり星は見えなかったが、そのうち晴れてくるでしょう。
お茶会は、DVDに自己紹介、おとうさん、おかあさんのお話といつもより長めの会であった。
皆さんのお話本当に楽しい。あとこの小屋に対する思いも素敵である。

囲炉裏を囲んで
室内はランプだけなので光量足りませんが、これはこれでいい。
お茶会の後、外へ出てみると満天の星空であった。
この時期にしては、温かく、このまま外で寝てもいい気分であった。
それでは、爆睡 チーン
第2日目
天候:晴れ
この日も晴れは約束されていた。
5時半のご飯の時間になっても皆さんご来光待ちであった。
そういう私も外で写真撮りまくりである。

雲海と東の空
雲海がきれいである。

雲海に浮かぶ浅間山
浅間山の少し左から陽は上がりそうだ。

餓鬼岳と雲海に浮かぶ八ヶ岳、富士山

ご来光
ちょっと雲があり、上がっているのだけれども太陽見えずという感じ。

槍、穂高
槍に奥穂、前穂と昨日見えなかった山々もきれいに見える。
そして、朝食いただき七倉山頂へ。
この日の雲海はボリュームあってよかった。

雲海

八ヶ岳、富士山
素敵な雲海。

槍穂

不動岳と薬師岳、水晶岳

針ノ木岳と立山、剣岳

七倉山頂から針ノ木岳と蓮華岳
ここへ来るとこんな素敵な景色が見られます。
そして、何といってもここ

船窪小屋と唐沢岳、燕岳、大天井岳
この小屋があるから、この景色もより素敵に見えるのでしょう。
そして、おかあさんと写真を撮って下山です。
いつも、素敵な笑顔とお食事ありがとうございます。
また来ますね。

昨日は、もう夕暮れで急いでいたのであまり写真は撮らなかったが、帰りは撮りながら行く。

チングルマの草紅葉

高瀬ダムと槍穂
今週末はあの辺りだなと見ながら下ります。

ナナカマドと唐沢岳
唐沢岳の斜面も紅葉していました。

ダケカンバとナナカマド



素敵な紅葉を見たあとは一気に下山です。
2時間ちょっとで七倉着。
下山後は、七倉荘で久しぶりにお湯に浸かって帰路につく。

来シーズンは、縦走して行ってみたい。同行者募集中(笑)
※紅葉山行第1弾
今週末で小屋閉めの船窪小屋。
松沢のおとうさん、おかあさんも喜寿を迎えこの小屋の記念すべき年に
まだ今年は上がっていない。
そこでちょうど最近はご無沙汰していたnomoemiさんから行かないかと
メールが来た。
私ももう小屋閉めまじかで、この日しかチャンスはないと行ってみた。
第1日目
天候:晴れのち曇り
週末から今日にかけて仕事であった。
昼に職場を出発。1時間ちょっとで七倉へ着。
nomoemiさんは少し前に先に行ってもらった。
駐車場は、平日ということもあり空いている。
13時半に出発。夕食の17時には行きたいところだ。
標準コースタイムは6時間。標高差も1400mある。
今回は、先週末からの鈍った体に鞭打っていくので、なるべく軽量化を図った。
のっけから急登で大汗。それでも地道に行くと1。時間ちょっとで
唐沢ノゾキ。
この日は気温高く暑い。
樹林の視界の効かない所を行くと、右に北葛岳が見えてきた。

北葛岳
岩小屋を過ぎたあたりから紅葉がきれいになってきた。
後ろを振り向くと大町の町並みと長野盆地も見えてきた。

大町から長野盆地方面
そして、唐沢岳も背後に見えてきた。

唐沢岳
そして、木のハシゴが連続する鼻突八丁。
この上にダケカンバとナナカマドの素敵な紅葉が出てきた。

樹林も低く、道もザレてくると一登りで天狗の庭。
ここからの展望は、いつ来てもすばらしい。

天狗の庭から高瀬ダム槍方面
残念ながら槍はガスがかかりたまにしか見えなかった。
上を見ると小屋のある稜線が見える。もう一息だ。

北葛岳と蓮華岳
天狗まで3時間と順調にきた。
しかしここからあまりペース上がらず。
稜線に出てからは、小走りで行く。

小屋手前
それでも何とか17時には到着。
恒例の鐘を鳴らしてもらい。お茶一杯いただき、夕食へ。
この日は、私も含め11名。若者が多かった。
いつもながらおいしい食事をいただく。

夕食
nomoemiさんが一生懸命担ぎ上げたマツタケも添えてあった。
国産天然ものはうまいね~
そして、18時半からのお茶会まで時間あったので、外でまったり。
まだ雲があり星は見えなかったが、そのうち晴れてくるでしょう。
お茶会は、DVDに自己紹介、おとうさん、おかあさんのお話といつもより長めの会であった。
皆さんのお話本当に楽しい。あとこの小屋に対する思いも素敵である。

囲炉裏を囲んで
室内はランプだけなので光量足りませんが、これはこれでいい。
お茶会の後、外へ出てみると満天の星空であった。
この時期にしては、温かく、このまま外で寝てもいい気分であった。
それでは、爆睡 チーン
第2日目
天候:晴れ
この日も晴れは約束されていた。
5時半のご飯の時間になっても皆さんご来光待ちであった。
そういう私も外で写真撮りまくりである。

雲海と東の空
雲海がきれいである。

雲海に浮かぶ浅間山
浅間山の少し左から陽は上がりそうだ。

餓鬼岳と雲海に浮かぶ八ヶ岳、富士山

ご来光
ちょっと雲があり、上がっているのだけれども太陽見えずという感じ。

槍、穂高
槍に奥穂、前穂と昨日見えなかった山々もきれいに見える。
そして、朝食いただき七倉山頂へ。
この日の雲海はボリュームあってよかった。

雲海

八ヶ岳、富士山
素敵な雲海。

槍穂

不動岳と薬師岳、水晶岳

針ノ木岳と立山、剣岳

七倉山頂から針ノ木岳と蓮華岳
ここへ来るとこんな素敵な景色が見られます。
そして、何といってもここ

船窪小屋と唐沢岳、燕岳、大天井岳
この小屋があるから、この景色もより素敵に見えるのでしょう。
そして、おかあさんと写真を撮って下山です。
いつも、素敵な笑顔とお食事ありがとうございます。
また来ますね。

昨日は、もう夕暮れで急いでいたのであまり写真は撮らなかったが、帰りは撮りながら行く。

チングルマの草紅葉

高瀬ダムと槍穂
今週末はあの辺りだなと見ながら下ります。

ナナカマドと唐沢岳
唐沢岳の斜面も紅葉していました。

ダケカンバとナナカマド



素敵な紅葉を見たあとは一気に下山です。
2時間ちょっとで七倉着。
下山後は、七倉荘で久しぶりにお湯に浸かって帰路につく。

来シーズンは、縦走して行ってみたい。同行者募集中(笑)