

<左:永山南公園の北側の陸橋から東方向を;右:左の写真に写っている交差点から西方向を>
パルテノン多摩の企画展「標本のチカラ」(~3月16日)を見に行った。かつて多摩市内で採集された「モウセンゴケ」などの植物標本のいくつかが展示されていると新聞記事で読んだからである。モウセンゴケの標本のラベルには、採取地「南多摩郡多摩町岩入池」採取日「1964年6月30日」採取者「畔上能力」とある。展示解説に「多摩市から消えた植物のリスト」があって、ヒツジグサ、カキラン、サギスゲ、コイヌノハナヒゲ、イヌノハナヒゲ、クモキリソウ、ミズチドリ、コバノトンボソウなどが岩ノ入池でみられたと書かれている。この池が残っていたとしたら、多摩市の(東京都の)宝になっていたことは間違いない。湧水湿地については以前すこし紹介した。
それにしても、この岩ノ入池とはどのあたりだったのであろうか。上記展示の解説の中では、「乞田」と書かれている。小林宏一氏『大栗川・乞田川 流域の水と文化』には永山の岩ノ入池と書かれている。
『多摩市の町名』(多摩市都市建設部都市計画課、平成4年)p.111によると
(引用はじめ)
岩ノ入(いわのいり)
永山・半過田の南隣にあり、西は貝取、東は連光寺・関戸字原地、南は川崎市黒川に接する。一般に、岩の字は岩石が露出していたり、石の多いところなどに使われるという。中央部を黒川の境付近から岩ノ入の沢が発し、北側に位置する旧乞田川に注いでいた山間部で、風土記(引用者注:新編武蔵風土記稿を指す)には岩ノ入山とある。中略。また、昔は現在の永山南公園北付近に池があったということである。
(引用終り)
さらに『多摩市史 通史編一』多摩市史編集員会編 p.157には池についての詳しい記述がある。
(引用はじめ)
多摩丘陵に刻み込まれた数多くの谷戸の奥には、現在の東京都からほとんど姿を消してしまった貴重な植物が多数生息していた。それを象徴的に物語ってくれたのが、現在の永山南公園付近にあたる、多摩村乞田字岩ノ入にあった、岩ノ入大池であった。面積約九八〇坪(3234平方メートル)で、南、南西方向に二岐し、全体としてV字形を呈し、広々とした沼地となって、ヨシの根が縦横に走り、その上に乗ってチゴザサやヤチカワズスゲ、ゴウソ、オニスゲ、マアザミ(キセルアザミ)などが繁茂していた。池畔の浅瀬にはモウセンゴケやムラサキミミカキグサが群生していた。水深の浅い部分はヨシやサンカクイ、カンガレイ、シズイなどが茂り、ノハナショウブ、ミズチドリ、ミズトンボ、サワギキョウ、オオニガナ、クサレダマ、ヒメナミキ、ヒナザサなどが季節に応じて美しい花を咲かせていた。水源部分良好なハンノキ林となっていて、その根際にはトキソウやクモキリソウなどが咲いていた。出口付近の湿地にはオグルマやサワヒヨドリ、アゼナルコスゲ、オニスゲ、ゴウソ、コイヌノハナヒゲなどが見られた。谷戸の水田にはサンショウモが多数浮遊し、農道の縁の崖にはオキナグサやホタルカズラなどが咲いていた。またハンノキ林の上部斜面においてムラサキも記録された。
(引用終り)
それにしてももったいないことをしたものだなあとしか言いようがない。


<左:永山南公園の北側には小学校(の跡?);右:永山北公園と永山南公園を結ぶ道、南方向を>
上記の『多摩市の町名』には「乞田の小字」という地図がついておりベース図には「岩ノ入」の地名が記入されている。また、『のびゆく多摩市』(多摩市中学校社会科副読本編集員会)の表紙裏には、明治39年測量2万分の一地形図が複製されており、それらしい位置に、池のような枠取りが書かれている。
これらの地図と、「永山南公園(の北)」という表記と、送電線の位置などを手がかりに、「岩ノ入池」のおよその位置を書き入れてみた。(形や大きさは違っています)

<ピンク色の楕円形が「岩ノ入池の推定位置」。赤の点は写真撮影位置
地図は杉本智彦『カシミール3D』(実業之日本社)より、国土地理院発行二万五千分の一地形図「武蔵府中」図幅の一部>




















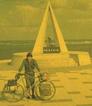





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます