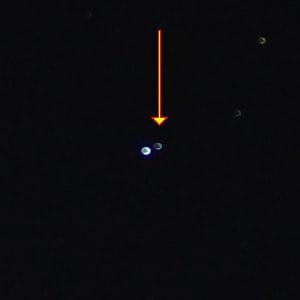ホタルの写真を撮るのは難しいし三脚などを用意しないといけない。そんなホタルの時期がやってきたけど夜の撮影修行は全然やらずに今年もこの時期を迎えた。ヨメが見に行こうって言うので重い腰を上げて見に行った。場所は歩いて5分くらいだから重い腰と言うには贅沢かも。街灯が LED になったりで誰も歩かない田舎道が無駄にギラギラしてて明るい。
 行く途中にある廃水処理上の明かりは一際眩しい
行く途中にある廃水処理上の明かりは一際眩しい
 たまに車が通る
たまに車が通る
一番見えそうな所にある家に限って玄関灯が煌々と光っていた。だからといって無粋だから消せとも言えない。暗い所を選んで撮った。今年はやや多めな気がする。この日ホタルを見に来た人はもう1人だけ。以前はもっと見に来る人が多かった。その半分が小さな子を連れていた。

ホタルの写真と言ったら長い光跡が入り混じってるようなのが良いのかな。それには三脚が必要だけどそんなのは持って来るつもりは無かったので手持ち撮影。

真っ暗だったところで光ってるのをストロボを焚いてテキトーに撮ったら思ったよりも良く撮れた。


星空だったので北斗七星を撮ってみた。
 下を向いてる柄杓
下を向いてる柄杓
柄杓の部分の端から2つ目の星は二重星。手ブレはあるけどまぁまぁ撮れてるかな。これが20代半ばくらいまでは肉眼で見えていた。
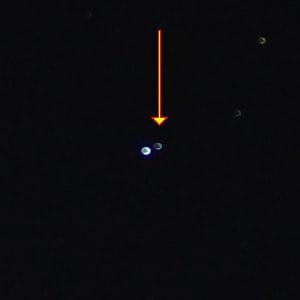 目の良い人は星が2つ見える
目の良い人は星が2つ見える
だからどうしたな蠍座の頭の部分。北斗七星とこれ以外は何の星座か全然分からないし空もボヤッとしてた。下のやや明るいのが一等星のアンタレス。
 蠍座の頭の部分
蠍座の頭の部分