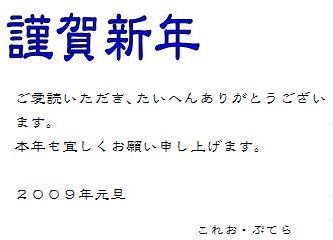森羅万象、政治・経済・思想を一寸観察 by これお・ぷてら
花・髪切と思考の
浮游空間
カレンダー
| 2009年1月 | ||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
||||||||
goo ブログ
最新の投稿
| 8月6日(土)のつぶやき |
| 8月5日(金)のつぶやき |
| 6月4日(土)のつぶやき |
| 4月10日(日)のつぶやき |
| 2月10日(水)のつぶやき |
| 11月12日(木)のつぶやき |
| 10月26日(月)のつぶやき |
| 10月25日(日)のつぶやき |
| 10月18日(日)のつぶやき |
| 10月17日(土)のつぶやき |
カテゴリ
| tweet(762) |
| 太田光(7) |
| 加藤周一のこと(15) |
| 社会とメディア(210) |
| ◆橋下なるもの(77) |
| ◆消費税/税の使い途(71) |
| 二大政党と政党再編(31) |
| 日米関係と平和(169) |
| ◆世相を拾う(70) |
| 片言集または花(67) |
| 本棚(53) |
| 鳩山・菅時代(110) |
| 麻生・福田・安倍時代(725) |
| 福岡五輪幻想(45) |
| 医療(36) |
| スポーツ(10) |
| カミキリムシ/浮游空間日記(77) |
最新のコメント
| Unknown/自殺つづくイラク帰還自衛隊員 |
| これお・ぷてら/7月27日(土)のつぶやき |
| 亀仙人/亀田戦、抗議電話・メールなど4万件突破 |
| inflatables/生活保護引き下げ発言にみる欺瞞 |
| これお・ぷてら/10月2日(火)のつぶやき |
| THAWK/10月2日(火)のつぶやき |
| これお・ぷてら/10月2日(火)のつぶやき |
| THAWK/国民の負担率は低いというけれど。 |
| THAWK/10月2日(火)のつぶやき |
| THAWK/[橋下市政]健康を奪い財政悪化招く敬老パス有料化 |
最新のトラックバック
ブックマーク
| ■ dr.stoneflyの戯れ言 |
| ■ machineryの日々 |
| ■ えちごっぺのヘタレ日記 |
| ■ すくらむ |
| ■ 代替案 |
| ■ 非国民通信 |
| ■ coleoの日記;浮游空間 |
| ■ bookmarks@coleo |
| ■ 浮游空間日記 |
過去の記事
検索
| URLをメールで送信する | |
| (for PC & MOBILE) | |
自衛隊勧誘という究極の貧困ビジネス
こんな事態を直視しつつ、不況で赤字必至などという宣伝が強調されているものの、利益はちゃんと確保するようなものにすぎず、働く者への解雇・雇い止めという仕打ちは決して不可避ではないことを国民の共通の認識にする作業が急がれるのではないか。同時に、現に首を切られ、明日からの生活の青写真などまったく立たない人びとへの緊急支援が必要だ。「派遣村」の経験はその意味で教訓に満ちている。私たちがこれまで聞いてきたことは、敗戦後の日本に、今日の「派遣村」のプロトタイプがあった。困った人びとに寄り添う取り組みを挙げるに事欠かない。たとえばセツルメントの活動も広義のその種の活動であった。「派遣村」の活動は、伝統をその意味で引き継いでいる。
先の話に戻ると、この地でも「派遣村」と同様の計画を立てようということで具体化が図られている。3月末までに解雇者は公認で8万5000人に及ぶといわれているくらいだから、実際にはその時点でその数倍になることも推測される。「災害」に直面した人びとへの緊急支援とともに、世論喚起の運動がいよいよ重要になってきた。
雇用をどのように確保するのか、首を切られた労働者の雇用をどのように保障するのか、これは容易な課題ではない。
そこで、こんな動きも表面化している。自衛隊が、派遣切りで解雇された労働者を対象に勧誘を強めているというのだ。
当ブログでは、米国を引き合いに出して、戦争が貧困ビジネスの最たるものだとのべてきた。堤未果さんが常々語っているが、米国のとくにマイノリティを対象に、戦争屋たちが高校生狩りに乗り出す。彼らの多くは貧困層だ。
自衛隊が派遣切りの労働者にねらいを定めようとする構図は、堤氏が伝える米国の兵士リクルータたちの行動と瓜二つのものだ。
我われは貧困大国だといわれる米国のこともそれほど知っているわけではないが、こんな相似性は、その米国同様に日本もまた「貧困大国」にならんとしているかのようにも思えるわけだ。
この不況といわれる時期に、それを逆手にとって、自衛隊入隊勧誘が勢いを増している。だとすれば、日本もまた究極の貧困ビジネスがはびこる事態に立ち至っているということだ。
(「世相を拾う」09013)
■応援をよろしく ⇒
■こちらもお願い⇒![]()
【関連エントリー】
堤未果『ルポ貧困大国アメリカ』を反ネオリベの書として読む。
貧困ビジネスの射程。または社会保障の展望。
堤未果『ルポ貧困大国アメリカ』-あとを追う日本は…。
堤未果『報道が教えてくれないアメリカ弱者革命』と新テロ法案
もう一つの日本の可能性
西松建設:幹部ら聴取 裏金を違法献金の疑い--東京地検
一方の献金を受ける側には、二階俊博氏、小沢一郎代表などの与野党の幹部があがっている。ようは、政権交代必至といわれている状況のなかで、関与が推定されている自民と民主両党、双方を同時にあげることに意味があるのだろう。その結果、マイナスイメージを有権者に植え付けられるのは、いうまでもなく民主党だ。しかも、党首の小沢氏が噛んでいるのだから。しかし、彼は、どこまで脇が甘いのだろう。この一点をとっても、私は、彼が従来の保守政治家の域を少しも出ていないと感じざるをえない。
とりあえず、私たちはこう指摘することが可能だろう。
企業献金が現行法に則って違法か否かを問わず、企業からの献金は政治にとって少しもよい方向には機能しないということ、企業の献金を受け取ってはばからない人に、今日取りざたされている不況時に働く者にのみしわ寄せを押し付ける大企業のふるまいに、働く者の立場に立ってモノがいえるはずがない、という思い、これである。二階氏よ、小沢氏よ、嫌疑をはらすのなら、堂々と、大企業にモノいえるということを体を張って示してほしいものだ。そういえば、二階氏はもとより、小沢氏が大企業を名指しで批判するのをこれまで聞いたためしがない。
当ブログでは、今日の不況をいわば逆手にとって、大企業が今日の事態で可能な限りの利益確保のために、もっとも手っ取り早い方途として労働者の首切り、たとえば派遣切りにいっせいに乗り出したことを強く批判してきたつもりだ。企業の論理とは所詮こんなものだ。
しかし、業績が下向きになったとはいえ、トヨタは純利益が赤字になることを見込んでいるわけではない。経営環境が悪くなったとしても、利益確保が至上命題なのだから。逆にいえば、労働者はそのための調整弁にはからずもなっているということだ。
このような企業と労働者の非対称を、そのまま何もいわず鵜呑みにせよといわれてひきさがるわけにはいかない。それでなくとも、これまで繰り返しいわれてきた新自由主義的施策のなかで、結局は割をくってきたのはほかならぬ労働者であった。正規と非正規の区別を最大限に利用しながら、あるいは両者の反目を利用しながら、潤ってきたのはとりもなおさず大企業・財界であったのだ。
当ブログは派遣切りが横行する今、これまで多大の貯め込み、つまり内部留保を蓄積した大企業がその一部を取り崩すことによって、経営を脅かすのであればまだしも、いくつかの試算でも明らかなように、多少の取り崩しでは企業はびくともしないことが想定されているのだ。これまで働く者からの収奪によって、正規雇用の非正規雇用への置き換えによって多額の利益を確保してきたのだから、その一部を取り崩すのは、企業の社会的責任を自認するのならしごく当然ではないだろうか。企業は、地方への企業進出の際、自治体からどれほどの助成金をいったい手中にしているのか。それに応えるのが社会的責任の一つであって、それを引き受けるのは企業なのだから。
こと今日にいたって、これまで貯め込んだ内部留保に着目せざるをえない。それは働く者の労働の結晶でもあるだろう。非正規への置換によって、固定費、端的にいえば人件費・労務経費を最小限に抑えることによって、利益拡大を図ってきたのだから、分かりやすくいえば、労働者から絞ったあげくもうけを積み立ててきたといってもよいだろう。不況になると、責めを負うのはひとり労働者なのか。一人ひとりの労働者はまったく見に覚えのない事態にちがいないし、それをなぜ引き受けなければならないのか。
それでも労働者に手っ取り早くしわ寄せし、利潤追求を第一義的に考える企業の論理に、異議を申し立てる必要が、今こそ求められるのではないのか。
異議を申し立て、企業のそうした論理にストップをかけ、労働者の働く権利を最大限に保障し、そして国民の生活を温めることによって、つまり国内消費を活発に増高させることで企業の経営活動を維持する方向というのは探ることができないのか。それを、国民一人ひとりが考える時期にさしかかっているのではないか。
ようするに、これまでの大企業のやりたい放題、横暴や勝手が見逃されるのではなく、国民生活の安定を重視した、そのことによって企業の経営も維持されうる方向が追求されるべきではないのか。それは可能ではないのか。
新自由主義に染まった90年代以降の日本の動向とは異なる、もう一つの日本社会のありようを議論すべきとき、それが今現在ではないのだろうか。
(「世相を拾う」09012)
■応援をよろしく ⇒
■こちらもお願い⇒![]()
「派遣村」をなぜ支援するか。
「派遣村」の取り組みは、本来、行政がカバーすべき分野であって、したがって、一連のいきさつによって、この問題での政府の実行力がほとんど皆無であることが明らかにされた。同時に、発端となったのが、解雇不可避を装うと表現してもおかしくはないくらいの、大企業の厚顔と横暴であって、大企業のこうしたふるまいがいかなるものか、今こそ、国民の関心がそこにも注がれないといけないことを、私たちに提示したのではないだろうか。
派遣というものが法律によって緩和され、しだいに正社員の置き換えによってそのウエイトを占め、一方でそうして大企業が膨大な利益を蓄積してきたという事実だけでなく、不況という事態になると、もっとも都合のいいように、まさに心を持たないモノのように扱われるのが派遣をふくめた非正規労働者であるという事実もまた、私たちの前に示したのであった。
正規労働者と非正規労働者という峻別が明確であればこそ、たとえば「努力すれば報われる」という言説、「自己責任論」、勝ち組・負け組をあおる風潮などに端的なように、分断と差別が受容される新自由主義を支えるための、ときの思想動員が貫徹されてきたといえる。労働者派遣法の施行と相次ぐ同法の改悪は、それを加速したといえるだろう。
こんにち、新自由主義のもたらした亀裂がさらに深まり、犠牲の及ぶ範囲がしだいに拡大し、圧倒的な部分がどこかおかしい、なぜこんな犠牲を強いられるのかと実感するにいたって、新自由主義の正体というものが認識されはじめたといえる。その沸点とはいわないまでも、今日の解雇・派遣切りはその最たるもの、こういった理解が広がっているのではないか。
だから、昨日のエントリーでふれたように、新自由主義によって自らの権益を確保しようとする勢力は、それを否定しようとする動向に少なからぬ関心をもち、抵抗するだろう。弁証法的に。
「派遣村」の経験が報道され、人の心をつかもうとすればするほど、それをくさし、否定するような巻き返し、反攻がはじまる。
坂本哲志の発言はその典型の一つだ。「派遣村」がまさに手を差し伸べようとする労働者を、特殊な一部として他の労働者と差別しようという魂胆である。支配層の抵抗勢力を押さえ込もうとする際の、抵抗勢力そのものを分断しようとする常套手段だ。しかし、話は複雑で、支配層からのこうした攻撃だけでなく、同じ対抗勢力のなかからも、足を引っ張る動きが出てくる。私はこのエントリーで示したのだが、たとえば赤木さん。彼の意思がどこにあったとしても、一部を全体から切り離し、その違いを強調することによって一部を排除しようという意図は否定できない(*1)。
「派遣村」に直接かかわった千葉茂さん(東京管理職ユニオン書記次長)が、朝日新聞「私の視点」(1・13付)で、「派遣村」にたいする支援と関心の深まりについて書いている。
千葉さんによれば、こんな反応があったらしい。
| 結局、あんたらの運動は、税金を使わせろということなのか。おれたち低賃金の労働者が納めた税金を何だと思っているのだ |
こんな電話だったという。これにこう答えている。
| 契約解除された派遣労働者もずっと税金を払っていたんです。その使い方について訴えて何が悪いんですか。ぜいたくをさせろと言っているわけじゃないんです。屋根のある場所で寝かせてくれと言うのは間違いですか |
千葉さんは、そのあとでこうのべている。至言である。
| 弱い者同士がいがみ合う構造から抜け出すことの重要さを、「派遣村」の活動は教えてくれた。 |
「派遣村」の活動を支持し、強く私が期待するのはこのためである。
今回の大量契約解除は、労働者を人間として見ていない企業が強行した「人災」だ。それを許したのは、規制緩和を進めた政府である--こう、千葉さんはのべている。事態をこれほど、明瞭に、しかも簡潔にとらえた言葉があるだろうか。
この点に、働く者は、その立場がいかに違おうと共感できるのではないだろうか。80年代から90年代に変わる時期を契機に、そして少なくとも小泉「構造改革」が進められて以降は明確に、社会保障など国民生活に直結する部門の切り捨てと同時に、働く者は絞りに絞られた結果、極論すればただ大企業のみが富を手にしたのではなかったか。
規制緩和を政府に迫りつつ、働く者を非人間的扱いで働かせて利益を集中させてきたのは、ほかならぬ大企業だった。それに手を貸したのは、政府にほかならなかった。そして、今日の労働者派遣法の改悪に手を貸したのは、自公だけでなく、民主、社民、国民新党の各党だったのだ。
大企業はその責任を果たさなければならない。政治は、一致して、大企業への規制を強く求めなければならない。
大企業の横暴勝手を正しうるかどうか、いよいよ重要である。それすら主張できないようでは何をかいわんやである。
(「世相を拾う」09011)
■応援をよろしく ⇒
■こちらもお願い⇒![]()
*1;ただ赤木氏は以下の文章で「派遣村」の運動にたいして一定の積極的な評価を表明している。
【眼光紙背】鶏口とならず、牛後となるべし
「この運動が大きな成果を得たのは、主催者たちが凄かったからではなく、年越し派遣村という、日比谷公園の小さな一角に、支援する側される側問わず、多くの人たちが集まったからであろう」などと、どうみても的外れといわざるをえないものも散見されるが。
キヤノンは横暴勝手の旗手か。
けれど、私たちがキヤノンの名を聞くのは、テレビで繰り返し流されるコマーシャルによってであって、さらにもう一つあげるとすると、昨年2月に国会質問で、志位共産党委員長が取り上げて以来のことでしょう。その後、キヤノンの名はしばしば雇用問題で取り上げられるのですが、マスメディアではなかなか扱われることは少ないようです。これは、メディアにたいしてトヨタがいかに圧力をかけているかを、以前にのべた(参照)のと、同じ事象だととらえてよいのでは。
そのキャノンですが、こんなあくどさは同社の一種の体質かもしれません。利益のためなら何でもやる、こんないわば決意にも相似するような同社の方針があるのでしょうか。これも、三大紙には報道されないでしょうから、ウェブ上の「しんぶん赤旗」から引用します(参照)。
| キヤノングループ2社など、大分県から多額の誘致補助金を受けた企業が、大量解雇を強行しても県には、いっさい連絡をしていなかったことが11日までにわかりました。「雇用機会の拡大」をうたって補助金をうけとっても大企業の身勝手がまかり通る制度であることが浮き彫りになりました。 |
経団連会長ならば、日本社会のなかでその影響力をもっとも揮える立場にある人であることはいうまでもなく、それだけではなく、財界のトップですから、社会的な識見もむろん備えているだろうと誰もが考えるでしょう。
けれど、キヤノンの現場の雇用実態、ふるまいは、そんなこととはおかまいなしに、横暴ぶりだけが伝わってくるようなものです。
県への報告について大分キヤノンマテリアルは「連絡はしていない。当社は減産をしただけ。当社と(解雇された)派遣社員は関係がない」。キヤノン本社も「(協定上の)操業短縮ではない。減産については県に伝えた」といい、キヤノン側は大量解雇であることを認めません。
大企業の横暴勝手の典型の一つがキヤノンだと思います。当ブログで扱ったキヤノンに関連する記事は以下に列記しているとおり。
キヤノンの恥辱- 杵築市が失業者を臨時雇用
「派遣切り」大企業経営者の顔- キヤノンの場合
止まらない人員整理- 産業予備軍としての非正規
2009年問題の展開― キヤノンの場合
ハケンはモノとして扱え。
これが「世界のキヤノン」か。
そのキヤノンの御手洗富士夫氏は、道州制の推進の旗を先頭きってふっています。「国と地方の公務員大削減と公共投資の「効率化」が可能」などといって、「行財政改革」の狙いが、財界・大企業の新たなもうけのための資金づくりをやろうとするものですから、どこまで御手洗氏はどこまでも大企業中心なのです。もちろん、地方自治体の改変にとどまらず、国の仕事を外交・軍事・司法などに限定する一方、教育・医療・福祉などにたいする国の責任を放棄し、地方におしつけることにほかなりません。
横暴勝手をさらにつきすすむつもりでしょうか。これだけ新自由主義、「構造改革」が残した貧困、格差に直面し、不況のなかにある我われは、企業の勝手を規制していくことがいかに重要かということを学んだのではないでしょうか。
(「世相を拾う」09010)
■応援をよろしく ⇒
■こちらもお願い⇒![]()
朝日新聞「資本主義はどこにいく」の語りかけるもの
| もし今、この二人が生きていたら。大恐慌下の73年前、その後の経済学を変える「一般理論」を書いた経済学者のケインズと、同じく恐慌を経験し「マネジメントを発明した男」と呼ばれる経営思想家のドラッカー。経済政策に企業経営に、どのような分析と提言をするのだろうか。詳しい2人に聞いた。 資本主義に基づく経済や社会はどう変化するのか。シリーズで考える。 |
こんなリードではじまる。
この企画もまた、表題に端的に尽くされているように、「大不況」の打開の方向をいまだ明確に示しえず、グリーンスパンに借りるなら「100年に一度」の経験なのだから、あたかも拱手傍観し、ただ事態を見守るばかりであるかのような今日の資本主義を問い直す作業の一つであることは論をまたない。だから資本主義は、果たしてどこにいくのか、いきつくのだろうかということだ。
シリーズとある。初回は、ケインズとドラッカー。
一般的になぞってみれば、新自由主義の破綻が明確になったといわれるくらいだから、それならばケインジアンの登場、こう推測できるはずで、伊東光晴氏の登場である。
まちがってならないのは、ケインズとドラッカーが今日を事態を、どう分析し、打開策を提起するのか、ということではない。むろん2人は過去の人だから、そんなことはできないし、2人を知悉する人物が、2人になりかわり、それをいわば代弁するという格好だ。
伊東氏も、ドラッカーを語る上田惇生氏も、重要な論点を提示している。
まずケインズの伊東氏。
| -では、ケインズはどんな失業対策を論じますか。 規制緩和がこんな事態を生んだと考えるでしょう。『派遣切り』された人や失業者に対し、生活保護に相当する額、例えば月12万円程度を渡したらどうですか。100万人で年に計約1兆5千億円。ばらまきの定額給付金をやめれば実現できます。月10万円の派遣労働なんかに行くな、と。そうして派遣をやめさせていきます。 |
上田氏。こうドラッカーを代弁している。
| -もし、日本企業のトップから「ドラッカーさん、あなたの言うことはわかる。しかしこのままでは会社が立ちゆかない。それでも非正規労働者を抱えろというのですか」と問われたら? 寮から出さなければ今すぐ会社がつぶれてしまうほどなのですか、内部留保もないのですか、かつて日本企業の多くは再就職の世話をしていましたね。そう彼は答えるでしょう。……。 |
つまり、伊東氏も、上田氏も、先達2人ならこ考えるだろうということを、上のとおり語っているわけだ。
伊東氏が先の引用で語るのは、政府の派遣切りに対する実践的な支援政策の方向だし、上田氏は、企業にたいして内部留保を吐き出すことによって労働者の生活を重視する姿勢を強調しているのだ。伊東氏のコメントは、先の引用のあとで、不況時の社会保障政策の拡充に及んでいる。
伊東氏が主に、政府のなすべきこと、上田氏は企業のそれに言及しているのは企画をふまえれば想定できることだが、ケインズと、ドラッカーならばこう語るということを解説する二氏の話を今、総合することが重要だろう。
つまり、政府は、思い切って国民政策重視の財政政策をとれということ、そして企業は、貯め込んだ内部留保、つまり労働者の労働の結晶ともいえるものの一部を今こそ吐き出すことで、その責任を果たせというのは、この時期に多数が一致できる打開のための第一歩といえるのではなかろうか。
ケインジアンも、ドラッカー信奉者も、上田氏が語るように「社会を壊すようなことはするな、重要なのは人であり社会なのだから」という一点では一致しうるのだろうから。逆に、この一点を、もっとも粗末にしたといえるのが新自由主義だろうからである。現時点で、この点での一致は要となるものではないか。
特集のテーマが「資本主義はどこへ」にあるのなら、それにふさわしい、もっとも重要な人物の一人であるマルクスを欠いてはこの特集は画竜点睛を欠く。以後を期待したい。
マルクスならば、はたしてどう語るだろうか。
(「世相を拾う」09009)
■応援をよろしく ⇒
■こちらもお願い⇒![]()
赤木智弘氏の着眼のおかしさ
帰宅途中、赤木氏の記事をこの目でたしかめようと毎日新聞の紙面を探してみたが、みつけることがかなわなかった。だから、古井戸さんの引用によるしかないことを最初に断っておく。
赤木氏の見解に疑問を私は率直にもつ。
引用によるかぎり、赤木氏は、連合のベア要求をやり玉にあげている。この、いわば非常時に何事かという意見は案外、支持を得るかもしれない。その上、このように赤木氏が連合にむかって、明確に批判するのだから。
しかし、この赤木氏の連合にたいする批判自体、裏返しにすると、連合がベア要求したことと同じ意味をもっている。ようは、今の局面でどこに手をつけるのか、という点で氏は異議申し立てをしているわけだ。
たとえば、このように。
| 現状でまっ先に課題とすべきは、ベアなどではなく、まず非正規の処遇 |
氏はこう主張する前提をなるほど置いているのだが、それはほとんど意味をなさない。氏によれば、その前提とは「自分たちが非正規問題の『従犯』だと認めるのならば」ということだ。だが、非正規労働問題にあたって「従犯は労働組合」だと連合・高木氏が仮にのべようとのべまいと、今現在の局面で第一義的課題は何かという問題はそれとは別に存在する。
私の考えでは、それは、氏がいうような「ベアなどではなく、まず非正規の処遇」でも、連合が主張するというベア(ただし、真っ先にベアだという表現を聞いたことはない)でもない、大企業に内部留保の一部を吐き出せ、それで雇用を守れということである。
氏の認識が引用のとおりだとすると、赤木氏は認識そのものを問われかねない。まるでイロハを理解していないかのようだ。
「私はまったく悲観していない。それどころか、不況になってくれてよかったと思っている。それにより社会の大勢には、弱者に対する同情心などなかったということが、ハッキリ示されたのではないか」というのはまだかわいいかぎりだが、しかし、これはどうか。
| 今回の連合によるベア要求は、格差問題がけっして「労働者vs経営者」という二元論に納まる問題ではないということを明らかにした。今後、現状の立ち位置をうやむやにしたまま「正規も非正規も関係なく、一緒に闘うべきだ」と共闘を訴えるだけの言論は説得力を失うだろう。 |
仮にも連合がいかなる立場の労働組合だったのか、氏が知らないはずはないだろう。かつても、おそらく今も昔流の言葉を使えば、連合が労使協調派という区分に該当することをだれも否定しないのだから。それとも、赤木智弘氏はこの事実をあえて隠しているのか。(こんな連合を)いわゆる労働組合一般に置き換えるという詐術をとっているといわれても仕方ないだろう。
このように、正規労働者が非正規労働者を差別するという彼特有の構図からいまだに脱しきれない赤木氏が、(非正規労働者を救うために)いったいこの局面打開のために、どんな影響力を発揮したのだろうか。
端緒ではあっても、湯浅氏や一部の労働組合の貧困に反対するという一連のキャンペーンは確実に世論を動かしつつあるという確信を私はもつ。そして、そうしたキャンペーンと同時に、具体的に雇用問題を解決しようとする実践、たとえば相談活動や年末からの「年越し福祉村」の取り組みが、連帯の機運をいかに広げているか、考えるべきだろう。
だからこそ、それを快く思わない勢力は、あらためてアンチ・キャンペーンの反攻に出ているわけだ。
昔の人はよくいったもので、運動が強まれば、そのことが反勢力の運動を招来する、つまり弁証法的にものごとは動くのだ。しかし、その展開にこそ発展の契機が見出しうるというわけだ。
湯浅氏らの実践はその意味で将来への萌芽を大いにふくむだろう。一方で、赤木氏の言説は、氏の本意がどこにあるのか知らないが、こうした階級間の対立を、傍観者的にながめつつ、実は、対抗する勢力、対抗しようとして連帯しうる勢力の間に、世間の晴れて「公認」となった言説でもって楔を打ち込むようなものだと表現しうるだろう。
赤木智弘氏の言説で労働者が励まされるようなことは一切ない。そうではなく、お互いの反目の契機があるのだとすれば、そこにあえて亀裂を拡大するように作用するだけのものだ。
氏は、これまでの言説の着眼から一歩も抜け出ていない。新自由主義は、国民の多くに、富と貧困という二極分化を鮮やかに示し、その一極に富を集中している大企業・財界があることを照らし出した。
だからこそ、今、われわれの眼は、大企業・財界に向けられないといけないだろう。
氏の限界は、これをまったく欠落させている点にこそある。
(「世相を拾う」09008)
■応援をよろしく ⇒
■こちらもお願い⇒![]()
【関連エントリー】
一部が苦しむ不平等か、全部が苦しむ平等かという問い。。
赤木智弘「正規が非正規を搾取する」。のだろうか。
オバマのナイ起用に対する懸念
オバマ新政権への期待は、医療保険制度の改革、金融危機への対応など、彼がこれまで取ってきた態度から判断して高まるばかりです。
私は、しかし、オバマが大統領選で当選した際、いくつかの懸念をもっていました。それは、以下のエントリーで記したとおりです。
この報道による限り、その懸念がますます深まる、そんな印象をもちます。
懸念の一つは、彼の対日外交姿勢でした。
ナイが駐日大使に選ばれたのは、先のエントリーで指摘した、オバマがナイをブレインにしていることと連続しています。つまり、その時点でもっとも私が心配したのは、「いっそう日本への要求、米国の肩代わりを求める圧力は強まる」ということでした。
ナイの駐日大使就任は、おそらくそれを追認することになるのではないでしょうか。
日本は今以上に、財政的・人的に負担を迫られるという覚悟を強いられるということです。
しかし、考えてみるに、日本の戦後は極論すればアメリカ一辺倒でした。アメリカという目標が一つあって、それに追いつき追い越そうというのが、戦後の歴史だった。いつでも米国の顔色をうかがい、いつでも米国にしたがう、米国といわば運命共同体ともいえる関係が築かれてきました。その大元に、日米安保条約があるのは周知のとおりです。政治的にも、経済的にも、離れがたい米国との関係を自ら位置づけてきたのでした。
敗戦から60数年。米国を盟主として、米国の要求に基本的に従順にしたがってきた結果の一つが、今日の金融危機とそれが及ぼす日本経済の影響に端的に表れています。おいおい明らかにされるでしょうが、米国側の要求にしたがって、今日の金融危機、世界経済の危機の発端となった、サブプライム関連の商品を買った日本の銀行資本の損害はいったいどれほどの金額になるのでしょうか。国民を納得させるような解説は今もってなされていません。それほどに、誤解を恐れずいえば、米国のいいなりに、盲目的に行動するのが日本だといいきってよいのではないか。
だから、このような日米のきわめて非対称な、主従の関係、あるいは一方が他方に追随する関係は、経済だけでなく、むろん政治にも貫徹されており、それを今、あらためて問い直す必要があると考えるのです。
当ブログが主張しつづけるのは、今日の日本政治のゆがみは、財界・大企業への途方もない優遇とともに、米国への盲目的といわんばかりの追随ぶりです。
ナイの就任前にあらためて喚起しなければなりません。
いっそうの米国の対日要求に、毅然として対処できる政府が必要です。
ナイの起用は、朝日がいうような「オバマ政権の対日関係重視の表れ」というきれいごとでは私はないと考える。日本の肩代わりを、まさに実行に移すための特段の起用だといえるのではないか、こう思うのです。
世間の米民主党・オバマ氏への期待とは裏腹に、強く懸念するのはこのことです。米国のアフリカ系住民の期待を一身に受けて当選したオバマ氏ですが、日本にひきつけて考えると、こんな不安を抱かせる政策の持ち主でもあることをけっして無視するわけにはいきません。
(「世相を拾う」09007)
■応援をよろしく ⇒
■こちらもお願い⇒![]()
【関連エントリー】
オバマ当選に思う
新テロ法延長の意味・または・民主党の動揺
坂本哲志発言と新自由主義からの決別ということ。
さかのぼれば臨調行革にたどりつく、日本の新自由主義の流れ。その残した亀裂に国民の多くが直面し、ようやくこれではだめだと気づくこととなった。臨調行革が路線として明確に敷かれることになったとき、私たちは、その特徴を分断と差別という言葉でよく表現したものであった。
今日の目でふりかえると、あながちそれはまちがいではなかったといえる。
あえて今日の新自由主義という言い方をすれば、これもまた、徹底して国民の分断を図り、そうして結果的に差別を合理化するものであった。国民のなかに亀裂をもちこむことが、支配ということにとっていかに重要か、新自由主義を推進しようとする時の支配者は知悉していたということになる。
勝ち組・負け組という言葉、自己責任という言葉をいまや知らない者はいないといってもよいだろう。つまり、世の中のあらゆることは自分で切り開け、できないのはおまえが悪いからだ。これが簡潔で端的な言い回しだった。そして、毎日の生活がままならぬ事態もまた、自分に回収してしまうようになっていった。格差が広がり、貧困に直面する人がしだいに増えても、それが可視化されず、問題として共有されなかった要因にそのことはおそらく直結している。この一連のしくみが、国民のなかに広く伝播する、そうでなければ浸透せず、路線として定着しないのが新自由主義である。
当ブログが再三、ハーヴェイを引用しつつ、運動の下支えが必ずあるといってきたのはこのことである。
つまり、私たち自身がいかに以上の新自由主義を本意ならずも推進する思想に染まっていたのか、今の時点でふりかえってみる必要がある。
坂本哲志総務政務官の発言が問題となっている。政府はまた頭の痛い問題を抱えることになった。しかし、今日の事態に私たちが直面して、あらためてそのおかしさに気づくのだろうが、あえていえば坂本氏と同様の考え方は、率直にいえば、深く、広く最近まで潜行していたのではないか。
先に、勝ち組・負け組のことをいったが、負け組になるまいとし、人を蹴落とすこともまたやむをえないと大方がおそらく考えた。しかも、この際、事態をいっそう複雑にするのは、負け組をさも「おまえが悪い。自業自得」といわんばかりの、あざ笑うかのような勝ち組と自ら判断する者の視線と口調ではなかったか。つまり、その心性が、まさに新自由主義を支えていたのだった。こんな形で今日まで臨調行革以来の分断と差別が貫かれていたのではなかろうか。
この際、私たちが結果的につき動かされ、促され、その気になっていったのは、こんな人物たちの発言の一つひとつであったろう。
たとえばその一つ。奥谷禮子氏。
| 自己管理しつつ自分で能力開発をしていけないような人たちは、ハッキリ言って、それなりの処遇でしかない。格差社会と言いますけれど、格差なんて当然出てきます。仕方ないでしょう、能力には差があるのだから。結果平等ではなく機会平等へと社会を変えてきたのは私たちですよ。下流社会だの何だの、言葉遊びですよ。そう言って甘やかすのはいかがなものか、ということです。 さらなる長時間労働、過労死を招くという反発がありますが、だいたい経営者は、過労死するまで働けなんて言えませんからね。過労死を含めて、これは自己管理だと私は思います。 |
氏の『週刊東洋経済』(07・1・13)での発言だ。
氏が語るのは、自己責任の強調である。あたかも努力すればそれが報われるかのような言説。それをまともに受け止めてきたのは、私たちであって、それが結果として新自由主義の徹底に少なからぬ役割を果たしたのだ。
けれど、こうして一時期は圧倒的な支持を得た、小泉流の新自由主義的改革、「構造改革」も時が経ち、「改革」が生み出す亀裂が多数の国民を飲み込む事態にいたって、国民の間にしだいにこのままでよいのか、という実感をもたらすことになった。つまり、湯浅氏が的確にたとえているように、研ぎ澄ませば研ぎ澄ますだけ実感されうる、明日は自分ではないかという「すべり台社会」の不安が現実のものに転嫁する。それがまさに今日伝えられる事態だろう。いまは非正規のことだと高をくくっていても、それが正規に及ばないと保障しうる人がどれだけいるのか。いない。これが働く者の不安となって現れている。現に、すでに伝えられるところでは正規もまた解雇の対象となっている。
日本をふくめて資本主義が金融・経済危機をいかに乗り切るのか。いまだに処方箋を明確にしえないという事実が、今日の資本主義そのものの危機をそのまま表現している。資本主義の限界をいいだすものもすでに少なからずいて、しかし、それは私たちの周りの状況を直視すると十分うなづけるものではないか。
つきつめると、それだけの危機に日本社会を牛耳る財界・大企業が直面しているわけだが、すなわち、別のことばでいえば、これは、かつて常套語であった階級的対立のなかに今、日本があるということを示している。それは、ある意味で単純で、古典的な労働者の首切りを軸にしているという点で、深刻でもある。
一日一日の首切りを許してはならない。今後、首切りの拡大を許せはしない。ましてや、これまで労働者を搾りに搾って貯め込みをつづけ、その一部を取り崩したくらいで、企業の経営活動に支障を来たすなど、到底いえないくらいのものであることは容易に推測できるものなのだから。そんな現実をまず私たちは共通のものにしないといけないだろう。内部留保の一部をはきだせ、これを党派を超えたものにしないといけないだろう。
坂本氏の発言はだから、現実をとらえたものとはまったくいえない程度の発言だ。
まじめに働こうとする意思の有る無しにかかわりなく、事態はもう深みにはまっている。そんな意思とはかかわりないところで、労働者の命を奪いかねないところにあるのが今の事態だ。まじめか否かとは別に、現に働いてきて、解雇され、手持ちの金が百円にも満たない30代の青年労働者が路頭に迷う。こんな事実がたとえ一人でもあったならば、そこにどう手を差し伸べるのか、大なり小なり、それが政治のやる仕事ではないか。
坂本氏は政治家であって、この現実にまったく向き合えない一人であることがあらためて確かめられたわけだ。しかし、こんないいようで、分断を図ろうとする意思が働いていることを見抜かなければならない。あたかも個々人の気持ちが問題であるかのように。
私たちが仮にもこれまでの新自由主義の日本の深化にたとい微々たる一部分ではあっても下支えしてきたという反省に立つのなら、きっぱりとこれまでをここで脱ぎ捨て、新自由主義にすがりつこうとする勢力に今度はしっぺ返しをしなくてはならないだろう。
総選挙は、その絶好の機会にしたいものだ。
新自由主義にすがりつこうとするか否かの試金石は、財界・大企業に対峙しうるか否か、悪いことは悪いと真正面から批判できるかどうか、そこにある。
それを、一つの物差しに、政党それぞれを監視し、選択しないといけない。これが新自由主義からの決別の意味ではなかろうか。
(「世相を拾う」09006)
■応援をよろしく ⇒
■こちらもお願い⇒![]()
朝日見解にたいする疑問- 「対決」を強調しても。。
通常国会が5日に開会しました。たしかに冒頭から、民主党は第2次補正予算をめぐって対決の姿勢ですが、少しも自民、民主の対決の姿が私には浮かびません。つまるところ、定額給付金をはずすかはずさないか、それをめぐって両党がつっぱりあっているにすぎないのではないでしょうか。
星さんと私がよぶのは、朝日新聞編集委員の星浩氏。そう、日曜日の田原総一朗の「サンデープロジェクト」にコメンテーターとして登場している人物です。
少し、その星さんのいうところを引用してみましょう。
| 自民、民主両党が政権を争う事実上、初めての総選挙。基本的には勝った方が政権に就き、首相を取り、政策を実現する。まさに天下分け目の戦いだ。政治家同士の真剣勝負を期待しよう |
ということなのですが、ほとんど有権者の意識と乖離していると私は思います。
たしかに今回の選挙にあたって、自民党はダメだと思う人が多いのは事実。世論調査でそのことははっきりしています。同時に、この種の調査が示しているのは、自民党に代わりうる政党として民主党なのかといえばそうではなく、ある意味で(有権者は)消極的選択に甘んじているというところでしょう。
私にいわせれば、消極的選択であるにせよ民主党に落ち着くようにセットされているという意味で、二大政党制を志向してきた支配層の思惑は保持されている、このことが重大ではないかとも思えるのですが、しかし、当初の二大政党制のねらいは、今日にいたって、事実上やや修正を迫られているようにも思える。事実をあげてみれば、昨年の参院選後の、福田・小沢の大連立密室協議は、少なくとも自民・民主で政権を維持し続けるという意味での二大政党制の本来の目的を根底から崩すものであったはずです。そして、今日。自民党の次期選挙での退潮を誰もが否定しない状況の下で、自民、あるいは民主党の周辺で何が起こっていて、私たち有権者の前に示されているのでしょうか。
どんな形で結実するのか、それを今の段階で予測するのは並大抵ではありませんが、少なくとも、従来の自民党と民主党の枠組みを超えたところで、新しい政党の姿というものを模索し議論せざるをえないところに、自民党は、そして民主党もまた追い込まれている、これが率直な感想です。
つまり、二大政党は変容を迫られているということでしょう。
もっと以前に遡ってもいえることなのですが、ごく最近でいえば、舛添氏が製造業での派遣を否定するかのような、あるいは企業の内部留保の活用に言及するような河村官房長官の発言は、「自民党は、そして民主党も追い込まれている」と私がのべたこととけっして無関係でないように思えるのです。もはや自民、民主を区別する意味すらない、事態はこのような地点まで進んでいるというのが私の見立てです。両党の境界は、事実上溶解して区別がつかないといえる。
たとえば、河村氏の発言が仮に本音だとすると、民主党はこれにどう応えられるか。答えは、ノーです。民主党の立場では、内部留保を取り崩せとはいえない。そんな方針すらもっていないのですから。すなわちこれは、これまでの自民党の立場と同じものです。発言が逆に本音から出たものでないとしても、民主党はおそらくこれに反論すらしないでしょう。
こういうふうに考えた上で星氏の文章に戻れば、星氏のいうところはまるで絵空事に思えます。まったくの虚構の対決だといいきってもよい。
そんな架空の対決を強調するより、今は、まさに日々、深刻化している景気悪化にたいする具体的な対応、そこに政治が手を差し伸べなければならないのでしょう。たとえば、それは、解雇拡大をこれ以上、広げないことで全党が一致することではないか。それに反対する政党があれば、その政党に総選挙で明確に審判を下す。これこそ、星氏がいう私たちが「試されている」ことではないでしょうか。
(「世相を拾う」09005)
■応援をよろしく ⇒
■こちらもお願い⇒![]()
内部留保を吐き出せ- 河村発言を全党一致で実行させよ。
河村官房長官:雇用維持、内部留保で 企業に活用促す
自民党の内閣官房長官にこう語らしめるのは何か、考え、疑った。
なにぶん、財界・大企業に拠ってきた自民党が雇用の確保に内部留保を活用せよというのだから。共産党がいっているのではない。河村氏の発言がパフォーマンスでないとすれば、大いに評価してしかるべきだ。
この際、自民党にはこの発言にもとづき、財界・大企業に強く要請し、形あるものを成果として我われの前に提出してほしい。あわせて、この官房長官の発言を受け、全ての政党が内部留保の活用で一致するならば、日本の政治史上、画期的な出来事だと評価しても、けっして大げさではないと私は思う。
すでに明確にこれを主張している共産党はともかく、そのほかの政党はこれに言及することはなかった。つまり、当ブログが再三、主張しているように日本の政治シーンでいったい大企業・財界にまともに要求をつきつけることがあったのか。そうではなく、大企業・財界には、たちまちモノいわぬ、まるで僕でもあるかのようにふるまってきたのが日本の政治だったのだから。
したがって、氏の言葉を額面どおりに受け止めれば、一つの驚きであることにまちがいはない。
金融危機が各国の実体経済を揺さぶりつづけ、今現在、明確な脱出法が示されたわけではけっしてない。いまだに対応策は見出しえてない。
だからこそ、大方のエコノミストたちがこぞって、深刻な今日の不況から回復できるのは2010年だと予測するのが、いよいよ真実味を帯びている。日経新聞は、それをつぎのように紹介している(1月3日付)。
| 2009年の日本経済は実質国内総生産(GDP)が米欧とともにマイナス成長に陥り、回復の糸口を見つけにくい状況が続きそうだ。民間エコノミスト15人に予測を聞いたところ、景気交代が深く長くなるとも見方が大勢を占めた。金融投機による世界と同時不況で昨秋以降、輸出と生産が急激に落ち込み、雇用調整が消費不振を招きつつある。本格回復は10年にずれ込む見通しだ。 |
と。
米国が主導するカジノ資本主義に浸りきり、海外での消費に依存してきた多国籍企業のこれまでのふるまいにまったく頓着することなく、「輸出と生産が急激に落ち込み、雇用調整が消費不振を招きつつある」と断じるところがいかにも日経的だ。国内消費を軽視する一方での輸出依存こそ、金融危機の影響を深刻にさせた要因なのは、すでに多くの識者によって指摘されているというのに。
国内消費を上向きにするためにも、国民の生活を温めなくてはならない。それは、たとえば雇用確保に最大限の努力を払うこととまったく矛盾しない。そのためにも、財界・大企業は率先して、これまで貯め込んできた内部留保を活用すべきなのだ。その一部で、どれくらいの雇用が確保できることか。いくつかの試算が明らかにされている。
この文脈にそっていえば、河村官房長官の発言自体は、積極的意味をもっているのだ。
冒頭に戻るが、河村氏がこう、仮にパフォーマンスであるにしても発言せざるをえないのは、不況の深刻化のなかで内需を高めなければならないという意見が正当で、それを与党といえども無視できなくなったからである。まったく身に覚えなく、突如、解雇を宣告されるのが労働者であって、片方で、その労働者の汗の結晶ともいえる利益確保で、財界・大企業が膨大な資本蓄積を図ってきたという、明らかに非対称な事実が多くの人に知られるようになったからである。
労働者を、あえてこの言葉を使うが搾取することによって、巨万の利益をわがものにし、株主に配当しておきながら、雇用調整の名のもとに、まるで使い捨てのように労働者を扱う姿に、多くの人が気付きつつあるからである。
内部留保の一部を取り崩すことで、大企業が立ち行かなくなる、そんな虚弱体質では、少なくとも日本の多国籍企業はない。十分に体力がある。
本来、企業はその利益を蓄積し、労働者の賃金にあてるか、設備投資に備えるか、そして、あるいは急激な経済的・金融事情の変化にあてるのだろう。
だから、今回の、まさに金融危機に際しては、内部留保を一部取り崩しそれに対応しなければならないだろう。それが企業の釈迦的責任ということに応えることになる。また、回りまわって、内需をよぶわけで、すなわち企業の経営活動にも寄与することになるだろう。
今こそすべての政党が、内部留保を一部吐き出せの声をあげるべきだ。共同歩調をとるべきだ。そして、実行に移させなければならない。強い指導と監視が要る。
そして、それに同意しない政党はどこか、それを国民は見極める必要がある。そんな政党は総選挙で選ばないことだ。
河村氏のいったことが言葉だけのものであるのなら、我われは、手痛いしっぺ返しを自民党に浴びせなければならない。
(「世相を拾う」09004)
■応援をよろしく ⇒
■こちらもお願い⇒![]()
【関連エントリー】
内部留保を一部はき出せ -派遣首切り
『サンデーモーニング』の語る「米国の黄昏」
「米国の黄昏」は、たとえば今日のドル安にも端的に表れているが、番組は、今日の米国社会の現状を知る上で有用な事実をいくつか紹介していた。今日の世界危機をもたらす発端になったサブプライムローン。その結果、物件の差し押さえ件数は280万件にのぼるという。
米国民の12%・350万人が「飢え」を感じている。その飢餓状態は、NPOの運営する無料食料配給所に何人もの人が群がる映像でよく分かるものだ。だが、これは対岸の火ではけっしてない。ここ数日、どのチャンネンルでも日比谷の「年越し派遣村」の様子をとりあげ、民間のこうした努力とは裏腹に、腹がたつほどに遅い政府の対応に関心と批判が集中している、いまの日本社会の一面とも重なるだろう。これが高じると、米国のようになる。誰もが予測できる、ある意味で決定づけられた方向である。
米国にはまた公的保険がないこともよく知られている。実に4600万人もの人がいわゆる無保険の状態にある。
番組は、限られた時間で、建国以来の米国の政治・経済・社会を跡付け、黄昏が歴史的にみて、たとえばベトナム戦争を契機とした軍事費の増大など、いくつかの要因をへてもたらされたことを伝えていた。実体とはかけ離れたところで動く、博打の世界たる金融経済。その結果が今日の米国ということになる。
しかし、日本はこの米国を敗戦以来、目標にしてきた。アメリカナイズが戦後、日本のある意味で目標であって実態であった。社会の表層がこうであるとすれば、深層の日米の関係は、政治的には日米安保条約で規定されるだろう。日本の対米従属。そのもとでこそ日本の高度成長もありえた。日本の戦後政治を規定するタームを一つだけあげれば、対米従属だ。あらゆる場面で米国の顔色をうかがい、米国に従う。それは今日でも少しも変わらない。日米安保条約に集約される日米の関係は、むろん日米の経済的関係も規定している。その従属と依存の関係は、したがって今日の金融危機にも表れた。
昨日のエントリーで朝日新聞の姿勢を扱った。「たくましい政治」という曖昧模糊とした言葉でもって、今日の日本社会のゆがみの原因に迫ろうとすることを遮ろうとする朝日の言説を批判した。
つまり、対米従属をあらためることは、今日の日本の窮状から脱却しようとすれば、避けて通れない課題だ。冷静に事態をみるならば、対米従属を改めることなしに、新自由主義からの脱却もありえないだろう。大企業・財界優遇をあらためることなく、新自由主義をいくら訴えても何も主張していないに等しいのとおなじように。
米国依存関係が社会にいかに亀裂をもたらしているか、それは日本だけのものではもちろんない。一つだけあげると、ウクライナも金融危機の波をかぶっている。
周知のようにウクライナも外貨導入と市場経済化を図ってきた。したがって、その分、グロバリゼーションの影響も大きい。テレビでしばしば伝えられるアイスランドの危機とその点で同じだ。
2000年以降、7%台を維持していたGDPも、05年に2%台に鈍化、08年も2.5%と推定されている。さらに不安をかきたてているのは、親米派といわれるユーシェンコ大統領とティモシェンコ首相の間に亀裂が入り、南オセチアをめぐるグルジア・ロシアの軍事衝突で政治的対立が決定的になったとされていることだ。その後、大統領と議会の対立など混乱がつづいている。
そのウクライナでは、いま外貨が急速に引き揚げ、国内の金融システムは危機的状況だといわれている。昨年10月だけで欧米の外貨130億ドルが流出したとされる。対外債務が1000億ドルを超える一方で、外貨準備高は346億ドルにすぎない。米国に追随するグローバル化の影響は否定しがたい。
番組のなかでコメンテーターが米国との関係を見つめ直すことが必要だと説いていたが、以上の意味でまったく妥当なもので、首肯せざるをえない。
つまるところ、大企業・財界優遇を問い直すこと、米国追随の政治を一から問い直すことが今、求められているということだ。
(「世相を拾う」09003)
■応援をよろしく ⇒
■こちらもお願い⇒![]()
新自由主義からの決別を語れない「朝日」社説
混迷の中で考える―人間主役に大きな絵を
しかし、「たくましい政治」とはきわめてあいまいで、いまの政治からどう転換を図るのか、まったく定かではない。結局、今の政治のゆがみを隠し、それに言及していないでおこうとする意図がそんな表現を強いるのだ。
繰り返し、当ブログは今の自民党政治の本質を、大企業優遇と米国追随だとのべてきた。これをたださないと、新自由主義から反転させることはできない。今の国会のなかの政党にも、そしてマスメディアの多くにも欠如しているのはこの点である。それは、すなわちこれまでの自民党政治の枠組みにとどまることを意味している。
もう一昨年のことになったが、サブプライムローンを引き金にしたバブルがはじけ、金融危機が昨年、世界中を覆い尽くし、たとえば解雇の横行にみられるような、日本では誰もが知る事態に至った。ここ2年ばかりの世界で引き起こされた事象が、ものの見事に、経済のグローバル化と新自由主義がもたらすものを示した。まさに劇的に。
新自由主義からの決別を多くの論者がいう。ブログ上でも。
ハーヴェイのいうように、それを下支えする運動があるのが新自由主義で、とくに小泉構造改革以後の日本はそれに覆われた。勝ち組、負け組の言葉が一世を風靡したように。自己責任がいたるところで強調されたように。
別の角度からみると、資本の論理の強調だった。戦後、高度成長とも結合した企業内で自己完結する企業社会と、新自由主義はうまく結合した。企業内の競争と正規・非正規の差別を徹底しようとする企業の思惑に、長年の企業社会を活用することはそれほどむつかしくはなかった。
そして、この企業社会の中で醸成された意識は、いまでも日本の底流に潜んでいるのではないか。
いままさに、非正規を切り捨てることで、資本蓄積の構造を維持しようとする企業の論理を問うことが、政治に求められている。自民党よ、民主党、社民党よ、いま大企業に解雇撤回をせまるべきではないのか。解雇されたものの具体的な支援を、政府と大企業に求め、実行に移させることではないか。
単なる一つの問題だが、各政党がこれまでの自民党政治からの転換を図ろうとしているのか否か、これが問われる試金石になる問題だと考える。
朝日の社説は、このような見方からすると、まったく体制内にとどまった主張だといえる。その意味であいまいなのだ。
メディアは、繰り返すと、大企業に牛耳られている。それを端的に示したのが、昨年の奥田発言、マスコミへの脅しだった。
つまり、事態は、日本の政治のゆがみを生み出す大本を照らし出す位置にいまあるということだ。新自由主義という路線は、財界・大企業優遇と米国追従にいかに日本政治が侵されているのか、それを私たちの眼前に示したのだ。
2009年は、だから支配層にとっては一つの困難に直面しているわけであって、総選挙では、国民が横暴・勝手を管理しうる政治を手にするための第一歩にしないといけない。新自由主義に賛成する政党は選ばないことだ。
国民にとって、ふさわしい政治とは新自由主義と真に決別した、財界・大企業優遇と米国追従のゆがみをただせる政治を意味している。
朝日は、新自由主義からの決別を語れない。
だから、朝日の社説はつまらないのである。
(「世相を拾う」09002)
■応援をよろしく ⇒

■こちらもお願い⇒
bookmark 紹介- オーソレ、何それ? 代替案 らび草子
以下は、開設以来のお気に入りというところです。 画像をクリックすると、それぞれブログに移動します。お立ち寄りいただければ、当ブログ管理人としてうれしいかぎりです。
一つ目は、オーソレ、何それ?
管理人さんは今、アメリカに転勤。エントリーには、もちろん当地の生活、風景がふんだんにでてきます。これが新鮮です。
| サンクスギビングの休日が終わり、アメリカの国民的行事「クリスマス・ショッピング」が始まりましたが、やはり例年よりも出足は鈍いようです。これからクリスマスへと続くアメリカで一番華やか時期にいかにも景気の悪い話で残念です。これもアメリカのエリート達が作ったシステムの破綻だとすれば自業自得といえないこともありませんが、庶民にとってはやはり災難だと思います。 http://blog.goo.ne.jp/o_sole_mio00/e/851b07e73a9543bb3f2d0b922bad9b70 |
o_sole_mioさんの優しいまなざしがここにあります。
つぎは、代替案。
管理人・関さんは大学の先生。ご専門は、地球温暖化に深く関係します。
ご縁ができたのは、チリのアジェンデ政権を扱ったことでしょうか。
米国の陰謀と軍部によって転覆させられましたが、いまや南米は、反新自由主義の強い絆で結ばれています。数十年ののちに、クーデタを断罪する潮流が太い流れになったということでしょう。
| 「ラテンアメリカとフリードマン: 神話の捏造」という記事を書いて、経済学者のミルトン・フリードマンと、フリードマンの経済理論を国家規模で初めて実践したチリの独裁者アウグスト・ピノチェトを批判しました。先月フリードマンが亡くなり、一ヶ月遅れて今月の10日にはピノチェトが亡くなりました。市場原理主義を唱導したフリードマンと、軍事的抑圧体制によってそれを実現したピノチェトは、今日に続く市場原理主義世界帝国の基礎を作った「キー・パースン」といえます。その二人が相次いで亡くなったことは、これから起こるであろう時代の変化の始まりを告げる象徴的なことかも知れません。 http://blog.goo.ne.jp/reforestation/e/bb33f28d51e92741fb2e79672df8498e |
そう、チリを新自由主義のいわば実験台にしたのは、米国の意を受けたあのミルトン・フリードマンでした。
最後は、らび草子。
管理人さんはどうやら、私と同じ県にお住まいの方らしい。憲法の問題で、ややヒートアップしたことが懐かしく思い出されます。
この世には女と男が存在するのは当たり前ですが、人は自分ではないもの、欠落するもの、ちがうものに関心を示すもの。
一つひとつのエントリーの文体に、私は強くそのことを感じるのです。
| 職場で大変お世話になった人に寄せ書きをすることになった。 空がたくさん写っている写真集を買ってきて、好きなページに好きな色のペンで言葉を書いていく。 青空のページに書いていると、それだけで胸がいっぱいになってくる。 楽しかったですね! ありがとう! と送り出しても、正直にいうと人がいなくなるのはやはり寂しい。 |
■応援をよろしく ⇒

■こちらもお願い⇒
大企業を規制する年に。
いま、ここ九州でも雪が舞っています。予報で最高気温が5度と伝えられているのですが、この冬いちばんの寒さのように感じられます。この寒波は、昨年来の不況の深刻化を理由に労働者の首きりが横行している日本の現状と、彼ら働く者のことを想起させないはずがありません。
年越し派遣村の村開きをニュースが伝え、深夜番組に湯浅誠が登場し、政治がやるべきことを強く主張する。
ここに、今日の日本社会の抱える、喫緊の課題があることは論を待ちません。2008年からの政治課題の中心の一つに、雇用問題がすわり、すなわちこれは、いまの日本の政治のあり方を問う問題として登場してきたといえます。
およそ20年前の労働者派遣法の施行以来、改悪に改悪がつづき、共産党を除く日本の政党すべてが改悪に賛成したこともあるくらいですから、この点で政治の責任はすでに大きいのです。規制を緩和するといっては、大企業のいいなりになって、結果的に奉仕してきたのですから。
世界に目を転じると、日本でこうした政策実行を支えてきた新自由主義というものが、金融危機を招き、実体経済に大きな脅威を与え、新年を迎えたということにもなる。
つまるところ、日本の政治がこのように大企業のいいなりになり、大企業の利益確保に加担する一方で、労働者の働く権利を脅かし、生活を奪う。金融危機を契機に、伝染するかのように各大企業がつぎつぎに人員整理計画を公表していることは、新自由主義的施策が国民にとっていかなる意味をもつのか、それを集中して表現したものではないでしょうか。
富と貧困の二極化。2009年は、この傾向が強く、太くなりそうな気配であることにちがいはなさそうです。
ところが、ほとんど統治能力がなくなったと私には思える政府が、実効ある政策を打ちだせないだけでなく、野党第一党の民主党もこの問題では少しも目立ちません。そう思われませんか。なるほど政策はつくったようですが、政権をとったらという条件に重きを置いた主張が繰り返される事態は、いっこうに変わりありません。極論すると、不作為を決め込んでいるようなものです。
今、求められているのは、実際に解雇された、あるいは解雇や雇い止めを宣告された労働者一人ひとりに手を差し伸べることです。冒頭に記した湯浅らの「年越し派遣村」などの支援活動のように。そして、共産党のように大企業に出向き、要求をつきつけることが求められている。政策を打ち出すことよりも、実効ある措置をとる、とらせることこそ必要でしょう。
こうした、とくに国会内の政党状況は何もこの派遣切り問題にとどまりませんでした。昨年をふりかえってみると、結局、自民党も、民主党も、国民が望む生活の苦しさを打開するという点で、政治を動かすことはできなかった。動かすには国会での論戦がもとより必要なのですが、率直な私の感想は、極論すれば自・民の間に論戦はなかったということです。政権維持と政権交代ばかりが前面に出た党略と政局に流れてしまう二党の姿勢は厳しく批判されないといけない、こう思います。
労働者の、とくに非正規雇用をめぐって、労働者の取り組みと国会の論戦が結合し、昨年は大企業の雇用実態が告発され、一定の改善がかちとられています。与党がやらないのなら、すべての野党がこうした、大企業に迫る行動を取ればよいと思うのですが、必ずしもこれが容易ではない。大企業にモノをいうこと、これが、日本の政治の現場ではまるでご法度になっているかのよう。実はここにこそ、今日のように極限に近い形まで政治と経済のゆがみを生んできた要因があるのですが。
大企業優遇の政治をあらため、これに規制を加えることが可能な政治。こうした政治を実現できるのかどうか、これが今年の課題になるのではないでしょうか。
横暴や勝手に規制を加え、ルールにもとづいた社会にする課題、これを一歩でも前にすすめることができるのかどうか、今年はこれが正面から問われそうです。
(「世相を拾う」09001)

■こちらもお願い⇒