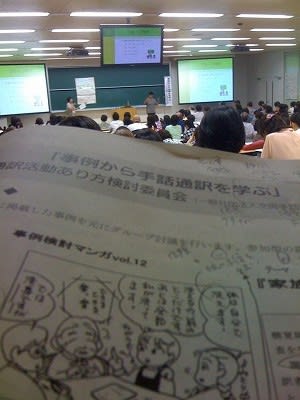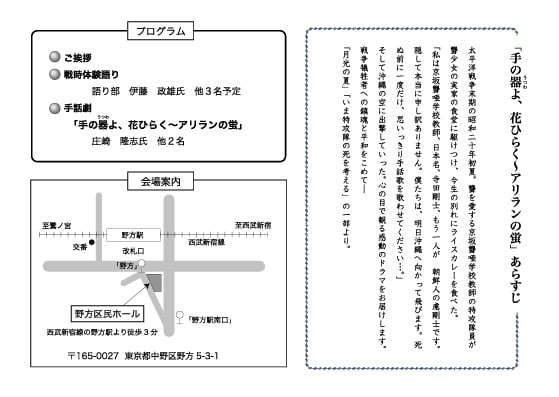第43回全国手話通訳問題研究集会in埼玉、第3日目(最終日)第5講座「コミュニケーション」は、楽しみにしていた水野真木子さんの講演会でした。
水野真木子先生は、名古屋の金城学院大学文学部教授をされています。ブログ「水野真木子の「文化」と「ことば」を語るブログ」も書かれています。
私は先生の著書「通訳のジレンマ」でしか存じ上げなかったのですが、非常にわかりやすいお話で大変勉強になりました。
取りあえず今夜は時間も遅いので当日のパワポを以下に再現しておきたいと思います。(一部、勝手に項番を付けさせていただきました。)
コミュニティ通訳とは
言語変換だけではない
通訳者として支援すること
1.今日お話ししたいこと
(1)コミュニティ通訳とは
(2)コミュニティ通訳者の役割
(3)コミュニティ通訳者に必要な能力と資質
(4)コミュニティ通訳者の倫理
2.通訳の種類
(1)会議系通訳
①会議通訳(国際会議、政府間交渉、講演)
②ビジネス通訳(企業間交渉、契約)
③放送通訳
④芸能通訳、スポーツ通訳 など
(2)コミュニティー系通訳
①司法通訳
②医療通訳
③行政通訳
④学校通訳
⑤災害時ボランティア通訳 など
3.音声言語通訳の形態
(1)同時通訳(ブースに入って行う形)
(2)逐次通訳(ダイアログ通訳を含む)
(3)ウィスパリング通訳
(4)要約通訳
(5)電話通訳(役場の窓口のトライフォン、税関、時差のある国など)
4.増加する外国人
5.暮らしの中の外国人
6.通訳の需要におけるシフト
(1)従来・・・会議・ビジネスなど、特定の目的のために来日する外国人のための通訳
↓(変化)
(2)近年・・・暮らしの中の外国人のニーズに対応する通訳=コミュニティ通訳
7.コミュニティ通訳の特徴
-会議通訳と比較して
(1)地域住民を対象にする
(2)力関係に差がある
(3)言葉のレベルが様々(言語の種類を含む)
(4)文化的要素が大きく関わる
(5)基本的人権の保護に直結している
→「言語権」という概念
8.言語権とは
・1960年代から70年代の公民権運動を通して確立した概念
・ヨーロッパ地方言語・少数言語憲章
(1992年、欧州評議会)
当事者たちによって理解されて自由に選ばれる言語による立法・行政・司法の行為、教育、メディアに対する権利を含む(ウィキペディア)
9.言語権と通訳
・通訳・翻訳という形での「言語権」の保障
→公的制度にかかわる現場での通訳・翻訳サービス
・公正な司法へのアクセス
・安全な医療へのアクセス
・学校教育へのアクセス
10.コミュニティ通訳の分類
・司法通訳(警察・検察・裁判所・拘置所など)
・医療通訳(病院・保健所・薬局など)
・教育通訳(教育支援の一環として)
+
・行政通訳(役場の相談窓口など)
・災害時ボランティア通訳
・交流イベント通訳
11.コミュニティ通訳の課題と今後の展望
①コミュニティ通訳の質の確保
┌ある程度のスクリーニングのシステム
┤ 手話通訳の認定制度を参考にできないか?
└定期的かつ系統的なトレーニング
(ユーザー・トレーニングも含む)
②倫理規程の確立
③公益事業の一環としての認識
④通訳者に対する報酬の確保
12.通訳者の役割モデル
①導管モデル(Conduit)
②文化仲介者(Cultural mediator)
③擁護者(Advocate)
・コミュニケーション促進役
(Communication facilitator)
・介助者(Helper)
┌通訳者に徹するのか?
┤
└援助者としても行動するのか?
→矛盾し合う概念「機械的か」「人間的か」
「介入的か」「介入的でないか」
13.通訳者に必要な能力と資質(1)
①高い語学力
②通訳のスキル
③分野別の知識
言語能力(手話を含む)があっても、
通訳スキルと分野別の知識がないと、
正確な通訳は保障できない。
通訳の「三位一体」
14.通訳者に必要な能力と資質(2)
④異文化に対する理解
異文化とは国家間、地域間に限ったものではない。聴覚障害者と健聴者との間にも、一定の「文化差異」は存在する。通訳者にはその橋渡しが求められることがある。
Bilingual+Bicultural=good interpreter
15.通訳者に必要な能力と資質(3)
⑤バランスの取れた強靱な精神
⑥豊かな人生経験
司法や医療など、人の生死や不幸に接する機会が多い通訳者の二次受傷(トラウマになる)が問題視されている。通訳者には強い精神力が求められることがある。
自分自身を助けられないなら、
他人を助けることはできない
16.倫理原則の主な柱
①守秘義務を守る
②原発言に忠実になる
③公平・中立な立場を取る
④文化に対する認識を持つ
⑤プロ意識を持つ
⑥*アドボケイト(擁護者)としての役割
医療通訳特有の概念
17.通訳者の守るべきことがら(1)
①守秘義務を守る
△1業務上知りえた秘密を外部に開示してはならない
△2業務上知りえた秘密を自己の利益のために利用してはいけない
18.通訳者の守るべきことがら(2)
②原発言に忠実になる
△3通訳者は、付け加えたり、省略したり、歪曲したり、編集したりすることなく、元のメッセージを忠実に伝えなければならない
△4通訳者は元の発言のスタイルにも忠実であることが望ましい
19.通訳者の守るべきことがら(3)
③公平・中立な立場を取る
△5通訳者は、専門職としての役割の範囲を守り、個人的な関与を控えなければならない
△6通訳者は、中立性を保つよう努め、相談に乗ったり助言したりしてはいけない
△7通訳者は、個人的偏見や信条を表明することを控えなければならない
20.通訳者の守るべきことがら(4)
④文化に対する認識を持つ
△8通訳者は、文化的状況を考慮しながら、話し手の元のメッセージの内容と精神を伝え、メッセージを正確に訳すよう努めなければならない
△9通訳者は、言葉だけでなく文化的差異についても、橋渡しをすることが望まれる
21.通訳者の守るべきことがら(5)
⑤プロ意識を持つ
△10通訳者は、自分の能力の限界を認識するとともに、引き受ける業務に対して責任ある態度をもって臨まなければならない
△11通訳者は、社会の進展に伴う新たな状況に対処できるように、常に研鑽に励まなければならない
22.⑥*アドボカシー(擁護)という概念
・通訳依頼人の健康、福利、あるいは尊厳が危機に晒(さら)されている場合、通訳者は、アドボガシー(擁護的行為)と呼ばれる行動を取ることが正当化される場合もある。
医療の現場では、健康上の良い結果支援するという意図を伴い、コミュニケーション促進の範囲を超えて、個人のために行われる行為であると理解される。
擁護は、状況を慎重に思慮深く分析した後に、そして、他のより介入的でない手段によって問題が解決されなかった場合のみ、行われるべきである。
→「中立性の原則に相反する」という反論
→ 通訳者の役割の定義に大きく関わる
→司法通訳には100%当てはまらない
23.通訳者のユーザーへの注意点
①通訳者を専門職として扱う
②事前に、差し支えのない範囲で情報提供をする
③通訳を介したコミュニケーションのプロセスについて知っておく
④通訳者にとって良い環境を提供する
⑤業務終了後のフォローアップ
24.裁判員制度と司法通訳
①裁判員制度に伴う通訳の問題
(1) 書面が事前に渡されないケースが多くなる
(2) 職業裁判官とは異なり、一般人は通訳者の訳し方から生じる印象に左右されやすいので、ますますレジスター(場面に応じて現れる特徴的な言葉遣い)の正確さが要求される
(3) 通訳を介した場合、固有名詞が追いつきにくいことや、見る側もたいへん疲れることに配慮する必要がある
(4) 公判前整理手続きには、非常に高度な通訳技術が必要となる
②日本通訳翻訳学会「法廷言語分析チーム」実験
(1) 模擬裁判員の受ける印象は通訳によって左右される
例)口汚い罵りの言葉も普通の言葉に訳したら裁判員は「挑発の度合い」を軽く見た
例)犯罪行為を連想させるような単語(取る→ひったくる)を多く使って訳すと逆に罪を重く見る
(2) 同じ外国語の証言を異なった口調で通訳
①丁寧な口調
②ぶっきらぼうな口調 → 印象異なる
③言いよどむ
水野真木子先生は、名古屋の金城学院大学文学部教授をされています。ブログ「水野真木子の「文化」と「ことば」を語るブログ」も書かれています。
私は先生の著書「通訳のジレンマ」でしか存じ上げなかったのですが、非常にわかりやすいお話で大変勉強になりました。
取りあえず今夜は時間も遅いので当日のパワポを以下に再現しておきたいと思います。(一部、勝手に項番を付けさせていただきました。)
コミュニティ通訳とは
言語変換だけではない
通訳者として支援すること
1.今日お話ししたいこと
(1)コミュニティ通訳とは
(2)コミュニティ通訳者の役割
(3)コミュニティ通訳者に必要な能力と資質
(4)コミュニティ通訳者の倫理
2.通訳の種類
(1)会議系通訳
①会議通訳(国際会議、政府間交渉、講演)
②ビジネス通訳(企業間交渉、契約)
③放送通訳
④芸能通訳、スポーツ通訳 など
(2)コミュニティー系通訳
①司法通訳
②医療通訳
③行政通訳
④学校通訳
⑤災害時ボランティア通訳 など
3.音声言語通訳の形態
(1)同時通訳(ブースに入って行う形)
(2)逐次通訳(ダイアログ通訳を含む)
(3)ウィスパリング通訳
(4)要約通訳
(5)電話通訳(役場の窓口のトライフォン、税関、時差のある国など)
4.増加する外国人
5.暮らしの中の外国人
6.通訳の需要におけるシフト
(1)従来・・・会議・ビジネスなど、特定の目的のために来日する外国人のための通訳
↓(変化)
(2)近年・・・暮らしの中の外国人のニーズに対応する通訳=コミュニティ通訳
7.コミュニティ通訳の特徴
-会議通訳と比較して
(1)地域住民を対象にする
(2)力関係に差がある
(3)言葉のレベルが様々(言語の種類を含む)
(4)文化的要素が大きく関わる
(5)基本的人権の保護に直結している
→「言語権」という概念
8.言語権とは
・1960年代から70年代の公民権運動を通して確立した概念
・ヨーロッパ地方言語・少数言語憲章
(1992年、欧州評議会)
当事者たちによって理解されて自由に選ばれる言語による立法・行政・司法の行為、教育、メディアに対する権利を含む(ウィキペディア)
9.言語権と通訳
・通訳・翻訳という形での「言語権」の保障
→公的制度にかかわる現場での通訳・翻訳サービス
・公正な司法へのアクセス
・安全な医療へのアクセス
・学校教育へのアクセス
10.コミュニティ通訳の分類
・司法通訳(警察・検察・裁判所・拘置所など)
・医療通訳(病院・保健所・薬局など)
・教育通訳(教育支援の一環として)
+
・行政通訳(役場の相談窓口など)
・災害時ボランティア通訳
・交流イベント通訳
11.コミュニティ通訳の課題と今後の展望
①コミュニティ通訳の質の確保
┌ある程度のスクリーニングのシステム
┤ 手話通訳の認定制度を参考にできないか?
└定期的かつ系統的なトレーニング
(ユーザー・トレーニングも含む)
②倫理規程の確立
③公益事業の一環としての認識
④通訳者に対する報酬の確保
12.通訳者の役割モデル
①導管モデル(Conduit)
②文化仲介者(Cultural mediator)
③擁護者(Advocate)
・コミュニケーション促進役
(Communication facilitator)
・介助者(Helper)
┌通訳者に徹するのか?
┤
└援助者としても行動するのか?
→矛盾し合う概念「機械的か」「人間的か」
「介入的か」「介入的でないか」
13.通訳者に必要な能力と資質(1)
①高い語学力
②通訳のスキル
③分野別の知識
言語能力(手話を含む)があっても、
通訳スキルと分野別の知識がないと、
正確な通訳は保障できない。
通訳の「三位一体」
14.通訳者に必要な能力と資質(2)
④異文化に対する理解
異文化とは国家間、地域間に限ったものではない。聴覚障害者と健聴者との間にも、一定の「文化差異」は存在する。通訳者にはその橋渡しが求められることがある。
Bilingual+Bicultural=good interpreter
15.通訳者に必要な能力と資質(3)
⑤バランスの取れた強靱な精神
⑥豊かな人生経験
司法や医療など、人の生死や不幸に接する機会が多い通訳者の二次受傷(トラウマになる)が問題視されている。通訳者には強い精神力が求められることがある。
自分自身を助けられないなら、
他人を助けることはできない
16.倫理原則の主な柱
①守秘義務を守る
②原発言に忠実になる
③公平・中立な立場を取る
④文化に対する認識を持つ
⑤プロ意識を持つ
⑥*アドボケイト(擁護者)としての役割
医療通訳特有の概念
17.通訳者の守るべきことがら(1)
①守秘義務を守る
△1業務上知りえた秘密を外部に開示してはならない
△2業務上知りえた秘密を自己の利益のために利用してはいけない
18.通訳者の守るべきことがら(2)
②原発言に忠実になる
△3通訳者は、付け加えたり、省略したり、歪曲したり、編集したりすることなく、元のメッセージを忠実に伝えなければならない
△4通訳者は元の発言のスタイルにも忠実であることが望ましい
19.通訳者の守るべきことがら(3)
③公平・中立な立場を取る
△5通訳者は、専門職としての役割の範囲を守り、個人的な関与を控えなければならない
△6通訳者は、中立性を保つよう努め、相談に乗ったり助言したりしてはいけない
△7通訳者は、個人的偏見や信条を表明することを控えなければならない
20.通訳者の守るべきことがら(4)
④文化に対する認識を持つ
△8通訳者は、文化的状況を考慮しながら、話し手の元のメッセージの内容と精神を伝え、メッセージを正確に訳すよう努めなければならない
△9通訳者は、言葉だけでなく文化的差異についても、橋渡しをすることが望まれる
21.通訳者の守るべきことがら(5)
⑤プロ意識を持つ
△10通訳者は、自分の能力の限界を認識するとともに、引き受ける業務に対して責任ある態度をもって臨まなければならない
△11通訳者は、社会の進展に伴う新たな状況に対処できるように、常に研鑽に励まなければならない
22.⑥*アドボカシー(擁護)という概念
・通訳依頼人の健康、福利、あるいは尊厳が危機に晒(さら)されている場合、通訳者は、アドボガシー(擁護的行為)と呼ばれる行動を取ることが正当化される場合もある。
医療の現場では、健康上の良い結果支援するという意図を伴い、コミュニケーション促進の範囲を超えて、個人のために行われる行為であると理解される。
擁護は、状況を慎重に思慮深く分析した後に、そして、他のより介入的でない手段によって問題が解決されなかった場合のみ、行われるべきである。
→「中立性の原則に相反する」という反論
→ 通訳者の役割の定義に大きく関わる
→司法通訳には100%当てはまらない
23.通訳者のユーザーへの注意点
①通訳者を専門職として扱う
②事前に、差し支えのない範囲で情報提供をする
③通訳を介したコミュニケーションのプロセスについて知っておく
④通訳者にとって良い環境を提供する
⑤業務終了後のフォローアップ
24.裁判員制度と司法通訳
①裁判員制度に伴う通訳の問題
(1) 書面が事前に渡されないケースが多くなる
(2) 職業裁判官とは異なり、一般人は通訳者の訳し方から生じる印象に左右されやすいので、ますますレジスター(場面に応じて現れる特徴的な言葉遣い)の正確さが要求される
(3) 通訳を介した場合、固有名詞が追いつきにくいことや、見る側もたいへん疲れることに配慮する必要がある
(4) 公判前整理手続きには、非常に高度な通訳技術が必要となる
②日本通訳翻訳学会「法廷言語分析チーム」実験
(1) 模擬裁判員の受ける印象は通訳によって左右される
例)口汚い罵りの言葉も普通の言葉に訳したら裁判員は「挑発の度合い」を軽く見た
例)犯罪行為を連想させるような単語(取る→ひったくる)を多く使って訳すと逆に罪を重く見る
(2) 同じ外国語の証言を異なった口調で通訳
①丁寧な口調
②ぶっきらぼうな口調 → 印象異なる
③言いよどむ