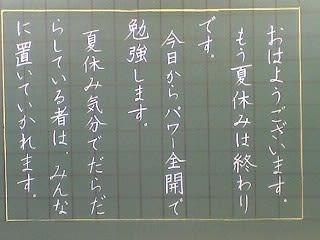夏休みが終わりました。いよいよ明日から学校の再開です。
今日は教室の掃除や教材研究などをし,明日に備えました。
夏休み明けの初日,黒板に子どもたちに向けたメッセージを書いている先生が多いと思います。
「夏休みは楽しい思い出ができましたか」
「これからも楽しいクラスを目指してがんばりましょう」
というようなことが書いてあることが多いようです。
私は休み明けに限らず,毎日黒板へのメッセージを書いているのですが,今日は写真のように書きました。
インパクトが大きいと思います。
こんなことを書いているクラスはほかにありません。
硬派なスタートとなりそうです。
実際,いきなり国語と算数の授業から始めます。
今日は教室の掃除や教材研究などをし,明日に備えました。
夏休み明けの初日,黒板に子どもたちに向けたメッセージを書いている先生が多いと思います。
「夏休みは楽しい思い出ができましたか」
「これからも楽しいクラスを目指してがんばりましょう」
というようなことが書いてあることが多いようです。
私は休み明けに限らず,毎日黒板へのメッセージを書いているのですが,今日は写真のように書きました。
インパクトが大きいと思います。
こんなことを書いているクラスはほかにありません。
硬派なスタートとなりそうです。
実際,いきなり国語と算数の授業から始めます。