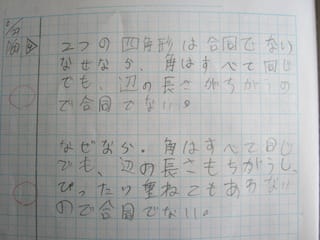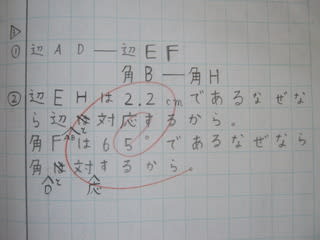今日は,私にとって記念日です。
私が初めてサークルに参加したのが,2001年7月25日。
この日,「スタートライン2000」に参加したのです。
今日でサークル活動に足を踏み入れてから,満10年となりました。
緊張しながら泉の市民センターに行ったのをはっきりと覚えています。
まだ立て直す前でボロボロの建物でした。
「興味があるぐらいでサークルに来ないでほしい」と,メールでは厳しい返答だった代表の村上さんが,笑顔で迎えてくださいました。
村上さんのほかに,千絵さん,澁谷さん,櫻井さん,瀬川さん,片倉さん,平間さんがいました。
片倉さんの石巻のシャッター通りを題材にした「まちづくり」の模擬授業,そして,千絵さんの屋台村のレポートに衝撃を受けました。
ちなみに,この日,私はレポートを持っていっていません。
どことなく敗北感がありました。
全てはここから始まったのです。
この10年間様々なことがありました。
本当に様々なことがありました。
いろいろな人たちに支えられて現在の私があります。
10年間続けてこられたのも,みなさんのおかげです。
鍵山秀三郎氏が「10年偉大なり,20年畏るべし,30年にして歴史なる」と述べています。
全く偉大な域には達していませんが,今後もコツコツと努力を積み重ねていきたいです。
今日からまた新しいスタートラインに立って,前進していきます。
私が初めてサークルに参加したのが,2001年7月25日。
この日,「スタートライン2000」に参加したのです。
今日でサークル活動に足を踏み入れてから,満10年となりました。
緊張しながら泉の市民センターに行ったのをはっきりと覚えています。
まだ立て直す前でボロボロの建物でした。
「興味があるぐらいでサークルに来ないでほしい」と,メールでは厳しい返答だった代表の村上さんが,笑顔で迎えてくださいました。
村上さんのほかに,千絵さん,澁谷さん,櫻井さん,瀬川さん,片倉さん,平間さんがいました。
片倉さんの石巻のシャッター通りを題材にした「まちづくり」の模擬授業,そして,千絵さんの屋台村のレポートに衝撃を受けました。
ちなみに,この日,私はレポートを持っていっていません。
どことなく敗北感がありました。
全てはここから始まったのです。
この10年間様々なことがありました。
本当に様々なことがありました。
いろいろな人たちに支えられて現在の私があります。
10年間続けてこられたのも,みなさんのおかげです。
鍵山秀三郎氏が「10年偉大なり,20年畏るべし,30年にして歴史なる」と述べています。
全く偉大な域には達していませんが,今後もコツコツと努力を積み重ねていきたいです。
今日からまた新しいスタートラインに立って,前進していきます。