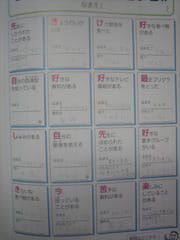昨日,避難訓練がありました。
避難の鉄則として「おはしの約束」というのがあります。
普通はこう言われています。
「お」……押さない
「は」……走らない
「し」……しゃべらない
しかし,私は「そうではない」と伝えました。
「お」……お話しない
「は」……話さない
「し」……しゃべらない
つまり,「口を閉じなさい」ということです。
非常時には,これを徹底しなければなりないと思います。
話をしていては,教師の指示が徹底しません。
放送も聞こえません。
もちろん「押さない」「走らない」も大切でしょうが,一番重要なのは「しゃべらない」であることは間違いないと思います。
とにかくしゃべっては駄目なのです。
指示や放送が聞こえない結果,命を失うことにもなりかねないのです。
私は毎年このような指導をしています。
3月11日の東日本大震災。
あの激しい揺れの中で,3年生の私のクラスの子は机の下に入り,黙って耐えていました。
長時間,黙って耐え抜いた子どもたちの態度は,本当に立派でした。
先月,休み時間に防犯警報が鳴ったことがありました。
これは,不審者が校内に侵入したときなどに鳴る警報なのです。
そのときも,私はまず子どもたちを黙らせました。
廊下にいた子たちを全員教室に入れました。
その上で,「先生が教室から出たら,鍵を掛けなさい」と言って,現場の確認に行きました。
警報が鳴った原因は誤作動だったのですが,もし本当に不審者が入ってきていたとしたら,そして,もし騒いでいて私の指示を聞き逃したとしたら,命の危険にさらされていたかもしれません。
今回の避難訓練も立派でした。
1人もしゃべっていなかったと思います。
整然とした態度で避難できました。
避難の鉄則として「おはしの約束」というのがあります。
普通はこう言われています。
「お」……押さない
「は」……走らない
「し」……しゃべらない
しかし,私は「そうではない」と伝えました。
「お」……お話しない
「は」……話さない
「し」……しゃべらない
つまり,「口を閉じなさい」ということです。
非常時には,これを徹底しなければなりないと思います。
話をしていては,教師の指示が徹底しません。
放送も聞こえません。
もちろん「押さない」「走らない」も大切でしょうが,一番重要なのは「しゃべらない」であることは間違いないと思います。
とにかくしゃべっては駄目なのです。
指示や放送が聞こえない結果,命を失うことにもなりかねないのです。
私は毎年このような指導をしています。
3月11日の東日本大震災。
あの激しい揺れの中で,3年生の私のクラスの子は机の下に入り,黙って耐えていました。
長時間,黙って耐え抜いた子どもたちの態度は,本当に立派でした。
先月,休み時間に防犯警報が鳴ったことがありました。
これは,不審者が校内に侵入したときなどに鳴る警報なのです。
そのときも,私はまず子どもたちを黙らせました。
廊下にいた子たちを全員教室に入れました。
その上で,「先生が教室から出たら,鍵を掛けなさい」と言って,現場の確認に行きました。
警報が鳴った原因は誤作動だったのですが,もし本当に不審者が入ってきていたとしたら,そして,もし騒いでいて私の指示を聞き逃したとしたら,命の危険にさらされていたかもしれません。
今回の避難訓練も立派でした。
1人もしゃべっていなかったと思います。
整然とした態度で避難できました。