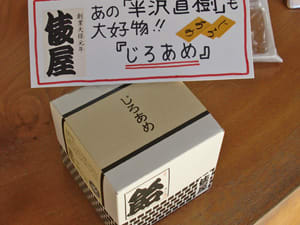金沢の観光スポット体験レポート その223(No.388)
◇「金沢五社参りウオーク」(2)宇多須神社、小坂神社
2014新春自宅より金沢五社参りウオークを行った。
ご利益ありますように!!
コースおよび時間
自宅(8:09)~上菊橋~椿原天満宮(9:09)~天神橋
~宇多須神社(9:47)~小坂神社(10:19)~彦三大橋
~安江八幡宮(11:04)~犀川大橋~神明宮(11:54)
~自宅(12:40)1日計歩数:26,098 約18km
2.宇多須神社
養老2年(718年)の創建。多聞天社と称して創建された。
慶長4年(1599年)に前田利家を密かに祀り、藩士が禄
高に応じて祭祀料を負担した。尾山神社の創建に伴い元
の祭神である高皇産霊神を遷座した。
明治2年(1869年)高皇産霊社と改め、同5年卯辰社と改
称、同33年(1900年)現在の宇多須神社と改め、同35年
県社に昇格された。
■写真は鳥居

■写真は拝殿

■写真は拝殿内部
現在地:金沢市東山1-30-8

利常公酒湯の井戸は卯辰八幡神社(現在の宇多須神社)創
建の慶長4年(1599)頃できたと伝えられている。歴代の
藩主以下奥方や家老のお参りは日常的にあり、この井戸も
ご神水として使用されていた。
中でも、五代綱紀公が疱瘡にかかられたとき、当社におい
て祈願をし、このご神水を沸かし、お酒を入れて「酒湯」
として体にかけ、治したとされる。
■写真は利常公酒湯の井戸

3.小坂神社
養老元年(720)の創建の延喜式内加賀十三座の中の一
社であり、社頭は一揆に依り焼失したが、寛永13年
(1636)加賀藩主前田家に依り再興され、北効一円の春
日社の総社として地域の人に親しまれ、藩主前田家もこ
とある毎に当社に祈願したとされている。又、富士社は
玉姫病気祈願所とされ、以来病に霊験のあるお社として
崇敬を集めている。
■写真は鳥居

主祭神:天児屋根命、経津主命、比神、武甕槌大神
現在地:金沢市山の上町42-1
■写真は稲荷社

■写真は天神社

■写真は拝殿

■写真は拝殿内部

■写真は本殿

■写真は芭蕉翁巡湯地碑