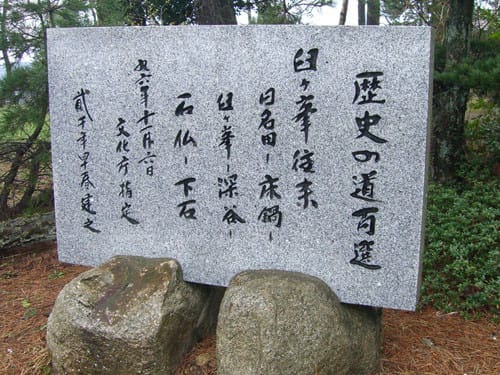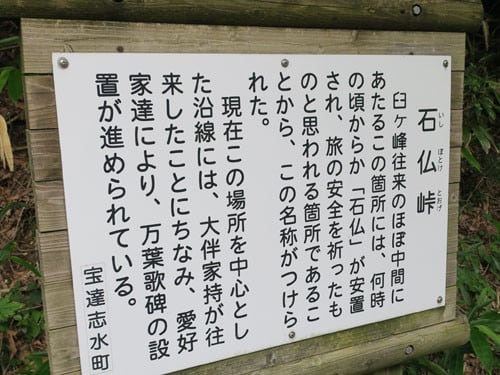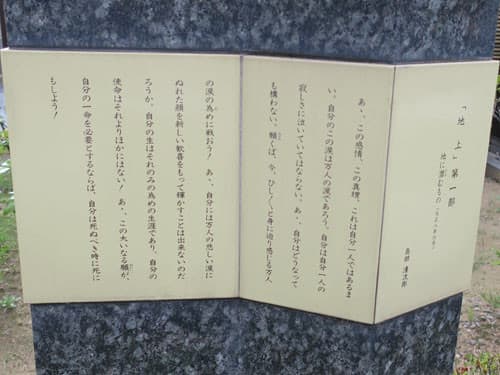金沢の観光スポットレポート その712(No.1070)
◇金沢の夏2017 ⑪ 長町武家屋敷跡-1
○長町の由来
長町は前田八家の1つ長氏の屋敷があったことから名付けられました。現在の長町武家屋敷一体は長氏、村井氏をはじめ上級武士から中級、下級武士などが住んでいました。現在では、当時の武家屋敷は殆ど残っていませんがその中で中級武士だった野村家邸は当時の武士の邸宅の様子を伺うことができます。

○前田土佐守家資料館
前田土佐守家資料館は、加賀藩祖前田利家の次男前田利政を家祖とする前田土佐守家所蔵の資料、約9,000点(石川県指定文化財)を保管、その一部を展示する施設です。
■写真は前田土佐守家資料館
□ 前田土佐守家資料館ホームページ

○金沢老舗記念館
天正7年開業の薬舗「中屋」を移築したこの記念館は藩政時代の面影を今に伝える建物です。1階には当時の店先を再現した「みせの間」があり、座卓、そろばん、帳簿などが商いの様子を伝えています。2階には金沢の伝統産業、町民文化に関する資料が展示されています。
□ 金沢老舗記念館ホームページ
□前田土佐守資料館、老舗資料館紹介ブログページ
■写真は金沢老舗記念館


■写真は青木悦子クッキング教室、レストラン「四季のテーブル」

■写真は大野庄用水

■写真は箔座長町

○ハガキの成る木
長町武家屋敷跡の一角で、珍しいハガキの木を発見!この木の葉っぱに尖ったもので字を書くと、葉が枯れても字が消えないことから、紙の代わりに使われたこともあり、葉書の語源になったといわれています。

■写真はハガキの成る木
■撮影日:2017.7.18
(つづく)