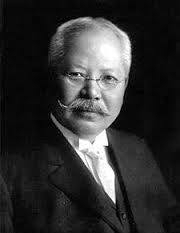金沢の観光スポット体験レポート その208(No.352)
◇にし茶屋街・寺町を歩く② 願念寺、妙立寺、国泰寺、六斗広見
にし茶屋街・寺町を約90分の観光ウオークを組んでみた。
距離は約3.5キロくらいなので、手軽に楽しめる。ただし
にし茶屋資料館、忍者寺など入館するとプラス70分が必
要になる。
□寺町の概況
寺町寺院群は、石川県金沢市寺町、野町にある寺院の総称
である。藩政期に一向一揆に対する防衛策として、犀川流
域にあたるこの地に寺院が集められた。
忍者寺として知られる妙立寺を始め、66の寺院が立ち並
び、市内の三つの寺院群の中で最大規模である。寺町、野
町、弥生の各一部、22.0ヘクタールが「金沢市寺町台伝統
的建造物群保存地区(重伝建地区)」の名称で国の重伝建
地区として選定されている。
重伝建地区指定は構築物161件、工作物30件、環境物件8件
となっている。
■写真は願念寺山門

3)願念寺(がんねんじ)
木一山願念寺は真宗大谷派のお寺で、創建慶長年間、万冶
2年(1659)現在地に移転。一笑(いっしょう)の菩提寺。
小杉一笑は金沢における蕉風の先駆をなした俳人。元禄2
年(1689)7月金沢入りした松尾芭蕉は一笑が前年の
霜月6日死去したことを知り慟哭(どうこく)。22日こ
こ願念寺で催された追悼会で、芭蕉は「塚も動け・・・」
とその悲しみを詠んだ。 この前々年(貞亨4年)近江の
人尚白が撰した「孤松集」に一笑の句が194句も入集されて
いる。芭蕉句碑は昭和42年建立。
■写真は願念寺芭蕉句碑

つかも動け 我が泣く声は 秋の風 (芭蕉句碑)
心から 雪うつくしや 西の雲 (一笑辞世句碑)
■写真は願念寺一笑句碑

4)妙立寺(みょうりつじ・忍者寺)
正久山妙立寺は日蓮宗のお寺で、寛永20年(1643)、三代藩主
前田利常の命により創建。日蓮聖人の尊像を安置し加賀前田家
の祈願所として、歴代藩主をはじめ身分や宗派を問わず多くの
人々が参詣した。
寺町寺院群の中心に位置する。戦略的には寺院群は、金沢城の
防御の一環として現在地に移築されたもので、その中心司令部
的な役目をもって建てられている。内部には隠し部屋、隠し階
段、落とし穴、切腹の間といった種々の仕掛けが施され、23の
部屋、29ヶ所の階段と4階7層からなる複雑な建築構造を有し、
忍者寺の名で親しまれている。
詳しくは妙立寺紹介ページ
http://blog.goo.ne.jp/kanazawa-uechan/e/2ad1d9bdd65049bf70174f5769ec54d4
http://blog.goo.ne.jp/kanazawa-uechan/e/63e271a79b94f8b9accf7a4c4b7cca59
http://blog.goo.ne.jp/kanazawa-uechan/e/37fc56c50948aeea1ca4db04406433ac
■写真は妙立寺

5)国泰寺(こくたいじ)
摩頂山国泰寺は金沢の寺町寺院群にある臨済宗のお寺です。元
々は高岡の臨済宗国泰寺派総本山の関連寺院だったそうです。
国泰寺の裏のほうに樹高16メートルのイチョウの大木のある
樹林がある。高峰譲吉の菩提寺でもあり、元和2年(1616)に
現地に移転してから大火からも逃れ金沢城下の寺院の中でも古
い様式を残した寺院です。
■写真は国泰寺
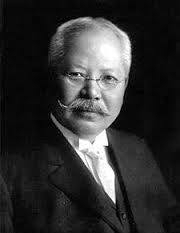
■写真は高峰譲吉

6)六斗広見(ろくとひろみ)
広見というのは、藩政時代、延焼を防ぎ大火としないための町
づくりの一つとして設けられたものであり、金沢のあちこちに
あった。地名は加賀国住人林六郎光明の郎等六動太郎光景に由
来し、ここから六動林、六斗林、六斗になったといわれている。
金沢には何箇所かあり、六斗の広見はその中でも最も広い、と
言われている。
■写真は六斗広見