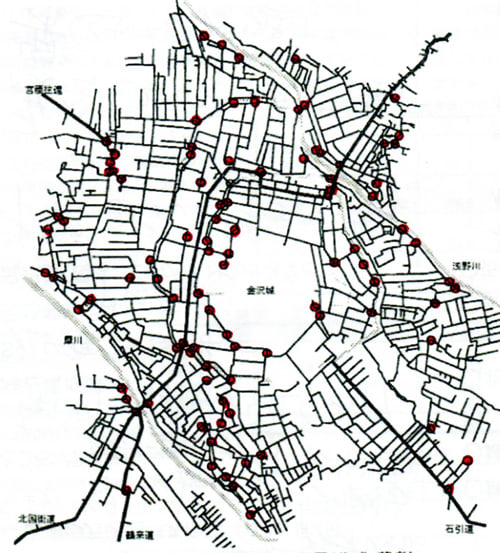金沢の観光スポットレポート その525(No.805)
◇金沢名建築物巡り 尾張町界隈 ②
4)金沢町民文化館
市内で唯一屋根に鯱がついている建物は、旧金沢貯蓄銀行で明治
4年(1907)建設。昭和51年(1976)に北陸銀行尾張町支店と
しての役割が終了。昭和52年(1977)に県が取得し、県立郷土
資料館分館・町民文化館として会館。
外観は黒漆喰の土蔵造りで内部はアメ色のギリシャ風エンタシス
の柱と共に不思議な歴史的調和を持っている。
■写真は金沢町民文化館全景


■写真は残されているカウンター

■写真は展示品

■写真は元頭取室

■写真は地下金庫入口

■写真は元事務室全景

5)尾張町老舗交流館
平成8年に眼鏡店跡を改装してオープン。金沢らしい商家の雰囲
気を持ち大和風炉、階段箱、セドへ通じる通り庭など大正ロマン
が漂う。館内に入ると明治~昭和初期当時の尾張町界隈の写真が
展示されている。
■写真は尾張町老舗交流館全景


■写真はメガネ展示ケースを利用している。



■写真は館内展示の様子

6月18日(土)開催された、歴史伝統文化講演会の「兼六園そ
の価値を知ろう」上田輝喜金沢城・兼六園研究会相談役に参加し
ました。兼六園の歴史や藩主の思いなど大変参考になりました。
この講演会は今年3年目で年10回開催される。
■写真は講演中の上田相談役
(つづく)