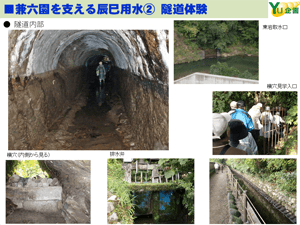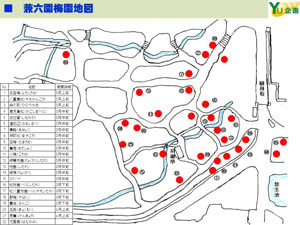金沢の観光スポット体験レポート その406(No.634)
◇兼六園の石塔巡り ①
兼六園には6個の石塔がある。桂坂口より入り霞が池~山山
~さざえ山~瓢池の順序で紹介します。
1)蓬莱島の石塔(ほうらいじまのせきとう)
霞ヶ池に浮ぶ蓬莱島は東にある立石が亀の頭、西にある石塔
を亀の尾と見立て、亀甲島とも呼ばれている。相輪部分で宝
珠の下の九輪は六輪しかなく、層塔は奇数層であるのが普通
だが、この塔は八重の塔という珍しい造りだ。もとは藩政時
代いまの茶店街の中央にあった内橋亭の露地に据えられてい
たが、蓬莱島を亀に見立てるため、現地に移されたといわれ
ている。
■写真は蓬莱島の石塔

■写真は蓬莱島(唐崎松方面から)

2)七福神山の毘沙門塔(びしゃもんとう)
七福神山のほぼ真ん中にある。藩政時代からのものではなく、
明治7年(1874)に兼六園が一般開放された時、茶店連が寄贈した
もの。石材は赤戸室石。火袋、火口がつけられて、灯籠風に造
られた石塔だ。あとからつけ加えられた造作物ではあるが、
石と樹木の築山の見事な添景となっている。
■写真は七福神山

■写真は七福神山の毘沙門塔

3)御室の塔(おむろのとう)
石川県立伝統産業工芸館の方から山崎山に上る道筋の途中に
ある。高さ約4m70cmで、塔全体は白川御影石、基壇は青戸室
石でつくられている。
名の由来は、京都仁和寺(御室御所)の古い塔を模倣したから
という説と、13代藩主斉泰の嫡母・真龍院(出自は関白の鷹司
家)の仁和寺への郷愁からという説があ
■写真は山山

■写真は山山の御室の塔
参考資料:「兼六園図鑑」インターネットより
(つづく)