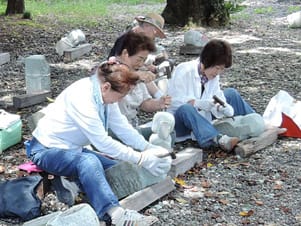金沢の観光スポット体験レポート その425(No.655)
◇兼六園の曲水、池、島、橋巡り ⑥
兼六園の曲水は、犀川上流約10Kmの辰巳用水を経て園内延長
574mで、4つの池や島、数多くの橋がある。
今回は、桂坂口から霞が池、千歳台、山山、内橋亭、梅園、時
雨亭、瓢池、噴水、桂坂口へと巡ってみたい。

24)汐見橋(しおみばし)
瓢池前の夕顔亭露地から百間堀通り側へ渡る木橋。作庭当時は樹
木の丈も低く、高層建築物もなかったことから、この橋の上からは
るか日本海まで眺めることができた。それが橋名の由来である。
橋の上に佇んで池を覗くと、鯉が寄ってくるのが楽しい。
■写真は汐見橋

25)日暮橋(ひぐらしばし)
瓢池前の夕顔亭露地から瓢池の中島にかかっている橋。「このほ
とりに立って、辺りを眺めているといくら見ても見飽きない、い
つしか日が暮れていた」ことから、その名が付いたといわれる。
戸室石の石板でつくられており、長さ13m、幅1m75cm。表面は四
半模様になっていて、その整然とした幾何学模様が美しい。

■写真は日暮橋

26)翠滝(みどりたき)
瓢池をはさんで夕顔亭対岸の茂みの中に見える滝。宝暦の大火
で焼失した蓮池庭を復興すべく、11代藩主治脩が、夕顔亭と同
様に安永3年(1774)につくったもの。造作にあたっては庭師に幾
たびも工夫を求めている由が『大梁公(治脩)日記』に記されて
いる。その甲斐あって、高さ6.6m、幅1.6mで水量豊富、滝音も
大きい実に雄大なものとなった。滝壷のない幅落ちで、落下し
た水は石にあたって砕けて広がり、瓢池に注ぐ。観るだけでな
く、音も聞いて楽しむ工夫である。

また滝の周辺には高尾や竜田、小倉山など、紅葉の名所から各種
のモミジを取り寄せて植栽。種類の違うモミジの取り合わせで
微妙な色の陰影が素晴らしい。紅葉滝とも呼ばれている。
■写真は翠滝

27)瓢池の中島
池の中に松の木が植えられた小島がある。
実は、ひさご池にはかつて3つの島があった。
海石塔のある場所も、夕顔亭のある場所も、かつては島となって
いて、作られた当初は池に3つの島が並ぶ形に作られていた。
不老長寿の神仙島の三島(蓬莱:ほうらい、万丈:ばんじょう、
瀛州:えいしゅう)になぞらえて、子孫繁栄、延命長寿、立身出
世を願って造られていたのだ。
■写真は瓢池の中島

28)瓢池の岩島(ひさごいけのいわしま)
瓢池の石橋「日暮橋」を渡ったところが亀島で、亀島から数mの
ところに松が植えられているのが岩島だ。亀島と対で、鶴に
見立てたものと思われる。
■写真は瓢池の岩島
参考資料:兼六園図鑑(インターネット)より
(つづく)