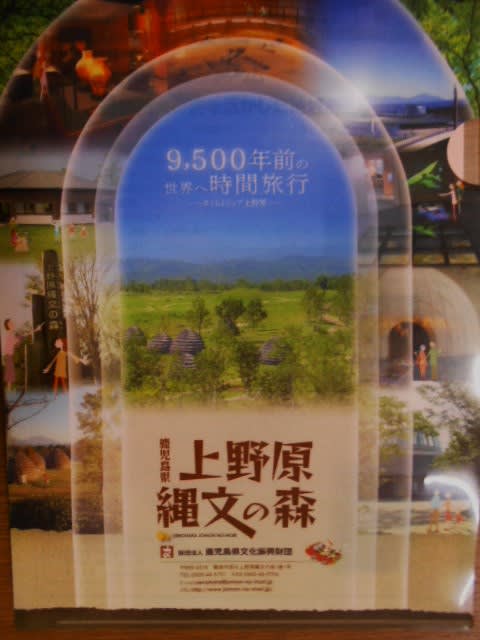今朝の新聞によれば、県都鹿児島市ではこれまでに夏日(最高気温25度以上)が189日になったとあり、年間の夏日が一年のうちの半分をはるかに超えてしまった。
大隅の鹿屋地区でもそこまではないが、おそらく100日くらいにはなったと思われる。
11月に入ってから夏日は2日くらいで、10日以降は最高気温25℃を下回る日が続く。
それでもこの頃は湿度の多い曇り空で、ときおり日が差すとかなり暑苦しい。
今月は鹿屋市の鉄道記念館でシルバーの仕事があり、来館者の中に大阪や千葉県などからの遠出組がいて、話を聞くと「やはり、暑いですね」と言われる。
大隅半島から大隅線98キロと志布志線38キロの鉄路と39の駅が消えて37年になるが、記念館として管理人がいるのはもうここだけになった。
昨日はたまたま長崎県でかつて鉄道マンだった人と、地元大隅で鉄道マンだった人が来館したが、館内を案内するこちらの方が勉強になった。
どちらも国鉄が民営化される前に勤めていた人で、その後の身の振り方は明かさなかったが、それぞれに苦労があったに違いない。
昨夜からの小雨は菜園をほど良く湿らせてくれた。
9月一杯続いたうだるような暑さは、その前に蒔いたダイコンにしろハクサイにしろ高温によるダメージを与え続け、ひょっとしたら育たないのではと思っていたのだが、10月の中旬以降は持ち直し、ようやく一息ついた感がする。

巻き始めたハクサイ。葉っぱに虫食いが多いがめげずに育っている。ダイコンも太さ2寸くらいのが地上に立ち上がって来た。
虫食いの全くないのがサニーレタスで、サラダ用に重宝している。
花の方も暑さの影響だろう、真夏日の下で咲き誇っていた鳳仙花のこぼれ種が芽を出し、十分な大きさになってまた咲いている。

向こうに見えるのはポーチュランカだが、これもこぼれ種からの二番手だ。だが太陽光をめっぽう好むタイプだから、花が哀れなくらい小さくなっている。
どちらも高温性の花だが、いつまで咲き続けるだろうか。