
先日、「大阪のおばちゃんの会」という面白い名前の真剣な勉強会で、
「特別支援と子どもたち」というタイトルでお話しをさせて頂きました。
そのとき、発達障害の法律的な背景や、障害の種別、例などについても触れたのですが、
『おこだでませんように』という絵本を読んで、
その感想をおっしゃってくださった方が多かったので、ご紹介します。
『おこだでませんように』くすのきしげのり(著)
アマゾンの内容紹介を引用させて頂きます。
「怒られてばかりいる子の心の中を描いた絵本
「ぼくは、いつでもおこられる。家でも学校でも…。休み時間に、友だちがなかまはずれにするからなぐったら、先生にしかられた」いつも誤解されて損ばかりしている少年が、七夕さまの短冊に書いた願いごとは…?」
内容(「BOOK」データベースより)
「ぼくはいつもおこられる。いえでもがっこうでも…。きのうもおこられたし、きょうもおこられている。きっとあしたもおこられるやろ…。ぼくはどないしたらおこられへんのやろ。ぼくはどないしたらほめてもらえるのやろ。ぼくは…「わるいこ」なんやろか…。ぼくは、しょうがっこうににゅうがくしてからおしえてもらったひらがなで、たなばたさまにおねがいをかいた。ひらがなひとつずつ、こころをこめて…。」
沢山の人が、この本を読んで、とにかく涙が出てしまう、と書いておられます。
私も、読むたびに、主人公の男の子の気持ちを考えると、声が震えてしまいます。
この本を読んで、
「そうや、叱ってばかりじゃだめだな」
と思う先生、親、たくさんいらっしゃると思います。
「ぼくも(私も)、しかられるのいややなあ」
と思う子ども達、たくさんいるでしょうね。
ですが、教師としては、そこで終わってしまわずに、もう一歩、よくよくこの子を見て欲しいと思います。
彼は、どんなところに「つまづき」や「生きにくさ」を感じているでしょうか。
彼が善意でしていること、たくさん誤解されていますね。
決して、悪気がないことが見て取れますね。
お友達とも、ルールが守れなくて仲間にいれてもらえていない。
コミュニケーションの問題があるのではないでしょうか。
彼の字、鏡文字になってますね。
これは、練習不足なのか、それとも、読み書きに問題があるのか、どちらでしょうか。
彼の家庭環境は、どうですか。
お母さんしかいないようですね、お母さんが帰ってくるまで小さい妹と二人きりで留守番。
きっと宿題も見てもらっていない・・・かも・・。
これは、「叱らない」ということは、何かの解決になるのか?
決して、それだけでは、この子の問題の何一つ、解決になりません。
彼に必要なのは、叱咤ではなく、
彼の“つまずき”を理解した上での支援ではないでしょうか?
友達とうまくコミュニケーションできて、
学校の勉強についていけるようになって、
そうしてようやく、彼は 「おこられない」子になるのではありませんか。
涙が出てしまうのは、自分は叱るばかりでこの子の気持ちの何もわかっていなかったことに気づく、
反省の意味も込めての涙なのであれば、
もう一歩進めましょう。
この子が泣かなくてもすむような、支援をしてやりましょう、と。
そういう風な視点で読める本ではないかな、と
紹介させて頂きました。
「特別支援と子どもたち」というタイトルでお話しをさせて頂きました。
そのとき、発達障害の法律的な背景や、障害の種別、例などについても触れたのですが、
『おこだでませんように』という絵本を読んで、
その感想をおっしゃってくださった方が多かったので、ご紹介します。
『おこだでませんように』くすのきしげのり(著)
アマゾンの内容紹介を引用させて頂きます。
「怒られてばかりいる子の心の中を描いた絵本
「ぼくは、いつでもおこられる。家でも学校でも…。休み時間に、友だちがなかまはずれにするからなぐったら、先生にしかられた」いつも誤解されて損ばかりしている少年が、七夕さまの短冊に書いた願いごとは…?」
内容(「BOOK」データベースより)
「ぼくはいつもおこられる。いえでもがっこうでも…。きのうもおこられたし、きょうもおこられている。きっとあしたもおこられるやろ…。ぼくはどないしたらおこられへんのやろ。ぼくはどないしたらほめてもらえるのやろ。ぼくは…「わるいこ」なんやろか…。ぼくは、しょうがっこうににゅうがくしてからおしえてもらったひらがなで、たなばたさまにおねがいをかいた。ひらがなひとつずつ、こころをこめて…。」
沢山の人が、この本を読んで、とにかく涙が出てしまう、と書いておられます。
私も、読むたびに、主人公の男の子の気持ちを考えると、声が震えてしまいます。
この本を読んで、
「そうや、叱ってばかりじゃだめだな」
と思う先生、親、たくさんいらっしゃると思います。
「ぼくも(私も)、しかられるのいややなあ」
と思う子ども達、たくさんいるでしょうね。
ですが、教師としては、そこで終わってしまわずに、もう一歩、よくよくこの子を見て欲しいと思います。
彼は、どんなところに「つまづき」や「生きにくさ」を感じているでしょうか。
彼が善意でしていること、たくさん誤解されていますね。
決して、悪気がないことが見て取れますね。
お友達とも、ルールが守れなくて仲間にいれてもらえていない。
コミュニケーションの問題があるのではないでしょうか。
彼の字、鏡文字になってますね。
これは、練習不足なのか、それとも、読み書きに問題があるのか、どちらでしょうか。
彼の家庭環境は、どうですか。
お母さんしかいないようですね、お母さんが帰ってくるまで小さい妹と二人きりで留守番。
きっと宿題も見てもらっていない・・・かも・・。
これは、「叱らない」ということは、何かの解決になるのか?
決して、それだけでは、この子の問題の何一つ、解決になりません。
彼に必要なのは、叱咤ではなく、
彼の“つまずき”を理解した上での支援ではないでしょうか?
友達とうまくコミュニケーションできて、
学校の勉強についていけるようになって、
そうしてようやく、彼は 「おこられない」子になるのではありませんか。
涙が出てしまうのは、自分は叱るばかりでこの子の気持ちの何もわかっていなかったことに気づく、
反省の意味も込めての涙なのであれば、
もう一歩進めましょう。
この子が泣かなくてもすむような、支援をしてやりましょう、と。
そういう風な視点で読める本ではないかな、と
紹介させて頂きました。











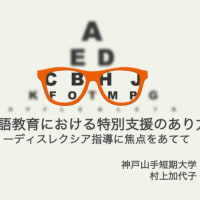



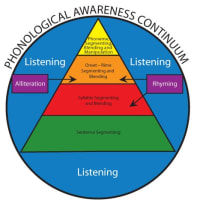
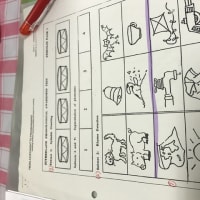



今日、Mayukaさんに会って、おばちゃんの会の内容をきき、先生のことも伺いました。このお話、今年の7月に読み込んで練習してサークルで読み聞かせをしたのです。初めてであった昨年は、とても人様の前で読める絵本ではなくて…(苦笑)今年は泣かないようにと練習したのでした。
このお話の別の見方をMayukaさんから聞きましてとても興味を持ちました。コミュニティにも参加させてくださいね。<(_ _)>
ああ、私もこの本を読むたびに、どうしても涙が出ますが、ずいぶんかくして読めるようになったクチですよ!!
この絵本、「いい話だ」で終わるにはとてももったいないと思いませんか。
ぜひ、指導者の立場で何ができるかなーのきっかけになるといいなーと思いました。
わたしなんてとても未熟ですが、一緒に勉強していけると心強いです。
コミュでも、よろしくお願いします。
涙があふれてきて、息子を受け入れることが出来るまでにいろいろ息子に言ってきたことを思い出し、なんてつらい言葉をかけてきたんだろうって・・・。
それでも、ともすればイラついて声を荒げてしまうことも・・・
そんなときのために、いつも見えるところにこの本を置いて、自分をリセットしたいと思いました。
私も、一生懸命読み込んで練習して、なにかの機会に読み聞かせをしてみたいです。
私は関東生まれですが、祖母が大阪出身で小さいときは大阪弁と関東弁のバイリンガル少女でした!でも中年となった今はもう全然・・・うまく伝えるために関西弁もお友達に習おうかな、って思っています。
素敵な本を紹介して頂いてありがとうございました!
大丈夫ですよ、なんちゃって関西弁で。
私はいつも、「せっかく・・」という一文になかされます。
そうだよね、子どもは本当に自分の可能性を疑いなく信じてきてるのに、大人がそれをギュウギュウ踏みつけて、できないこって決めつけちゃったんだよね・・・ごめんね・・って。
お母さんとしても、教師としても、反省点ばっかり感じちゃいます。
ですが、この子をハッピーにできるのも、先生やお母さんです!!!そこでがんばっていきましょう。
http://www.dokusyokansoubun.jp/text55/stei.html
すてきなリンク、ありがとう。
読みました。うーん、とうなってしまった。
これ、シェアさせてくださいね。