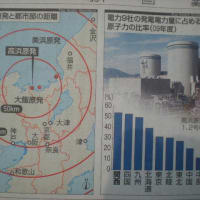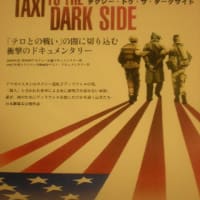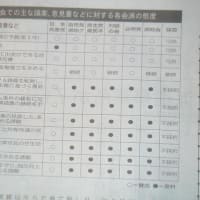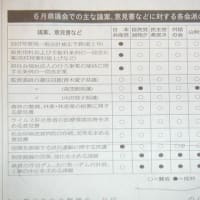【毎日新聞特集「湖国の人たち」:オピニオン’12 高城一哉さん
◇養子から親に「在日」の縁 寂しいまま、他人を大切に
自然の中で健常者と障害者や里子たちが共に暮らし、自給自足を目指す「大萩茗荷村(おおはぎみょうがむら)」(東近江市百済寺甲町)。旧愛東町の協力で82年に開かれ、現在は日野町などにも拠点が広がり約150人が暮らす。開村の中心になった高城一哉さんは妻の正子さん(63)とこれまで30人以上の里子を育ててきた。自身も実の親の顔を知らずに育ったという一哉さん。その数寄な出合いと歩みを聞いた。【村瀬優子】
−−お生まれは戦後すぐですね。
私は自分の生みの親を知らんのです。母のおなかにいる時、養子にほしいという在日朝鮮人のご夫婦がいて、血はつながっていないけれど子供にしてくれました。けれども5歳の時に離婚し、養父は在日の女性と再婚しました。その継母(けいぼ)に3人の子供が生まれ、私が養子に来た意味がなくなってしまった。3人は在日の学校に行きましたが、私は日本人として育てられ、ハングル(朝鮮語)も教わりませんでした。
養父たちは民族を大切にし、同化せず「在日」を貫いていた。植民地政策に対する民族としての誇りだったのかもしれませんね。私を「日本人」として大事にしてくれましたが、どこかでいつも疎外感がありました。17歳の時に自立しようと家を出ました。
それからは書店で住み込みで働いたり、農業を始めたり。本の配達先の福祉施設で、寮長をしていた田村一二先生と知り合いました。田村先生の「茗荷村見聞記」(障害者と健常者が助け合って生きる村を描いた小説=1971年刊)が映画化され、感銘を受けた有志たちと開村にかかわりました。83年に妻と実子3人、里子1人の一家6人で移住しました。
−−茗荷村のどこにひかれたのですか?
最も弱い人たちが大切にされる場を作りたいと思っていました。79年に大津市で障害者の共同作業所を開きましたが、近江学園(知的障害児の入所施設)などの施設を出た後のアフターケアができていないと感じていました。施設から地域へ、という考え方もありました。茗荷村では全体で協力し、物資的・経済的に自立することを目指しています。
過疎の村を理想の村にし、自然の中で豊かに農業をしながら暮らしていく。失敗したり笑ったりしながら、みんなが仲良く暮らそうと努力するプロセス、それが茗荷村だと思っています。
−−里子と接する中で感じたことは?
初めて里子にしたのは2歳の男の子です。里子を引き取るために乳児院に行ったら、在日の子がいて、縁を感じました。当時は乳児院で一緒に遊んで、気心が合った者同士が親子になっていたんです。彼は神様、仏様が縁をくださった私の子なんでしょうね。今は成人して頑張っています。
昔から「親のない子は神様や仏様の子だ」と育てられたと聞きます。私もそう思って里子の子を育てています。養父が亡くなってから私は帰化しましたが、日本国籍を取り戻しても、自分が誰だか分からない。その空白を埋めてくれるのが養父母の「親としての家系」です。
村に来る親のいない子は寂しさを抱えているでしょうが、それをぬぐい去ることはできなくても、埋めることはできる。寂しいままで、他人を大切にすることができたら、それを超えることができると思います。それを伝えたいです。
−−今後の活動は?
在日の人たちへのご恩返しにと、20年ほど前から韓国の被爆者や慶州ナザレ園(身寄りのない在韓日本人女性のための老人保護施設)の支援を村の人たちと続けています。
また、昨年10月から宮城県東松島市で、大震災で被災した子供たちの世話などをするファミリーホームを運営しています。傷ついた大人たちも子供を見たら元気になります。子供が元気に育つ手伝いをしたいですね。
==============
■提言
◇平等な教育社会で支え
里子たちの実の親には社会的弱者が多いのです。子供は親の社会的立場を基盤にしてしか育つことができません。親が生活保護に頼ると、子供にも連鎖しやすい。貧富の差からくる養育力の差もあります。すべての子供が平等に養育や教育を受けられるような社会づくりに取り組まないといけません。
==============
■人物略歴
◇たかしろ・いっさい
1946年5月、大津市生まれ。生後すぐに在日朝鮮人の夫婦の養子になる。83年に大萩茗荷村に移住し、村の初代代表を務める。障害者の就労支援などをする社会福祉法人「美輪湖の家」理事長。
(4月21日付け毎日新聞・電子版)
http://mainichi.jp/area/shiga/news/20120421ddlk25040441000c.html
http://mainichi.jp/area/shiga/news/20120421ddlk25040441000c2.html
http://mainichi.jp/area/shiga/news/20120421ddlk25040441000c3.html
http://mainichi.jp/area/shiga/news/20120421ddlk25040441000c4.html