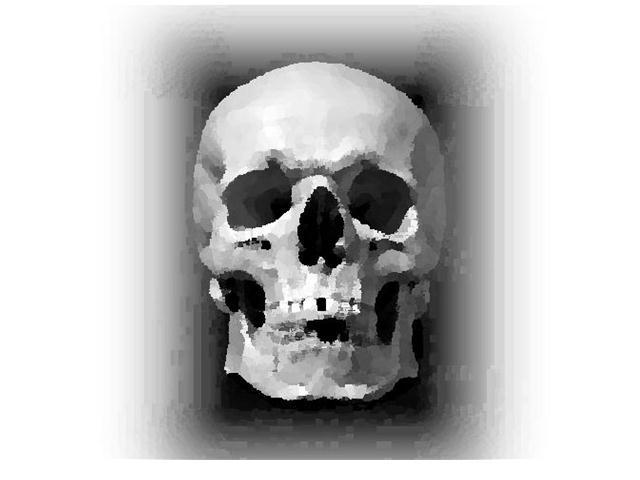「合掌土偶」が見つかって、この姿が「縄文の心」と一致するように思いました。
願いをかなえてもらうための姿でしょうか
両手を合わせるしぐさが「あ、そうだ?」という気持ちに誘い込んだのです。

はじめに、三内丸山遺跡の六本柱に出会い「手を合わせる」のモニュメントでないかと意味付けすることができました。

六本柱が「縄文の心」を表すものであり本来的には「10本柱」であったと想像しました。
風張遺跡の「合掌土偶」といわれる姿です。この姿は縄文時代からあったことを「合掌の姿」が証明しています。

自然との共存を志す縄文ヒトの生き方を示す指標になると考えます。もちろん現代ヒトに対する指標でもあります。
図面は10本柱が円形状に並んでいます。真脇遺跡の「環状木柱列」とよばれているものです。
次に示すのは「チカモリ遺跡の柱列」です。

10本の柱の図がありますが親指を想像できる手を合わせた姿のようです。
縄文土器(土偶)を解読しないで縄文文化は語れない。
「縄文の心」は、全ての縄文遺跡が世界に伝えるべき価値があるものと思います。
「両手の法則」(合掌)を縄文ヒトは意識の中核に備えていた。
縄文楽 浄山(北黄金貝塚ガイド 小倉)