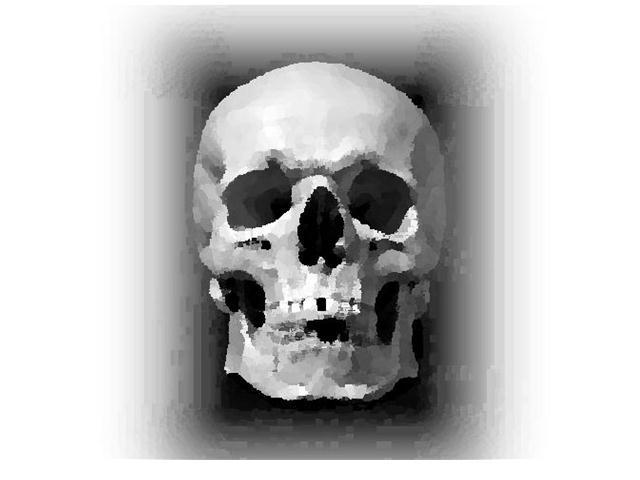1、土器の説明
「長野県原村・大石遺跡・13.2cmH・八ヶ岳美術館所蔵
縄文・前期から中期、富士眉月弧地域に現れた独特の土器、有孔鍔付土器。」
と解説があった。
この土器の使用法については、次の様な説をよく聞きます。①酒造りの醸造器と想像されている説。・小穴が発酵ガスの排気口とし、醸造器説を主張する。②太鼓だとする説
・小穴に紐を通して皮を固定したものだとする。
2、 . . . 本文を読む
1、解説文の一部
・一の沢遺跡は、山梨県笛吹市境川町小黒坂字一の沢にある。
・縄文時代中期を中心とした集落遺跡。
・2つの大規模な環状集落があり、ひとつは県内でも例のない井戸尻式期の集落。
以上が解説の抜粋です。
2、土器から見える事
・周辺の風景(山、川、湖沼など)が、この土器に表現されていないようです。
・「おらの世界」が設定できないのです。
・模様は景色という . . . 本文を読む
縄文余話・鍋
縄文土器は「鍋」として 本当に使用していたのだろうか ?
ここに「内耳土器」という土器が あります。
これは中世の時代に使われたということです。
もともと鉄鍋というのが大陸から入ってきて煮炊きをするようになったと感じています。
ところが鉄鍋は特別な技術が必要で製造や加工が簡単にできないので、これを何とか土製で作られないかということで考えられたと想像するのです。
ところで、 . . . 本文を読む
1、土器の解説の抜粋
似たような作りの土器が並んでいます。天空に祈っているように見えます。
・群馬県は関東平野と中部山岳地帯との中間部にあり、原始より平野部からの人々や山脈を越えた人々との交流が見られる地域です。
・新潟県や長野県、南関東、北関東周辺地域との文化交流の様子や、赤城山麓に芽生えた地域文化の特色を示す土器群です
・特に本遺跡の特徴として、「焼町土器(やけまちどき)」がありま . . . 本文を読む
1、以前と同じ遺跡の土器
・人々との交流が見られる地域です。
・赤城山麓に芽生えた地域文化の特色を示す土器群です
・赤城山麓一帯で縄文時代中期に地域に根ざした地方独自の生活・文化が営まれていたことを示す貴重な遺物です。
2、土器を解明
以前と同じ遺跡の土器です。似ていますので比べて調べるつもりです。
この土器の解説に戻ります。
・ . . . 本文を読む
1、大館町遺跡(岩手県)・縄文時代中期/4500年前・高さが約93cmもある,国内最大級の縄文土器です。
・キャリパー形という口縁部分がふくらみ,胴部分がくびれる独特の器形
2、大きな土器を考える
・大きな土器だ。何を入れるかは、日用的な品を入れる土器があるのかと思う。
・「甕棺」が順当な考えとも思うが・・。
・なぜ、このような土器を作るのか。意味が有ると . . . 本文を読む
縄文時代中期になると紋様が立体化し造形的に最も装飾的になるといわれる。
土器には必ず意味が有り、意味の無い土器を作ることはしません。その縄文ヒトの意識を込めた意味を少しでも解明できたらと願いたいものです。
これは、中期の最初の土器で66㎝の大きなものです。
1、解説
「東関東の中期前半を代表する土器。
四つの大きな扇状の突起を持ち耳状の隆線 . . . 本文を読む
山形県押出遺跡土器
この遺跡の土器を調べていると、器形が二段になった土器が偶然見つかったのです。
これは一体何だろうということで取り上げることにしました。
土器と同じ画面にこの風景が目に入ったのです。
なんとなく風景と土器の形が似ているのです。
底は浅い丸底で、水面を境にして二段になった地形です。
二段になっていて浮き輪のように水に浮いているように思います。
「浮島」に住んでいるよ . . . 本文を読む
1、解説内容
山形県押出遺跡土器 「写真の土器は、高さ14.5cm、径23cmで、体部が優美な丸味をおび、口縁のまわりには小さな孔がめぐっている。
底は丸底で、そのままでは立たない。
赤漆を地に黒漆で文様が描かれている。
それは体部の上半と下半に区切られ、渦巻文を4ヵ所に配し、それから弧状や三角状の文様が広がっている。同時期の土器の文様構成に共通している。 」と解説文がある。
. . . 本文を読む
1、はじめに
時間が経つとまた別な考えが浮かんできます。このようにして積み重ねることによって確かなものになると考えます
2,土器を観察して
縄文土器のようにムラに一つというモノではない。
生活環境を描いていると考えるのでイノシシという動物の環境は考えられない。生き物でも植物であろう。
これは日常的にいつも目にして必要にしているものではないか。
土器面の模様から川のあるところ . . . 本文を読む