北九州八幡から発信
八幡、やはた、やわた、はちまん
旧唐津街道・芦屋宿を歩く

先日の「筑前芦屋だごびーなとわら馬まつり」に行った時、
旧唐津街道・芦屋宿を、ちょっぴり歩いてきました。
芦屋小学校前の交差点(信号)から、
遠賀川の方向に歩き、突き当たった所から川上の方へ、
この道が多分、旧街道だと思う。

旧唐津街道は、
若松宿~肥前唐津城間(30里、約118km)に13宿あり、
「若松宿」の次が「芦屋宿」です。
☆○o...:**:...o○☆**☆○o...:**:...o○☆**☆○o...:**:..
「筑前蘆屋宿場構口の跡」です。
(芦屋の【芦】は、昔は【蘆】を使っていました。)
構口(かまえぐち)とは、
いわゆる宿場の出入口のことです。
この石碑が無ければ、
ここが昔栄えた宿場だったとは、全く分かりません。

劇場大國座跡です。(構口のすぐ近くです。)
大国座は1900(明治33)年に建てられた建物で、
定員820人の大劇場と言うから凄いです。
昭和19年に焼失し、戦後の昭和23年に再建されましたが、
経営不振のため、昭和41年に閉鎖・解体。
えっ、こんな所に!って感じです。
跡地の一部に建てたのだろうか?
横の建物は幸町公民館とありました。

蘆屋警察署跡です。
明治八年(1875年)福岡県第五大区芦屋警察掛巡視所として、
この地に設置さる。
仝十年芦屋警察署と改称し、のちに分署を若松・黒崎・赤間に置く
(當時県下では、福岡 久留米 柳川 甘木 八屋 飯塚 小倉と芦屋の八署)
時代の変還に伴い明治二十二年若松に移り、芦屋はその分署となる。
(石碑の裏の説明文より)

更に進むと、遠賀川に突き当たりました。
これより、右側(川上)へ向かいます。

川下を眺めると、なみかけ大橋が、

川上の方は、芦屋橋(現在建替え中)
その後ろに皿倉山と権現山がはっきりと、
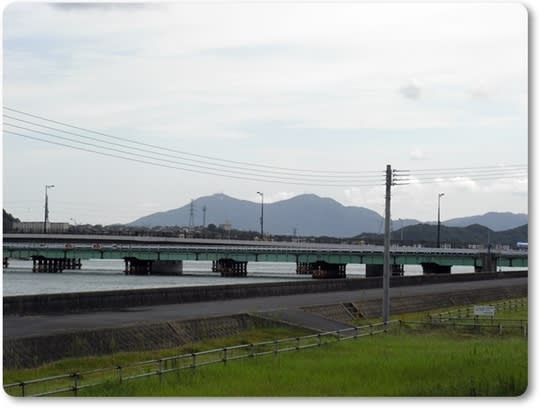
川沿いの街道筋です。

福岡藩焚石會所跡です。 (焚石、即ち石炭のことです。)
1837(天保8)年、
福岡藩は新たに制度強化した焚石会所を芦屋・若松に設け、
松本平内の献策した仕組法により、筑豊の石炭の採掘から、
売りさばきまで、藩直営としました。

筑前蘆屋釜鋳造跡です。
芦屋釜は遠賀川の砂鉄を使い、鎌倉時代より独特の技法で鋳造され、梵鐘・鰐口・香爐等と共に天下に珍重されました。
茶道をやられている方は、ご存知と思いますが、
国の重要文化財に指定されている茶の湯釜9個のうち8個までを芦屋釜が占めています。


芦屋は昔、
福岡藩の米蔵が建ち遠賀川流域の年貢や生産物が集まる町として栄え、「芦屋千軒」と称されるほどの賑わっていました。
宝暦13年(1763年)、堀川運河(芦屋と若松をつなぐ運河)の完成により藩の米蔵が若松に移転し、その後、藩内唯一の石炭の積出港でしたが、これも後に若松に移され、衰退していきました。
それでも、明治の時代まで郡役所があり、遠賀郡の政治・経済の中心であったことは、間違いありません。
現在は、基地(航空自衛隊)の町、競艇の町、農業と漁業の町、
北九州のベッドタウン、そしてリゾートの町でしょうか。
コメント ( 10 ) | Trackback ( 0 )
| « だごびーな と... | 10月の皿倉山 » |





自分ではずっと歩いて記事を書きましたが
近くの町のブログ友が歩いて下さった・・・嬉しいなぁ~
1番上の蔵のある家 お友達の実家です。奥は河口というか海と思ってました。船が家に直接着いてました。
大國座 子供の頃行きました。あの松井須磨子もきてるんですよ。。
もうすぐ開通する芦屋橋 ふもとは蘆屋の船着き場だっから石碑があったのを
工事中 公民館に置いてあります。工事が終わったら
きっと立てられると思います。
私の唐津街道の記事に写真を入れています。
芦屋町のご紹介ありがとうございます。10月の航空祭にもいらっしゃって下さいね。
オバサンがコンデジ持ってあっちウロこっちウロしていたら
それは私ですから・・・・
最初の写真は、白壁で一番気に入ったもんだから、トップに、
友達の実家ですか、昔からの由緒ある家のようでした。
大國座の昭和19年の焼失しは、空襲の為かと思っていたが、
調べたら、廣澤虎造の浪曲公演中の火災で全焼したそうですね。
あまり予備知識は無かったが、街道は芦屋橋の辺りから、
渡し舟で山鹿へと、続くんですね。
ちょっと新しいようでしたが、説明の石碑があって分かり易かったです。
栄枯盛衰だなぁ~という思いになっちゃいます。
今ある私たちの町も10年後いや100年、200年後
どういう位置づけになっているのでしょう。
面白くもあり、寂しくもあり、複雑でもあります。
九州の芦屋って、福岡藩の要所として栄えた
歴史ある町なんですねぇ・・
茶の湯釜製造の技術もピカイチやったんやね!
私の住む兵庫県の芦屋は
市になってまだ60年、歴史浅いねぇ
春休みのデッサン室さんがコメントされているように
私たちの住む街の未来は、どんな風になっているんでしょうね
栄枯盛衰ですか?
芦屋は、つい最近まで財政豊かな町でした。
町営住宅や町の公共施設は、立派な物ばかりです。
それと下水道の完備は、北九州市よりかなり前に行われています。
基地の補助金、競艇の収入だそうで、今は競艇の収入も減って、
周辺の町との合併とか? (何かうまく、いかなかったようで、)
本当のことを言うと、芦屋がそんなに歴史のある町だとは知らなかった。
海がきれいで、夏の海水浴場としてしか、最近は海水浴も行かないからなぁ!
兵庫の芦屋ですか?
良く分からないが、それなりの歴史も古いのでは?
イメージは六甲の麓、海が見下ろせる高級住宅が並ぶ街、
勿論、住んでる人も有名人、関西の財界人が住む超裕福な人ばかり。
だけじゃ無いだろうが、芦屋に住んでいるだけでも自慢の種??
先だって能楽堂で観た「鵺(ぬえ)」の舞台。
旅の僧が攝津・蘆屋里で不思議な舟人と出会う。この男は実は「鵺」の亡霊でだった。帝を苦しめた罪により源頼政に射られた様を語り、弔いを頼み、姿を消す。詩情味豊かな鬼能。
「鵺」とは平家物語に登場する「変化(へんげ)の者」。頭は猿、尾は蛇、手足は虎の如くで、鳴く声は「ヌエ(トラツグミ)」に似ているという。近衛天皇を悩ませたが源頼政により、弓で射られた。
当時は強い豪族の支配する里村だったのでしょう。
「鵺」は現代では遺伝子操作で作り出すキメラみたいだが、強くて怖かったんでしょう。
芦屋の街中を歩く事って無い私。
昔はこの街道を多くの人たちが、行き交って居たんですね。
そう思いながら写真を見てました。
各場所に石碑があるので、一つ一つ辿っていくのも
面白いでしょうね。
なかなか行く事がない芦屋の写真、ありがとうございました。
芦屋と云ったら、競艇と思い浮かぶ人もいるだろうが、
私はやらないので、やっぱり海ですね。
その競艇、海でやってるかと思ったら、違うんですね。
海から、ず~と離れた田圃の中?
巨大な人工の池・プールを造ってやっているようです。
芦屋は浜木綿が咲く頃の、夏井ヶ浜が一番いいです。
兵庫の芦屋
>住んでる人も有名人裕福な人、だけじゃ無いだろうが・・
そうそう
この場をお借りして・・
natukasuiiさんへ
鵺の伝説のお話を、ありがとうございます。
家の近所に「鵺塚」の碑があります
源頼政の矢で射られた鵺が
淀川から大阪湾に流れ、芦屋の浜に流れついたそう。
これをとむらい塚にしたのが始まり、なのだとか。
街の歴史も調べてみると、興味深いですね!
※ブログ管理者のみ、編集画面で設定の変更が可能です。