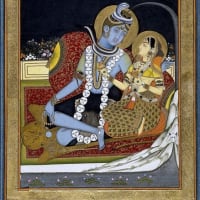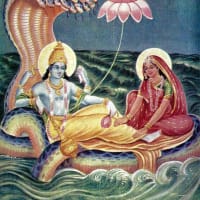※更科功(サラシナイサオ)(1961生)『爆発的進化論 1%の奇跡がヒトを作った』新潮新書、2016年
第5章「肺」酸素をどう手に入れるのか
(17) B「硬骨魚類」のうちB-1「肉鰭類」(ニクキルイ)は肺を持つ!B-2「条鰭類」(ジョウキルイ)のうちB-2-1「分岐鰭類」はエラのほかに肺もある!B-2-2「分岐鰭類以外の条鰭類」はいわゆる普通の魚でエラ呼吸だ!
金魚が水面で口をパクパクさせる時、金魚は空気中の酸素を吸って呼吸できる。そもそも魚の中には肺呼吸できる魚がいる。現存の魚はA「軟骨魚類」(Ex. サメ、エイ)とB「硬骨魚類」(ほとんどの魚!)からなる。硬骨魚類は、B-1「肉鰭類」(ニクキルイ)(肉質のヒレを持ち、肺もエラも持つ、Ex. シーラカンス、肺魚;ただしシーラカンスの肺は使わないので脂肪が詰まっている)とB-2「条鰭類」(ジョウキルイ)(一般的な魚のひれを持つ)からなる。「条鰭類」のうち約20種類はB-2-1「分岐鰭類」(ブンキキルイ)でエラのほかに肺もある。(Ex. ポリプテルス)B-2-2「分岐鰭類以外の条鰭類」(3万種以上)はいわゆる普通の魚(Ex. メダカ、マグロ)で、エラで水中の酸素を取り入れ、空気呼吸をしない。(89-93頁)
※陸上脊椎動物はB-1「肉鰭類」から進化したと言われる。
(17)-2 うきぶくろと肺は「相同」な器官だが、「うきぶくろが肺に進化した」のでない!「肺がうきぶくろへと進化した」!
さてうきぶくろと肺は両方とも、消化管が膨らんでできた器官で、「相同」な器官(つまり祖先では同じだった器官)だ。だからといって、「動物は水中から陸上に上がったので、うきぶくろが肺に進化した」というわけでない。さかさまに「肺がうきぶくろへと進化した」のだ。(93-94頁)
(17)-3「肺がうきぶくろへと進化した」理由1:「オッカムのかみそり」(仮説が複数ある時は単純な仮説を選ぶ)!「硬骨魚類」の最終共通祖先が持っていたのは、うきぶくろでなく肺だ!肺からうきぶくろが進化した!
「硬骨魚類」の共通祖先が「うきぶくろ」を持っていたとすると(仮説①)、B-1「肉鰭類」(ニクキルイ)になった時、「肺」へ進化した。またB-2「条鰭類」(ジョウキルイ)からB-2-1「分岐鰭類」(ブンキキルイ)になった時、「うきぶくろ」が「肺」に進化した。つまり「うきぶくろ」から「肺」への進化が2度起きたことになる。他方で「硬骨魚類」の共通祖先がもともと「肺」を持っていたとすると(仮説②)、「肺」から「うきぶくろ」への進化はB-2「条鰭類」(ジョウキルイ)がB-2-2「分岐鰭類以外の条鰭類」になる時1度起きればよい。「オッカムのかみそり」(仮説が複数ある時は単純な仮説を選ぶ)によれば、仮説②が正しいと考えるべきだ。(95-97頁)
(17)-4「肺がうきぶくろへと進化した」理由2:エラ呼吸より肺呼吸の方が、ずっと効率がいい!水中に住む「硬骨魚類」でも、肺呼吸が出来て損はない!
「硬骨魚類」において「うきぶくろより先に肺が進化した」の、エラ呼吸より肺呼吸の方が、ずっと効率がいいからだ。(実は水中には酸素があまり溶けていない。分子数で比べると、大気中の3%くらいだ。)水中に住む「硬骨魚類」でも、肺呼吸が出来て損はない。水中にいても、たまに口を水面から出すなどして空気を吸えば、効率的だ。(Cf. クジラは水中に住むが肺呼吸する。)(97-99頁)
第5章「肺」酸素をどう手に入れるのか
(17) B「硬骨魚類」のうちB-1「肉鰭類」(ニクキルイ)は肺を持つ!B-2「条鰭類」(ジョウキルイ)のうちB-2-1「分岐鰭類」はエラのほかに肺もある!B-2-2「分岐鰭類以外の条鰭類」はいわゆる普通の魚でエラ呼吸だ!
金魚が水面で口をパクパクさせる時、金魚は空気中の酸素を吸って呼吸できる。そもそも魚の中には肺呼吸できる魚がいる。現存の魚はA「軟骨魚類」(Ex. サメ、エイ)とB「硬骨魚類」(ほとんどの魚!)からなる。硬骨魚類は、B-1「肉鰭類」(ニクキルイ)(肉質のヒレを持ち、肺もエラも持つ、Ex. シーラカンス、肺魚;ただしシーラカンスの肺は使わないので脂肪が詰まっている)とB-2「条鰭類」(ジョウキルイ)(一般的な魚のひれを持つ)からなる。「条鰭類」のうち約20種類はB-2-1「分岐鰭類」(ブンキキルイ)でエラのほかに肺もある。(Ex. ポリプテルス)B-2-2「分岐鰭類以外の条鰭類」(3万種以上)はいわゆる普通の魚(Ex. メダカ、マグロ)で、エラで水中の酸素を取り入れ、空気呼吸をしない。(89-93頁)
※陸上脊椎動物はB-1「肉鰭類」から進化したと言われる。
(17)-2 うきぶくろと肺は「相同」な器官だが、「うきぶくろが肺に進化した」のでない!「肺がうきぶくろへと進化した」!
さてうきぶくろと肺は両方とも、消化管が膨らんでできた器官で、「相同」な器官(つまり祖先では同じだった器官)だ。だからといって、「動物は水中から陸上に上がったので、うきぶくろが肺に進化した」というわけでない。さかさまに「肺がうきぶくろへと進化した」のだ。(93-94頁)
(17)-3「肺がうきぶくろへと進化した」理由1:「オッカムのかみそり」(仮説が複数ある時は単純な仮説を選ぶ)!「硬骨魚類」の最終共通祖先が持っていたのは、うきぶくろでなく肺だ!肺からうきぶくろが進化した!
「硬骨魚類」の共通祖先が「うきぶくろ」を持っていたとすると(仮説①)、B-1「肉鰭類」(ニクキルイ)になった時、「肺」へ進化した。またB-2「条鰭類」(ジョウキルイ)からB-2-1「分岐鰭類」(ブンキキルイ)になった時、「うきぶくろ」が「肺」に進化した。つまり「うきぶくろ」から「肺」への進化が2度起きたことになる。他方で「硬骨魚類」の共通祖先がもともと「肺」を持っていたとすると(仮説②)、「肺」から「うきぶくろ」への進化はB-2「条鰭類」(ジョウキルイ)がB-2-2「分岐鰭類以外の条鰭類」になる時1度起きればよい。「オッカムのかみそり」(仮説が複数ある時は単純な仮説を選ぶ)によれば、仮説②が正しいと考えるべきだ。(95-97頁)
(17)-4「肺がうきぶくろへと進化した」理由2:エラ呼吸より肺呼吸の方が、ずっと効率がいい!水中に住む「硬骨魚類」でも、肺呼吸が出来て損はない!
「硬骨魚類」において「うきぶくろより先に肺が進化した」の、エラ呼吸より肺呼吸の方が、ずっと効率がいいからだ。(実は水中には酸素があまり溶けていない。分子数で比べると、大気中の3%くらいだ。)水中に住む「硬骨魚類」でも、肺呼吸が出来て損はない。水中にいても、たまに口を水面から出すなどして空気を吸えば、効率的だ。(Cf. クジラは水中に住むが肺呼吸する。)(97-99頁)