都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「画鬼・暁斎ーKYOSAI」 三菱一号館美術館
三菱一号館美術館
「画鬼・暁斎ーKYOSAI 幕末明治のスター絵師と弟子コンドル」
6/27-9/6

三菱一号館美術館で開催中の「画鬼・暁斎ーKYOSAI 幕末明治のスター絵師と弟子コンドル」のプレスプレビューに参加してきました。
かつての三菱一号館を設計したイギリス人建築家、ジョサイア・コンドル。日本美術の愛好家でもあった彼は、明治時代の絵師、河鍋暁斎に弟子入りをして、絵を学んでいたことがあったそうです。
コンドルの目を通して、河鍋暁斎の業績を検証します。出品はコンドルの作品も含めて135点。うち途中に一度、展示替えを挟みます。殆どは河鍋暁斎記念美術館のコレクションです。ほかにも数点、静嘉堂文庫、そしてメトロポリタン美術館から作品がやって来ています。

河鍋暁斎「東京名所之内 上野山内一覧之図」 明治14年 河鍋暁斎記念美術館
二人の出会い、それは明治14年の上野でした。同年に上野の山で行われた内国勧業博覧会、そのパビリオンとも言える上野博物館の本館を若きコンドルが設計します。

河鍋暁斎「枯木寒鴉図」 明治14年 榮太樓總本鋪
それを暁斎が錦絵、「東京名所之内 上野山内一覧之図」に描きます。また博覧会は美術の公募展でもありました。暁斎も4点ほど出品。うち「枯木寒鴉図」が絵画の分野での最高賞を受賞しました。

ジョサイア・コンドル「鯉之図」 明治時代 河鍋暁斎記念美術館
おそらくはそれをコンドルを見たことでしょう。この年、暁斎に弟子入り。暁斎50歳、コンドル29歳のことです。二人はとても親密に交流します。明治18年には日光へ連れ立って写生旅行。その旅立つ姿を暁斎は「暁斎絵日記」に描きました。また絵の手習いを受けていたコンドルも作品を残しています。例えば「鯉之図」です。暁斎の「鯉魚遊泳図」に倣った一枚。二匹の鯉が上下に向き合うように泳いでいます。タッチは軽快です。ただし鱗の描写は細かい。小魚を加え、鯉の大きさを強調してもいます。

河鍋暁斎「大和美人図屏風」 明治17-18年 京都国立博物館(寄託)
彩色鮮やかな屏風に目を奪われました。暁斎の「大和美人図屏風」です。二曲一隻、いわゆる遊女でしょうか。ともに立派な立ち姿をしています。赤い衣に花かご、後ろの屏風には稲作の様子が描かれています。ほかに漆器や畳みなど、これでもかというほど日本の文物を描きこんでいますが、実は本作、コンドルが自国に持ち帰ることを想定して暁斎がわざわざ制作したもの。一年もかけて完成した作品でもあるのです。

ジョサイア・コンドル著「Paintings & Studies by Kawanabe Kyosai」 明治44年 河鍋暁斎記念美術館
裕福であったコンドルは暁斎の弟子でありながら、作品のコレクターでもありました。また暁斎の死後、画家の人生や業績を記した「Paintings & Studies by Kawanabe Kyosai」を出版。カラーの口絵に「大和美人図屏風」を掲載しています。結果的にこの本によって暁斎が西洋で知られるようになったそうです。
さて本展、確かに起点はコンドルと暁斎の二人にありますが、展示中盤からは言わば暁斎祭。怒濤のように暁斎画が並んでいます。
それにしても暁斎、何でも描けてしまいます。まさしく芸達者です。動物画に神道や仏教主題の人物画、そして幽霊・妖怪画に山水、戯画、風俗画に美人画などと幅広い。風刺画でも人気を得ていました。しかもそれらがいずれも魅せる。国芳に弟子入りし、狩野派の門を叩いた暁斎。有り余る才知を絵に表現してはぶつけたのでしょう。明治3年には書画会で描いた作品が原因で捕えられてしまったこともあったそうです。ともかく活動は一定の枠に収まりません。

河鍋暁斎「鳥獣戯画 猫又と狸」 明治時代 河鍋暁斎記念美術館
「鳥獣戯画 猫又と狸」はどうでしょうか。右上に猫又、左は狸、下にはイタチにモグラもいます。それらが脚を振り上げながらも一本脚で立つという作品。ともかく猫又の眼光が鋭い。何やら劇画調です。エグ味すらある。構図にも躍動感があります。

河鍋暁斎「三番叟図」 明治前半 河鍋暁斎記念美術館
一転して軽快なのが「三番叟図」です。能や狂言の題からとった舞の姿。素早い筆遣いには迷いもありません。彩色にも透明感があります。ちなみに暁斎、自らが舞台に立つほど能に通じていたそうです。

河鍋暁斎「美人愛猫図」 明治前半 岡田美術館
また「美人愛猫図」も素晴らしい。懐に猫を入れて愛でる遊女。小袖の紋様が艶やかです。女性の表情も穏やかで優しい。着物を少しはだけて描いているのが暁斎風なのでしょうか。肉筆浮世絵の伝統的な画題を美人画として描き出しています。

「画鬼・暁斎ーKYOSAI」展春画コーナー
春画に目を向けているのもポイントです。暁斎もほかの江戸の絵師同様、当然の如く春画を描いています。ここで特徴的なのは「貴賎を問わず入り乱れ、暁斎らしい狂騒が繰り広げられている」(図録より)ことです。情事を笑い飛ばして見るかのような明るさがあります。また古典をパロディー化した作品も目を引きますが、そこにあえてやまと絵の描法を踏襲しています。一筋縄ではいきません。
なお春画のコーナーはカーテンで隔離されています。18歳未満は大人同伴でないと観覧出来ません。ご注意下さい。

右:河鍋暁斎「木菟図」 明治21年頃 メトロポリタン美術館
左:河鍋暁斎「小禽を捕らえる鷲図」 明治21年頃 メトロポリタン美術館
100年ぶり里帰りした連作も要注目ではないでしょうか。現在の所蔵はメトロポリタン美術館です。かつてコンドルの暁斎の共通の知人であるイギリス人が所蔵していたもので、後にアメリカのコレクターへ渡り、メトロポリタン美術館に収められた作品です。
いずれも主題は動物、また子どもを描いて風俗画的な様相も見せています。蛙を捉まえる猫なども可愛らしいもの。押さえつけられた蛙がまるで叫び声をあけているかのようにひっくり返っています。またおそらく元絵となった「英国人画貼下絵」(河鍋暁斎記念美術館)もパネルで紹介されています。見比べるのも面白そうです。

河鍋暁斎「横たわる美人に猫図」 明治前半 河鍋暁斎記念美術館
最後に特に惹かれた一枚を挙げておきましょう。それが「横たわる美人に猫図」です。実は本作、今よりもう10年も前、私が初めて暁斎を見知ったステーションギャラリーの「国芳 暁斎展」で強く印象に残ったもの。もちろんほかの展覧会にも出品されていたかもしれません。ともかく涼し気な眼差しで猫を見やる女性が美しい。映像的と言うには語弊があるやもしれませんが、ふとその一瞬、猫に顔を向けた女性の動き、ようは所作を巧みに切り出しています。

「画鬼・暁斎ーKYOSAI」展館内撮影パネル
暁斎の弟子、コンドルにもゆかりのある三菱一号館美術館での暁斎展。会見時には、河鍋暁斎記念美術館の館長で、暁斎の曾孫でもある河鍋楠美さんが「ありのままの暁斎を知って欲しい。」とのメッセージを寄せられました。確かにここでは等身大、とはいえ常人では到底及ばぬ画業を展開した暁斎の姿を知ることが出来ます。
図録が秀逸です。論考は充実の全8本。本展を担当された一号館の野口学芸員の論文をはじめ、安村先生がメトロポリタン美術館の「動物画帖」を検証したテキスト、また河鍋楠美さんがドナルド・キーンや隈研吾と対談したインタビューなどが掲載されています。いずれも読み応え十分です。
 「芸術新潮2015年7月号/河鍋暁斎/新潮社」
「芸術新潮2015年7月号/河鍋暁斎/新潮社」
会期中、一部作品の展示替えがあります。
前期:6月27日~8月2日
後期:8月4日~9月6日
既に早々から多くの方で賑わっているそうです。金曜の夜間開館(20時まで)なども狙い目ではないでしょうか。また一号館は後半に混雑が集中する傾向があります。まずは早めの観覧をおすすめします。

「画鬼・暁斎ーKYOSAI」展会場風景
9月6日まで開催されています。
「画鬼・暁斎ーKYOSAI 幕末明治のスター絵師と弟子コンドル」 三菱一号館美術館(@kyosai2015)
会期:6月27日(土)~9月6日(日)
*展示替えあり。前期:8月2日(日)まで/後期:8月4日(火)から
休館:月曜日。但し7月20と8月31日は開館。
時間:10:00~18:00。
*毎週金曜日と会期最終週の平日は20時まで。
*入館は閉館の30分前まで。
料金:大人1500円、高校・大学生1000円、小・中学生500円。
*ペアチケットあり:チケットぴあのみで販売。一般ペア2600円。
住所:千代田区丸の内2-6-2
交通:東京メトロ千代田線二重橋前駅1番出口から徒歩3分。JR東京駅丸の内南口・JR有楽町駅国際フォーラム口から徒歩5分。
注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。
「画鬼・暁斎ーKYOSAI 幕末明治のスター絵師と弟子コンドル」
6/27-9/6

三菱一号館美術館で開催中の「画鬼・暁斎ーKYOSAI 幕末明治のスター絵師と弟子コンドル」のプレスプレビューに参加してきました。
かつての三菱一号館を設計したイギリス人建築家、ジョサイア・コンドル。日本美術の愛好家でもあった彼は、明治時代の絵師、河鍋暁斎に弟子入りをして、絵を学んでいたことがあったそうです。
コンドルの目を通して、河鍋暁斎の業績を検証します。出品はコンドルの作品も含めて135点。うち途中に一度、展示替えを挟みます。殆どは河鍋暁斎記念美術館のコレクションです。ほかにも数点、静嘉堂文庫、そしてメトロポリタン美術館から作品がやって来ています。

河鍋暁斎「東京名所之内 上野山内一覧之図」 明治14年 河鍋暁斎記念美術館
二人の出会い、それは明治14年の上野でした。同年に上野の山で行われた内国勧業博覧会、そのパビリオンとも言える上野博物館の本館を若きコンドルが設計します。

河鍋暁斎「枯木寒鴉図」 明治14年 榮太樓總本鋪
それを暁斎が錦絵、「東京名所之内 上野山内一覧之図」に描きます。また博覧会は美術の公募展でもありました。暁斎も4点ほど出品。うち「枯木寒鴉図」が絵画の分野での最高賞を受賞しました。

ジョサイア・コンドル「鯉之図」 明治時代 河鍋暁斎記念美術館
おそらくはそれをコンドルを見たことでしょう。この年、暁斎に弟子入り。暁斎50歳、コンドル29歳のことです。二人はとても親密に交流します。明治18年には日光へ連れ立って写生旅行。その旅立つ姿を暁斎は「暁斎絵日記」に描きました。また絵の手習いを受けていたコンドルも作品を残しています。例えば「鯉之図」です。暁斎の「鯉魚遊泳図」に倣った一枚。二匹の鯉が上下に向き合うように泳いでいます。タッチは軽快です。ただし鱗の描写は細かい。小魚を加え、鯉の大きさを強調してもいます。

河鍋暁斎「大和美人図屏風」 明治17-18年 京都国立博物館(寄託)
彩色鮮やかな屏風に目を奪われました。暁斎の「大和美人図屏風」です。二曲一隻、いわゆる遊女でしょうか。ともに立派な立ち姿をしています。赤い衣に花かご、後ろの屏風には稲作の様子が描かれています。ほかに漆器や畳みなど、これでもかというほど日本の文物を描きこんでいますが、実は本作、コンドルが自国に持ち帰ることを想定して暁斎がわざわざ制作したもの。一年もかけて完成した作品でもあるのです。

ジョサイア・コンドル著「Paintings & Studies by Kawanabe Kyosai」 明治44年 河鍋暁斎記念美術館
裕福であったコンドルは暁斎の弟子でありながら、作品のコレクターでもありました。また暁斎の死後、画家の人生や業績を記した「Paintings & Studies by Kawanabe Kyosai」を出版。カラーの口絵に「大和美人図屏風」を掲載しています。結果的にこの本によって暁斎が西洋で知られるようになったそうです。
さて本展、確かに起点はコンドルと暁斎の二人にありますが、展示中盤からは言わば暁斎祭。怒濤のように暁斎画が並んでいます。
それにしても暁斎、何でも描けてしまいます。まさしく芸達者です。動物画に神道や仏教主題の人物画、そして幽霊・妖怪画に山水、戯画、風俗画に美人画などと幅広い。風刺画でも人気を得ていました。しかもそれらがいずれも魅せる。国芳に弟子入りし、狩野派の門を叩いた暁斎。有り余る才知を絵に表現してはぶつけたのでしょう。明治3年には書画会で描いた作品が原因で捕えられてしまったこともあったそうです。ともかく活動は一定の枠に収まりません。

河鍋暁斎「鳥獣戯画 猫又と狸」 明治時代 河鍋暁斎記念美術館
「鳥獣戯画 猫又と狸」はどうでしょうか。右上に猫又、左は狸、下にはイタチにモグラもいます。それらが脚を振り上げながらも一本脚で立つという作品。ともかく猫又の眼光が鋭い。何やら劇画調です。エグ味すらある。構図にも躍動感があります。

河鍋暁斎「三番叟図」 明治前半 河鍋暁斎記念美術館
一転して軽快なのが「三番叟図」です。能や狂言の題からとった舞の姿。素早い筆遣いには迷いもありません。彩色にも透明感があります。ちなみに暁斎、自らが舞台に立つほど能に通じていたそうです。

河鍋暁斎「美人愛猫図」 明治前半 岡田美術館
また「美人愛猫図」も素晴らしい。懐に猫を入れて愛でる遊女。小袖の紋様が艶やかです。女性の表情も穏やかで優しい。着物を少しはだけて描いているのが暁斎風なのでしょうか。肉筆浮世絵の伝統的な画題を美人画として描き出しています。

「画鬼・暁斎ーKYOSAI」展春画コーナー
春画に目を向けているのもポイントです。暁斎もほかの江戸の絵師同様、当然の如く春画を描いています。ここで特徴的なのは「貴賎を問わず入り乱れ、暁斎らしい狂騒が繰り広げられている」(図録より)ことです。情事を笑い飛ばして見るかのような明るさがあります。また古典をパロディー化した作品も目を引きますが、そこにあえてやまと絵の描法を踏襲しています。一筋縄ではいきません。
なお春画のコーナーはカーテンで隔離されています。18歳未満は大人同伴でないと観覧出来ません。ご注意下さい。

右:河鍋暁斎「木菟図」 明治21年頃 メトロポリタン美術館
左:河鍋暁斎「小禽を捕らえる鷲図」 明治21年頃 メトロポリタン美術館
100年ぶり里帰りした連作も要注目ではないでしょうか。現在の所蔵はメトロポリタン美術館です。かつてコンドルの暁斎の共通の知人であるイギリス人が所蔵していたもので、後にアメリカのコレクターへ渡り、メトロポリタン美術館に収められた作品です。
いずれも主題は動物、また子どもを描いて風俗画的な様相も見せています。蛙を捉まえる猫なども可愛らしいもの。押さえつけられた蛙がまるで叫び声をあけているかのようにひっくり返っています。またおそらく元絵となった「英国人画貼下絵」(河鍋暁斎記念美術館)もパネルで紹介されています。見比べるのも面白そうです。

河鍋暁斎「横たわる美人に猫図」 明治前半 河鍋暁斎記念美術館
最後に特に惹かれた一枚を挙げておきましょう。それが「横たわる美人に猫図」です。実は本作、今よりもう10年も前、私が初めて暁斎を見知ったステーションギャラリーの「国芳 暁斎展」で強く印象に残ったもの。もちろんほかの展覧会にも出品されていたかもしれません。ともかく涼し気な眼差しで猫を見やる女性が美しい。映像的と言うには語弊があるやもしれませんが、ふとその一瞬、猫に顔を向けた女性の動き、ようは所作を巧みに切り出しています。

「画鬼・暁斎ーKYOSAI」展館内撮影パネル
暁斎の弟子、コンドルにもゆかりのある三菱一号館美術館での暁斎展。会見時には、河鍋暁斎記念美術館の館長で、暁斎の曾孫でもある河鍋楠美さんが「ありのままの暁斎を知って欲しい。」とのメッセージを寄せられました。確かにここでは等身大、とはいえ常人では到底及ばぬ画業を展開した暁斎の姿を知ることが出来ます。
図録が秀逸です。論考は充実の全8本。本展を担当された一号館の野口学芸員の論文をはじめ、安村先生がメトロポリタン美術館の「動物画帖」を検証したテキスト、また河鍋楠美さんがドナルド・キーンや隈研吾と対談したインタビューなどが掲載されています。いずれも読み応え十分です。
 「芸術新潮2015年7月号/河鍋暁斎/新潮社」
「芸術新潮2015年7月号/河鍋暁斎/新潮社」会期中、一部作品の展示替えがあります。
前期:6月27日~8月2日
後期:8月4日~9月6日
既に早々から多くの方で賑わっているそうです。金曜の夜間開館(20時まで)なども狙い目ではないでしょうか。また一号館は後半に混雑が集中する傾向があります。まずは早めの観覧をおすすめします。

「画鬼・暁斎ーKYOSAI」展会場風景
9月6日まで開催されています。
「画鬼・暁斎ーKYOSAI 幕末明治のスター絵師と弟子コンドル」 三菱一号館美術館(@kyosai2015)
会期:6月27日(土)~9月6日(日)
*展示替えあり。前期:8月2日(日)まで/後期:8月4日(火)から
休館:月曜日。但し7月20と8月31日は開館。
時間:10:00~18:00。
*毎週金曜日と会期最終週の平日は20時まで。
*入館は閉館の30分前まで。
料金:大人1500円、高校・大学生1000円、小・中学生500円。
*ペアチケットあり:チケットぴあのみで販売。一般ペア2600円。
住所:千代田区丸の内2-6-2
交通:東京メトロ千代田線二重橋前駅1番出口から徒歩3分。JR東京駅丸の内南口・JR有楽町駅国際フォーラム口から徒歩5分。
注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
参加型web座談会「2015夏休みwebアートトーク」を開催します
2015年7月19日(日)朝10時より、PCやスマホで参加出来るweb座談会、「2015夏休みwebアートトーク」を開催します。
[参加型web展覧会座談会~2015夏休みwebでアートトーク 開催概要]
・日時:2015年7月19日(日) 10:00~11:30
開始時間の10分前から指定したwebサイトにログインしてください。
アクセス方法についてはお申込み後、メールにてご案内いたします。
・出演
青い日記帳のTak(たけ)さん、はろるど。
青い日記帳 http://bluediary2.jugem.jp/
はろるど http://blog.goo.ne.jp/harold1234
・トーク内容
第1部 2015年の夏休みお薦め展覧会
第2部 展覧会の楽しみ方について~練馬区立美術館 若林館長に聞く~
《ゲスト》 練馬区立美術館 館長 若林覚
・参加費:無料
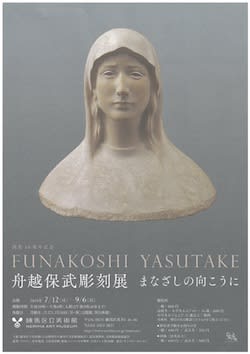
「舟越保武彫刻展 まなざしの向こうに」@練馬区立美術館
URL:http://www.neribun.or.jp/museum.html
会期:7月12日(日)~9月6日(日)
開始は7月19日の日曜日の朝10時です。まずはお馴染みの「青い日記帳」のTakさんと「はろるど」こと私が、この夏の都内近郊の展覧会についてご紹介した後、ゲストに練馬区立美術館の若林館長をお迎えし、展覧会の楽しみ方などについてお話いただきます。
[座談会の特徴]
・参加者の皆さんもチャットを通じて参加可能!
(自分の意見も述べられ、他の参加者の意見もわかります。)
・座談会の途中に皆さんの意見をアンケートで集約!
(みんなの意見がすぐにわかります。)
・終了後のアンケートにご協力いただいた方には展覧会の招待券などをプレゼント。
あくまでもWEBのイベントです。会場にお越しいただく必要はありません。PCやスマホを通して、ご自宅や好きな場所でご参加いただけます。
[ご参加にあたって]
・ライブでご参加ただけるwebイベントです。会場にお越しいただく必要はありません。
・ご自宅のパソコンなどからご視聴ください。
座談会ではご参加いたただいた方もチャットを通じてコメントを表明することが可能です。またリアルタイムでアンケートなども行います。双方向の参加型イベントです。
[注意事項]
・PC環境や通信環境によっては、ご覧いただけないこともあります。
・申込みいただいた方にPC環境や通信環境の「事前確認サイト」をご案内致しますので、実施日前に確認願います。
・タブレットやスマートフォンでもご覧にいただけますが、事前にアプリをインストール願います
・アプリのダウンロードサイトについては、お申込みいただいた方にご連絡致します。
受付は先着順です。下記の専用申込みフォームよりお申し込み下さい。もちろん一切の料金はかかりません。
[受付について]
・先着順にてご応募を受け付けております。定員に達し次第、受付終了となります。
・web座談会の参加方法などの詳細はメールにて追ってお知らせいたします。
・申込専用フォーム→https://admin.prius-pro.jp/m/win/form.php?f=1
ところでこのWEB上での座談会イベントですが、実は今から2年前の2013年にも一度開催したことがありました。
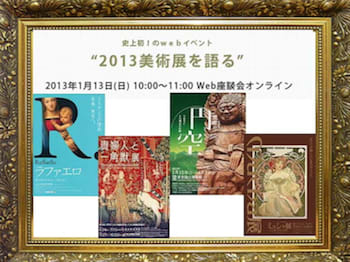
「WEBイベント 2013年美術展を語る」を開催しました(はろるど)
今回は練馬の若林館長をお迎えしてのパワーアップバージョンです。また山種美術館の山崎館長も一部、ご出演いただける予定です。時間も90分とやや拡大して、皆さんとやり取りしながらざっくばらんに進められればと思っています。
「やってみなはれの精神で運営 練馬区立美術館」(朝日新聞デジタル)
「練馬区立美術館館長・若林覚氏 経験+知識に資格で不足補う」(zakzak)
「ねりま人 バックナンバー 若林覚さん」(練馬区観光協会)
2015年7月19日(日)の朝10時から参加型web座談会「2015夏休みwebアートトーク」。お時間のある方、ご興味のある方のご参加をお待ちしております。
申込専用フォーム→https://admin.prius-pro.jp/m/win/form.php?f=1
[参加型web展覧会座談会~2015夏休みwebでアートトーク 開催概要]
・日時:2015年7月19日(日) 10:00~11:30
開始時間の10分前から指定したwebサイトにログインしてください。
アクセス方法についてはお申込み後、メールにてご案内いたします。
・出演
青い日記帳のTak(たけ)さん、はろるど。
青い日記帳 http://bluediary2.jugem.jp/
はろるど http://blog.goo.ne.jp/harold1234
・トーク内容
第1部 2015年の夏休みお薦め展覧会
第2部 展覧会の楽しみ方について~練馬区立美術館 若林館長に聞く~
《ゲスト》 練馬区立美術館 館長 若林覚
・参加費:無料
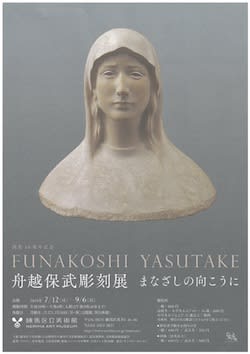
「舟越保武彫刻展 まなざしの向こうに」@練馬区立美術館
URL:http://www.neribun.or.jp/museum.html
会期:7月12日(日)~9月6日(日)
開始は7月19日の日曜日の朝10時です。まずはお馴染みの「青い日記帳」のTakさんと「はろるど」こと私が、この夏の都内近郊の展覧会についてご紹介した後、ゲストに練馬区立美術館の若林館長をお迎えし、展覧会の楽しみ方などについてお話いただきます。
[座談会の特徴]
・参加者の皆さんもチャットを通じて参加可能!
(自分の意見も述べられ、他の参加者の意見もわかります。)
・座談会の途中に皆さんの意見をアンケートで集約!
(みんなの意見がすぐにわかります。)
・終了後のアンケートにご協力いただいた方には展覧会の招待券などをプレゼント。
あくまでもWEBのイベントです。会場にお越しいただく必要はありません。PCやスマホを通して、ご自宅や好きな場所でご参加いただけます。
[ご参加にあたって]
・ライブでご参加ただけるwebイベントです。会場にお越しいただく必要はありません。
・ご自宅のパソコンなどからご視聴ください。
座談会ではご参加いたただいた方もチャットを通じてコメントを表明することが可能です。またリアルタイムでアンケートなども行います。双方向の参加型イベントです。
[注意事項]
・PC環境や通信環境によっては、ご覧いただけないこともあります。
・申込みいただいた方にPC環境や通信環境の「事前確認サイト」をご案内致しますので、実施日前に確認願います。
・タブレットやスマートフォンでもご覧にいただけますが、事前にアプリをインストール願います
・アプリのダウンロードサイトについては、お申込みいただいた方にご連絡致します。
受付は先着順です。下記の専用申込みフォームよりお申し込み下さい。もちろん一切の料金はかかりません。
[受付について]
・先着順にてご応募を受け付けております。定員に達し次第、受付終了となります。
・web座談会の参加方法などの詳細はメールにて追ってお知らせいたします。
・申込専用フォーム→https://admin.prius-pro.jp/m/win/form.php?f=1
ところでこのWEB上での座談会イベントですが、実は今から2年前の2013年にも一度開催したことがありました。
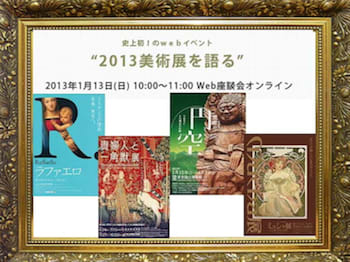
「WEBイベント 2013年美術展を語る」を開催しました(はろるど)
今回は練馬の若林館長をお迎えしてのパワーアップバージョンです。また山種美術館の山崎館長も一部、ご出演いただける予定です。時間も90分とやや拡大して、皆さんとやり取りしながらざっくばらんに進められればと思っています。
「やってみなはれの精神で運営 練馬区立美術館」(朝日新聞デジタル)
「練馬区立美術館館長・若林覚氏 経験+知識に資格で不足補う」(zakzak)
「ねりま人 バックナンバー 若林覚さん」(練馬区観光協会)
2015年7月19日(日)の朝10時から参加型web座談会「2015夏休みwebアートトーク」。お時間のある方、ご興味のある方のご参加をお待ちしております。
申込専用フォーム→https://admin.prius-pro.jp/m/win/form.php?f=1
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
「ウルトラ植物博覧会」 ポーラミュージアムアネックス
ポーラミュージアムアネックス
「ウルトラ植物博覧会 西畠清順と愉快な植物たち」
7/3-8/16

ポーラミュージアムアネックスで開催中の「ウルトラ植物博覧会 西畠清順と愉快な植物たち」を見てきました。
まさしく奇想天外、一瞬フェイクかと見間違えるほどに不思議な植物が銀座のスペースを妖しく彩っています。
世界各地、幻の植物を追い求めて旅しているのが西畠清順氏。プラントハンターと呼ばれているそうです。江戸時代から続く花と植木の卸問屋「花宇」の5代目でもあります。
その彼がまさしく世界中から採取してきた稀少植物がずらり。中には学名が定まっていないものまでありました。

また大きさも草のような小さなものから、天井近くまで枝をのばす樹木までと幅広い。全部で約50種類です。まるで鬱蒼としたジャングルに迷い込んだかのようでした。

ピンク色がかった赤い花に目を奪われました。和名で「砂漠のバラ」。科名では「チョウチクトウ」と呼ばれています。イエメンやサウジアラビアの砂漠に分布します。種はタンポポのような羽をもって飛ぶそうです。透明感のある花弁と言ったら美しいもの。砂漠の中で生きているとは思えないほど可憐に咲いています。

魚の鱗のような木肌が特徴的です。科名で「リュウゼツラン」、メキシコからアメリカに分布しています。同じユッカ属で保護対象であるジョシュアツリーに対して、このリュウゼツランはメキシコ政府が積極的に輸出を奨励しているとか。水やりは入りません。庭木の素材として人気があるそうです。

何ともグロテスクな実を付けていました。和名で「仏手柑」。つまりミカンです。原産はインド。中国では不老不死の沈果として珍重されています。まるで人の手のような実、観賞用として用いられるそうですが、食べることも出来ます。やはりミカンだけに甘酸っぱいのでしょうか。口にするのもやや憚れるような形です。驚きました。

またこうした大きな植物だけでなく、小さな草や実にも興味深いものがいくつもあります。その最たる例がこの実です。手のひらよりもずっと小さい。和名も強烈です。何と「ライオン殺し」。南アフリカに分布します。実に恐ろしい名前ですが、ライオンが実を踏んだ足から口で引き抜こうとすると、逆に深く口に突き刺さってくることに由来するそうです。しかもその後、発芽し、ライオンの肉を肥料として成長します。凄まじい破壊力です。その姿から想像もつきません。

ともかくこのように見たことも、名前も知らない稀少植物が目白押しです。また一点一点の植物について西畠氏がコメントを付けた解説の小冊子も面白いもの。「落ちたら死ぬ」やら「タイの変態植物育苗家」、また「酔っ払いの木」などの個性溢れるネーミングも注目に値します。

2012年からはそらの植物園という「ひとの心に植物を植える活動」(チラシより)をされているそうです。冊子に寄せた「開催にあたって伝えたい、大事なこと。」というメッセージからは、氏の植物に対する強い情熱を汲み取ることも出来ました。

人気の展示です。場内、多くの人で賑わっていました。撮影も可能です。

8月16日まで開催されています。
「ウルトラ植物博覧会 西畠清順と愉快な植物たち」 ポーラミュージアムアネックス(@POLA_ANNEX)
会期:7月3日(金)~8月16日(日)
休館:会期中無休
時間:11:00~20:00 *入場は閉館の30分前まで
住所:中央区銀座1-7-7 ポーラ銀座ビル3階
交通:東京メトロ有楽町線銀座1丁目駅7番出口よりすぐ。JR有楽町駅京橋口より徒歩5分。
「ウルトラ植物博覧会 西畠清順と愉快な植物たち」
7/3-8/16

ポーラミュージアムアネックスで開催中の「ウルトラ植物博覧会 西畠清順と愉快な植物たち」を見てきました。
まさしく奇想天外、一瞬フェイクかと見間違えるほどに不思議な植物が銀座のスペースを妖しく彩っています。
世界各地、幻の植物を追い求めて旅しているのが西畠清順氏。プラントハンターと呼ばれているそうです。江戸時代から続く花と植木の卸問屋「花宇」の5代目でもあります。
その彼がまさしく世界中から採取してきた稀少植物がずらり。中には学名が定まっていないものまでありました。

また大きさも草のような小さなものから、天井近くまで枝をのばす樹木までと幅広い。全部で約50種類です。まるで鬱蒼としたジャングルに迷い込んだかのようでした。

ピンク色がかった赤い花に目を奪われました。和名で「砂漠のバラ」。科名では「チョウチクトウ」と呼ばれています。イエメンやサウジアラビアの砂漠に分布します。種はタンポポのような羽をもって飛ぶそうです。透明感のある花弁と言ったら美しいもの。砂漠の中で生きているとは思えないほど可憐に咲いています。

魚の鱗のような木肌が特徴的です。科名で「リュウゼツラン」、メキシコからアメリカに分布しています。同じユッカ属で保護対象であるジョシュアツリーに対して、このリュウゼツランはメキシコ政府が積極的に輸出を奨励しているとか。水やりは入りません。庭木の素材として人気があるそうです。

何ともグロテスクな実を付けていました。和名で「仏手柑」。つまりミカンです。原産はインド。中国では不老不死の沈果として珍重されています。まるで人の手のような実、観賞用として用いられるそうですが、食べることも出来ます。やはりミカンだけに甘酸っぱいのでしょうか。口にするのもやや憚れるような形です。驚きました。

またこうした大きな植物だけでなく、小さな草や実にも興味深いものがいくつもあります。その最たる例がこの実です。手のひらよりもずっと小さい。和名も強烈です。何と「ライオン殺し」。南アフリカに分布します。実に恐ろしい名前ですが、ライオンが実を踏んだ足から口で引き抜こうとすると、逆に深く口に突き刺さってくることに由来するそうです。しかもその後、発芽し、ライオンの肉を肥料として成長します。凄まじい破壊力です。その姿から想像もつきません。

ともかくこのように見たことも、名前も知らない稀少植物が目白押しです。また一点一点の植物について西畠氏がコメントを付けた解説の小冊子も面白いもの。「落ちたら死ぬ」やら「タイの変態植物育苗家」、また「酔っ払いの木」などの個性溢れるネーミングも注目に値します。

2012年からはそらの植物園という「ひとの心に植物を植える活動」(チラシより)をされているそうです。冊子に寄せた「開催にあたって伝えたい、大事なこと。」というメッセージからは、氏の植物に対する強い情熱を汲み取ることも出来ました。

人気の展示です。場内、多くの人で賑わっていました。撮影も可能です。

8月16日まで開催されています。
「ウルトラ植物博覧会 西畠清順と愉快な植物たち」 ポーラミュージアムアネックス(@POLA_ANNEX)
会期:7月3日(金)~8月16日(日)
休館:会期中無休
時間:11:00~20:00 *入場は閉館の30分前まで
住所:中央区銀座1-7-7 ポーラ銀座ビル3階
交通:東京メトロ有楽町線銀座1丁目駅7番出口よりすぐ。JR有楽町駅京橋口より徒歩5分。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
「前田青邨と日本美術院ー大観・古径・御舟」 山種美術館
山種美術館
「前田青邨と日本美術院ー大観・古径・御舟」
6/27-8/23
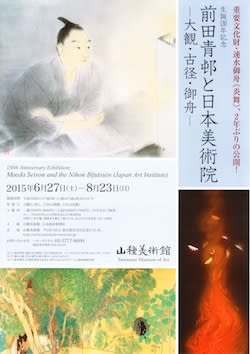
山種美術館で開催中の「前田青邨と日本美術院ー大観・古径・御舟」のプレスプレビューに参加してきました。
今年、生誕130年を迎えた日本画家、前田青邨(1885~1977)。山種コレクションの青邨作品が全て公開されるのは、1994年以来、21年ぶりのことです。
本展では青邨を中心に、日本美術院の先人である大観、春草、観山、そして同時代の古径、靫彦、御舟、さらには院展の後進の画家までを紹介します。
[前田青邨と日本美術院 展示構成]
第1章:日本美術院の開拓者たち
第2章:青邨と日本美術院の第二世代ー古径・靫彦とともに
第3章:紅児会の仲間と院展の後進たち
出品は全58点。うち青邨が13点です。途中の展示替えはありません。

左:橋本雅邦「日本武尊像」 明治26年頃 絹本・彩色
冒頭は青邨も属した日本美術院の先人たちです。堂々たるは「日本武尊像」。描いたのは橋本雅邦です。青邨よりも50歳年上の画家、生まれは江戸時代の天保年間です。元々は狩野派に学びました。確かに本作でも岩や木に狩野派風の表現が見られるのではないでしょうか。

横山大観「燕山の巻」 明治43年 紙本・墨画
大観はどうでしょうか。それこそ雅邦や天心の薫陶を受けた日本美術院の一期生。長大な「燕山の巻」が目を引きました。大観自身が中国へ行き、初めて描いたという水墨画巻。かの大作「生々流転」の先駆けとしても知られていますが、ここには雪舟に対する意識を汲み取ることも出来ます。軽妙な水墨の筆致が中国北方の雄大な景色を情緒的に表しています。

下:梶田半古「赤いショール(口絵木版)」 明治30年代 多色刷木版
青邨の師が梶田半古です。「赤いショール」、小ぶりの木版の作品ですが、そもそも半古は挿絵画家として人気を集めていました。ゆえに多くの木版が世に出回ったそうです。

下村観山「老松白藤」 大正10年 紙本金地・彩色
青邨が深く尊敬していたのが下村観山でした。やはり目立つのが「老松白藤」、6曲1双の金地の屏風です。明治神宮の命によって伏見宮家に奉献するために制作した作品、琳派を思わせる面もありますが、構図自体は等伯や永徳らの桃山の大障壁画を踏襲しています。しかしながら藤の精緻な描写や蔓の表現などは応挙風でもあります。つまり円山四条派と桃山の折衷のスタイルです。ちなみに画面には一匹の熊蜂が飛んでいます。巨大な松からすればあまりにも小さい。写真では分かりません。是非会場で確かめて下さい。

下村観山「不動明王」 明治37年頃 絹本・彩色
観山では「不動明王」にも目が留まりました。雲に乗って飛来した不動明王、ともかく体つきに注目です。何やら奇妙なほどに筋肉は隆々、まるでギリシャ彫刻のようではありませんか。西洋絵画の影響を指摘されますが、実際にも観山はこの作品を英国留学時に描きました。左下にはアルファベットのサインもあります。またニューヨークタイムスにレビューが掲載されたことから、アメリカの展覧会に出品されたとも考えられているそうです。
ちなみに青邨は観山の死に際して、古径とともに下村邸に参じては、観山のデスマスクを制作しました。その深い悲しみは想像に難くありません。
さて主役の青邨です。安田靫彦は青邨を「色彩家」、「類のない達筆」、「人を愉快にさせること無類」と評しています。確かに色彩は非常に華やかです。それでいておおらかとも呼べる筆致が明朗な画面を作り上げてもいます。

前田青邨「大物浦」 昭和43年 紙本・彩色
色の魅力、まずは「大物浦」でしょう。この深く、またニュアンスに富んだ青み。美しい。主題は源平の争乱です。頼朝に追われた義経が摂津辺りを航行中、大きな嵐に襲われたというエピソード。船上の武士たちは波に飲まれまいと必死にしがみついています。甲冑は思いがけないほど細かく描かれていました。そして折重なる大波は力強い。波や屋根における三角形が目立ちはしないでしょうか。どこか面的な構成が目につきます。

前田青邨「腑分」 昭和45年 紙本・彩色
「腑分」には驚きました。時は宝暦4年、山脇東洋が日本で初めて解剖を行った様子を描いたものです。いわゆる白衣なのでしょうか。うっすら灰色を帯びた衣に身を纏った人々たち。画面右下に裸の女性の姿が見えます。その上の半袖の男が執刀者です。皆鋭い目つき、ふと見やると手を前にして祈りを捧げている者もいます。
このように青邨は歴史画を得意としていました。いわゆる有職故実や古典を熱心に研究します。また実地の取材にも事欠きません。例えば先の「腑分」では解剖学者の協力を得て、わざわざ大学病院にまで手術を見学しに行ったそうです。また「異装行列の信長」では、信長の穿いた豹や虎の袴を描くため、実際の動物園へ出かけては観察、スケッチをしたこともありました。
色彩に関して目立つのはたらし込みでしょうか。いずれも瑞々しい。色は時に輪郭線を超えて広がっています。

小林古径「闘草」 明治40年 絹本・彩色
古径は全部で6点ほど出ていました。うちやはり見入るのは「闘草」です。既によく知られた名品ですが、人物の輪郭線を朱色で描いていることに気がつくでしょうか。ここで古径は仏画の描法を踏襲しています。また近年、修復がなされました。それゆえか以前よりもより明るく見えるかもしれません。

左:奥村土牛「犢」 昭和59年 紙本・彩色
同時代の院展では、奥村土牛、小茂田青樹、速水御舟らの画家が取り上げられています。それに院展参加前の青邨に影響を与えた紅児会の画家たちも重要です。安田靫彦を筆頭に、今村紫紅、御舟、さらに古径と青邨らを加えたグループが結成されます。彼らは親しく交じながらも、切磋琢磨しては制作に励みました。

右:今村紫紅「大原の奥」 明治42年 絹本・彩色
紫紅の「大原の奥」は紅児会への出品作です。清盛の娘である徳子が晩年、出家して建礼門院と名乗って余生を過ごしたことに因んだ一作、舞台は京都大原の寂光院です。薄墨の衣をまとい、全てを達観したかのような表情を見せる建礼門院の姿。背景はやや装飾的とも言えるのではないでしょうか。何とももの悲し気な作品でもあります。

守屋多々志「平家厳島納経」 昭和53年 紙本・彩色
青邨の後進の画家にも着目しています。名は守屋多々志、月岡栄貴、平山郁夫、小山硬らです。中でも守屋の「平家厳島納経」が目立っていました。清盛一門が厳島神社に平家納経を奉納した当日の様子を表した屏風、武士らが船で大鳥居をくぐっては進み行きます。制作の前年に亡くなった師の青邨を悼んで描いた作品だそうです。
ラストは「炎舞」です。山種コレクションでも最も人気のあると言って良い傑作、思いの外に久々のお出ましです。2年ぶりに公開されています。

速水御舟「炎舞」 大正14年 絹本・彩色 重要文化財
深い闇を背景に浮かぶ炎。蛾はまるで煙に沿って舞うように群がっています。御舟は本作にあたって毎晩のように焚き火し、蛾を熱心に観察しました。ゆえに蛾などは写実的です。ただしそれだけではありません。炎は仏画を連想させる面もあります。さも彼岸の世界をも覗き込んだような妖気すら漂っているのです。
ぐっと抑えられた照明の効果もあってか、ともかく炎の赤みが際立っていますが、実は照明をLEDに交換してから初めての公開だそうです。監修の山下先生によれば「より赤みが増した。」と評する今回の展示。言葉を変えれば「凄みが増した。」とも表せないでしょうか。思わず炎に吸い寄せられてしまうかのような迫力すらあります。身震いしてしまいました。

「前田青邨と日本美術院ー大観・古径・御舟」会場風景
青邨から院展の流れを前史を踏まえて追える展覧会です。相互の影響関係にも言及しています。まさに青邨のメモリアルイヤーならではの企画だと言えそうです。
8月23日まで開催されています。
「前田青邨と日本美術院ー大観・古径・御舟」 山種美術館(@yamatanemuseum)
会期:6月27日(土)~8月23日(日)
休館:月曜日
時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。
料金:一般1000(800)円、大・高生800(700)円、中学生以下無料。
*( )内は20名以上の団体料金。
*きもの・ゆかた割引:きもの・ゆかたで来館すると団体割引料金を適用。
住所:渋谷区広尾3-12-36
交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。
注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。作品は全て山種美術館蔵。
「前田青邨と日本美術院ー大観・古径・御舟」
6/27-8/23
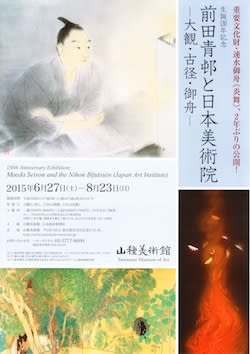
山種美術館で開催中の「前田青邨と日本美術院ー大観・古径・御舟」のプレスプレビューに参加してきました。
今年、生誕130年を迎えた日本画家、前田青邨(1885~1977)。山種コレクションの青邨作品が全て公開されるのは、1994年以来、21年ぶりのことです。
本展では青邨を中心に、日本美術院の先人である大観、春草、観山、そして同時代の古径、靫彦、御舟、さらには院展の後進の画家までを紹介します。
[前田青邨と日本美術院 展示構成]
第1章:日本美術院の開拓者たち
第2章:青邨と日本美術院の第二世代ー古径・靫彦とともに
第3章:紅児会の仲間と院展の後進たち
出品は全58点。うち青邨が13点です。途中の展示替えはありません。

左:橋本雅邦「日本武尊像」 明治26年頃 絹本・彩色
冒頭は青邨も属した日本美術院の先人たちです。堂々たるは「日本武尊像」。描いたのは橋本雅邦です。青邨よりも50歳年上の画家、生まれは江戸時代の天保年間です。元々は狩野派に学びました。確かに本作でも岩や木に狩野派風の表現が見られるのではないでしょうか。

横山大観「燕山の巻」 明治43年 紙本・墨画
大観はどうでしょうか。それこそ雅邦や天心の薫陶を受けた日本美術院の一期生。長大な「燕山の巻」が目を引きました。大観自身が中国へ行き、初めて描いたという水墨画巻。かの大作「生々流転」の先駆けとしても知られていますが、ここには雪舟に対する意識を汲み取ることも出来ます。軽妙な水墨の筆致が中国北方の雄大な景色を情緒的に表しています。

下:梶田半古「赤いショール(口絵木版)」 明治30年代 多色刷木版
青邨の師が梶田半古です。「赤いショール」、小ぶりの木版の作品ですが、そもそも半古は挿絵画家として人気を集めていました。ゆえに多くの木版が世に出回ったそうです。

下村観山「老松白藤」 大正10年 紙本金地・彩色
青邨が深く尊敬していたのが下村観山でした。やはり目立つのが「老松白藤」、6曲1双の金地の屏風です。明治神宮の命によって伏見宮家に奉献するために制作した作品、琳派を思わせる面もありますが、構図自体は等伯や永徳らの桃山の大障壁画を踏襲しています。しかしながら藤の精緻な描写や蔓の表現などは応挙風でもあります。つまり円山四条派と桃山の折衷のスタイルです。ちなみに画面には一匹の熊蜂が飛んでいます。巨大な松からすればあまりにも小さい。写真では分かりません。是非会場で確かめて下さい。

下村観山「不動明王」 明治37年頃 絹本・彩色
観山では「不動明王」にも目が留まりました。雲に乗って飛来した不動明王、ともかく体つきに注目です。何やら奇妙なほどに筋肉は隆々、まるでギリシャ彫刻のようではありませんか。西洋絵画の影響を指摘されますが、実際にも観山はこの作品を英国留学時に描きました。左下にはアルファベットのサインもあります。またニューヨークタイムスにレビューが掲載されたことから、アメリカの展覧会に出品されたとも考えられているそうです。
ちなみに青邨は観山の死に際して、古径とともに下村邸に参じては、観山のデスマスクを制作しました。その深い悲しみは想像に難くありません。
さて主役の青邨です。安田靫彦は青邨を「色彩家」、「類のない達筆」、「人を愉快にさせること無類」と評しています。確かに色彩は非常に華やかです。それでいておおらかとも呼べる筆致が明朗な画面を作り上げてもいます。

前田青邨「大物浦」 昭和43年 紙本・彩色
色の魅力、まずは「大物浦」でしょう。この深く、またニュアンスに富んだ青み。美しい。主題は源平の争乱です。頼朝に追われた義経が摂津辺りを航行中、大きな嵐に襲われたというエピソード。船上の武士たちは波に飲まれまいと必死にしがみついています。甲冑は思いがけないほど細かく描かれていました。そして折重なる大波は力強い。波や屋根における三角形が目立ちはしないでしょうか。どこか面的な構成が目につきます。

前田青邨「腑分」 昭和45年 紙本・彩色
「腑分」には驚きました。時は宝暦4年、山脇東洋が日本で初めて解剖を行った様子を描いたものです。いわゆる白衣なのでしょうか。うっすら灰色を帯びた衣に身を纏った人々たち。画面右下に裸の女性の姿が見えます。その上の半袖の男が執刀者です。皆鋭い目つき、ふと見やると手を前にして祈りを捧げている者もいます。
このように青邨は歴史画を得意としていました。いわゆる有職故実や古典を熱心に研究します。また実地の取材にも事欠きません。例えば先の「腑分」では解剖学者の協力を得て、わざわざ大学病院にまで手術を見学しに行ったそうです。また「異装行列の信長」では、信長の穿いた豹や虎の袴を描くため、実際の動物園へ出かけては観察、スケッチをしたこともありました。
色彩に関して目立つのはたらし込みでしょうか。いずれも瑞々しい。色は時に輪郭線を超えて広がっています。

小林古径「闘草」 明治40年 絹本・彩色
古径は全部で6点ほど出ていました。うちやはり見入るのは「闘草」です。既によく知られた名品ですが、人物の輪郭線を朱色で描いていることに気がつくでしょうか。ここで古径は仏画の描法を踏襲しています。また近年、修復がなされました。それゆえか以前よりもより明るく見えるかもしれません。

左:奥村土牛「犢」 昭和59年 紙本・彩色
同時代の院展では、奥村土牛、小茂田青樹、速水御舟らの画家が取り上げられています。それに院展参加前の青邨に影響を与えた紅児会の画家たちも重要です。安田靫彦を筆頭に、今村紫紅、御舟、さらに古径と青邨らを加えたグループが結成されます。彼らは親しく交じながらも、切磋琢磨しては制作に励みました。

右:今村紫紅「大原の奥」 明治42年 絹本・彩色
紫紅の「大原の奥」は紅児会への出品作です。清盛の娘である徳子が晩年、出家して建礼門院と名乗って余生を過ごしたことに因んだ一作、舞台は京都大原の寂光院です。薄墨の衣をまとい、全てを達観したかのような表情を見せる建礼門院の姿。背景はやや装飾的とも言えるのではないでしょうか。何とももの悲し気な作品でもあります。

守屋多々志「平家厳島納経」 昭和53年 紙本・彩色
青邨の後進の画家にも着目しています。名は守屋多々志、月岡栄貴、平山郁夫、小山硬らです。中でも守屋の「平家厳島納経」が目立っていました。清盛一門が厳島神社に平家納経を奉納した当日の様子を表した屏風、武士らが船で大鳥居をくぐっては進み行きます。制作の前年に亡くなった師の青邨を悼んで描いた作品だそうです。
ラストは「炎舞」です。山種コレクションでも最も人気のあると言って良い傑作、思いの外に久々のお出ましです。2年ぶりに公開されています。

速水御舟「炎舞」 大正14年 絹本・彩色 重要文化財
深い闇を背景に浮かぶ炎。蛾はまるで煙に沿って舞うように群がっています。御舟は本作にあたって毎晩のように焚き火し、蛾を熱心に観察しました。ゆえに蛾などは写実的です。ただしそれだけではありません。炎は仏画を連想させる面もあります。さも彼岸の世界をも覗き込んだような妖気すら漂っているのです。
ぐっと抑えられた照明の効果もあってか、ともかく炎の赤みが際立っていますが、実は照明をLEDに交換してから初めての公開だそうです。監修の山下先生によれば「より赤みが増した。」と評する今回の展示。言葉を変えれば「凄みが増した。」とも表せないでしょうか。思わず炎に吸い寄せられてしまうかのような迫力すらあります。身震いしてしまいました。

「前田青邨と日本美術院ー大観・古径・御舟」会場風景
青邨から院展の流れを前史を踏まえて追える展覧会です。相互の影響関係にも言及しています。まさに青邨のメモリアルイヤーならではの企画だと言えそうです。
8月23日まで開催されています。
「前田青邨と日本美術院ー大観・古径・御舟」 山種美術館(@yamatanemuseum)
会期:6月27日(土)~8月23日(日)
休館:月曜日
時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。
料金:一般1000(800)円、大・高生800(700)円、中学生以下無料。
*( )内は20名以上の団体料金。
*きもの・ゆかた割引:きもの・ゆかたで来館すると団体割引料金を適用。
住所:渋谷区広尾3-12-36
交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。
注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。作品は全て山種美術館蔵。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
シャルフベックの「お誕生日会」が開催されます
東京藝術大学大学美術館で開催中の「ヘレン・シャルフベックー魂のまなざし」展。知られざるフィンランドの「国民画家」、シャルフベックの画業を日本で初めて紹介。全84点です。初期のレアリスムから晩年の抽象を伴った表現までを追いかけています。

「ヘレン・シャルフベックー魂のまなざし」
東京藝術大学大学美術館
URL:http://helene-fin.exhn.jp/
会期:5月2日(火)~7月26日(日)
そのシャルフベック、生まれが1862年の7月10日だったそうです。つまり誕生日に因んだイベントです。7月11日(土)に「シャルフベックのお誕生会」と題したイベントが行われます。
[シャルフベックのお誕生会 開催概要]
・日時:2015年7月11日(土) *13時より大浦食堂にて整理券配布開始
・スケジュール
14:00~ トークセッション「フィンランドの風土と人々を語るーフィンランドが生んだシャルフベック」
登壇:ウッラ・キンヌネン氏/佐藤直樹氏/日沼禎子氏
15:20頃~ ケーキ登場
「パティシェ イナムラ ショウゾウ」のシェフ稲村省三氏特製バースデーケーキ
・定員:先着80名。(*本展覧会の観覧券が必要。半券でも可。)
・会場:東京藝術大学大学美術館1階 大浦食堂

「お針子(働く女性)」 1905年 油彩・カンヴァス
フィンランド国立アテネウム美術館
場所は同美術館内の大浦食堂。7月11日の土曜のお昼のイベントです。まず14時から本展を企画された芸大の佐藤直樹先生、また女子美の日沼先生のほか、フィンランド文化担当マネージャーのウッラ氏を交えたトークセッションが行われます。その後、谷中の超有名店「パティシェ イナムラ ショウゾウ」によるバースデーケーキが振る舞われます。
[シャルフベックのお誕生会 内容]
7月10日がシャルフベックの誕生日であることを記念し、7月11日(土)にバースデーパーティーを開催する運びとなりました。
当日は、「フィンランドの風土と人々を語るーフィンランドが生んだシャルフベック」と題し、ウッラ・キンヌネン氏(フィンランドセンター 文化・コミュニケーションマネージャー)×佐藤直樹氏(東京藝術大学准教授)×日沼禎子氏(女子美術大学准教授)による、 フィンランドとアートにまつわるトークセッションを開催するとともに、セッション後は、「パティシェ イナムラ ショウゾウ」のシェフ稲村省三氏がつくる特製バースデーケーキをご参加の皆様にお召し上がりいただき、シャルフベックの誕生日をお祝いいたします。
イベント自体は無料です。展覧会の半券があれば誰でも参加出来ます。なお定員は80名です。トークに先立つ13時より大浦食堂にて整理券が配布されます。おそらくすぐに配布終了となることが予想されます。

「自画像、光と影」 1945年 油彩・カンヴァス
ユレンベリ美術館
それにしてもシャルフベック展、私も先日見てきましたが、画風の変遷は興味深く、画家の置かれた境遇、さらには自らの心情を写したかのような晩年の自画像などには強く心打たれたものでした。
「ヘレン・シャルフベック展」@東京藝術大学大学美術館(はろるど)
おそらく日本では最初で最後のシャルフベック回顧展ではないかと思います。お誕生会もケーキのお披露目だけではなく、硬派なトーク付き。当日は会期中、佐藤先生のお話を聞く最後のチャンス(東京展において)でもあります。
7月11日(土)に行われる「シャルフベックのお誕生会」。気がつけば展示も会期の半分を過ぎました。興味のある方は参加しては如何でしょうか。
「ヘレン・シャルフベック展」は7月26日まで開催されています。
「ヘレン・シャルフベックー魂のまなざし」 東京藝術大学大学美術館
会期:5月2日(火)~7月26日(日)
休館:月曜日。但し7/20(月)は開館。翌21日(火)は休館。
時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。
料金:一般1500(1200)円、高校・大学生1000(700)円、中学生以下無料。
*( )内は20名以上の団体料金。
住所:台東区上野公園12-8
交通:JR線上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ千代田線根津駅より徒歩10分。京成上野駅、東京メトロ日比谷線・銀座線上野駅より徒歩15分。

「ヘレン・シャルフベックー魂のまなざし」
東京藝術大学大学美術館
URL:http://helene-fin.exhn.jp/
会期:5月2日(火)~7月26日(日)
そのシャルフベック、生まれが1862年の7月10日だったそうです。つまり誕生日に因んだイベントです。7月11日(土)に「シャルフベックのお誕生会」と題したイベントが行われます。
[シャルフベックのお誕生会 開催概要]
・日時:2015年7月11日(土) *13時より大浦食堂にて整理券配布開始
・スケジュール
14:00~ トークセッション「フィンランドの風土と人々を語るーフィンランドが生んだシャルフベック」
登壇:ウッラ・キンヌネン氏/佐藤直樹氏/日沼禎子氏
15:20頃~ ケーキ登場
「パティシェ イナムラ ショウゾウ」のシェフ稲村省三氏特製バースデーケーキ
・定員:先着80名。(*本展覧会の観覧券が必要。半券でも可。)
・会場:東京藝術大学大学美術館1階 大浦食堂

「お針子(働く女性)」 1905年 油彩・カンヴァス
フィンランド国立アテネウム美術館
場所は同美術館内の大浦食堂。7月11日の土曜のお昼のイベントです。まず14時から本展を企画された芸大の佐藤直樹先生、また女子美の日沼先生のほか、フィンランド文化担当マネージャーのウッラ氏を交えたトークセッションが行われます。その後、谷中の超有名店「パティシェ イナムラ ショウゾウ」によるバースデーケーキが振る舞われます。
[シャルフベックのお誕生会 内容]
7月10日がシャルフベックの誕生日であることを記念し、7月11日(土)にバースデーパーティーを開催する運びとなりました。
当日は、「フィンランドの風土と人々を語るーフィンランドが生んだシャルフベック」と題し、ウッラ・キンヌネン氏(フィンランドセンター 文化・コミュニケーションマネージャー)×佐藤直樹氏(東京藝術大学准教授)×日沼禎子氏(女子美術大学准教授)による、 フィンランドとアートにまつわるトークセッションを開催するとともに、セッション後は、「パティシェ イナムラ ショウゾウ」のシェフ稲村省三氏がつくる特製バースデーケーキをご参加の皆様にお召し上がりいただき、シャルフベックの誕生日をお祝いいたします。
イベント自体は無料です。展覧会の半券があれば誰でも参加出来ます。なお定員は80名です。トークに先立つ13時より大浦食堂にて整理券が配布されます。おそらくすぐに配布終了となることが予想されます。

「自画像、光と影」 1945年 油彩・カンヴァス
ユレンベリ美術館
それにしてもシャルフベック展、私も先日見てきましたが、画風の変遷は興味深く、画家の置かれた境遇、さらには自らの心情を写したかのような晩年の自画像などには強く心打たれたものでした。
「ヘレン・シャルフベック展」@東京藝術大学大学美術館(はろるど)
おそらく日本では最初で最後のシャルフベック回顧展ではないかと思います。お誕生会もケーキのお披露目だけではなく、硬派なトーク付き。当日は会期中、佐藤先生のお話を聞く最後のチャンス(東京展において)でもあります。
7月11日(土)に行われる「シャルフベックのお誕生会」。気がつけば展示も会期の半分を過ぎました。興味のある方は参加しては如何でしょうか。
「ヘレン・シャルフベック展」は7月26日まで開催されています。
「ヘレン・シャルフベックー魂のまなざし」 東京藝術大学大学美術館
会期:5月2日(火)~7月26日(日)
休館:月曜日。但し7/20(月)は開館。翌21日(火)は休館。
時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。
料金:一般1500(1200)円、高校・大学生1000(700)円、中学生以下無料。
*( )内は20名以上の団体料金。
住所:台東区上野公園12-8
交通:JR線上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ千代田線根津駅より徒歩10分。京成上野駅、東京メトロ日比谷線・銀座線上野駅より徒歩15分。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
「フィラデルフィア美術館浮世絵名品展 春信一番!写楽二番!」 三井記念美術館
三井記念美術館
「フィラデルフィア美術館浮世絵名品展 春信一番!写楽二番!」
6/20-8/16

三井記念美術館で開催中の「フィラデルフィア美術館浮世絵名品展 春信一番!写楽二番!」を見てきました。
フィラデルフィア美術館の浮世絵コレクションが日本でまとめて公開されるのは初めてのことだそうです。
アメリカはペンシルベニア州のフィラデルフィア美術館。創立は1877年です。既に130年以上もの歴史を誇ります。コレクションは膨大です。洋の東西を問わず、古代から現代美術までを網羅しています。その数、約30万点です。うち浮世絵を4000点ほど所蔵しています。
今回の開催の切っ掛けは、昨年、同美術館で行われた浮世絵の調査でした。その成果披露の機会ということなのでしょう。「選りすぐり」(チラシより)の150点が紹介されています。(展示替えあり。)
さてフィラデルフィア美術館浮世絵名品展、展示にはいくつか特徴があります。

二代鳥居清倍「今やうやくしゃふう」 寛保(1741~44)期 フィラデルフィア美術館
展示期間:7月22日~8月16日
まずは浮世絵の通史をほぼ俯瞰出来ることです。初期の鳥居派や奥村政信に始まり、春信、勝川春章へと続きます。もちろん人気の鳥居清長、歌麿、写楽も登場します。さらには北斎、広重も網羅しつつ、ラストにはともすると馴染みのない上方の浮世絵師までを視野に入れているのです。
中でもタイトルにもあるように、春信と写楽が極めて充実しています。春信は全30点です。一度の展示替えを挟むため、現会期(前期)では約15点ほどが出ています。
写楽の大首絵は10点です。こちらも展示替えのため、前後期でほぼ5点ずつ並んでいました。

鈴木春信「やつし芦葉達磨」 明和2~4年(1765~67)頃 フィラデルフィア美術館
展示期間:全期間
春信好きにはたまらないラインアップではないでしょうか。例えば「やつし芦葉達磨」です。何やら川面の上に浮いているような女性の立ち姿。風がやや強く吹いているのかもしれません。左手で衣を支えています。紅色、いや桃色の彩色も美しい。足元には一葉の芦が広がっています。そして女性はこの芦に乗っているのです。もちろん実際にはあり得ませんが、何でも元は中国の高僧の伝記によるとか。それをやつし絵、つまり見立て描いています。
総じて発色が良い作品が多いのも特徴かもしれません。写楽です。有名な「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」も素晴らしいもの。背景となる雲母の煌めきも美しく、状態は見るからに上々です。何度も目にする作品ではありますが、前にぐいと手を出しては見得を切る江戸兵衛の迫力もより増しているように見えました。
写楽の展示室も効果的です。と言うのも写楽作は一揃えで展示室6、つまり同館で最も狭いスペースに集められていますが、そこのガラスケースはいずれも薄く、作品を目と鼻の先で味わえるのです。もちろん狭いゆえに多少混み合う場合もありますが、これほど状態の良い浮世絵を間近で見られる機会もなかなかありません。

初代喜多川歌麿「歌撰恋之部 稀ニ逢恋」 寛政5~6年(1793~94)頃 フィラデルフィア美術館
展示期間:6月20日~7月20日
大首絵といえば歌麿の「歌撰恋之部 稀ニ逢恋」も絶品でした。町家の女性をモチーフにした大首絵シリーズの一枚。同連作の中では一番若い女性が描かれています。うっすらと紅色がかった雲母は瑞々しく、ツヤのある髪の毛はまだ濡れているかのような質感をたたえています。袖口から垣間見える小さな手先は何とも可憐でした。
清長の「菖蒲の池」にも魅せられました。いわゆる屋外の群像美人画、大判2枚続のワイド画面です。菖蒲の花を愛でる女性たちが描かれていますが、得意のすらりとした7頭身、8頭身のプロポーションも流麗極まりないもの。キセルを加えたり、花に触ったりと、思い思いにポーズをとっては花見を楽しんでいます。

鳥居清長「吉原の花見」 天明5年(1785) フィラデルフィア美術館
展示期間:7月22日~8月16日
なお後期にはさらに1枚増えた3枚続の「吉原の花見」が出品されるそうです。そちらもまた目を引くのではないでしょうか。
改めて展示替えの情報です。一部作品を除き、会期中に一度、作品が入れ替わります。
フィラデルフィア美術館浮世絵名品展出品目録(PDF)
前期:6月20日~7月20日
後期:7月22日~8月16日
相当数の入れ替えです。ほぼ前後期ほ2つで1つの展覧会と捉えて差し支えありません。なお後期の観覧にはリピーター割が有用です。会期中、一般券ないしは学生券を提示すると、2度目は団体料金で入場出来ます。
東京駅周辺の美術館にて「七夕フェア」が開催されています(はろるど)
「七夕フェア」のフェア内容(三井記念美術館)
また以前、拙ブログでもご紹介しましたが、現在、同館では期間限定で「七夕フェア」を開催しています。うち特にお得なのは「カップル割」です。7月7日までにペアで入場すると1名分の料金が無料になります。
[フィラデルフィア美術館浮世絵名品展 巡回予定]
静岡市美術館:8月23日(日)~9月27日(日)
あべのハルカス美術館:10月10日(土)~12月6日(日)
浮世絵展は展示室4以降での展開でした。順路に先立つ同館自慢の立体展示室では「三井記念美術館所蔵の工芸品ー夏に寄せて」を開催中。江戸後期から昭和へ至る蒔絵やタバコ入れ、それに自在置物などを紹介しています。
中でも安藤緑山の「染象牙果菜置物」は要注目ではないでしょうか。昨年の「超絶技巧!明治工芸の粋」でも驚きをもって迎えられた緑山の置物。柿や蜜柑がまさしく本物と見間違えるほどに精巧に作られています。改めて目を奪われました。

葛飾北斎「富嶽三十六景 凱風快晴」 天保元~3年(1830~32)頃 フィラデルフィア美術館
展示期間:全期間
会場内、食い入るように一点一点の作品を見ている方が多いのが印象に残りました。まだ余裕がありましたが、ひょっとすると後半にかけて混雑してくるやもしれません。
8月16日まで開催されています。
「特別展 錦絵誕生250年 フィラデルフィア美術館浮世絵名品展 春信一番!写楽二番!」 三井記念美術館
会期:6月20日(土)~8月16日(日)
休館:月曜日、7月21日(火)。但し7/20(月・祝)は休館。
時間:10:00~17:00 *入館は閉館の30分前まで。
料金:一般1300(1100)円、大学・高校生800(700)円、中学生以下無料。
*( )内は20名以上の団体料金。
*70歳以上は1000円。
*リピーター割引:会期中、一般券、学生券の半券を提示すると、2回目以降は団体料金を適用。
*割引引換券
場所:中央区日本橋室町2-1-1 三井本館7階
交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線三越前駅A7出口より徒歩1分。JR線新日本橋駅1番出口より徒歩5分。
「フィラデルフィア美術館浮世絵名品展 春信一番!写楽二番!」
6/20-8/16

三井記念美術館で開催中の「フィラデルフィア美術館浮世絵名品展 春信一番!写楽二番!」を見てきました。
フィラデルフィア美術館の浮世絵コレクションが日本でまとめて公開されるのは初めてのことだそうです。
アメリカはペンシルベニア州のフィラデルフィア美術館。創立は1877年です。既に130年以上もの歴史を誇ります。コレクションは膨大です。洋の東西を問わず、古代から現代美術までを網羅しています。その数、約30万点です。うち浮世絵を4000点ほど所蔵しています。
今回の開催の切っ掛けは、昨年、同美術館で行われた浮世絵の調査でした。その成果披露の機会ということなのでしょう。「選りすぐり」(チラシより)の150点が紹介されています。(展示替えあり。)
さてフィラデルフィア美術館浮世絵名品展、展示にはいくつか特徴があります。

二代鳥居清倍「今やうやくしゃふう」 寛保(1741~44)期 フィラデルフィア美術館
展示期間:7月22日~8月16日
まずは浮世絵の通史をほぼ俯瞰出来ることです。初期の鳥居派や奥村政信に始まり、春信、勝川春章へと続きます。もちろん人気の鳥居清長、歌麿、写楽も登場します。さらには北斎、広重も網羅しつつ、ラストにはともすると馴染みのない上方の浮世絵師までを視野に入れているのです。
中でもタイトルにもあるように、春信と写楽が極めて充実しています。春信は全30点です。一度の展示替えを挟むため、現会期(前期)では約15点ほどが出ています。
写楽の大首絵は10点です。こちらも展示替えのため、前後期でほぼ5点ずつ並んでいました。

鈴木春信「やつし芦葉達磨」 明和2~4年(1765~67)頃 フィラデルフィア美術館
展示期間:全期間
春信好きにはたまらないラインアップではないでしょうか。例えば「やつし芦葉達磨」です。何やら川面の上に浮いているような女性の立ち姿。風がやや強く吹いているのかもしれません。左手で衣を支えています。紅色、いや桃色の彩色も美しい。足元には一葉の芦が広がっています。そして女性はこの芦に乗っているのです。もちろん実際にはあり得ませんが、何でも元は中国の高僧の伝記によるとか。それをやつし絵、つまり見立て描いています。
総じて発色が良い作品が多いのも特徴かもしれません。写楽です。有名な「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」も素晴らしいもの。背景となる雲母の煌めきも美しく、状態は見るからに上々です。何度も目にする作品ではありますが、前にぐいと手を出しては見得を切る江戸兵衛の迫力もより増しているように見えました。
写楽の展示室も効果的です。と言うのも写楽作は一揃えで展示室6、つまり同館で最も狭いスペースに集められていますが、そこのガラスケースはいずれも薄く、作品を目と鼻の先で味わえるのです。もちろん狭いゆえに多少混み合う場合もありますが、これほど状態の良い浮世絵を間近で見られる機会もなかなかありません。

初代喜多川歌麿「歌撰恋之部 稀ニ逢恋」 寛政5~6年(1793~94)頃 フィラデルフィア美術館
展示期間:6月20日~7月20日
大首絵といえば歌麿の「歌撰恋之部 稀ニ逢恋」も絶品でした。町家の女性をモチーフにした大首絵シリーズの一枚。同連作の中では一番若い女性が描かれています。うっすらと紅色がかった雲母は瑞々しく、ツヤのある髪の毛はまだ濡れているかのような質感をたたえています。袖口から垣間見える小さな手先は何とも可憐でした。
清長の「菖蒲の池」にも魅せられました。いわゆる屋外の群像美人画、大判2枚続のワイド画面です。菖蒲の花を愛でる女性たちが描かれていますが、得意のすらりとした7頭身、8頭身のプロポーションも流麗極まりないもの。キセルを加えたり、花に触ったりと、思い思いにポーズをとっては花見を楽しんでいます。

鳥居清長「吉原の花見」 天明5年(1785) フィラデルフィア美術館
展示期間:7月22日~8月16日
なお後期にはさらに1枚増えた3枚続の「吉原の花見」が出品されるそうです。そちらもまた目を引くのではないでしょうか。
改めて展示替えの情報です。一部作品を除き、会期中に一度、作品が入れ替わります。
フィラデルフィア美術館浮世絵名品展出品目録(PDF)
前期:6月20日~7月20日
後期:7月22日~8月16日
相当数の入れ替えです。ほぼ前後期ほ2つで1つの展覧会と捉えて差し支えありません。なお後期の観覧にはリピーター割が有用です。会期中、一般券ないしは学生券を提示すると、2度目は団体料金で入場出来ます。
東京駅周辺の美術館にて「七夕フェア」が開催されています(はろるど)
「七夕フェア」のフェア内容(三井記念美術館)
また以前、拙ブログでもご紹介しましたが、現在、同館では期間限定で「七夕フェア」を開催しています。うち特にお得なのは「カップル割」です。7月7日までにペアで入場すると1名分の料金が無料になります。
[フィラデルフィア美術館浮世絵名品展 巡回予定]
静岡市美術館:8月23日(日)~9月27日(日)
あべのハルカス美術館:10月10日(土)~12月6日(日)
浮世絵展は展示室4以降での展開でした。順路に先立つ同館自慢の立体展示室では「三井記念美術館所蔵の工芸品ー夏に寄せて」を開催中。江戸後期から昭和へ至る蒔絵やタバコ入れ、それに自在置物などを紹介しています。
中でも安藤緑山の「染象牙果菜置物」は要注目ではないでしょうか。昨年の「超絶技巧!明治工芸の粋」でも驚きをもって迎えられた緑山の置物。柿や蜜柑がまさしく本物と見間違えるほどに精巧に作られています。改めて目を奪われました。

葛飾北斎「富嶽三十六景 凱風快晴」 天保元~3年(1830~32)頃 フィラデルフィア美術館
展示期間:全期間
会場内、食い入るように一点一点の作品を見ている方が多いのが印象に残りました。まだ余裕がありましたが、ひょっとすると後半にかけて混雑してくるやもしれません。
8月16日まで開催されています。
「特別展 錦絵誕生250年 フィラデルフィア美術館浮世絵名品展 春信一番!写楽二番!」 三井記念美術館
会期:6月20日(土)~8月16日(日)
休館:月曜日、7月21日(火)。但し7/20(月・祝)は休館。
時間:10:00~17:00 *入館は閉館の30分前まで。
料金:一般1300(1100)円、大学・高校生800(700)円、中学生以下無料。
*( )内は20名以上の団体料金。
*70歳以上は1000円。
*リピーター割引:会期中、一般券、学生券の半券を提示すると、2回目以降は団体料金を適用。
*割引引換券
場所:中央区日本橋室町2-1-1 三井本館7階
交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線三越前駅A7出口より徒歩1分。JR線新日本橋駅1番出口より徒歩5分。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
7月の展覧会・ギャラリーetc
梅雨らしい天気が続きます。7月中に見たい展覧会をリストアップしてみました。
展覧会
・「フランス絵画の贈り物」 泉屋博古館分館(~8/2)
・「没後180年 田能村竹田」 出光美術館(~8/2)
・「レオナルド・ダ・ヴィンチと『アンギアーリの戦い』展」 東京富士美術館(~8/9)
・「旅の風景 安野光雅 ヨーロッパ周遊旅行」 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館(7/7~8/23)
・「没後20年 ルーシー・リー展」 千葉市美術館(7/7~8/30)
・「エリック・サティとその時代展」 Bunkamura ザ・ミュージアム(7/8~8/30)
・「あの歌麿が帰ってきた!ー『深川の雪』再公開」 岡田美術館(~8/31)
・「ニッポンのマンガ*アニメ*ゲーム」 国立新美術館(~8/31)
・「アール・ヌーヴォーのガラス展」 パナソニック汐留ミュージアム(7/4~9/6)
・「動く、光る、目がまわる!キネティック・アート」 埼玉県立近代美術館(7/4~9/6)
・「ドイツと日本を結ぶものー日独修好150年の歴史」 国立歴史民俗博物館(7/7~9/6)
・「舟越保武彫刻展 まなざしの向こうに」 練馬区立美術館(7/12~9/6)
・「伝説の洋画家たち 二科100年展」 東京都美術館(7/18~9/6)
・「特別展示 発掘!知られざる原爆の図」 丸木美術館(~9/12)
・「ペコちゃん展」 平塚市美術館(7/11~9/13)
・「村野藤吾の建築ー模型が語る豊饒な世界」 目黒区美術館(7/11~9/13)
・「うらめしや~、冥途のみやげ展」 東京藝術大学大学美術館(7/22~9/13)
・「ボルドー展ー美と陶酔の都へ」 国立西洋美術館(~9/23)
・「妖怪と出会う夏」 千葉県立中央博物館(7/11~9/23)
・「木村伊兵衛写真賞 40周年記念展」 川崎市市民ミュージアム(7/18~9/23)
・「鈴木理策写真展 意識の流れ」 東京オペラシティ アートギャラリー(7/18~9/23)
・「セザンヌー近代絵画の父になるまで」 ポーラ美術館(~9/27)
・「東の正倉院 金沢文庫」 神奈川県立金沢文庫(7/2~9/27)
・「鎌倉からはじまった。1951-2016 PART2」 神奈川県立近代美術館鎌倉館(7/4~10/4)
・「オスカー・ニーマイヤー展 ブラジルの世界遺産をつくった男」 東京都現代美術館(7/18~10/12)
・「ディン・Q・レ展:明日への記憶」 森美術館(7/25~10/12)
・「アーティスト・ファイル 2015 隣の部屋ー日本と韓国の作家たち」 国立新美術館(7/29~10/12)
・「蔡國強展:帰去来」 横浜美術館(7/11~10/18)
ギャラリー
・「遠藤利克 空洞説 – 水の座」 SCAI(7/3~8/1)
・「資本空間ースリー・ディメンショナル・ロジカル・ピクチャーの彼岸 Vol.3 豊嶋康子」 ギャラリーαM(7/18~8/29)
・「平子雄一 Grafted Tree」 waitingroom(~7/26)
さていつもながらに興味深い展覧会が続きますが、今月はあえて地元千葉の美術館と博物館をピックアップしたいと思います。
まずはお馴染みの千葉市美術館です。「没後20年 ルーシー・リー展」が開催されます。

「没後20年 ルーシー・リー展」@千葉市美術館(7/7~8/30)
既に先行して茨城県陶芸美術館でも行われた国内巡回中のルーシー・リー展。夏は千葉市美術館での開催です。ルーシー・リーの制作を時間を追って辿ります。出品は全200点にも及びます。
なおルーシー・リー展といえば2010年に国立新美術館でも回顧展がありましたが、今回の出品作の大半は日本初公開です。さらに新出もあり、国立新美術館の内容とは重ならないそうです。また国立新美術館では展示方法も優れていました。千葉市美術館での工夫にも期待したいと思います。
同じく千葉市内に位置する博物館です。千葉県立中央博物館にて「妖怪と出会う夏」が開催されます。

「妖怪と出会う夏」@千葉県立中央博物館(7/11~9/23)
千葉にゆかりのある妖怪を紹介する展覧会です。内容は大変に幅広い。県内の寺院に伝わる妙薬から天狗像、妖怪の浮世絵に人魚の絵、そしてまじないの札、さらには思い切ってご当地の妖怪キャラまでを網羅します。
千葉県立中央博物館、最寄の京成千葉寺駅からは歩いて20分ほどかかりますが、場所自体は千葉市美術館と同じ中央区内です。十分にハシゴは出来ます。あわせて見てくるつもりです。
最後は佐倉の歴博です。「ドイツと日本を結ぶものー日独修好150年の歴史」が開催されます。

「ドイツと日本を結ぶものー日独修好150年の歴史」@国立歴史民俗博物館(7/7~9/6)
ドイツと日本の外交史を紹介する異色の企画です。資料は多数。日独外交黎明期、幕末にやってきたプロイセンの使節団やシーボルトの活動、また明治以降のジャポニスムの受容、そしてあの第二次大戦下における関係、さらには戦後までを見据えています。
それにしても目を引くチラシです。そして現在、同じく佐倉の川村記念美術館では「絵の住処ー作品が暮らす11の部屋」も開催中。そちらと絡めて出かけても良さそうです。
[お知らせ]
江戸東京博物館で開催中の「花燃ゆ」展(7/20まで)のチケットが若干枚数手元にあります。先着順にてお一人様一枚ずつ差し上げます。ご希望の方は件名に「花燃ゆ展チケット希望」、本文にフルネームでお名前とメールアドレスを明記の上、拙ブログアドレス harold1234アットマークgoo.jp までご連絡下さい。(アットマークの表記は@にお書き直し下さい。)なお迷惑メール対策のため、携帯電話のアドレスからはメールを受け付けておりません。ご了承下さい。*「花燃ゆ」展の専用チケットです。常設展は観覧出来ません。
それでは今月も宜しくお願いします。
展覧会
・「フランス絵画の贈り物」 泉屋博古館分館(~8/2)
・「没後180年 田能村竹田」 出光美術館(~8/2)
・「レオナルド・ダ・ヴィンチと『アンギアーリの戦い』展」 東京富士美術館(~8/9)
・「旅の風景 安野光雅 ヨーロッパ周遊旅行」 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館(7/7~8/23)
・「没後20年 ルーシー・リー展」 千葉市美術館(7/7~8/30)
・「エリック・サティとその時代展」 Bunkamura ザ・ミュージアム(7/8~8/30)
・「あの歌麿が帰ってきた!ー『深川の雪』再公開」 岡田美術館(~8/31)
・「ニッポンのマンガ*アニメ*ゲーム」 国立新美術館(~8/31)
・「アール・ヌーヴォーのガラス展」 パナソニック汐留ミュージアム(7/4~9/6)
・「動く、光る、目がまわる!キネティック・アート」 埼玉県立近代美術館(7/4~9/6)
・「ドイツと日本を結ぶものー日独修好150年の歴史」 国立歴史民俗博物館(7/7~9/6)
・「舟越保武彫刻展 まなざしの向こうに」 練馬区立美術館(7/12~9/6)
・「伝説の洋画家たち 二科100年展」 東京都美術館(7/18~9/6)
・「特別展示 発掘!知られざる原爆の図」 丸木美術館(~9/12)
・「ペコちゃん展」 平塚市美術館(7/11~9/13)
・「村野藤吾の建築ー模型が語る豊饒な世界」 目黒区美術館(7/11~9/13)
・「うらめしや~、冥途のみやげ展」 東京藝術大学大学美術館(7/22~9/13)
・「ボルドー展ー美と陶酔の都へ」 国立西洋美術館(~9/23)
・「妖怪と出会う夏」 千葉県立中央博物館(7/11~9/23)
・「木村伊兵衛写真賞 40周年記念展」 川崎市市民ミュージアム(7/18~9/23)
・「鈴木理策写真展 意識の流れ」 東京オペラシティ アートギャラリー(7/18~9/23)
・「セザンヌー近代絵画の父になるまで」 ポーラ美術館(~9/27)
・「東の正倉院 金沢文庫」 神奈川県立金沢文庫(7/2~9/27)
・「鎌倉からはじまった。1951-2016 PART2」 神奈川県立近代美術館鎌倉館(7/4~10/4)
・「オスカー・ニーマイヤー展 ブラジルの世界遺産をつくった男」 東京都現代美術館(7/18~10/12)
・「ディン・Q・レ展:明日への記憶」 森美術館(7/25~10/12)
・「アーティスト・ファイル 2015 隣の部屋ー日本と韓国の作家たち」 国立新美術館(7/29~10/12)
・「蔡國強展:帰去来」 横浜美術館(7/11~10/18)
ギャラリー
・「遠藤利克 空洞説 – 水の座」 SCAI(7/3~8/1)
・「資本空間ースリー・ディメンショナル・ロジカル・ピクチャーの彼岸 Vol.3 豊嶋康子」 ギャラリーαM(7/18~8/29)
・「平子雄一 Grafted Tree」 waitingroom(~7/26)
さていつもながらに興味深い展覧会が続きますが、今月はあえて地元千葉の美術館と博物館をピックアップしたいと思います。
まずはお馴染みの千葉市美術館です。「没後20年 ルーシー・リー展」が開催されます。

「没後20年 ルーシー・リー展」@千葉市美術館(7/7~8/30)
既に先行して茨城県陶芸美術館でも行われた国内巡回中のルーシー・リー展。夏は千葉市美術館での開催です。ルーシー・リーの制作を時間を追って辿ります。出品は全200点にも及びます。
なおルーシー・リー展といえば2010年に国立新美術館でも回顧展がありましたが、今回の出品作の大半は日本初公開です。さらに新出もあり、国立新美術館の内容とは重ならないそうです。また国立新美術館では展示方法も優れていました。千葉市美術館での工夫にも期待したいと思います。
同じく千葉市内に位置する博物館です。千葉県立中央博物館にて「妖怪と出会う夏」が開催されます。

「妖怪と出会う夏」@千葉県立中央博物館(7/11~9/23)
千葉にゆかりのある妖怪を紹介する展覧会です。内容は大変に幅広い。県内の寺院に伝わる妙薬から天狗像、妖怪の浮世絵に人魚の絵、そしてまじないの札、さらには思い切ってご当地の妖怪キャラまでを網羅します。
千葉県立中央博物館、最寄の京成千葉寺駅からは歩いて20分ほどかかりますが、場所自体は千葉市美術館と同じ中央区内です。十分にハシゴは出来ます。あわせて見てくるつもりです。
最後は佐倉の歴博です。「ドイツと日本を結ぶものー日独修好150年の歴史」が開催されます。

「ドイツと日本を結ぶものー日独修好150年の歴史」@国立歴史民俗博物館(7/7~9/6)
ドイツと日本の外交史を紹介する異色の企画です。資料は多数。日独外交黎明期、幕末にやってきたプロイセンの使節団やシーボルトの活動、また明治以降のジャポニスムの受容、そしてあの第二次大戦下における関係、さらには戦後までを見据えています。
それにしても目を引くチラシです。そして現在、同じく佐倉の川村記念美術館では「絵の住処ー作品が暮らす11の部屋」も開催中。そちらと絡めて出かけても良さそうです。
[お知らせ]
江戸東京博物館で開催中の「花燃ゆ」展(7/20まで)のチケットが若干枚数手元にあります。先着順にてお一人様一枚ずつ差し上げます。ご希望の方は件名に「花燃ゆ展チケット希望」、本文にフルネームでお名前とメールアドレスを明記の上、拙ブログアドレス harold1234アットマークgoo.jp までご連絡下さい。(アットマークの表記は@にお書き直し下さい。)なお迷惑メール対策のため、携帯電話のアドレスからはメールを受け付けておりません。ご了承下さい。*「花燃ゆ」展の専用チケットです。常設展は観覧出来ません。
それでは今月も宜しくお願いします。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
「世界報道写真展2015」 東京芸術劇場ギャラリー1
東京芸術劇場ギャラリー1
「世界報道写真展2015」
6/27-8/9

東京芸術劇場ギャラリー1で開催中の「世界報道写真展2015」のプレスプレビューに参加してきました。
1956年にオランダ・アムステルダムで始まった世界報道写真展。今年で58回目です。コンテストには131の国と地域から計5692名のプロのカメラマンが参加。応募総数は97912点にも及びます。
うち選定された8部門41名の受賞作品を紹介する展覧会です。作品数は62点。コンテスト8部門には単写真(写真1枚)と組写真(複数の写真で構成)に分かれています。
うち全部門から最も優れた写真を1点選定。「世界報道写真大賞」が贈られました。今年の大賞受賞者はデンマークのカメラマン、マッズ・ニッセンです。

マッズ・ニッセン(デンマーク)「Scanpix/Panos Pictures」 ロシア、サンクトペテルブルク
まるでバロック絵画のワンシーンを切り取ったかのような一枚。被写体はサンクトペテルブルクの同性愛のカップルです。現在のロシアでは、レズビアンやゲイ、トランスジェンダーらの暮らしが困難になっているとのこと。社会的差別やヘイトクライムの被害に遭うことも少なくないそうです。
審査員の一人をして「世界のあらゆる問題に対する答えは愛だという主張が含まれている」と評された作品。確かにその姿は美しく、強く訴えかけてくるものがあります。

マッシモ・セスティーニ リビア沖(2014年6月7日)
地中海においてアフリカ人をのせたボート難民を捉えています。一般ニュースの部で2位を受賞したマッシモ・セスティーニは、リビア沖でイタリアの巡洋艦に救助された難民を写し出しました。
参考リンク:「地中海に殺到するボート難民、イタリアは悲鳴」(THE WALL STREET JOURNAL)
2014年には何と15万名もの難民が保護されたそうです。もちろん航路は大きな危険を伴います。問題の根本には北アフリカ地域全体の政情不安もあります。貧困もあるでしょう。青い海に浮くボートにひしめきあうように乗る難民たち。もはや身動きすらとれそうもありません。急増する難民にどのように対処していくのか。解決の難しさを改めて感じました。

アル・ベッロ(アメリカ)「Getty Images」 アメリカ、ニュージャージー州イーストラザフォード
一転しての躍動感のある写真に目を奪われました。スポーツの部です。同部門で2位を受賞したアメリカのアル・ベッロの作品、ご覧の通りアメフトです。片手でタッチダウンを決めた選手の動きといったら凄まじい。大きく反り返ってはボールを掴みます。まさに神業と言っても良いのかもしれません。

右:アミ・ヴィタール(アメリカ) ナショナルジオグラフィック誌 ケニア北部、レワダウンズ自然保護区
自然の部では1位に中国の儲永志、2位にアメリカのアミ・ヴィタールが選ばれました。ともに動物保護の問題です。儲が写したのは中国のサーカスで芸を仕込まれたサル。実は既に同国ではサーカスに動物を出すことを禁じていますが、実際には多くの調教師が依然として動物を使っているそうです。
一方、アミが写したのがケニアのクロサイです。優し気に撫でているのは地域の先住民族の人々。クロサイは密猟によって絶滅の危機に瀕していますが、今、こうした先住民族の人々が密猟を防ぐために立ち上がっているそうです。その取り組みを伝えてもいます。

「世界報道写真展2015」(東京)会場風景
部門はほかにポートレートや日常生活、スポットニュース、そして現代社会の問題の部と多岐に渡ります。また今回からは長期取材の部も新設されました。単年度だけでなく、長期的なプロジェクトによって撮影された作品です。一人のアメリカの貧しい女性に取材しながら、貧困、エイズ、薬物、暴力などの問題を引き出したダーシー・パディーラの「ジュリーの物語」が1位を受賞しました。

「世界報道写真展2015」(東京)会場風景
ほかにはISの空爆やイランの公開処刑を捉えたものなど、思わず目を背けてしまうような作品も少なくありません。しかしながらだからこそ見入り、また考えさせられるもの。辛くまた厳しく、時に胸に詰まるような光景も全て現実の一端であります。

トゥーリ・カラファート(イタリア)
今年は日本人の応募が60件あったそうですが、残念ながら入賞作には選ばれませんでした。しかしただ1点、舞台を日本に取材した作品があります。イタリア人のトゥーリ・カラファートの作品です。舞台は名古屋のファストフード店。包装紙からしてマクドナルドでしょうか。ブラインド越しに並んでは食する人々。我々にとっては馴染みのある光景ですが、この一人用の席にカメラマンは反応したようです。そこに何とも言い難い「孤独」を見出しています。

「世界報道写真展2015」(東京)会場風景
世界45カ国、100会場(2014年度実績)を巡る世界最大規模の写真展。展示の形態からプリントはオリジナルというわけにはいきませんが、それでも写真パネル自体の迫力も並々ならぬものがあります。
ところで世界報道写真展はこれまで恵比寿の都写真美術館で開催されていましたが、現在、同館は大規模改修工事のため休館中。そのため今年は会場を池袋の芸術劇場(5階のギャラリー)に移しています。なお来年の2016年展は、リニューアルを終えた都写真美術館で再び行われるそうです。
[世界報道写真展2015 巡回予定]
ハービスHALL(大阪):8月11日(火)~8月20日(木)
イオンレイクタウンkaze(埼玉):8月23日(日)~9月6日(日)
立命館大学国際平和ミュージアム(京都):9月9日(水)~10月4日(日)
立命館大学びわこ・くさつキャンパス(滋賀):10月6日(火)~10月18日(日)
立命館アジア太平洋大学(大分):10月21日(水)~11月4日(水)
イオンモール広島祇園(広島):11月7日(土)~11月18日(水)

「世界報道写真展2015」(東京)会場入口
8月9日まで開催されています。
「世界報道写真展2015」(@wppjapan) 東京芸術劇場ギャラリー1
会期:6月27日(土)~8月9日(日)
休館:7月6日、7月27日。
時間:10:00~17:00
*毎週金・土曜日は20時まで。
*入館は閉館30分前まで。
料金:一般800(700)円、学生600(500)円、中高生・65歳以上400(350)円。
*( )内は20名以上の団体料金。
場所:豊島区西池袋1-8-1 東京芸術劇場5階
交通:JR線・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線池袋駅西口より徒歩5分。駅地下通路2b出口と直結。
注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。
「世界報道写真展2015」
6/27-8/9

東京芸術劇場ギャラリー1で開催中の「世界報道写真展2015」のプレスプレビューに参加してきました。
1956年にオランダ・アムステルダムで始まった世界報道写真展。今年で58回目です。コンテストには131の国と地域から計5692名のプロのカメラマンが参加。応募総数は97912点にも及びます。
うち選定された8部門41名の受賞作品を紹介する展覧会です。作品数は62点。コンテスト8部門には単写真(写真1枚)と組写真(複数の写真で構成)に分かれています。
うち全部門から最も優れた写真を1点選定。「世界報道写真大賞」が贈られました。今年の大賞受賞者はデンマークのカメラマン、マッズ・ニッセンです。

マッズ・ニッセン(デンマーク)「Scanpix/Panos Pictures」 ロシア、サンクトペテルブルク
まるでバロック絵画のワンシーンを切り取ったかのような一枚。被写体はサンクトペテルブルクの同性愛のカップルです。現在のロシアでは、レズビアンやゲイ、トランスジェンダーらの暮らしが困難になっているとのこと。社会的差別やヘイトクライムの被害に遭うことも少なくないそうです。
審査員の一人をして「世界のあらゆる問題に対する答えは愛だという主張が含まれている」と評された作品。確かにその姿は美しく、強く訴えかけてくるものがあります。

マッシモ・セスティーニ リビア沖(2014年6月7日)
地中海においてアフリカ人をのせたボート難民を捉えています。一般ニュースの部で2位を受賞したマッシモ・セスティーニは、リビア沖でイタリアの巡洋艦に救助された難民を写し出しました。
参考リンク:「地中海に殺到するボート難民、イタリアは悲鳴」(THE WALL STREET JOURNAL)
2014年には何と15万名もの難民が保護されたそうです。もちろん航路は大きな危険を伴います。問題の根本には北アフリカ地域全体の政情不安もあります。貧困もあるでしょう。青い海に浮くボートにひしめきあうように乗る難民たち。もはや身動きすらとれそうもありません。急増する難民にどのように対処していくのか。解決の難しさを改めて感じました。

アル・ベッロ(アメリカ)「Getty Images」 アメリカ、ニュージャージー州イーストラザフォード
一転しての躍動感のある写真に目を奪われました。スポーツの部です。同部門で2位を受賞したアメリカのアル・ベッロの作品、ご覧の通りアメフトです。片手でタッチダウンを決めた選手の動きといったら凄まじい。大きく反り返ってはボールを掴みます。まさに神業と言っても良いのかもしれません。

右:アミ・ヴィタール(アメリカ) ナショナルジオグラフィック誌 ケニア北部、レワダウンズ自然保護区
自然の部では1位に中国の儲永志、2位にアメリカのアミ・ヴィタールが選ばれました。ともに動物保護の問題です。儲が写したのは中国のサーカスで芸を仕込まれたサル。実は既に同国ではサーカスに動物を出すことを禁じていますが、実際には多くの調教師が依然として動物を使っているそうです。
一方、アミが写したのがケニアのクロサイです。優し気に撫でているのは地域の先住民族の人々。クロサイは密猟によって絶滅の危機に瀕していますが、今、こうした先住民族の人々が密猟を防ぐために立ち上がっているそうです。その取り組みを伝えてもいます。

「世界報道写真展2015」(東京)会場風景
部門はほかにポートレートや日常生活、スポットニュース、そして現代社会の問題の部と多岐に渡ります。また今回からは長期取材の部も新設されました。単年度だけでなく、長期的なプロジェクトによって撮影された作品です。一人のアメリカの貧しい女性に取材しながら、貧困、エイズ、薬物、暴力などの問題を引き出したダーシー・パディーラの「ジュリーの物語」が1位を受賞しました。

「世界報道写真展2015」(東京)会場風景
ほかにはISの空爆やイランの公開処刑を捉えたものなど、思わず目を背けてしまうような作品も少なくありません。しかしながらだからこそ見入り、また考えさせられるもの。辛くまた厳しく、時に胸に詰まるような光景も全て現実の一端であります。

トゥーリ・カラファート(イタリア)
今年は日本人の応募が60件あったそうですが、残念ながら入賞作には選ばれませんでした。しかしただ1点、舞台を日本に取材した作品があります。イタリア人のトゥーリ・カラファートの作品です。舞台は名古屋のファストフード店。包装紙からしてマクドナルドでしょうか。ブラインド越しに並んでは食する人々。我々にとっては馴染みのある光景ですが、この一人用の席にカメラマンは反応したようです。そこに何とも言い難い「孤独」を見出しています。

「世界報道写真展2015」(東京)会場風景
世界45カ国、100会場(2014年度実績)を巡る世界最大規模の写真展。展示の形態からプリントはオリジナルというわけにはいきませんが、それでも写真パネル自体の迫力も並々ならぬものがあります。
ところで世界報道写真展はこれまで恵比寿の都写真美術館で開催されていましたが、現在、同館は大規模改修工事のため休館中。そのため今年は会場を池袋の芸術劇場(5階のギャラリー)に移しています。なお来年の2016年展は、リニューアルを終えた都写真美術館で再び行われるそうです。
[世界報道写真展2015 巡回予定]
ハービスHALL(大阪):8月11日(火)~8月20日(木)
イオンレイクタウンkaze(埼玉):8月23日(日)~9月6日(日)
立命館大学国際平和ミュージアム(京都):9月9日(水)~10月4日(日)
立命館大学びわこ・くさつキャンパス(滋賀):10月6日(火)~10月18日(日)
立命館アジア太平洋大学(大分):10月21日(水)~11月4日(水)
イオンモール広島祇園(広島):11月7日(土)~11月18日(水)

「世界報道写真展2015」(東京)会場入口
8月9日まで開催されています。
「世界報道写真展2015」(@wppjapan) 東京芸術劇場ギャラリー1
会期:6月27日(土)~8月9日(日)
休館:7月6日、7月27日。
時間:10:00~17:00
*毎週金・土曜日は20時まで。
*入館は閉館30分前まで。
料金:一般800(700)円、学生600(500)円、中高生・65歳以上400(350)円。
*( )内は20名以上の団体料金。
場所:豊島区西池袋1-8-1 東京芸術劇場5階
交通:JR線・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線池袋駅西口より徒歩5分。駅地下通路2b出口と直結。
注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
| 次ページ » |









