都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「没後180年 田能村竹田」 出光美術館
出光美術館
「没後180年 田能村竹田」
6/20-8/2
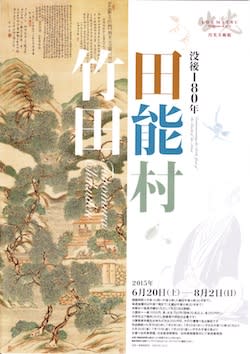
出光美術館で開催中の「没後180年 田能村竹田」を見てきました。
豊後国岡藩の藩医の子に生まれながら、若くして隠遁。絵を描き続けながら儒者としての道を歩んだ田能村竹田(たのむらちくでん。1777~1835)。
必ずしも良く知られた画家とは言えないかもしれませんが、密に過度でなく、疎に絶妙な文人画の世界は素直に見入るものがあります。
出光美術館としては18年ぶりの回顧展です。作品は全て同館のコレクション。初期から晩年までの作品、約55点が展示されています。
1.精妙無窮ー竹田画の魅力と特質
2.山水に憩うー自娯適意の諸相
3.微細な色彩と薫りー生命あるものへ
4.眼差しの記憶ー「旅」と確かな実感
5.幕末文人、それぞれの理想
田能村竹田、先に倣うのは中国の文人山水画です。例えば「青緑山水図」は雨後に濡れた岩山を描いたもの。緑青、群青を配した色の塗り分けも軽妙で美しい。「三津浜図」は伊東の景色を表した作品です。砂浜を鳥瞰的、ないし覗き込むような構図は西湖図風でしょうか。手前には小さな人影も見えます。
それにしても竹田の文人画、筆致は実に繊細です。時に肉眼では分からないほどに細かいこともあります。単眼鏡があっても良いかもしれません。
季節感、また空気感を巧みに伝えているのも竹田画の魅力ではないでしょうか。重要文化財の「梅花書屋図」では水辺越しの梅林を描いています。馬に乗って小径を進む人の姿も垣間見えました。そしてこの梅林の何とも可憐な様と言ったら素晴らしいもの。仄かなピンク色をした花からは梅の薫りが漂ってくるかのようであります。
「高客吹笛図」にも惹かれました。モチーフは喫茶を楽しむ高士たちです。背景は岩山、滝の姿も見えます。筆は思いの外に大胆。しかしながら高士たちの表現は緻密です。ヒゲ、髪の毛の線は細かく、また着衣の線も無駄がありません。杯を持っては茶を飲み交わす男たちの愉快な雰囲気も伝わってきます。
「寄春詩図巻」も絶品でした。縦長の軸画の目立つ竹田画の中ではやや珍しい横長の図巻です。梅と竹、それに小鳥を描いていますが、興味深いのは竹におそらくは青を用いていることです。一方で梅は墨。小鳥も生き生きと描かれています。意図したものではないかもしれせんが、さも月明かりに照らされた光景のようにも見えました。
「東山図」はどうでしょうか。旅好きの竹田、全国各地を渡り歩いては絵に残したそうですが、本作でも舞台は京都の東山です。山々を吹き散らかしの筆で颯爽と描いています。擦れるような墨の滲みも情感深い。細かな曲線を多用しては、こんもりとした山の緑を表しています。
一転して色鮮やかな作品に目が留まりました。「春園富貴図」です。見るも大きな牡丹に太湖石のモチーフ。極彩色と言っても良いのではないでしょうか。太湖石の緑青、そして牡丹の紫、ピンク、白などが力強いまでに塗りこまれています。
「蘭図」も魅惑的でした。群生する蘭を瑞々しく描いた一枚。「蘭は心で、心は蘭だ。筆遣いの巧拙などは気にする必要がない。」。竹田はこのようにも述べています。
遊び心にも満ちた「書画貼交屏風」も良い。鳩に猫に鵞鳥に蟹などを描いていますが、特に蟹が可愛らしい。全部で7匹です。脚を広げては忙しそうに行き交っていました。
文人画ということで賛が付けられていましたが、大半の作品に訓読と大意を記したキャプションが付けられています。賛を読み、絵を愛でては、竹田の自然、あるいは人々に対する温かい眼差しを知る。実のところ私にとっては未知の画家でしたが、まさかこれほど惹かれるとは思いませんでした。
竹田の先輩格に当たる池大雅に与謝蕪村、また同時代の文人による作品も10点ほど出ていました。こちらも楽しめるのではないでしょうか。
一部作品において会期中に頁替えがありますが、展示替えはありません。
 「田能村竹田/宗像健一/新潮日本美術文庫」
「田能村竹田/宗像健一/新潮日本美術文庫」
8月2日まで開催されています。
「没後180年 田能村竹田」 出光美術館
会期:6月20日(土)~8月2日(日)
休館:月曜日。但し7月20日は開館。
時間:10:00~17:00
*毎週金曜日は19時まで開館。入館は閉館の30分前まで。
料金:一般1000(800)円、高・大生700(500)円、中学生以下無料(但し保護者の同伴が必要。)
*( )内は20名以上の団体料金。
住所:千代田区丸の内3-1-1 帝劇ビル9階
交通:東京メトロ有楽町線有楽町駅、都営三田線日比谷駅B3出口より徒歩3分。東京メトロ日比谷線・千代田線日比谷駅から地下連絡通路を経由しB3出口より徒歩3分。JR線有楽町駅国際フォーラム口より徒歩5分。
「没後180年 田能村竹田」
6/20-8/2
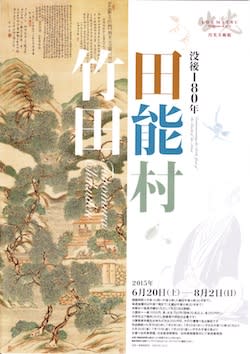
出光美術館で開催中の「没後180年 田能村竹田」を見てきました。
豊後国岡藩の藩医の子に生まれながら、若くして隠遁。絵を描き続けながら儒者としての道を歩んだ田能村竹田(たのむらちくでん。1777~1835)。
必ずしも良く知られた画家とは言えないかもしれませんが、密に過度でなく、疎に絶妙な文人画の世界は素直に見入るものがあります。
出光美術館としては18年ぶりの回顧展です。作品は全て同館のコレクション。初期から晩年までの作品、約55点が展示されています。
1.精妙無窮ー竹田画の魅力と特質
2.山水に憩うー自娯適意の諸相
3.微細な色彩と薫りー生命あるものへ
4.眼差しの記憶ー「旅」と確かな実感
5.幕末文人、それぞれの理想
田能村竹田、先に倣うのは中国の文人山水画です。例えば「青緑山水図」は雨後に濡れた岩山を描いたもの。緑青、群青を配した色の塗り分けも軽妙で美しい。「三津浜図」は伊東の景色を表した作品です。砂浜を鳥瞰的、ないし覗き込むような構図は西湖図風でしょうか。手前には小さな人影も見えます。
それにしても竹田の文人画、筆致は実に繊細です。時に肉眼では分からないほどに細かいこともあります。単眼鏡があっても良いかもしれません。
季節感、また空気感を巧みに伝えているのも竹田画の魅力ではないでしょうか。重要文化財の「梅花書屋図」では水辺越しの梅林を描いています。馬に乗って小径を進む人の姿も垣間見えました。そしてこの梅林の何とも可憐な様と言ったら素晴らしいもの。仄かなピンク色をした花からは梅の薫りが漂ってくるかのようであります。
「高客吹笛図」にも惹かれました。モチーフは喫茶を楽しむ高士たちです。背景は岩山、滝の姿も見えます。筆は思いの外に大胆。しかしながら高士たちの表現は緻密です。ヒゲ、髪の毛の線は細かく、また着衣の線も無駄がありません。杯を持っては茶を飲み交わす男たちの愉快な雰囲気も伝わってきます。
「寄春詩図巻」も絶品でした。縦長の軸画の目立つ竹田画の中ではやや珍しい横長の図巻です。梅と竹、それに小鳥を描いていますが、興味深いのは竹におそらくは青を用いていることです。一方で梅は墨。小鳥も生き生きと描かれています。意図したものではないかもしれせんが、さも月明かりに照らされた光景のようにも見えました。
「東山図」はどうでしょうか。旅好きの竹田、全国各地を渡り歩いては絵に残したそうですが、本作でも舞台は京都の東山です。山々を吹き散らかしの筆で颯爽と描いています。擦れるような墨の滲みも情感深い。細かな曲線を多用しては、こんもりとした山の緑を表しています。
一転して色鮮やかな作品に目が留まりました。「春園富貴図」です。見るも大きな牡丹に太湖石のモチーフ。極彩色と言っても良いのではないでしょうか。太湖石の緑青、そして牡丹の紫、ピンク、白などが力強いまでに塗りこまれています。
「蘭図」も魅惑的でした。群生する蘭を瑞々しく描いた一枚。「蘭は心で、心は蘭だ。筆遣いの巧拙などは気にする必要がない。」。竹田はこのようにも述べています。
遊び心にも満ちた「書画貼交屏風」も良い。鳩に猫に鵞鳥に蟹などを描いていますが、特に蟹が可愛らしい。全部で7匹です。脚を広げては忙しそうに行き交っていました。
文人画ということで賛が付けられていましたが、大半の作品に訓読と大意を記したキャプションが付けられています。賛を読み、絵を愛でては、竹田の自然、あるいは人々に対する温かい眼差しを知る。実のところ私にとっては未知の画家でしたが、まさかこれほど惹かれるとは思いませんでした。
竹田の先輩格に当たる池大雅に与謝蕪村、また同時代の文人による作品も10点ほど出ていました。こちらも楽しめるのではないでしょうか。
一部作品において会期中に頁替えがありますが、展示替えはありません。
 「田能村竹田/宗像健一/新潮日本美術文庫」
「田能村竹田/宗像健一/新潮日本美術文庫」8月2日まで開催されています。
「没後180年 田能村竹田」 出光美術館
会期:6月20日(土)~8月2日(日)
休館:月曜日。但し7月20日は開館。
時間:10:00~17:00
*毎週金曜日は19時まで開館。入館は閉館の30分前まで。
料金:一般1000(800)円、高・大生700(500)円、中学生以下無料(但し保護者の同伴が必要。)
*( )内は20名以上の団体料金。
住所:千代田区丸の内3-1-1 帝劇ビル9階
交通:東京メトロ有楽町線有楽町駅、都営三田線日比谷駅B3出口より徒歩3分。東京メトロ日比谷線・千代田線日比谷駅から地下連絡通路を経由しB3出口より徒歩3分。JR線有楽町駅国際フォーラム口より徒歩5分。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )









