都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「風景画の誕生 ウィーン美術史美術館所蔵」 Bunkamura ザ・ミュージアム
Bunkamura ザ・ミュージアム
「風景画の誕生 ウィーン美術史美術館所蔵」
9/9-12/7
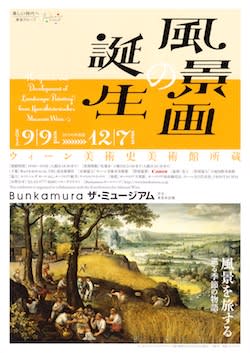
Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「風景画の誕生 ウィーン美術史美術館所蔵」のプレスプレビューに参加してきました。
山や海をはじめ、深い森、また都市などの景観が美しく表現された風景画。好きな作品の一つや二つはすぐに思い浮かぶかもしれません。ただ風景画が興ったのは何時の頃に遡るのでしょうか。あまり意識することはないかもしれません。
はじまりは聖書や神話の物語でした。15世紀以降、絵画の中の「描かれた窓」(解説より)の中に取り入れられた風景。いわゆる後景と言っても良いでしょう。宗教画でも多く描かれるようになります。

左:南ネーデルラントの画家「東方三博士の礼拝」 1520年頃 油彩・板
南ネーデルラントの画家の「東方三博士の礼拝」です。中央の青、ないし深緑色の服を着て座るのが聖母マリア。両手には幼子のイエスを抱きかかえています。そしてマリアと向き合い、イエスを見やるのが三博士。恭しく贈り物を差し出そうとしています。ほか着飾った多くの人物たちも描かれています。ともすると風景にはあまり目が向かないかもしれません。
ただ確かに中央の奥には山や家などの風景が描かれています。そして右最上段、アーチ状の建造物に立つ二人の人物に注目です。分かりにくいかもしれませんが、描かれているのは後ろ姿のみ。ほかの人物がほぼマリアやイエスを見ているのに対し、まるで反対側を向いています。とすれば何を見ているのでしょうか。結論から言えば後ろに広がる風景を見渡しているのです。

右:ヨアヒム・パティニール「聖カタリナの車輪の奇跡」 1515年以前 油彩・板
美術史上、初めて「風景画家」と呼ばれた人物がいます。ヨハヒム・パティニールです。かのデューラーが「良き風景画家」と讃えました。「聖カタリナの車輪の奇跡」では確かにカタリナの伝説を描いていますが、主役はもはや広大なる風景と言っても良いかもしれません。高い位置から岩山を俯瞰し、城館を見据え、海を望んでいます。
うっすらと帯びた後景の青。色彩遠近法です。前景に暖色、後ろに寒色を配しては奥行き感を巧みに作り上げています。ただここではカタリナの奇跡の様子もドラマテックで面白いもの。中景の左で燃え上がるのが哲学者らを殺害した薪の山。一方、右手中段、燃え上がる車輪の前で跪き、祈りを捧げているのがカタリナです。ともに描写は細かい。剣を持ち、ひっくり返っている男たちも真に迫っています。

ヒエロニムス・ボスの模倣者「楽園図」 1540~50年後頃 油彩・板
僅か縦25センチほどの小さな画面ながらも実に緻密です。「楽園図」です。画家はおそらくはボスの模倣者。風景というよりも奇景。摩訶不思議な植物や生き物が現れます。ボスが描き、現在はプラド美術館にある「快楽の園」に倣ったと考えられているそうです。
一つのハイライトとも言えるのではないでしょうか。月暦画です。画家の名はレアンドロ・バッサーノ。1年12ヶ月の生活、季節毎に変わりゆく人々の生活や労働の様子を表現。自然の風景とともに、天体の進行、星座とあわせて、一つのスペクタクルとも言うべき絵画世界を展開しています。

レアンドロ・バッサーノ「月暦画」連作 展示風景
ウィーン美術史美術館にはうち9月、10月、12月意外の9枚を所蔵。その全てが一部屋をぐるりと囲むように展示されています。(9、10はプラハに所蔵。12月は行方不明になっているそうです。)

右:レアンドロ・バッサーノ「8月」 1585年 油彩・キャンヴァス
あえて一枚挙げるとするならば「8月」。人々が一生懸命に樽を作っていますが、もちろんこれはこの後に収穫されるぶどう、すなわちワインを貯蔵するためのもの。また奥では羊の毛を刈り込んでいます。そして空を眺めれば乙女座を表す女性のシンボル。ユニコーンの姿も見えました。

右:ダーフィット・テニールス(父)「メルクリウスとアルゴス、イオ」 1638年 油彩・銅板
それにしても本展、ともかく風景画の誕生から成立に至るまでの前半部が充実しています。ほかヤン・ブリューゲル父子、ドッソ・ドッシ、ダーフィット・テニールス父、ファルケンボルフなどに目を引く作品が多い。いずれもウィーン美術史美術館のコレクションです。フランドル、オランダなどの北方絵画に定評のある同美術館ならでは展示と言えそうです。
さて後半は風景画の展開です。17世紀になると風景は物語の舞台ではなく、独立した主題として描かれるようになりました。

右:アールト・ファン・デル・ネール「月明かりの下の船のある川の風景」 1665~70年頃 油彩・キャンヴァス
アールト・ファン・デル・ネールの「月明かりの下の船のある川の風景」はどうでしょうか。水辺の風景、たくさんの帆船が浮かび、漁をする小舟の姿も見えます。左には廃墟、右は木立に館。画面の大半を占めるのが空です。明るい満月。まるで夕景の如く空をピンク色に染めています。一方で水面や背景は青白い。独特の詩情をたたえてもいます。

左:ヤーコブ・ファン・ロイスダール「渓流のある風景」 1670~80年頃 油彩・板で裏打ちされたキャンヴァス
日本でもお馴染みの風景画家も登場します。例えばロイスダールです。名は「渓流のある風景」。かなり激しい水の流れ落ちる川を捉えた一枚。岩場には木が横倒しになり、洪水の後のようにも見えます。そして小屋の前にいる小さな人影。荒々しい土地です。背後には雄大な山も垣間見えます。自然の厳しい姿を表現しています。

右:カナレット「ヴェネツィアのスキアヴォーニ河岸」 1730年頃 油彩・キャンヴァス
ラストはイタリアの風景、カナレットです。「ヴェネツィアのスキアヴォーニ河岸」。広く、うっすら桃色を帯びた雲の下に広がるヴェネツィアの町。パノラマです。右手に建物が連なり、行く手にはサン・マルコ広場の鐘楼も見えます。左は岸。大小様々な船がたくさん浮かんでいます。線に色に緻密な表現。いわゆる都市景観図です。特にイタリアを訪れたイギリスの人々に人気を集めました。
出品は全70点。ウィーン美術史美術館のコレクションで辿る風景画の歴史。テーマは明快です。思いの外に読ませる展示でもありました。
9月25日(金)より金・土曜の夜間開館時のみに利用出来る新たなタブレットガイド貸出サービスが始まりました。
「スペシャルコンテンツ収録のタブレットガイドが登場!」(Bunkamura ザ・ミュージアム)
タブレットには美術ジャーナリスト藤原えりみさんの見どころ解説のほか、石井ゆかりさんの「星座メッセージ」、また福岡伸一さんや原田マハさんによるエッセイ、さらにはリアルタイムで参加可能な作品ランキングなどのコンテンツを搭載。専門的な内容からエンターテイメントまでと盛りだくさんです。タブレットを操作することで、様々な角度から展覧会を楽しむことが出来ます。

「風景画の誕生 ウィーン美術史美術館所蔵」展タブレットガイド
タブレットガイドの貸出は上記にもあるように9月25日(金)以降、展覧会終了までの毎週金、土曜の夜間開館時(19時~21時)のみ。貸出台数は50台。利用料金は通常の音声ガイドと同じく520円です。(受付で通常のガイドかタブレットのどちらかを選ぶことが出来ます。)
最後に学生のみなさんにお得な情報です。10月5日(月)は「キヤノン・ミュージアム・キャンパス」のため無料で入館出来ます。
[特別プログラム キヤノン・ミュージアム・キャンパス]
日時:10月5日(月) 10:00~17:00(最終入場16:30)
会場:Bunkamuraザ・ミュージアム
対象:大学生(大学院生、短期大学生、専門学校生、高等専門学校の4・5年生を含む)
申込み:不要
料金:無料
当日は休館日。学生のみを対象とした無料観覧日です。つまり学生のみの貸し切りイベントです。平日の月曜ではありますが、これを機会にBunkamuraまで出かけてみては如何でしょうか。

12月7日まで開催されています。
「風景画の誕生 ウィーン美術史美術館所蔵」 Bunkamura ザ・ミュージアム(@Bunkamura_info)
会期:9月9日(水)~12月7日(月)
休館:10月5日(月)。
時間:10:00~19:00。
*毎週金・土は21:00まで開館。入館は閉館の30分前まで。
料金:一般1500(1300)円、大学・高校生1000(800)円、中学・小学生700(500)円。
*( )内は20名以上の団体料金。要事前予約。
住所:渋谷区道玄坂2-24-1
交通:JR線渋谷駅ハチ公口より徒歩7分。東急東横線・東京メトロ銀座線・京王井の頭線渋谷駅より徒歩7分。東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線・東京メトロ副都心線渋谷駅3a出口より徒歩5分。
注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。作品は全てウィーン美術史美術館所蔵。
「風景画の誕生 ウィーン美術史美術館所蔵」
9/9-12/7
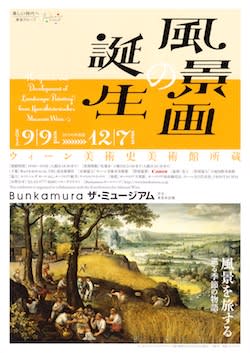
Bunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「風景画の誕生 ウィーン美術史美術館所蔵」のプレスプレビューに参加してきました。
山や海をはじめ、深い森、また都市などの景観が美しく表現された風景画。好きな作品の一つや二つはすぐに思い浮かぶかもしれません。ただ風景画が興ったのは何時の頃に遡るのでしょうか。あまり意識することはないかもしれません。
はじまりは聖書や神話の物語でした。15世紀以降、絵画の中の「描かれた窓」(解説より)の中に取り入れられた風景。いわゆる後景と言っても良いでしょう。宗教画でも多く描かれるようになります。

左:南ネーデルラントの画家「東方三博士の礼拝」 1520年頃 油彩・板
南ネーデルラントの画家の「東方三博士の礼拝」です。中央の青、ないし深緑色の服を着て座るのが聖母マリア。両手には幼子のイエスを抱きかかえています。そしてマリアと向き合い、イエスを見やるのが三博士。恭しく贈り物を差し出そうとしています。ほか着飾った多くの人物たちも描かれています。ともすると風景にはあまり目が向かないかもしれません。
ただ確かに中央の奥には山や家などの風景が描かれています。そして右最上段、アーチ状の建造物に立つ二人の人物に注目です。分かりにくいかもしれませんが、描かれているのは後ろ姿のみ。ほかの人物がほぼマリアやイエスを見ているのに対し、まるで反対側を向いています。とすれば何を見ているのでしょうか。結論から言えば後ろに広がる風景を見渡しているのです。

右:ヨアヒム・パティニール「聖カタリナの車輪の奇跡」 1515年以前 油彩・板
美術史上、初めて「風景画家」と呼ばれた人物がいます。ヨハヒム・パティニールです。かのデューラーが「良き風景画家」と讃えました。「聖カタリナの車輪の奇跡」では確かにカタリナの伝説を描いていますが、主役はもはや広大なる風景と言っても良いかもしれません。高い位置から岩山を俯瞰し、城館を見据え、海を望んでいます。
うっすらと帯びた後景の青。色彩遠近法です。前景に暖色、後ろに寒色を配しては奥行き感を巧みに作り上げています。ただここではカタリナの奇跡の様子もドラマテックで面白いもの。中景の左で燃え上がるのが哲学者らを殺害した薪の山。一方、右手中段、燃え上がる車輪の前で跪き、祈りを捧げているのがカタリナです。ともに描写は細かい。剣を持ち、ひっくり返っている男たちも真に迫っています。

ヒエロニムス・ボスの模倣者「楽園図」 1540~50年後頃 油彩・板
僅か縦25センチほどの小さな画面ながらも実に緻密です。「楽園図」です。画家はおそらくはボスの模倣者。風景というよりも奇景。摩訶不思議な植物や生き物が現れます。ボスが描き、現在はプラド美術館にある「快楽の園」に倣ったと考えられているそうです。
一つのハイライトとも言えるのではないでしょうか。月暦画です。画家の名はレアンドロ・バッサーノ。1年12ヶ月の生活、季節毎に変わりゆく人々の生活や労働の様子を表現。自然の風景とともに、天体の進行、星座とあわせて、一つのスペクタクルとも言うべき絵画世界を展開しています。

レアンドロ・バッサーノ「月暦画」連作 展示風景
ウィーン美術史美術館にはうち9月、10月、12月意外の9枚を所蔵。その全てが一部屋をぐるりと囲むように展示されています。(9、10はプラハに所蔵。12月は行方不明になっているそうです。)

右:レアンドロ・バッサーノ「8月」 1585年 油彩・キャンヴァス
あえて一枚挙げるとするならば「8月」。人々が一生懸命に樽を作っていますが、もちろんこれはこの後に収穫されるぶどう、すなわちワインを貯蔵するためのもの。また奥では羊の毛を刈り込んでいます。そして空を眺めれば乙女座を表す女性のシンボル。ユニコーンの姿も見えました。

右:ダーフィット・テニールス(父)「メルクリウスとアルゴス、イオ」 1638年 油彩・銅板
それにしても本展、ともかく風景画の誕生から成立に至るまでの前半部が充実しています。ほかヤン・ブリューゲル父子、ドッソ・ドッシ、ダーフィット・テニールス父、ファルケンボルフなどに目を引く作品が多い。いずれもウィーン美術史美術館のコレクションです。フランドル、オランダなどの北方絵画に定評のある同美術館ならでは展示と言えそうです。
さて後半は風景画の展開です。17世紀になると風景は物語の舞台ではなく、独立した主題として描かれるようになりました。

右:アールト・ファン・デル・ネール「月明かりの下の船のある川の風景」 1665~70年頃 油彩・キャンヴァス
アールト・ファン・デル・ネールの「月明かりの下の船のある川の風景」はどうでしょうか。水辺の風景、たくさんの帆船が浮かび、漁をする小舟の姿も見えます。左には廃墟、右は木立に館。画面の大半を占めるのが空です。明るい満月。まるで夕景の如く空をピンク色に染めています。一方で水面や背景は青白い。独特の詩情をたたえてもいます。

左:ヤーコブ・ファン・ロイスダール「渓流のある風景」 1670~80年頃 油彩・板で裏打ちされたキャンヴァス
日本でもお馴染みの風景画家も登場します。例えばロイスダールです。名は「渓流のある風景」。かなり激しい水の流れ落ちる川を捉えた一枚。岩場には木が横倒しになり、洪水の後のようにも見えます。そして小屋の前にいる小さな人影。荒々しい土地です。背後には雄大な山も垣間見えます。自然の厳しい姿を表現しています。

右:カナレット「ヴェネツィアのスキアヴォーニ河岸」 1730年頃 油彩・キャンヴァス
ラストはイタリアの風景、カナレットです。「ヴェネツィアのスキアヴォーニ河岸」。広く、うっすら桃色を帯びた雲の下に広がるヴェネツィアの町。パノラマです。右手に建物が連なり、行く手にはサン・マルコ広場の鐘楼も見えます。左は岸。大小様々な船がたくさん浮かんでいます。線に色に緻密な表現。いわゆる都市景観図です。特にイタリアを訪れたイギリスの人々に人気を集めました。
出品は全70点。ウィーン美術史美術館のコレクションで辿る風景画の歴史。テーマは明快です。思いの外に読ませる展示でもありました。
9月25日(金)より金・土曜の夜間開館時のみに利用出来る新たなタブレットガイド貸出サービスが始まりました。
「スペシャルコンテンツ収録のタブレットガイドが登場!」(Bunkamura ザ・ミュージアム)
タブレットには美術ジャーナリスト藤原えりみさんの見どころ解説のほか、石井ゆかりさんの「星座メッセージ」、また福岡伸一さんや原田マハさんによるエッセイ、さらにはリアルタイムで参加可能な作品ランキングなどのコンテンツを搭載。専門的な内容からエンターテイメントまでと盛りだくさんです。タブレットを操作することで、様々な角度から展覧会を楽しむことが出来ます。

「風景画の誕生 ウィーン美術史美術館所蔵」展タブレットガイド
タブレットガイドの貸出は上記にもあるように9月25日(金)以降、展覧会終了までの毎週金、土曜の夜間開館時(19時~21時)のみ。貸出台数は50台。利用料金は通常の音声ガイドと同じく520円です。(受付で通常のガイドかタブレットのどちらかを選ぶことが出来ます。)
最後に学生のみなさんにお得な情報です。10月5日(月)は「キヤノン・ミュージアム・キャンパス」のため無料で入館出来ます。
[特別プログラム キヤノン・ミュージアム・キャンパス]
日時:10月5日(月) 10:00~17:00(最終入場16:30)
会場:Bunkamuraザ・ミュージアム
対象:大学生(大学院生、短期大学生、専門学校生、高等専門学校の4・5年生を含む)
申込み:不要
料金:無料
当日は休館日。学生のみを対象とした無料観覧日です。つまり学生のみの貸し切りイベントです。平日の月曜ではありますが、これを機会にBunkamuraまで出かけてみては如何でしょうか。

12月7日まで開催されています。
「風景画の誕生 ウィーン美術史美術館所蔵」 Bunkamura ザ・ミュージアム(@Bunkamura_info)
会期:9月9日(水)~12月7日(月)
休館:10月5日(月)。
時間:10:00~19:00。
*毎週金・土は21:00まで開館。入館は閉館の30分前まで。
料金:一般1500(1300)円、大学・高校生1000(800)円、中学・小学生700(500)円。
*( )内は20名以上の団体料金。要事前予約。
住所:渋谷区道玄坂2-24-1
交通:JR線渋谷駅ハチ公口より徒歩7分。東急東横線・東京メトロ銀座線・京王井の頭線渋谷駅より徒歩7分。東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線・東京メトロ副都心線渋谷駅3a出口より徒歩5分。
注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。作品は全てウィーン美術史美術館所蔵。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )









