カート・ヴォネガット『タイタンの妖女』(ハヤカワ文庫SF、浅倉久志訳)
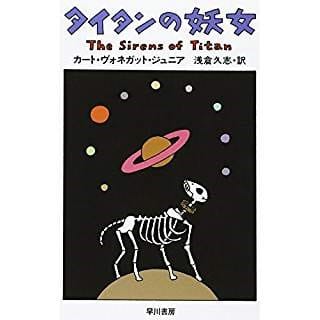
時空を超えたあらゆる時と場所に波動現象として存在する、ウィンストン・ナイルズ・ラムファードは、神のような力を使って、さまざまな計画を実行し、人類を導いていた。その計画で操られる最大の受難者が、全米一の大富豪マラカイ・コンスタントだった。富も記憶も奪われ、地球から火星、水星へと太陽系を流浪させられるコンスタントの行く末と、人類の究極の運命とは?巨匠がシニカルかつユーモラスに描いた感動作。(「BOOK」データベースより)
◎『タイタンの妖女』は不発でしたが
カート・ヴォネガットは、発表年次の順番に読んできました。いずれもハヤカワ文庫SFです。『プレイヤー・ピアノ』(1952)『タイタンの妖女』(1959)『猫のゆりかご』(1963)『チャンピオンたちの朝食』(1973)『ホーカス・ポーカス』(1990)……。
翻訳もののSFは、アイザック・アシモフ、コニー・ウィリス、ロバート・A・ハイライン、フィリップ・K・ディック、シオドア・スタージョン、カート・ヴォネカットを中心に読んでいます。間口がせまいものですから、偉そうに語る資格はないと思っています。ただし読んでおもしろかった作品は、紹介しないではいられません。
カート・ヴォネガットは1976年まで、カート・ヴォネガット・ジュニアという名前で著作を書いています。したがって「ジュニア」がとれた作品は、まだ1冊しか読んでいないことになります。
ヴォネガットは1922年アメリカに生まれ、2007年に亡くなっています。第2次大戦のときは徴兵され、ドイツ軍の捕虜になっています。そしてドレスデンで連合軍の無差別爆撃を体験しています。この体験はその後の作品に、大きな影響をあたえます。。
カート・ヴォネガットについて、紹介された2つの文章を引用させていただきます。
――人間というのは、じつに不完全で愚かな生き物だけれど、それは仕方がないんだ。何かを盲目的に信じるのではなく、つねに疑いながら、笑いながら生きていこうよ。彼の作品からはいつもそんなメッセージが伝わってくる。だから、我々は彼の作品を何よりも愛したし、これからも愛し続けるだろう。(渡辺英樹、『SFマガジン』2012年9月号より)
――ヴォネガットが、宇宙規模のしかも科学的なものを配慮にいれた態度で、この世界全体を考え、そこにひとりの人間として生きていることはどういうことかを、もっとも今日的に反省している作家であり、かれが厖大な数のアメリカの、またソヴィエトにもひろがりうる、若い知識人たちの自己表現のかわりをなしている、ということに注目したいのであります。(大江健三郎『言葉によって・状況。文学』新潮社より)
大江健三郎の文章は、ちょっとまわりくどくてわかりにくいかもしれません。大江は現在の生きざまを反省し、それを宇宙規模で描く技術をもっているのはヴォネガットだけである、と評価しています
デビュ作の『プレイヤー・ピアノ』は、テクノロジーの進歩を皮肉った作品ですが、かんばしい評価をえられませんでした。今回とりあげる『タイタンの妖女』も同じような評価でした。ヴォネガット作品が話題になったのは、『猫のゆりかご』からです。謎の宗教ボコノン教を描いた風刺に満ちた作品は、アメリカの若者から高い評価をうけました。
Kindle版『タイタンの妖女』のあとがきに、オールディス『十億年の宴・SFその起源と歴史』の紹介がありました。本書は古書店でも入手できないので、引用させていただきます。『タイタンの妖女』はつぎのように評価されています。
――純粋なヴォネガット流の悦楽は、初期の長篇『タイタンの妖女』(1959年)と、ボコノン教という優雅な新興宗教を作り出した『猫のゆりかご』(1963年)の中に見出される。とくに『タイタンの妖女』は、奇想天外なアイディアの奔流であり、あっちこっちへ跳び移るその技法は、ワイドスクリーン・バロック派の洗練された応用である。込み入ったプロットは、例外的に陽気なディックの小説を思わせる。(Kindle版『タイタンの妖女』あとがきより)
ヴォネガット崇拝者である栗本慎一郎は、著作のなかでトニー・タナー『言語の都市―現代アメリカ小説』(白水社)をこきおろしています。ヴォネガットを過小評価しており、誤った偏見を糾弾しています。本書は古書店でも発見できません。
――ヴォネガットが博愛的無政府主義者に近いとか、その調子があからさまな感傷に陥る傾向があるとか、いったいタナーは一冊でもヴォネガットを読んでいるのかと憤慨すら感じる。(栗本慎一郎『反文学論』光文社文庫より)
◎火星、水星そして土星へ
主人公のマラカイ・コンスタントは、アメリカの大富豪です。ある日彼はラムフォード邸に招かれます。そこには主人である、ウィンストン・ナイルス・ラムフォードはおりません。
ラムフォードは宇宙探検家でした。彼は愛犬のカザックとともに、「時間等曲率漏斗」へはいりこんでしまっているのです。ラムフォードと愛犬はそのなかに存在しています。地球のような惑星がそこを横切ると、一時的にその惑星で実体化します。コンスタントが招かれたのは、実体化する日だったのです。
コンスタンは実体化したラムフォードから、奇妙な予言をあたえられます。ラムフォードの妻ビアトリスとともに火星に行き、2人は結ばれてクロノという息子が生まれるというのです。その後は水星と地球を経て、土星のタイタンにたどりつくと告げられます。
事態は予言どおりに進行します。コンスタンのところに、火星から迎えがくるのです。(ここまでの文章は『現代作家ガイド6・カート・ヴォネガット』彩流社を参考にさせてもらいました)
舞台は火星へととびます。ここにはたくさんの地球からの入植者がいます。すべての記憶を消されたアンクという中年兵がいます。彼は命令により、親友を絞め殺してしまいます。もちろん対象がだれかをわからないままにです。息絶えるまえに、親友は秘密の手紙について語ります。秘密の手紙の中味についてはふれません。最後にタイタンへととびます。そこにはトラルファマドール星人サロがいました。
森毅は「ぼくのSFベスト3」の1冊として、『タイタンの妖女』をあげています。ほかの2冊はバラード『沈んだ世界』(創元SF文庫)とカルヴィーノ『レ・コスミコミケ』(ハヤカワepi文庫)です。そしてつぎのように書いています。
――ヴォネガットというのはふしぎな作家で、村上春樹の、とくに初期の作品にはヴォネガットの影響が強い。彼の初期作品には、たとえば最後に「それもいいさ」というセリフがしょっちゅう出てくるんですが、あれはヴォネガットのスタイルです。たぶんヴォネガットの影響だと思います。(森毅『ゆきあたりばったり文学談義』ハルキ文庫P149より)
森毅の推測はあたっています。小林信彦は著作のなかで、おなじセリフに着目しています。
――トラファマドール星人は人間の死について醒めた見方をしており、それはドレスデン爆撃についての〈ヒューマニスティックな怒り〉さえ相対化させるものだ。そこから導き出されるのは、作中で、しつこく繰りかえされる「そういうものだ」(So it goes.)という呟きであり、諦念である。(小林信彦『小説世界のロビンソン』新潮文庫P294より)
私にとってヴォネガット作品の魅力は、ミステリーツアのように見知らぬ世界へつれていってくれる点です。稀有壮大な世界のなかで、最初のうちはとまどってしまいます。そのうちに登場人物と同化している自分を発見します。細かな科学的なことはよくわかりませんが、気がつくと別の宇宙に立っている自分がいます。ヴォネガット作品を読んでいると、ひんぱんに1眼レフのシャッター音が、きこえているような感覚になります。
そしていつも、いい旅に感謝をささげています。
(山本藤光:2012.07.05初稿、2018.03.07改稿)
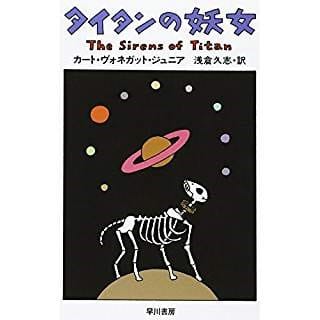
時空を超えたあらゆる時と場所に波動現象として存在する、ウィンストン・ナイルズ・ラムファードは、神のような力を使って、さまざまな計画を実行し、人類を導いていた。その計画で操られる最大の受難者が、全米一の大富豪マラカイ・コンスタントだった。富も記憶も奪われ、地球から火星、水星へと太陽系を流浪させられるコンスタントの行く末と、人類の究極の運命とは?巨匠がシニカルかつユーモラスに描いた感動作。(「BOOK」データベースより)
◎『タイタンの妖女』は不発でしたが
カート・ヴォネガットは、発表年次の順番に読んできました。いずれもハヤカワ文庫SFです。『プレイヤー・ピアノ』(1952)『タイタンの妖女』(1959)『猫のゆりかご』(1963)『チャンピオンたちの朝食』(1973)『ホーカス・ポーカス』(1990)……。
翻訳もののSFは、アイザック・アシモフ、コニー・ウィリス、ロバート・A・ハイライン、フィリップ・K・ディック、シオドア・スタージョン、カート・ヴォネカットを中心に読んでいます。間口がせまいものですから、偉そうに語る資格はないと思っています。ただし読んでおもしろかった作品は、紹介しないではいられません。
カート・ヴォネガットは1976年まで、カート・ヴォネガット・ジュニアという名前で著作を書いています。したがって「ジュニア」がとれた作品は、まだ1冊しか読んでいないことになります。
ヴォネガットは1922年アメリカに生まれ、2007年に亡くなっています。第2次大戦のときは徴兵され、ドイツ軍の捕虜になっています。そしてドレスデンで連合軍の無差別爆撃を体験しています。この体験はその後の作品に、大きな影響をあたえます。。
カート・ヴォネガットについて、紹介された2つの文章を引用させていただきます。
――人間というのは、じつに不完全で愚かな生き物だけれど、それは仕方がないんだ。何かを盲目的に信じるのではなく、つねに疑いながら、笑いながら生きていこうよ。彼の作品からはいつもそんなメッセージが伝わってくる。だから、我々は彼の作品を何よりも愛したし、これからも愛し続けるだろう。(渡辺英樹、『SFマガジン』2012年9月号より)
――ヴォネガットが、宇宙規模のしかも科学的なものを配慮にいれた態度で、この世界全体を考え、そこにひとりの人間として生きていることはどういうことかを、もっとも今日的に反省している作家であり、かれが厖大な数のアメリカの、またソヴィエトにもひろがりうる、若い知識人たちの自己表現のかわりをなしている、ということに注目したいのであります。(大江健三郎『言葉によって・状況。文学』新潮社より)
大江健三郎の文章は、ちょっとまわりくどくてわかりにくいかもしれません。大江は現在の生きざまを反省し、それを宇宙規模で描く技術をもっているのはヴォネガットだけである、と評価しています
デビュ作の『プレイヤー・ピアノ』は、テクノロジーの進歩を皮肉った作品ですが、かんばしい評価をえられませんでした。今回とりあげる『タイタンの妖女』も同じような評価でした。ヴォネガット作品が話題になったのは、『猫のゆりかご』からです。謎の宗教ボコノン教を描いた風刺に満ちた作品は、アメリカの若者から高い評価をうけました。
Kindle版『タイタンの妖女』のあとがきに、オールディス『十億年の宴・SFその起源と歴史』の紹介がありました。本書は古書店でも入手できないので、引用させていただきます。『タイタンの妖女』はつぎのように評価されています。
――純粋なヴォネガット流の悦楽は、初期の長篇『タイタンの妖女』(1959年)と、ボコノン教という優雅な新興宗教を作り出した『猫のゆりかご』(1963年)の中に見出される。とくに『タイタンの妖女』は、奇想天外なアイディアの奔流であり、あっちこっちへ跳び移るその技法は、ワイドスクリーン・バロック派の洗練された応用である。込み入ったプロットは、例外的に陽気なディックの小説を思わせる。(Kindle版『タイタンの妖女』あとがきより)
ヴォネガット崇拝者である栗本慎一郎は、著作のなかでトニー・タナー『言語の都市―現代アメリカ小説』(白水社)をこきおろしています。ヴォネガットを過小評価しており、誤った偏見を糾弾しています。本書は古書店でも発見できません。
――ヴォネガットが博愛的無政府主義者に近いとか、その調子があからさまな感傷に陥る傾向があるとか、いったいタナーは一冊でもヴォネガットを読んでいるのかと憤慨すら感じる。(栗本慎一郎『反文学論』光文社文庫より)
◎火星、水星そして土星へ
主人公のマラカイ・コンスタントは、アメリカの大富豪です。ある日彼はラムフォード邸に招かれます。そこには主人である、ウィンストン・ナイルス・ラムフォードはおりません。
ラムフォードは宇宙探検家でした。彼は愛犬のカザックとともに、「時間等曲率漏斗」へはいりこんでしまっているのです。ラムフォードと愛犬はそのなかに存在しています。地球のような惑星がそこを横切ると、一時的にその惑星で実体化します。コンスタントが招かれたのは、実体化する日だったのです。
コンスタンは実体化したラムフォードから、奇妙な予言をあたえられます。ラムフォードの妻ビアトリスとともに火星に行き、2人は結ばれてクロノという息子が生まれるというのです。その後は水星と地球を経て、土星のタイタンにたどりつくと告げられます。
事態は予言どおりに進行します。コンスタンのところに、火星から迎えがくるのです。(ここまでの文章は『現代作家ガイド6・カート・ヴォネガット』彩流社を参考にさせてもらいました)
舞台は火星へととびます。ここにはたくさんの地球からの入植者がいます。すべての記憶を消されたアンクという中年兵がいます。彼は命令により、親友を絞め殺してしまいます。もちろん対象がだれかをわからないままにです。息絶えるまえに、親友は秘密の手紙について語ります。秘密の手紙の中味についてはふれません。最後にタイタンへととびます。そこにはトラルファマドール星人サロがいました。
森毅は「ぼくのSFベスト3」の1冊として、『タイタンの妖女』をあげています。ほかの2冊はバラード『沈んだ世界』(創元SF文庫)とカルヴィーノ『レ・コスミコミケ』(ハヤカワepi文庫)です。そしてつぎのように書いています。
――ヴォネガットというのはふしぎな作家で、村上春樹の、とくに初期の作品にはヴォネガットの影響が強い。彼の初期作品には、たとえば最後に「それもいいさ」というセリフがしょっちゅう出てくるんですが、あれはヴォネガットのスタイルです。たぶんヴォネガットの影響だと思います。(森毅『ゆきあたりばったり文学談義』ハルキ文庫P149より)
森毅の推測はあたっています。小林信彦は著作のなかで、おなじセリフに着目しています。
――トラファマドール星人は人間の死について醒めた見方をしており、それはドレスデン爆撃についての〈ヒューマニスティックな怒り〉さえ相対化させるものだ。そこから導き出されるのは、作中で、しつこく繰りかえされる「そういうものだ」(So it goes.)という呟きであり、諦念である。(小林信彦『小説世界のロビンソン』新潮文庫P294より)
私にとってヴォネガット作品の魅力は、ミステリーツアのように見知らぬ世界へつれていってくれる点です。稀有壮大な世界のなかで、最初のうちはとまどってしまいます。そのうちに登場人物と同化している自分を発見します。細かな科学的なことはよくわかりませんが、気がつくと別の宇宙に立っている自分がいます。ヴォネガット作品を読んでいると、ひんぱんに1眼レフのシャッター音が、きこえているような感覚になります。
そしていつも、いい旅に感謝をささげています。
(山本藤光:2012.07.05初稿、2018.03.07改稿)





















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます