城山三郎『部長の大晩年』(新潮文庫)
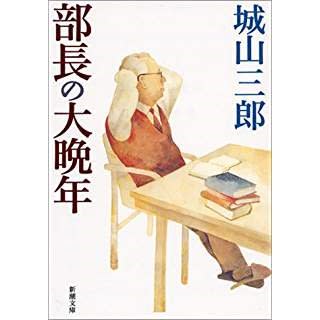
彼の人生は、定年からが本番だった。三菱製紙高砂工場では、ナンバー3の部長にまでなり、会社員としても一応の出世をした永田耕衣。しかし、俳人である永田には、会社勤めは「つまらん仕事」でしかない。55歳で定年を迎えた永田は、人生の熱意を俳句や書にたっぷり注いで行く。異端の俳人の人生を、その97歳の大往生まで辿りながら、晩年をいかにして生きるかを描いた人物評伝の傑作。(「BOOK」データベースより)
◎俳人・永田耕衣の晩年に限った伝記
最初に、城山三郎『部長の大晩年』(新潮文庫)のモデルである、俳人・永田耕衣の句のいくつかを引いておきます。
夢の世に葱を作りて寂しさよ
朝顔や百たび訪はば母死なむ
後ろにも髪脱け落つる山河かな
泥鰌浮いて鯰も居るというて沈む
死螢に照らしをかける螢かな
かたつむりつるめば肉の食い入るや
少年や六十年後の春の如し
白梅や天没地没虚空没
永田耕衣の持論を紹介している文章があります。引用させていただきます。
――耕衣の持論は「俳句の面白さの核心は人生的であるべきや」「思いどおりにならん人生やからこそ、人間の詩をつくり、歌を詠ませるんや」だった。(安原顕『だからどうした本の虫』双葉社)
城山三郎『部長の大晩年』(新潮文庫)は、タイトルに惹かれて読みました。そして装画の井筒啓之に魅せられました。残念ながら文庫にはありません。本書は俳人・永田耕衣の、晩年に限った伝記です。私はその人を知りません。しかし、それでも思わず読みたくなったほど、魅力あふれる表情の単行本だったのです。
永田耕衣は三菱製紙高砂工場で、製造部長兼研究部長として55歳で定年を迎えます。定年後は現役時代からたしなんでいた俳句や、書三昧の人生を送ります。その耕衣について筆者は、「読売新聞」(1998年9月5日)のインタビューで次のように語っています。
――会社という公の世界と、俳句という私の世界をしゅん別し、どちらも全力疾走した。だからこそ定年で会社という器がなくなっても、たじろがなかったのでしょう。
人生は「生徒・学生期」「会社・家族期」「老年期」の3層構造になっています。長い長い「老年期」を充実したものにするためには、「会社・家族期」をいかに過ごすかにかかっています。本書の主人公は、みごとに第3期に突入したのです。
◎永田耕衣の人柄
サラリーマンなら、誰にでも訪れる定年というゴール。永田耕衣の場合は、そこからの40年余を美しく完全燃焼し,97歳で大往生をとげています。
耕衣の人柄が、顕著に見える個所を抜粋してみます。第1は定年を迎えたとき。部下たちが送別会を企画します。
――「御免こうむる。そんなもん好かん。せんでええ」「でも、これはしきたりということで……」「アホなことを。わしはしきたりで生きとるんやないで」(本文より)
部下たちが困り顔になると、耕衣はひとつの提案をします。みんなで倉敷の大原美術館へ行こうというのです。世の中で一番大切なのは、本物をみることだといい添えます。
第2は還暦祝いにと息子、娘夫婦が神戸の中華料理屋に招いてくれたときのことです。彼は喜んで「実にうまい」といってよく食べました。ところが主宰する誌上にはこう書いてしまいます。
――元来貧乏性の私は、その翌朝いつもの習慣の豆腐の味噌汁と、その一椀の後の目刺し一ぴきで、何ともいえぬ天上の舌楽を満喫せしめられたのであった。(本文より)
第3は耕衣が阪神大震災に、遭遇したときのことです。家は全壊し、彼はトイルに閉じ込められます。そのときのことを、耕衣はこう述懐しています。
――潰れた家の中で銅器をカンカラカンと鳴らしたとき、自分で自分を茶化す気分になり、「踊りの一つでも踊ってやろうかという気さえ起こらないわけではなかった」(本文より)
城山三郎が『毎日が日曜日』(新潮文庫)を書いたのは、この作品の20年前になります。晩年はひたむきな人生を貫いた人の、伝記を書き続けていました。人間の数だけ人生がある、といったのは誰だったでしょうか。ただし定年後の人生となると、なんとなく紋切り型のような気がしていました。
ちなみに「毎日が日曜日」という言葉は、城山三郎の小説から生まれたと信じています。違っていたら教えてください。もっと早くからあった、いいまわしだったのでしょうか。
◎定年後の心構え
本書はそんな私に、一石を投じてくれました。仕事という車輪を失い、安定走行が崩れるケースは多々あります。「趣味」というそれを補って余りある、車輪を持っていることの大切さ。本書はそうしたことを教えてくれました。城山三郎は最後に、こう書いています。
――もし耕衣が墓の中から自作の句を詠み上げるとすれば、さて、どの句であろうか。「茄子や皆事の終るは寂しけれ」か、それとも、「放せ俺(わい)は昔の夕日だというて沈む」なのか。(本文より)
私は後者だと確信しています。「永田耕衣句集」は何冊か出版されています。私は『永田耕衣・秋元不死男・平畑静塔集』(朝日文庫)を買い求めました。
◎城山三郎のこと
城山三郎を戦争文学の範ちゅうに、くくっている分類があります。現に『城山三郎昭和の戦争文学』(全6巻、角川書店)という全集が出ているほどです。しかし城山三郎は、経済小説の先達であることを忘れてはいけません。
――城山はもともと経済小説という新分野を開拓した作家である。商社員の海外における苛酷な商戦を描いた彼のデビュー作『輸出』が、発表された昭和32年の時点でどんなに新鮮にみえたかは、これが純文学作家の登竜門である文学界新人賞を受賞したことからも察せられるだろう。(百目鬼恭三郎『現代の作家一〇一人』新潮社)
デビュー作『輸出』は、『経済小説名作選』(集英社文庫)で読むことができます。本書の巻末に、城山三郎と山田智彦の対談があります。 その部分を拾って、佐高信は著作の中で、次のように書いています。
――組織はその存続のために大義を振りかざし、個人の思いなどをはじきとばしていく。少年の日に国家という組織を信じて、手ひどいヤケドを負った城山は、つねに組織を疑い、大義に疑問を突きつけて、小説を書いてきた。その城山に、デビューしたころ、「この人は組織というものを軽信している」と見当違いの批評を投げつけた者がいた。「ぼくは過信ならいいと思ったけど、軽信って言われたから、ちょっと腹が立った。(佐高信『城山三郎の昭和』角川文庫P235-236)
紹介するスペースがなくなりました。城山三郎をもっと知りたい方には、娘さんが書いた2冊をお薦めします。
井上紀子『父でもなく、城山三郎でもなく』(新潮文庫)
井上紀子『城山三郎が娘に語った戦争』(朝日文庫)
(山本藤光:1998.09.14初稿、2018.03.13改稿)
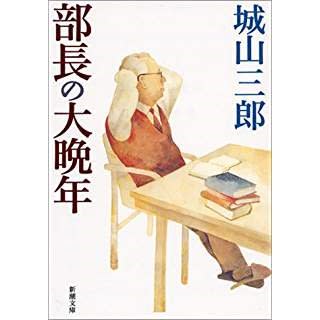
彼の人生は、定年からが本番だった。三菱製紙高砂工場では、ナンバー3の部長にまでなり、会社員としても一応の出世をした永田耕衣。しかし、俳人である永田には、会社勤めは「つまらん仕事」でしかない。55歳で定年を迎えた永田は、人生の熱意を俳句や書にたっぷり注いで行く。異端の俳人の人生を、その97歳の大往生まで辿りながら、晩年をいかにして生きるかを描いた人物評伝の傑作。(「BOOK」データベースより)
◎俳人・永田耕衣の晩年に限った伝記
最初に、城山三郎『部長の大晩年』(新潮文庫)のモデルである、俳人・永田耕衣の句のいくつかを引いておきます。
夢の世に葱を作りて寂しさよ
朝顔や百たび訪はば母死なむ
後ろにも髪脱け落つる山河かな
泥鰌浮いて鯰も居るというて沈む
死螢に照らしをかける螢かな
かたつむりつるめば肉の食い入るや
少年や六十年後の春の如し
白梅や天没地没虚空没
永田耕衣の持論を紹介している文章があります。引用させていただきます。
――耕衣の持論は「俳句の面白さの核心は人生的であるべきや」「思いどおりにならん人生やからこそ、人間の詩をつくり、歌を詠ませるんや」だった。(安原顕『だからどうした本の虫』双葉社)
城山三郎『部長の大晩年』(新潮文庫)は、タイトルに惹かれて読みました。そして装画の井筒啓之に魅せられました。残念ながら文庫にはありません。本書は俳人・永田耕衣の、晩年に限った伝記です。私はその人を知りません。しかし、それでも思わず読みたくなったほど、魅力あふれる表情の単行本だったのです。
永田耕衣は三菱製紙高砂工場で、製造部長兼研究部長として55歳で定年を迎えます。定年後は現役時代からたしなんでいた俳句や、書三昧の人生を送ります。その耕衣について筆者は、「読売新聞」(1998年9月5日)のインタビューで次のように語っています。
――会社という公の世界と、俳句という私の世界をしゅん別し、どちらも全力疾走した。だからこそ定年で会社という器がなくなっても、たじろがなかったのでしょう。
人生は「生徒・学生期」「会社・家族期」「老年期」の3層構造になっています。長い長い「老年期」を充実したものにするためには、「会社・家族期」をいかに過ごすかにかかっています。本書の主人公は、みごとに第3期に突入したのです。
◎永田耕衣の人柄
サラリーマンなら、誰にでも訪れる定年というゴール。永田耕衣の場合は、そこからの40年余を美しく完全燃焼し,97歳で大往生をとげています。
耕衣の人柄が、顕著に見える個所を抜粋してみます。第1は定年を迎えたとき。部下たちが送別会を企画します。
――「御免こうむる。そんなもん好かん。せんでええ」「でも、これはしきたりということで……」「アホなことを。わしはしきたりで生きとるんやないで」(本文より)
部下たちが困り顔になると、耕衣はひとつの提案をします。みんなで倉敷の大原美術館へ行こうというのです。世の中で一番大切なのは、本物をみることだといい添えます。
第2は還暦祝いにと息子、娘夫婦が神戸の中華料理屋に招いてくれたときのことです。彼は喜んで「実にうまい」といってよく食べました。ところが主宰する誌上にはこう書いてしまいます。
――元来貧乏性の私は、その翌朝いつもの習慣の豆腐の味噌汁と、その一椀の後の目刺し一ぴきで、何ともいえぬ天上の舌楽を満喫せしめられたのであった。(本文より)
第3は耕衣が阪神大震災に、遭遇したときのことです。家は全壊し、彼はトイルに閉じ込められます。そのときのことを、耕衣はこう述懐しています。
――潰れた家の中で銅器をカンカラカンと鳴らしたとき、自分で自分を茶化す気分になり、「踊りの一つでも踊ってやろうかという気さえ起こらないわけではなかった」(本文より)
城山三郎が『毎日が日曜日』(新潮文庫)を書いたのは、この作品の20年前になります。晩年はひたむきな人生を貫いた人の、伝記を書き続けていました。人間の数だけ人生がある、といったのは誰だったでしょうか。ただし定年後の人生となると、なんとなく紋切り型のような気がしていました。
ちなみに「毎日が日曜日」という言葉は、城山三郎の小説から生まれたと信じています。違っていたら教えてください。もっと早くからあった、いいまわしだったのでしょうか。
◎定年後の心構え
本書はそんな私に、一石を投じてくれました。仕事という車輪を失い、安定走行が崩れるケースは多々あります。「趣味」というそれを補って余りある、車輪を持っていることの大切さ。本書はそうしたことを教えてくれました。城山三郎は最後に、こう書いています。
――もし耕衣が墓の中から自作の句を詠み上げるとすれば、さて、どの句であろうか。「茄子や皆事の終るは寂しけれ」か、それとも、「放せ俺(わい)は昔の夕日だというて沈む」なのか。(本文より)
私は後者だと確信しています。「永田耕衣句集」は何冊か出版されています。私は『永田耕衣・秋元不死男・平畑静塔集』(朝日文庫)を買い求めました。
◎城山三郎のこと
城山三郎を戦争文学の範ちゅうに、くくっている分類があります。現に『城山三郎昭和の戦争文学』(全6巻、角川書店)という全集が出ているほどです。しかし城山三郎は、経済小説の先達であることを忘れてはいけません。
――城山はもともと経済小説という新分野を開拓した作家である。商社員の海外における苛酷な商戦を描いた彼のデビュー作『輸出』が、発表された昭和32年の時点でどんなに新鮮にみえたかは、これが純文学作家の登竜門である文学界新人賞を受賞したことからも察せられるだろう。(百目鬼恭三郎『現代の作家一〇一人』新潮社)
デビュー作『輸出』は、『経済小説名作選』(集英社文庫)で読むことができます。本書の巻末に、城山三郎と山田智彦の対談があります。 その部分を拾って、佐高信は著作の中で、次のように書いています。
――組織はその存続のために大義を振りかざし、個人の思いなどをはじきとばしていく。少年の日に国家という組織を信じて、手ひどいヤケドを負った城山は、つねに組織を疑い、大義に疑問を突きつけて、小説を書いてきた。その城山に、デビューしたころ、「この人は組織というものを軽信している」と見当違いの批評を投げつけた者がいた。「ぼくは過信ならいいと思ったけど、軽信って言われたから、ちょっと腹が立った。(佐高信『城山三郎の昭和』角川文庫P235-236)
紹介するスペースがなくなりました。城山三郎をもっと知りたい方には、娘さんが書いた2冊をお薦めします。
井上紀子『父でもなく、城山三郎でもなく』(新潮文庫)
井上紀子『城山三郎が娘に語った戦争』(朝日文庫)
(山本藤光:1998.09.14初稿、2018.03.13改稿)





















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます