東野圭吾『秘密』(文春文庫)その2
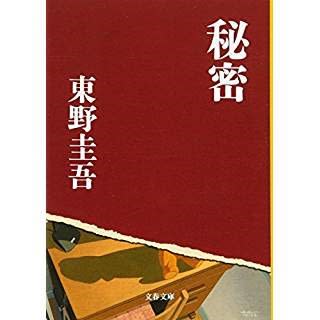
6.在るべきところへの執着
東野圭吾は「居所」に、とことんこだわります。それは幼いころの境遇と、無縁ではないでしょう。東野には2人の姉がいて、部屋は共同でした。その後、生家は何度も増改築を重ねます。小学校の途中から、姉たちが隣室である和室へと移りました。しかし東野の部屋は、姉たちを越えて階下へと降りる通路でもありました。上の姉が家を出ます。今度は下の姉との共同部屋となりました。
結局、東野は家をでるまで、のんびりと1人部屋で過ごす機会には恵まれませんでした。1浪後に大阪府立大学電気工学科へ入学します。トイレと炊事場が共用の、安アパートに暮すことになります。念願の1人暮しを満喫するには、ほど遠い環境であったわけです。
大学卒業後は、愛知県の自動車部品メーカーの独身寮へはいります。ここでも3DKを3人で分割する、共同生活を余儀なくされました。25歳で結婚。棟続きの社宅へと移りました。東野はいいます。
――みんな自分のいちばん落ち着く場所を探しているんでしょうけど、僕自身は大阪のゴミゴミした商店街の、自然も緑もないところで生まれ育っていますから。街の中にいるのが楽なんですよ」( 「週刊文春」1999年8月5日号「家の履歴書」より)
「居所」へのこだわりは、『秘密』のなかにも登場します。つぎに引用するのは、妻の直子のセリフです。直子が示す家への執着はすさまじいものです。これは東野自身の叫びともいえるでしょう。
――とにかくね、今買わなきゃ。今買わないと、平ちゃん、永遠に家なんて買えない気がする。永久に借家住まいだよ。そんなのいやでしょ? 自分の家、ほしいでしょ? 欲しかったら買おうよ。すぐ買おうよ」(本文より)
杉田平介のマイホームは、三鷹駅からバスで数分のところにあります。直子にスピッツがほえるように、きゃんきゃんいわれて買った中古住宅です。平介も十分に満足しています。マイホームを象徴する、こんな場面があります。
――平介がこの家を気に入った第一の理由も、この広い浴室だったといってもいい。(本文より)
東野圭吾は、ていねいに家の間取りを描きます。これは改装をくりかえした大阪の生家の影響でしょう。こうした描写は、いたるところに認められます。
(2001.07.20)
7.新聞をあまり読まない平介
『秘密』は、結末部分が大きな話題になりました。しかし私は、冒頭部分に強い印象を受けています。主人公の杉田平介は、「テレビ」好きとされています。作品のなかに、テレビを観ている場面はふんだんに登場します。ところが「新聞」は、あまり出てきません。私の疑問は、その点にあります。
まず作品の冒頭を引いてみましょう。
――予感めいたものなど、何ひとつなかった。/この日夜勤明けで、午前八時ちょうどに帰宅した平介は、四畳半の和室に入るなりテレビのスイッチを入れた。それは昨日の相撲の結果を知りたかったからにほかならなかった。」(本文より)
昨日の相撲の結果が知りたいのなら、新聞の方がてっとり早いと思います。それをいつ映るかもしれない、テレビで待ちつづける。これは常識的には、考えにくいことです。新聞を購読していないのだろうか、との疑問がおきました。40歳を目前にした会社員が、新聞をとっていないのは不自然だからです。
私は「新聞」の2文字を、作品のなかに追い求めました。そして発見しました。やはり新聞は購読していたのです。
――新聞を拾い上げようとして、部屋の隅に押しやられている本やノートに目がいった。(本文126ページ)
ただし平介が新聞を読む場面は、全編を通じて2回しか出てきません。それも熱心には読まれていません。
――彼(平介)はそばにあった新聞を広げた。地価依然上昇という見出しが出ている。だがその記事は読んではいなかった。(本文275ページより)
――食事の後は風呂に入り、その後は新聞を読んだりテレビを見たりして過ごした。(本文381ページ)
この引用が、新聞を読む2つの場面なのです。当然、新聞を読んでもおかしくない場面でも、平介は新聞を読みません。つぎの場面はどうでしょうか。私なら「新聞や雑誌」と書く場面なのですが。
――昼過ぎまで布団の中で雑誌を読み、午後からはゴルフ番組と野球中継を見た。(本文より)
「時計」同様に「新聞」の扱いも貧弱なものです。ところが「新聞」は、重要な場面の小道具として扱われます。あたかも「懐中時計」のような意味合いで。
――リビングボードを少し前にずらし、壁との隙間にレコーダーとテレフォンピックを押し込めるようにした。さらに隙間が見えないよう、古新聞を積んでおいた。古新聞を処分するのは平介の仕事だ。(本文322ページより)
では冒頭部分に戻りましょう。平介は相撲の結果を観るためにつけたテレビから、妻・直子と小学生の娘・藻奈美を乗せたバス事故を知るのです。この時間に「新聞」では事故を知る術はありません。東野圭吾が平介のテレビ好きを強調し過ぎているのは、冒頭部分の矛盾を釈明するためではないでしょうか。
(2001.08.05)
8.『秘密』のなかの「秘密」
『秘密』のなかに、いくつかの「秘密」がでてきます。以下はその場面の引用です。これらを解き明かしてしまうと、完全なネタばらしになってしまいます。だからさらりと整理するにとどめたいと思います。
奇跡的な生還をとげた藻奈美は、平介に「自分は直子である」と告白します。妻でなければ知らないことを、藻奈美の口からつぎつぎに明らかにされます。事態を理解した平介は、そのことを2人だけの「秘密」としなければならないと考えます。
――どうすればいいかなあ。人にいっても、とても信用してもらえんだろうしなあ。医者にだって、どうすることもできんだろう」/「精神病院に入れられるのがオチでしょうね」/「だろうなあ」平介は腕組みをして、唸った。(本文42ページより)
結局、このことは誰にも明かされない2人だけの「秘密」となりました。2つめの「秘密」は、つぎの場面です。引用文の2人は、平介と直子のことです。
――「このテディベアの正体は、二人だけの秘密ね」そういって直子はぬいぐるみを胸に抱きしめた。(本文73ページより)
平介があずかった懐中時計の裏蓋にも、秘密は隠されていました。この「秘密」は物語の展開に重要な意味をもちます。これも詳細は説明できません。
遺族会の集まりでは、つぎの場面がでてきます。これも「秘密」の一種です。
――幹事の林田が再び立ち上がり、今後の方針などについて話した。さらに、ここでの話し合いの内容については極力口外しないでほしいという注意が添えられた。特にマスコミには気をつけるようにとのことだった。(本文より)
松野時計店の浩三は、平介に物語上最大の秘密の告白をおこないます。その部分だけ引用してみたいと思います。
――「これねえ、藻奈美ちゃんからは口止めされてたんだけど、やっぱり話しておくよ。あんまりいい話だから」(本文より)
終章に近い部分に、直子と藻奈美の「交換日記」の話がでてきます。これも「秘密」の一形態といえます。さらにこんな場面があります。
――「お父さん」彼女がいった。「長い間、本当に長い間、お世話になりました」涙声になっていた。/うん、と平介は頷いた。永遠の秘密を認める首肯でもあった。(本文より)
表紙カバーの帯をめくると、下の方から藻奈美の部屋のイラストがあらわれます。このイラストにも、ある「秘密」が隠されています。
(2001.08.14)
9.飽くなき「笑い」の追求
東野は『秘密』を「自分ではものすごい笑いのつもり」で書いたといいます。ところが「書き上げてみると切ない話」になっていたともいっています。(「東野圭吾が選ぶ笑いの10冊」ダ・ヴィンチ1999年9月号)
実際に、そんな箇所を検証してみたいと思います。その前に東野が選んだ10冊のうち、いくつかを紹介しておきます。
井上ひさし『モッキンポット師の後始末』(講談社文庫)
群ようこ『無印OL物語』(角川文庫)
筒井康隆『日本列島七曲り』(角川書店)
清水義範『国語入試問題必勝法』(講談社文庫)
阿刀田高『ナポレオン狂』(講談社文庫)
「笑い」にこだわる東野らしいラインナップだと思います。本文から「笑い」を意図したと思われる個所を引用してみます。
――冷蔵庫の中には、ほかにハンバーグとビーフシチューが入っている。明日の朝はハンバーグにしよう、と彼は今から決めていた。
――まず味噌汁を啜り、少し迷ってから唐揚げに箸を伸ばした。唐揚げは直子の得意料理であり、平介の大好物でもあった。
――プロポーズの言葉は単純に、「結婚してくれ」だった。直子はそれを聞いて、なぜか笑い転げた。そして笑いがおさまった後、「いいよ」と答えたのだった。
――彼はポケットからよれよれのハンカチを出し、目を押さえた。洟が出てきたので、鼻の下も拭った。ハンカチはたちまちびしょぬれになった。
――「初めて俺が君の部屋へ行った時のことは?」/「覚えている。とっても寒い日だった」/「うん、寒かったな」/「あなた、ズボンを脱いだら、下にパジャマを穿いてた」
平介が時折見せる仕種のなかに、たくさんの「笑い」の種を発見できます。東野が選んだ「笑い」の作品は、いずれも高度な笑いを得意にした作家により書かれたものです。ミステリー作品に散りばめられた「笑い」。東野は不思議な作家です。本来なら「笑い」の部分は、作品のなかで浮いてしまいかねないのですが。
引用文をじっくりと読んでいただきたいと思います。明日の朝食メニューを今から決めてしまう平介。迷ったあげく唐揚げに箸を伸ばす平介。日常のなかのさり気ないひとこまを、東野はあっさり「笑い」の種にしてしまいます。それが巧みであり、作品をひっぱる原動力ともなっているのです。主人公を読者に近づける方法としては、危なっかしい挿話は効果的であるようです。
(2001.08.18)
10.多用する「対極」
ミステリーにかぎらず多くの作品は、2つの極の微妙なバランスで構成されています。それがミステリーなら、加害者と被害者、追うものと逃げるものなどの形であらわれます。この構図は乱用すると、退屈きわまりないものになってしまいます。
「対極」にあるもの同士が、なにかのきっかけで接近しはじめます。ミステリーの面白さはその場面にあります。遠くにあった2つが、なにかのはずみで、しだいに重なりあいます。その妙がミステリーの楽しさなのです。
『秘密』には、たくさんの「対極」が登場します。「夫」と「妻」。平介と直子の取り合わせが究極ですが、バス運転手・梶川と後妻の征子の関係も忘れられません。「親」と「子」、「加害者」と「被害者」、「親会社」と「下請け会社」、「上司」と「部下」、「男の子」と「女の子」、「肉体」と「精神」、「公立の建物」と「安アパート」……数え上げたりキリがありません。
東野はこれらのバランスを重んじ、「対極」をきわだたせるための人物造形を、ていねいにおこないました。登場人物はいちようにやさしく、相手への思いやりがあります。本来なら、プラスとマイナスに働く「対極構造」です。それをけっして、強者と弱者のパターンには落とさないのが東野流なのでしょう。
故バス運転手の妻・征子が、遺族に謝罪する場面があります。平介の隣りにいた藤崎が立ち上がり、「あんたの旦那は人殺しだ」と叫びます。このときに平介はつぎのように考えます。
――皆がどう思っているのか、平介にはわからなかった。はっきりしていることは、藤崎の台詞によって救われた者など一人もいないということだった。彼が口にしたのは禁句だったのだ。(本文95ページより)
平介は征子にたいしても、同じ被害者じゃないかと思える度量の広さをもっています。この気持ちが「対極」の緩衝材となっています。平介が妻・直子に注ぐ愛情。娘・藻奈美にみせる慈愛。そして平介が周囲の人たちに示すやさしさ。『秘密』は、ほのぼのとさせられるミステリーでもありました。(おわり)
「ミステリーZ」の読者のみなさまへ
長い間おつきあいいただきありがとうございます。1冊の本を読み、素人でもこのくらいは読書を広げることができます。雑誌や新聞からの切抜きを作品と重ねて、じっくりと読んでみる。ぜひ試みてください。すごく楽しいです。藤光伸。(補:これは以前つかっていたペンネームです)
(山本藤光:2001.08.19初稿、2014.11.29改稿)
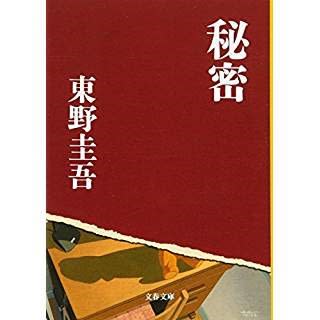
6.在るべきところへの執着
東野圭吾は「居所」に、とことんこだわります。それは幼いころの境遇と、無縁ではないでしょう。東野には2人の姉がいて、部屋は共同でした。その後、生家は何度も増改築を重ねます。小学校の途中から、姉たちが隣室である和室へと移りました。しかし東野の部屋は、姉たちを越えて階下へと降りる通路でもありました。上の姉が家を出ます。今度は下の姉との共同部屋となりました。
結局、東野は家をでるまで、のんびりと1人部屋で過ごす機会には恵まれませんでした。1浪後に大阪府立大学電気工学科へ入学します。トイレと炊事場が共用の、安アパートに暮すことになります。念願の1人暮しを満喫するには、ほど遠い環境であったわけです。
大学卒業後は、愛知県の自動車部品メーカーの独身寮へはいります。ここでも3DKを3人で分割する、共同生活を余儀なくされました。25歳で結婚。棟続きの社宅へと移りました。東野はいいます。
――みんな自分のいちばん落ち着く場所を探しているんでしょうけど、僕自身は大阪のゴミゴミした商店街の、自然も緑もないところで生まれ育っていますから。街の中にいるのが楽なんですよ」( 「週刊文春」1999年8月5日号「家の履歴書」より)
「居所」へのこだわりは、『秘密』のなかにも登場します。つぎに引用するのは、妻の直子のセリフです。直子が示す家への執着はすさまじいものです。これは東野自身の叫びともいえるでしょう。
――とにかくね、今買わなきゃ。今買わないと、平ちゃん、永遠に家なんて買えない気がする。永久に借家住まいだよ。そんなのいやでしょ? 自分の家、ほしいでしょ? 欲しかったら買おうよ。すぐ買おうよ」(本文より)
杉田平介のマイホームは、三鷹駅からバスで数分のところにあります。直子にスピッツがほえるように、きゃんきゃんいわれて買った中古住宅です。平介も十分に満足しています。マイホームを象徴する、こんな場面があります。
――平介がこの家を気に入った第一の理由も、この広い浴室だったといってもいい。(本文より)
東野圭吾は、ていねいに家の間取りを描きます。これは改装をくりかえした大阪の生家の影響でしょう。こうした描写は、いたるところに認められます。
(2001.07.20)
7.新聞をあまり読まない平介
『秘密』は、結末部分が大きな話題になりました。しかし私は、冒頭部分に強い印象を受けています。主人公の杉田平介は、「テレビ」好きとされています。作品のなかに、テレビを観ている場面はふんだんに登場します。ところが「新聞」は、あまり出てきません。私の疑問は、その点にあります。
まず作品の冒頭を引いてみましょう。
――予感めいたものなど、何ひとつなかった。/この日夜勤明けで、午前八時ちょうどに帰宅した平介は、四畳半の和室に入るなりテレビのスイッチを入れた。それは昨日の相撲の結果を知りたかったからにほかならなかった。」(本文より)
昨日の相撲の結果が知りたいのなら、新聞の方がてっとり早いと思います。それをいつ映るかもしれない、テレビで待ちつづける。これは常識的には、考えにくいことです。新聞を購読していないのだろうか、との疑問がおきました。40歳を目前にした会社員が、新聞をとっていないのは不自然だからです。
私は「新聞」の2文字を、作品のなかに追い求めました。そして発見しました。やはり新聞は購読していたのです。
――新聞を拾い上げようとして、部屋の隅に押しやられている本やノートに目がいった。(本文126ページ)
ただし平介が新聞を読む場面は、全編を通じて2回しか出てきません。それも熱心には読まれていません。
――彼(平介)はそばにあった新聞を広げた。地価依然上昇という見出しが出ている。だがその記事は読んではいなかった。(本文275ページより)
――食事の後は風呂に入り、その後は新聞を読んだりテレビを見たりして過ごした。(本文381ページ)
この引用が、新聞を読む2つの場面なのです。当然、新聞を読んでもおかしくない場面でも、平介は新聞を読みません。つぎの場面はどうでしょうか。私なら「新聞や雑誌」と書く場面なのですが。
――昼過ぎまで布団の中で雑誌を読み、午後からはゴルフ番組と野球中継を見た。(本文より)
「時計」同様に「新聞」の扱いも貧弱なものです。ところが「新聞」は、重要な場面の小道具として扱われます。あたかも「懐中時計」のような意味合いで。
――リビングボードを少し前にずらし、壁との隙間にレコーダーとテレフォンピックを押し込めるようにした。さらに隙間が見えないよう、古新聞を積んでおいた。古新聞を処分するのは平介の仕事だ。(本文322ページより)
では冒頭部分に戻りましょう。平介は相撲の結果を観るためにつけたテレビから、妻・直子と小学生の娘・藻奈美を乗せたバス事故を知るのです。この時間に「新聞」では事故を知る術はありません。東野圭吾が平介のテレビ好きを強調し過ぎているのは、冒頭部分の矛盾を釈明するためではないでしょうか。
(2001.08.05)
8.『秘密』のなかの「秘密」
『秘密』のなかに、いくつかの「秘密」がでてきます。以下はその場面の引用です。これらを解き明かしてしまうと、完全なネタばらしになってしまいます。だからさらりと整理するにとどめたいと思います。
奇跡的な生還をとげた藻奈美は、平介に「自分は直子である」と告白します。妻でなければ知らないことを、藻奈美の口からつぎつぎに明らかにされます。事態を理解した平介は、そのことを2人だけの「秘密」としなければならないと考えます。
――どうすればいいかなあ。人にいっても、とても信用してもらえんだろうしなあ。医者にだって、どうすることもできんだろう」/「精神病院に入れられるのがオチでしょうね」/「だろうなあ」平介は腕組みをして、唸った。(本文42ページより)
結局、このことは誰にも明かされない2人だけの「秘密」となりました。2つめの「秘密」は、つぎの場面です。引用文の2人は、平介と直子のことです。
――「このテディベアの正体は、二人だけの秘密ね」そういって直子はぬいぐるみを胸に抱きしめた。(本文73ページより)
平介があずかった懐中時計の裏蓋にも、秘密は隠されていました。この「秘密」は物語の展開に重要な意味をもちます。これも詳細は説明できません。
遺族会の集まりでは、つぎの場面がでてきます。これも「秘密」の一種です。
――幹事の林田が再び立ち上がり、今後の方針などについて話した。さらに、ここでの話し合いの内容については極力口外しないでほしいという注意が添えられた。特にマスコミには気をつけるようにとのことだった。(本文より)
松野時計店の浩三は、平介に物語上最大の秘密の告白をおこないます。その部分だけ引用してみたいと思います。
――「これねえ、藻奈美ちゃんからは口止めされてたんだけど、やっぱり話しておくよ。あんまりいい話だから」(本文より)
終章に近い部分に、直子と藻奈美の「交換日記」の話がでてきます。これも「秘密」の一形態といえます。さらにこんな場面があります。
――「お父さん」彼女がいった。「長い間、本当に長い間、お世話になりました」涙声になっていた。/うん、と平介は頷いた。永遠の秘密を認める首肯でもあった。(本文より)
表紙カバーの帯をめくると、下の方から藻奈美の部屋のイラストがあらわれます。このイラストにも、ある「秘密」が隠されています。
(2001.08.14)
9.飽くなき「笑い」の追求
東野は『秘密』を「自分ではものすごい笑いのつもり」で書いたといいます。ところが「書き上げてみると切ない話」になっていたともいっています。(「東野圭吾が選ぶ笑いの10冊」ダ・ヴィンチ1999年9月号)
実際に、そんな箇所を検証してみたいと思います。その前に東野が選んだ10冊のうち、いくつかを紹介しておきます。
井上ひさし『モッキンポット師の後始末』(講談社文庫)
群ようこ『無印OL物語』(角川文庫)
筒井康隆『日本列島七曲り』(角川書店)
清水義範『国語入試問題必勝法』(講談社文庫)
阿刀田高『ナポレオン狂』(講談社文庫)
「笑い」にこだわる東野らしいラインナップだと思います。本文から「笑い」を意図したと思われる個所を引用してみます。
――冷蔵庫の中には、ほかにハンバーグとビーフシチューが入っている。明日の朝はハンバーグにしよう、と彼は今から決めていた。
――まず味噌汁を啜り、少し迷ってから唐揚げに箸を伸ばした。唐揚げは直子の得意料理であり、平介の大好物でもあった。
――プロポーズの言葉は単純に、「結婚してくれ」だった。直子はそれを聞いて、なぜか笑い転げた。そして笑いがおさまった後、「いいよ」と答えたのだった。
――彼はポケットからよれよれのハンカチを出し、目を押さえた。洟が出てきたので、鼻の下も拭った。ハンカチはたちまちびしょぬれになった。
――「初めて俺が君の部屋へ行った時のことは?」/「覚えている。とっても寒い日だった」/「うん、寒かったな」/「あなた、ズボンを脱いだら、下にパジャマを穿いてた」
平介が時折見せる仕種のなかに、たくさんの「笑い」の種を発見できます。東野が選んだ「笑い」の作品は、いずれも高度な笑いを得意にした作家により書かれたものです。ミステリー作品に散りばめられた「笑い」。東野は不思議な作家です。本来なら「笑い」の部分は、作品のなかで浮いてしまいかねないのですが。
引用文をじっくりと読んでいただきたいと思います。明日の朝食メニューを今から決めてしまう平介。迷ったあげく唐揚げに箸を伸ばす平介。日常のなかのさり気ないひとこまを、東野はあっさり「笑い」の種にしてしまいます。それが巧みであり、作品をひっぱる原動力ともなっているのです。主人公を読者に近づける方法としては、危なっかしい挿話は効果的であるようです。
(2001.08.18)
10.多用する「対極」
ミステリーにかぎらず多くの作品は、2つの極の微妙なバランスで構成されています。それがミステリーなら、加害者と被害者、追うものと逃げるものなどの形であらわれます。この構図は乱用すると、退屈きわまりないものになってしまいます。
「対極」にあるもの同士が、なにかのきっかけで接近しはじめます。ミステリーの面白さはその場面にあります。遠くにあった2つが、なにかのはずみで、しだいに重なりあいます。その妙がミステリーの楽しさなのです。
『秘密』には、たくさんの「対極」が登場します。「夫」と「妻」。平介と直子の取り合わせが究極ですが、バス運転手・梶川と後妻の征子の関係も忘れられません。「親」と「子」、「加害者」と「被害者」、「親会社」と「下請け会社」、「上司」と「部下」、「男の子」と「女の子」、「肉体」と「精神」、「公立の建物」と「安アパート」……数え上げたりキリがありません。
東野はこれらのバランスを重んじ、「対極」をきわだたせるための人物造形を、ていねいにおこないました。登場人物はいちようにやさしく、相手への思いやりがあります。本来なら、プラスとマイナスに働く「対極構造」です。それをけっして、強者と弱者のパターンには落とさないのが東野流なのでしょう。
故バス運転手の妻・征子が、遺族に謝罪する場面があります。平介の隣りにいた藤崎が立ち上がり、「あんたの旦那は人殺しだ」と叫びます。このときに平介はつぎのように考えます。
――皆がどう思っているのか、平介にはわからなかった。はっきりしていることは、藤崎の台詞によって救われた者など一人もいないということだった。彼が口にしたのは禁句だったのだ。(本文95ページより)
平介は征子にたいしても、同じ被害者じゃないかと思える度量の広さをもっています。この気持ちが「対極」の緩衝材となっています。平介が妻・直子に注ぐ愛情。娘・藻奈美にみせる慈愛。そして平介が周囲の人たちに示すやさしさ。『秘密』は、ほのぼのとさせられるミステリーでもありました。(おわり)
「ミステリーZ」の読者のみなさまへ
長い間おつきあいいただきありがとうございます。1冊の本を読み、素人でもこのくらいは読書を広げることができます。雑誌や新聞からの切抜きを作品と重ねて、じっくりと読んでみる。ぜひ試みてください。すごく楽しいです。藤光伸。(補:これは以前つかっていたペンネームです)
(山本藤光:2001.08.19初稿、2014.11.29改稿)









