ここのところ気温の上下変動が激しい。1日毎に最高気温の変動が10~15度くらいに及ぶことがある。冬から春へ、春から夏へとゆっくり変わってゆく季節感がない。人間のみならず、動植物、農作物などすべての生き物が戸惑っているのではないか。
どうしてこのような激しい変動が頻繁に起こるのであろうか。これまでは太平洋高気圧と北極高気圧が、多少の局所的な流動があっても、大域的には安定的に存在し、太陽を回る地球の公転とともに、ゆっくりと、どちらかが拡大し、どちらかが縮小する事で、季節の移り変わりをもたらしていたのであった。
ところが、大都市や工業地帯の熱放射によって、赤道よりやや北側の地球をめぐる地帯(ここに大部分の大都市圏、工業圏が集中している)に、局所的な熱気団がいくつか生じ、それが上の大域的な気団の分布を不安定にし、大気の流れにこれまでとは異なる擾乱を引き起こしているのではないか。この乱れによって、急激に、あるときは太平洋高気圧が流れ込んだり、北極高気圧が流れ込んだりして、気温の急激な乱高下を惹き起こしているのであろう。
したがって、気象予報をする場合、局所的な熱気団を考慮に入れた新しいモデルが必要と思われる。気象庁は、スーパーコンピュータの性能を上げれば予報の精度が上がる、と主張するが、モデルが正しくなければ、いくらスーパーコンピュータの性能を上げても、正しい結果は得られない。
われわれは物事をいつもモデル化して対処しているといってよい。したがって、正しいモデルを構築する事が重要である。モデルの構築は、人間の思考(頭脳)による。つまり、科学技術の進歩の基本は人間の思考であり、スーパーコンピュータの性能アップだけでもたらされるものではない(これが大きなサポートとなることは認めるとしても)。(青)
追記:この小文を書き上げた同じ日に、NHKテレビが、地球上の全地域のCO2の分布を観測できる衛星の話しを報じていた。これではもうこの小文は珍論・奇説の範疇に入らないのかもしれない。
どうしてこのような激しい変動が頻繁に起こるのであろうか。これまでは太平洋高気圧と北極高気圧が、多少の局所的な流動があっても、大域的には安定的に存在し、太陽を回る地球の公転とともに、ゆっくりと、どちらかが拡大し、どちらかが縮小する事で、季節の移り変わりをもたらしていたのであった。
ところが、大都市や工業地帯の熱放射によって、赤道よりやや北側の地球をめぐる地帯(ここに大部分の大都市圏、工業圏が集中している)に、局所的な熱気団がいくつか生じ、それが上の大域的な気団の分布を不安定にし、大気の流れにこれまでとは異なる擾乱を引き起こしているのではないか。この乱れによって、急激に、あるときは太平洋高気圧が流れ込んだり、北極高気圧が流れ込んだりして、気温の急激な乱高下を惹き起こしているのであろう。
したがって、気象予報をする場合、局所的な熱気団を考慮に入れた新しいモデルが必要と思われる。気象庁は、スーパーコンピュータの性能を上げれば予報の精度が上がる、と主張するが、モデルが正しくなければ、いくらスーパーコンピュータの性能を上げても、正しい結果は得られない。
われわれは物事をいつもモデル化して対処しているといってよい。したがって、正しいモデルを構築する事が重要である。モデルの構築は、人間の思考(頭脳)による。つまり、科学技術の進歩の基本は人間の思考であり、スーパーコンピュータの性能アップだけでもたらされるものではない(これが大きなサポートとなることは認めるとしても)。(青)
追記:この小文を書き上げた同じ日に、NHKテレビが、地球上の全地域のCO2の分布を観測できる衛星の話しを報じていた。これではもうこの小文は珍論・奇説の範疇に入らないのかもしれない。

















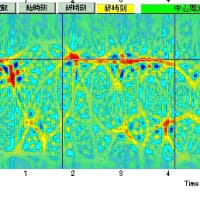
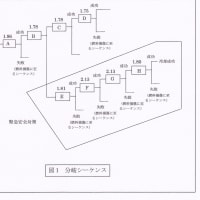

熱のことをエントロピーに関して調べているところですが、地球環境の熱配分は、太陽からもたらされる熱エネルギーと宇宙温度(2.7度K)に放射される熱とによって定まります。
このことを背景にすると人間活動に原子力エネルギーとか化石エネルギーを用いると地球環境の熱配分が変化することは充分考えられます。
地球環境の熱配分について、様々なモデルによりコンピュータ・シミュレーションを並列的に実施することは今後の人類生存維持のため、必須な課題であって、珍論・奇説ではありません。