

7駅目の「馬来田」(まくた)駅はホームが高台にあって、短い階段を降りると、懐かしい改札と、いい感じの木造駅舎(横見クン調)のある有人駅(ボランティア委託)だった。駅前もちゃんとあって、タクシーが1台停まっている。1995年ごろまではれっきとした交換駅で、ホームも二面存在していた。
(久留里線には、反対側にホーム跡の残っている駅も多い)
馬来田周辺は散歩に向いている。コスモスロードと呼ばれる道の先には湧水で有名な「いっせんぼく」があり、メルヘン散歩が楽しめる。これぞ里山といった風景を歩きたい人は、羽雄神社まで足を延ばし、馬乗り馬頭観音像や石仏を巡るのもいいだろう。晩秋から初冬にかけてが特に良さそうだ。個人的には、小春日和の一日に、ふらっと歩いてみたい。
40分ほど待ち時間があるので、唯一のタクシーで羽雄神社まで連れていってもらい、徒歩で駅まで戻る手もあったが、今回は駅弁以外の出費を一切しないことに決めていた。駅の周りをうろうろしている間に、10時16分の上り線がやってきた。


馬来田の 嶺(ね)ろに隠り居 かくだにも
国の遠かば 汝(ながめ)が目欲(ほ)りせむ (万葉集より)
駅前に、馬来田を詠った和歌の石碑があった。東歌だろうか? 馬来田に住んでいる恋人を想う内容から察すると、防人の歌かもしれない。万葉の時代、馬来田(まくた)は、「うまくた」とも呼ばれていたそうだ。

6駅目の「東横田」。『鉄子の旅』第1回の頃は、貨車を利用した待合室だったが、今風のこざっぱりしたものに建替えられていた。とうとう、小雨が降ってきた。軒が狭いので、傘を差していないと濡れてしまう。待ち時間が8分と短かったので東横田へ戻ったけれど、次は一気に久留里まで向かう。


8駅目の「下郡」(しもごおり)。『鉄子の旅』に描かれた頃と全く同じ。ホーム前方の「秘密の小径」は誰が使うのだろう? その答えは帰り道に見つかった。


(右上)9駅目の「小櫃」(おびつ)。駅の斜め向かいにSLが停まっている。走行中にSLの写真を撮ったが、行きも帰りも見事に失敗した。
(左上)10駅目の「俵田」も何もないところ。待合室の写真を撮るのに精一杯で、駅の周りがどんなだったか、さっぱり覚えていない。帰り道に観察しておけばよかった・・・やはり全駅下車が必要?


雨の中、11駅目の「久留里」駅へ到着。上り列車がすでに入線していた。ここでもタブレットを交換して上りと下りがすれ違う。当初の予定より2時間半早い10時51分に到着。
駅前は、向かって右に市役所、左に公民館。久留里城まで1.1km、30分だと職員から聞き、折りたたみ傘を差していざ行かん。12時36分までに戻ってくればいいのだから、楽勝だよね・・・


久留里城商店街を右に曲がって街道をてくてく歩き、「久留里の井戸水」を過ぎたところで、左に曲がるよう案内標識があった。道なりに進むと、坂道とトンネルが現われた。この先、きつい登りが待っているとは・・・


トンネルを抜けると・・・雪国じゃなくて、駐車場に出た。以後の道のりは、何人たりとも自分の足でゆくしかない。写真ではそれほど急な坂道には見えないが、息があがる、膝が笑う、汗が噴き出す、雨脚は強まるわ、素晴らしい道だった。こうなれば矢でも鉄砲でも持って来い! みるみる高度を稼いでいった。


(右上)資料館へと続く「獣道」。舗装した道もあるがワイルドに行きたい! で、ワイルドに転んだ・・・資料館は月曜休館だった。
(左上)思えば遠くに来たもんだ~、四角く見えるのは濠や二の丸&三の丸跡。右の方から霧が立ちこめ、1分後に真っ白になった。

資料館からさらに150mほど登って、ようやく天守閣にたどり着いた。ロープが張られて立ち入り禁止になっているのは、シャチホコが傾いてしまい、落下のおそれがあるため。
伝承によると、久留里城は関東の守り神でもある反逆者=平将門の三男がお告げにより築城したといわれており、今から1000年前に遡るが、実際に築いたのは、上総武田氏の祖である武田信長で、1455年ごろに完成させたそうだ。その後、里見氏のものとなり、戦国時代には関東一の実力者だった北条氏と、城を巡って激しい攻防戦を繰り広げている。地形をフルに活用した典型的な山城だったのだろう。
天守閣に着いてしばらく佇んでいる間に、霧が天守閣を覆い隠していった。久留里城が雨城、霧降城と呼ばれた由縁である。雨の演出に納得して下山・・・


(右上)資料館の倉庫で雨宿りをしながら「漁り弁当」(1000円)を食べた。アサリがたっぷり乗った炊き込みご飯にカキフライやひじきがつく。非常に美味だった。
(左上)帰りがけに、久留里の井戸水をペットボトルに入れた。枡の中には金魚が泳いでいる。帰宅後、この水でコーヒーを淹れてみた。気持ちの問題かもしれないけれど、おいしかった~♪ 【後記】久留里の井戸水は全国的にも知られていて、2008年7月、NHK『小さな旅 ~幸せの水くれる井戸(千葉県 久留里)」は、この井戸水が番組の柱になっていた。
【後記】久留里の井戸水は全国的にも知られていて、2008年7月、NHK『小さな旅 ~幸せの水くれる井戸(千葉県 久留里)」は、この井戸水が番組の柱になっていた。


12時36分、上り列車と下り列車がタブレットを交換してすれ違う。終点の上総亀山目指して、やや山の中に入っていく。 三連休は変則的に月曜日だけ仕事になりました。明日&明後日は、フリー切符の2~3回目を使う予定。明日はいぶし銀みたいなローカル線を訪ねます。最近、鉄道の記事ばかりですが、映画に美術に音楽、そして『ちりとてちん』。やっぱり、芸術の秋なんだろうか? 一日48時間欲しい~!
三連休は変則的に月曜日だけ仕事になりました。明日&明後日は、フリー切符の2~3回目を使う予定。明日はいぶし銀みたいなローカル線を訪ねます。最近、鉄道の記事ばかりですが、映画に美術に音楽、そして『ちりとてちん』。やっぱり、芸術の秋なんだろうか? 一日48時間欲しい~!














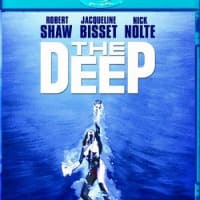





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます