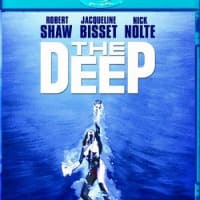子供の頃はとてつもなく大きかった羽村の堰。空は今も広い。
最上段の水の中に佇んでいるのは・・・?(わかるかなあ~)
こちらの記事を先に書いていたのですが、不名誉の負傷(といっても小指を切っただけ)をしたので?そちらの記事を先に書いてしまいました。さて・・・
あんこさんから、懐かしい「社会科見学」についてコメントいただきましたが、私がこうした文章をブログに書いているのも、自分が物知りだからではなく、(大げさにいえば)「勉強」しているからに過ぎません。身近なものを見ているだけなのに、このトシになっても「目からウロコ」の連続です。それをそのままにしておくと片っ端から忘れてしまうので、散歩や小さな旅から帰ってきてから、復習して記録してるというわけ。
インターネットの功罪については、もしかすると「罪」の方がパーセンテージが高いかもしれませんが、ブログを始めたおかげで、以前と比べて格段に世界が広がったと思います。最近ご無沙汰してくれるけど、ほんと、背中を押してくれたびわちゃさんには、背中を向けて眠れません。


堰の浅瀬に佇んでいた白い影は・・・シロサギでした。望遠側に切り換えて後を追います。獲物を狙っているのかと思ったら、そうでもないみたいで、雨の羽村の堰を悠然と逍遥している感じに見えました。水の流れはかなり速いのですが、シロサギはそれをものともせず、マイペースで足を運んでいきます。まるで、水墨画から抜け出してきたような・・・


(右)玉川上水の取水口。1654年に設置された。現在の形になったのは、明治33年(1900)。
(左)一定量以上の水は堰に戻される。結構すごい勢いで水が噴き出していた。


(左)桜の若葉が青々と茂る中をかなりの勢いで下ってゆく玉川上水。ここから下流1kmほどは、桜の名所として有名。
(右)玉川上水を開削した玉川兄弟。玉川上水は全長43km。自然落下のみで引かれた水道として世界屈指の存在。しかも上流から下流まで高低差が92mしかないので、工事は困難を極めた(単純計算して、100mで21.3cmしか勾配を取れない)。言い伝えによると、玉川兄弟は幕府から6000両を渡されたが、2度の失敗で資金が足りなくなり、私財を投げうち、ようやく開設させたらしい。


「羽村の堰」の上流100mほどの川の向かい側にある羽村市郷土博物館。縄文時代の出土品から、水道関連、養蚕、そして羽村の自然など、実に見学しがいがあるのに入場無料! ここまで来たら、寄らない手はない。羽村の堰の下流にかけられた橋を渡って向こう岸に渡り、遊歩道を上流に向かって10分ほど歩くと、郷土博物館に到着する。
右の写真は、羽村の堰の上流から向こう岸に覗く博物館の三角屋根。「はなと水のまつり」の会場に向かう途中に撮影した。


堰の実物大模型。開設当時の水門(左)と、現在の水門。現在も、都水の3割は玉川上水から取水されている。



郷土博物館に隣に残されている「旧下田屋住宅」。1847年に建てられた農家を移築した。生活用具や養蚕道具など1200点が展示されている。ここの縁側で昼寝したいな~(この日は雨宿りだけど)。この頃になって、雨粒が写真に写るほど本格的に降ってきた。


(右)江戸時代中期に作られた「赤門」。昭和10年に中里介山が譲り受け、中里介山記念館の正門にした。記念館閉館後に寄贈され、現在の地に立っている。
(左)〈旧田中家〉にあった長屋門。門の左右に6畳ほどの土間があるので長屋門と呼んでいるのだろうか? 土間は使用人の住まいや物置として使われたが、農村ではかなり珍しい門だとか・・・二百年以上前に作られ、1986年に寄贈された。


(右)郷土美術館の前の川原に置かれていた「牛枠」。水の勢いを弱め、堤防が崩れるのを防ぐ「川倉」の一種。「牛枠」は、堤防に植えた川畔林を切り出し、川床の玉石をつめた蛇籠で固定して作ります。堤防を強化する林が治水の材料を提供。地産地消でエコですね~。
(左)堤防を築いている河畔林。雨なのに、鳥たちはさかんに鳴いていた。初めて聴く声も多かった。


マクロ機能のついたコンデジだと、こういう写真も取れる・・・このあとチューリップ会場へ足を向けたのですが、4月とは思えない暑い日が続いたので、開花は例年より遅かったのに、大半のチューリップが終わってしまい・・・羽村駅に戻りました。「三度目の正直」というわけで、河辺の駅前温泉「梅の湯」に繰り出しました。「梅の湯」については、改めて・・・