山行き記録は、ヤマレコをご覧ください
172三浦半島ハイキング、見えた!富士山、東京スカイツリ-、... [房総・三浦] 
12/23(金)、青春18切符で大阪から金沢八景(横浜市金沢区)へ、電車を乗り継ぐこと9回、約10時間の長旅だった。感心したのは往復とも、JRの電車はダイヤ通りの運行だった。
往路 復路

この春、就職した二男のアパートへ。しばらくは、ここを拠点の山行きです。
12/24(土)丹沢山へ登る予定が出発が遅れたのと、足慣らしのため地元の三浦半島・縦走ハイキングに出かけた。
晴天に恵まれ、富士山や東京スカイツリーも見えた、さらにどの山頂からも360度の大パノラマだった。

神奈川県
金沢八景から京急・長沢駅へ ここから三浦半島縦走に出発。最初のピークが三浦富士。


三浦富士山頂から西方向に、雲の上に冠雪した山頂部だけの富士山
三浦富士から南東方向、三浦湾に遠く房総半島
武山山頂から北東、東京湾・浦賀水道に浮かぶ二つの東京湾海堡が見えた。
東京湾要塞の重要な設備として、東京湾入口の最挟部に造成された人工島の海堡がある。海堡には砲台が備えられ、浦賀水道の沿岸砲台を突破した敵艦艇を海上から砲撃する任務を持っていた。このため各海堡の備砲は横須賀側の猿島や走水の砲台と合わせて全体で浦賀水道全体を射程に納めるように配置された。海堡は、明治の中頃に建設が始まり30年にわたる海上工事と多大な工事費、及び犠牲者を出しつつ大正時代に完成を見て15センチカノン砲などが配備された。
第三海堡が完成した2年後の関東大震災によって第二・第三海堡が被災、復旧は困難との判断になり除籍され、第一海堡のみの運用となる。第三海堡は大きく支障があるとのことで、2000年12月から2007年8月にかけて撤去作業が行われた。第一・第二海堡は現存しているが、第二海堡には海上保安庁によって灯台が設置されている。




大楠山山頂から北北東、横須賀・横浜の市街、東京湾、遠くに東京スカイツリー



一見、灯台のような大楠山レーダー雨量観測所と展望塔


大楠山山頂から北西方向、江ノ島、湘南海岸、丹沢山脈、富士山は雲がかかって見えない























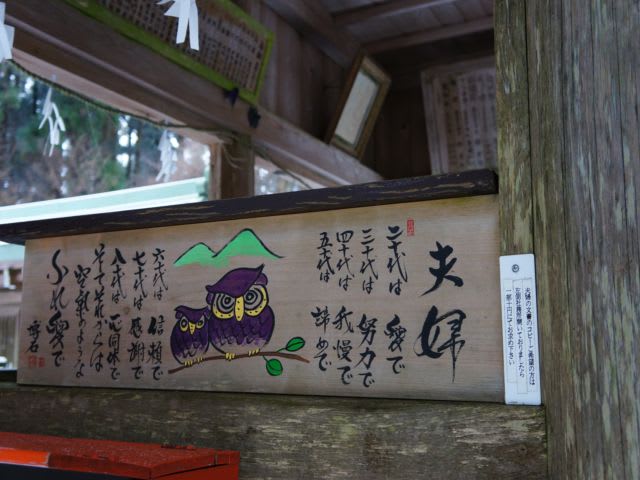


















 熊注意の看板も
熊注意の看板も












































































































































































































































































































































































