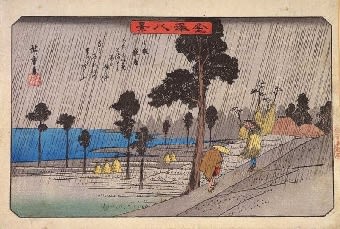山行き記録は、ヤマレコをご覧ください。
188雪の金剛山・千早峠からダイトレ・文珠尾道 [金剛山・岩湧山] 
今年6回目の金剛山。今日は千早赤阪村・馬場谷付近から池の川谷林道で千早峠へ、ダイトレ道に合流し久留野峠
伏見峠を経て金剛山・千早園地へと登った。昼食後は展望台から文珠岩屋まで進み、ここから文珠尾道で馬場谷へと下山した。
出発点から反時計回りに一周するコースであった。スタートまもなくの林道で犬を連れた青年と出合う。ほぼ同じコースを歩くという。
追いつ追われつで、ちはや園地まで一緒した。ダイトレ道には数センチの残雪があり、凍って固まった状態。下りの階段は滑りやすく
アイゼンが役に立った。中葛城山付近で、逆回りされている年配の方と出会い言葉を交わす。
雲一色の天候だったが中葛城山や、ちはや園地展望台からは、大峯山系の山並みがくっきり浮かび上がっていた。
中葛城山付近から南東方向に大峰山系の山並みが素晴らしい。弥山山頂は一際、白かった。
ちはや園地・展望台(標高1070m)から南東方向に大峰山系の山並みが素晴らしかった。
池の川谷林道を進む、林業ガレージの先で2分岐、3分岐点有り



池の川谷のせせらぎ



千早峠からダイトレ道で金剛山へ、中葛城山付近まで、ダイトレ道のすぐ近くを新しい林道工事の音がしていた。




中葛城山、この付近南側の展望が素晴らしい。今日は雲一色だったが、以外にも遠く大峰の山並みがはっきり浮かんでいた。




伏見峠、ちはや園地・金剛山キャンプ場

ちはや園地の大屋根広場で昼食をとった。





ちはや園地・展望台から西南西方向の山並み、岩湧山や和泉山脈

文珠岩屋 文珠岩屋のすぐ下から文珠尾道が始まる。